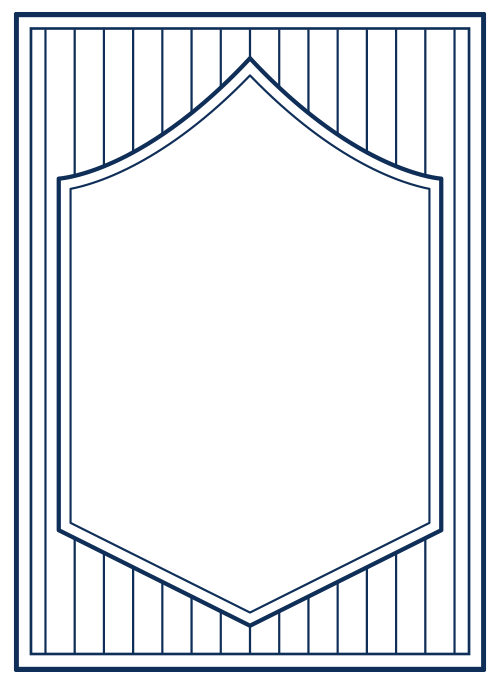「それは、幻夜さまが冥府の番人だからですか? でも、実体が揺らぐって……?」
(いったい、どういう意味なの?)
想像もつかない。
「旦那様は一見、普通の人となにも変わらないのですが、触れようとすると手が旦那様の御身を通り抜けてしまうのです。実体はあるのに触れようとしても触れられない。その状態を旦那様は『揺らぐ』と表現しておられました」
「で、でも、幻夜さまはこの家の扉だって開けておられましたよ?」
「物には触れます。お食事も、私たちとおなじように取られます。ただ、命あるものには触れられないのです」
「そんな」
突拍子もない話に、返す言葉が見つからない。けれど、辰野は大真面目だ。
「といっても、旦那様は間違いなく普通の方と変わりませんよ! 味音痴でいらっしゃいますが、普通です」
「味音痴なのですか? そうは見えませんでした」
「ええ。旦那様は誰にもバレてないとお思いのようなので、ここだけの話ですが」
辰野は口元で人差し指を立て、神妙な顔をする。
「ですが、ほんとうに普通ですから! だからどうぞ、旦那様をお嫌いにならないでください……!」
「嫌いになんてなりません。幻夜さまはわたしの恩人ですもの」
「沙和様のお優しいこと! 村では大変な目に遭われたと聞きましたのに、恨み言のひとつもおっしゃらないですし」
「それは幻夜さまのおかげです。あの方がいてくださったから」
(そうよ。触れられないくらい、大したことではないわ)
「これまで旦那様が不憫でなりませんでしたが……沙和様がそばにいてくだされば、旦那様も救われることと思います。ぜひとも末長く、旦那様をよろしくお願いします! 早く、仕立てたお着物を旦那様にご覧頂きたいですね。きっとお喜びになりますよ」
辰野がはしゃぐ。幻夜が喜んでくれるところを想像して、沙和も心が弾んだ。
着物が仕立て上がった日、沙和はさっそくそのうちの一着を身につけた。着れば、早く幻夜に見せたくなる。
最初は離れの玄関で待っていたが、待ちきれなくなって屋敷の門扉まで出ると、夜も更けてから幻夜が帰ってきた。いつも幻夜の帰りは遅い。
「幻夜さま、お帰りなさいませ」
「ただいま。寝てなかったのか」
「これを早くお見せしたくて、お待ちしていました」
沙和は着物の両袖がよく見えるようにして、幻夜に披露する。
幻夜は靴を脱ぎながら満足そうに目を細めた。
「へぇ……いいじゃないか、沙和。帝都じゅうに見せびらかしてやりたくなる」
「ありがとうございます! 幻夜さまに喜んでいただけるように、一生懸命、選びました」
「そうか……」
幻夜が口元に拳を当てる。嬉しそう、なのだろうか。
「俺を喜ばせるのもいいが、沙和の好きなものにしたか?」
「実はこの生地の色、幻夜さまに拾っていただいたときの空の色みたいで、ひと目で気に入ったんです……!」
「うっ、そうか」
幻夜はまた口元に手を当てると、足元に敷かれた飛び石を離れへと歩く。沙和もそのあとをついて歩いたが、袴姿のときと同様に大股になったのがいけなかったのか、石畳につまずいた。
「ひゃっ」
「なんだ?」
ひとつ先の飛び石にいた幻夜がふり向いたそのとき、沙和はぶざまに転んでしまった。
「痛っ……」
「大丈夫か!?」
幻夜が手を差し伸べかけ、引っこめた。それには気づかず、沙和は立ちあがって着物の裾を軽く払う。
(いったい、どういう意味なの?)
想像もつかない。
「旦那様は一見、普通の人となにも変わらないのですが、触れようとすると手が旦那様の御身を通り抜けてしまうのです。実体はあるのに触れようとしても触れられない。その状態を旦那様は『揺らぐ』と表現しておられました」
「で、でも、幻夜さまはこの家の扉だって開けておられましたよ?」
「物には触れます。お食事も、私たちとおなじように取られます。ただ、命あるものには触れられないのです」
「そんな」
突拍子もない話に、返す言葉が見つからない。けれど、辰野は大真面目だ。
「といっても、旦那様は間違いなく普通の方と変わりませんよ! 味音痴でいらっしゃいますが、普通です」
「味音痴なのですか? そうは見えませんでした」
「ええ。旦那様は誰にもバレてないとお思いのようなので、ここだけの話ですが」
辰野は口元で人差し指を立て、神妙な顔をする。
「ですが、ほんとうに普通ですから! だからどうぞ、旦那様をお嫌いにならないでください……!」
「嫌いになんてなりません。幻夜さまはわたしの恩人ですもの」
「沙和様のお優しいこと! 村では大変な目に遭われたと聞きましたのに、恨み言のひとつもおっしゃらないですし」
「それは幻夜さまのおかげです。あの方がいてくださったから」
(そうよ。触れられないくらい、大したことではないわ)
「これまで旦那様が不憫でなりませんでしたが……沙和様がそばにいてくだされば、旦那様も救われることと思います。ぜひとも末長く、旦那様をよろしくお願いします! 早く、仕立てたお着物を旦那様にご覧頂きたいですね。きっとお喜びになりますよ」
辰野がはしゃぐ。幻夜が喜んでくれるところを想像して、沙和も心が弾んだ。
着物が仕立て上がった日、沙和はさっそくそのうちの一着を身につけた。着れば、早く幻夜に見せたくなる。
最初は離れの玄関で待っていたが、待ちきれなくなって屋敷の門扉まで出ると、夜も更けてから幻夜が帰ってきた。いつも幻夜の帰りは遅い。
「幻夜さま、お帰りなさいませ」
「ただいま。寝てなかったのか」
「これを早くお見せしたくて、お待ちしていました」
沙和は着物の両袖がよく見えるようにして、幻夜に披露する。
幻夜は靴を脱ぎながら満足そうに目を細めた。
「へぇ……いいじゃないか、沙和。帝都じゅうに見せびらかしてやりたくなる」
「ありがとうございます! 幻夜さまに喜んでいただけるように、一生懸命、選びました」
「そうか……」
幻夜が口元に拳を当てる。嬉しそう、なのだろうか。
「俺を喜ばせるのもいいが、沙和の好きなものにしたか?」
「実はこの生地の色、幻夜さまに拾っていただいたときの空の色みたいで、ひと目で気に入ったんです……!」
「うっ、そうか」
幻夜はまた口元に手を当てると、足元に敷かれた飛び石を離れへと歩く。沙和もそのあとをついて歩いたが、袴姿のときと同様に大股になったのがいけなかったのか、石畳につまずいた。
「ひゃっ」
「なんだ?」
ひとつ先の飛び石にいた幻夜がふり向いたそのとき、沙和はぶざまに転んでしまった。
「痛っ……」
「大丈夫か!?」
幻夜が手を差し伸べかけ、引っこめた。それには気づかず、沙和は立ちあがって着物の裾を軽く払う。