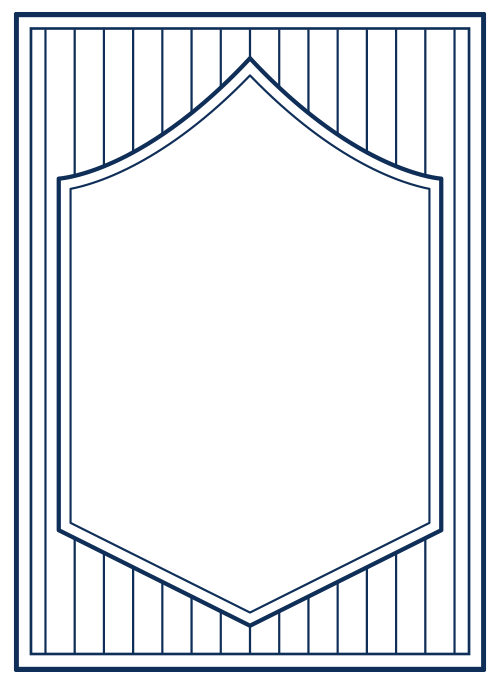「幻夜さま、わたしたちはいつのまに霧谷の村を出たのでしょう……?」
沙和が呆然とつぶやくと、瀟洒な玄関扉を開けようとした幻夜がふり向いて苦笑する。
「そもそも、村にいなかったからな」
「え? でも……それにしたって、川原を歩いていたはずなのに……ここはどこなのでしょう」
見慣れた川原の風景はいつのまにかぼんやりと薄れ、沙和はとある家に立っていた。
それも、家の前ではなく敷地の内側にいて、離れだという立派な洋館の玄関をくぐろうとしている。
「心配しなくても、現世の俺の家だ」
「では、ここは帝都なのですか」
趣のある庭は広々として、敷地には洋館のほかに平屋建ての日本家屋もあった。大きさを見るに、そちらが主屋なのだろう。
そのとき玄関扉が内側から勢いよく開き、女中が出迎えた。
「旦那様、お帰りなさいませ。まあ! お連れ様がいらっしゃるなら、連絡してくださればよかったのに」
「急で悪いが、これから沙和をここに置く。不便のないようにしてやってくれ」
「なんと、それは……! めでたいことです。沙和様、どうぞなんでもおっしゃってくださいな」
辰野と名乗った女中は、幻夜のひと回りほど年上だろうか。お喋りではきはきした印象を受ける。
沙和は挨拶すら満足に言う隙も与えられないまま、辰野に中へ引き入れられた。
「お邪魔、します。あの……めでたいことというのはなんですか?」
「それはですねえ、幻夜さまは」
「辰野。くっちゃべってないで、沙和を案内してくれ」
「旦那様ってば。女性の扱いには注意してくださいね。粗忽だと嫌われますよ」
幻夜は苦々しそうにしたけれど、辰野には頭が上がらないようだ。
でも、幻夜が辰野を大事にしている雰囲気は伝わってくる。沙和が引き取られた叔父夫婦の家とは大違いな様子に、緊張はすぐに解けた。
そうして、幻夜との暮らしが始まった。
日中、幻夜は屋敷を留守にする。冥府に赴いて、死者を受け入れたりしているらしい。
けれど、寂しいと感じる暇は少しもなかった。辰野があれやこれやと沙和の世話を焼きたがるからだ。
湯を使えばこれでもかというほど肌をぴかぴかに磨かれ、よい匂いのパウダーをはたかれる。髪はといえば専用の油を使ってていねいに梳られ、しっとりと濡れたような艶を引き出される。
仕上げに唇にはほんのり紅を差されれば、沙和は村での姿とは見違えるほどに美しくなった。
「あの、わたしは幻夜さまの元で働かせていただければじゅうぶんなのですが……」
「なにをおっしゃいますか! お洒落をしていただくのが、沙和様のお務めなんですよ」
さらに、衣服といえば色あせた巫女装束しかなかった沙和に、辰野はあれこれ着せるのが楽しくてしかたがないらしい。
「旦那様からも、沙和様には誰よりも美しく着飾らせるよう命じられておりますから」
辰野はその指示に忠実に従うつもりのようで、幻夜が贔屓にする呉服屋の店主まで呼び寄せた。
「沙和様は素材がよろしくていらっしゃるから、お着物でも洋装でも似合いますね!」
店主が用意した着物を、辰野はさっそく片っ端から沙和の体にに当てていく。
「どれでも好きなものを好きなだけ選ぶようにと、旦那様から仰せつかっておりますよ。沙和様は遠慮なさっちゃいけませんからね」
「でもわたし……自分で選んだことなんてなくて、どれが好きかも……」
好みを口にする機会なんて与えられなかったから、急に尋ねれても困惑しかない。
眉を下げた沙和に、辰野は手をぽんと叩いた。
「そういうことなら、ぜんぶ買い取りましょうか」
「そ、そんなのご迷惑になります! わかりました、わかりましたから。選びます!」
暴走しそうな辰野を押し留め、わからないなりに懸命に選ぶ。
目にも綾なる生地の数々から、沙和はいくつか着物に仕立ててもらうことになった。
さらに、一着はあったほうがいいという店主の言葉でドレスも仕立ててもらうことになる。
自分で自分の着たいものを選ぶ楽しみがこの世にあるのだと、沙和は初めて知った。
「なぜ、これほどよくしてくださるのですか?」
店主が帰ったのち、休憩に出されたお茶と茶菓子をいただきながら、沙和は尋ねた。
沙和がなかなか決められなくても、辰野は嫌な顔ひとつせず付き合ってくれたのだ。
「あら、それは訊くまでもないことですよ。旦那様が連れてこられたかたですからね! あの、誰とも一生結婚しないとおっしゃっていた旦那様がですよ?」
「誰とも結婚しない?」
辰野は手にしていた湯呑みを座卓に置き、「ええ」と首を縦に振る。
「沙和様はご存知だとお聞きしましたから申し上げますが、旦那様は少々……ご事情がおありでしょう? そのせいで、実体が揺らいでおられるのです」
沙和が呆然とつぶやくと、瀟洒な玄関扉を開けようとした幻夜がふり向いて苦笑する。
「そもそも、村にいなかったからな」
「え? でも……それにしたって、川原を歩いていたはずなのに……ここはどこなのでしょう」
見慣れた川原の風景はいつのまにかぼんやりと薄れ、沙和はとある家に立っていた。
それも、家の前ではなく敷地の内側にいて、離れだという立派な洋館の玄関をくぐろうとしている。
「心配しなくても、現世の俺の家だ」
「では、ここは帝都なのですか」
趣のある庭は広々として、敷地には洋館のほかに平屋建ての日本家屋もあった。大きさを見るに、そちらが主屋なのだろう。
そのとき玄関扉が内側から勢いよく開き、女中が出迎えた。
「旦那様、お帰りなさいませ。まあ! お連れ様がいらっしゃるなら、連絡してくださればよかったのに」
「急で悪いが、これから沙和をここに置く。不便のないようにしてやってくれ」
「なんと、それは……! めでたいことです。沙和様、どうぞなんでもおっしゃってくださいな」
辰野と名乗った女中は、幻夜のひと回りほど年上だろうか。お喋りではきはきした印象を受ける。
沙和は挨拶すら満足に言う隙も与えられないまま、辰野に中へ引き入れられた。
「お邪魔、します。あの……めでたいことというのはなんですか?」
「それはですねえ、幻夜さまは」
「辰野。くっちゃべってないで、沙和を案内してくれ」
「旦那様ってば。女性の扱いには注意してくださいね。粗忽だと嫌われますよ」
幻夜は苦々しそうにしたけれど、辰野には頭が上がらないようだ。
でも、幻夜が辰野を大事にしている雰囲気は伝わってくる。沙和が引き取られた叔父夫婦の家とは大違いな様子に、緊張はすぐに解けた。
そうして、幻夜との暮らしが始まった。
日中、幻夜は屋敷を留守にする。冥府に赴いて、死者を受け入れたりしているらしい。
けれど、寂しいと感じる暇は少しもなかった。辰野があれやこれやと沙和の世話を焼きたがるからだ。
湯を使えばこれでもかというほど肌をぴかぴかに磨かれ、よい匂いのパウダーをはたかれる。髪はといえば専用の油を使ってていねいに梳られ、しっとりと濡れたような艶を引き出される。
仕上げに唇にはほんのり紅を差されれば、沙和は村での姿とは見違えるほどに美しくなった。
「あの、わたしは幻夜さまの元で働かせていただければじゅうぶんなのですが……」
「なにをおっしゃいますか! お洒落をしていただくのが、沙和様のお務めなんですよ」
さらに、衣服といえば色あせた巫女装束しかなかった沙和に、辰野はあれこれ着せるのが楽しくてしかたがないらしい。
「旦那様からも、沙和様には誰よりも美しく着飾らせるよう命じられておりますから」
辰野はその指示に忠実に従うつもりのようで、幻夜が贔屓にする呉服屋の店主まで呼び寄せた。
「沙和様は素材がよろしくていらっしゃるから、お着物でも洋装でも似合いますね!」
店主が用意した着物を、辰野はさっそく片っ端から沙和の体にに当てていく。
「どれでも好きなものを好きなだけ選ぶようにと、旦那様から仰せつかっておりますよ。沙和様は遠慮なさっちゃいけませんからね」
「でもわたし……自分で選んだことなんてなくて、どれが好きかも……」
好みを口にする機会なんて与えられなかったから、急に尋ねれても困惑しかない。
眉を下げた沙和に、辰野は手をぽんと叩いた。
「そういうことなら、ぜんぶ買い取りましょうか」
「そ、そんなのご迷惑になります! わかりました、わかりましたから。選びます!」
暴走しそうな辰野を押し留め、わからないなりに懸命に選ぶ。
目にも綾なる生地の数々から、沙和はいくつか着物に仕立ててもらうことになった。
さらに、一着はあったほうがいいという店主の言葉でドレスも仕立ててもらうことになる。
自分で自分の着たいものを選ぶ楽しみがこの世にあるのだと、沙和は初めて知った。
「なぜ、これほどよくしてくださるのですか?」
店主が帰ったのち、休憩に出されたお茶と茶菓子をいただきながら、沙和は尋ねた。
沙和がなかなか決められなくても、辰野は嫌な顔ひとつせず付き合ってくれたのだ。
「あら、それは訊くまでもないことですよ。旦那様が連れてこられたかたですからね! あの、誰とも一生結婚しないとおっしゃっていた旦那様がですよ?」
「誰とも結婚しない?」
辰野は手にしていた湯呑みを座卓に置き、「ええ」と首を縦に振る。
「沙和様はご存知だとお聞きしましたから申し上げますが、旦那様は少々……ご事情がおありでしょう? そのせいで、実体が揺らいでおられるのです」