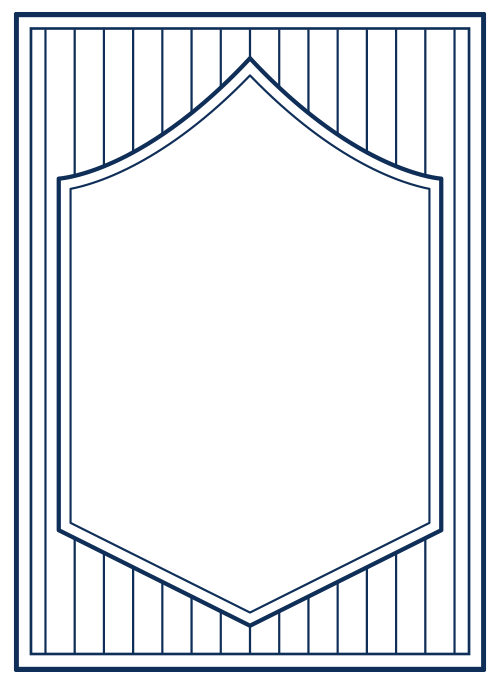粗野な響きのある口調だけれど、胸に心地よい声だ。びくっと肩が跳ね、沙和は声の主のほうをふり向いた。
新雪を思わせる白銀の髪を鎖骨の下まで髪を伸ばした青年が、沙和に近づいてくる。上下とも黒の洋装は、村では目にしたことがないものだ。
一本、芯が通ったような、すっとした立ち姿が沙和の目を奪う。
「あなたは……?」
「冥府の番人だ。ここは、死んだ者が冥府へと向かう道。俺は、こいつらが間違いなく冥府に入るのを見届けてる」
青年が前髪を払うと、夜の青みを帯びた切れ長の目が沙和を射抜く。
吸いこまれそうな色だ。それに、顔の輪郭まで無駄な部分がどこにもなく美しい。切れ味の鋭い刃を思わせる。ただ、鋭くはあっても、険しいとは思わなかった。
青年がさらに間合いをつめると、耳の上あたりに挿したかんざしで、銀髪の一部をまとめているのが目に入る。
「ここはまだおまえには早い」
沙和はあっ、と口に当てた。
「そうでした。わたし、川に放りこまれて……」
「放りこまれた? 誰にだ」
「いえ、今のはお聞き逃しください」
「誰だ。言ってみろ。ここで言ったところで、そいつには聞こえん。……ふぅん、身内か。巫女失格だとでも言われたか?」
「冥府の番人さまは、心の内もお読みになるのですか……!?」
「そんなわけあるか。その格好と、霧谷の村の事情を重ね合わせればだいたいわかる。庇うのは身内ってのも鉄板だろ。反吐が出るな」
青年は吐き捨てるように言って笑ったが、沙和を笑ったのではなく、どうやら叔母の仕打ちに向けたものらしい。
その昔、神の姿は誰にとっても目に見えるものだった。八百万の神は、米粒ほどの大きさから空を覆うものまで、いずれも人々のそばにあった。
しかし時代が下るにつれて、神々の大半が人の世を去っていく。残った神も、人の目から姿を隠すようになった。
多くの人々にとって、神は不可視のものになった。
「村の事情もご存知なのですか」
「特別な祈祷で鎮守の神を巫女に降ろし、巫女の口を通じて意思を伺う。だろ?」
沙和はこくこくとうなずく。
鎮守の神の加護を得て、霧谷の村は平穏な日々を維持してきた。
「でも、鎮守様に降りていただくように、頑張ったのですが……わたしは一度もできませんでした」
沙和が巫女になってから、異変が起きた。鎮守の神が降りなくなったのだ。
加えてこの一年半ほど、村は不作続き。村人たちは困窮に喘いでいた。
そのため、沙和は一刻も早く鎮守の神を降ろして神意を得るよう迫られていた。
神を降ろすための祈祷は丸一日かかる。飲まず食わずでの祈祷は辛かったが、村のため懸命に祈祷を行なった。
でも、鎮守の神は沙和に降りない。
一昨日も、沙和は役目を果たせなかったから……こんなことになったのだ。
「わたし、死んだのでしょうか?」
「まだ早いと言っただろ。よく聞けよ。今はまだ死んじゃいない。だが、丸きり無事なわけでもない。というか、おまえは村に戻りたいか?」
尋ねられて沙和はうつむいた。自分でもどうしたいのか、よくわからない。
戻らなければ死んでしまうのだろう。それは怖い。
けれど、戻ったところでどうなるというのだろう。役目も果たせず、家では邪魔者のままで。
新雪を思わせる白銀の髪を鎖骨の下まで髪を伸ばした青年が、沙和に近づいてくる。上下とも黒の洋装は、村では目にしたことがないものだ。
一本、芯が通ったような、すっとした立ち姿が沙和の目を奪う。
「あなたは……?」
「冥府の番人だ。ここは、死んだ者が冥府へと向かう道。俺は、こいつらが間違いなく冥府に入るのを見届けてる」
青年が前髪を払うと、夜の青みを帯びた切れ長の目が沙和を射抜く。
吸いこまれそうな色だ。それに、顔の輪郭まで無駄な部分がどこにもなく美しい。切れ味の鋭い刃を思わせる。ただ、鋭くはあっても、険しいとは思わなかった。
青年がさらに間合いをつめると、耳の上あたりに挿したかんざしで、銀髪の一部をまとめているのが目に入る。
「ここはまだおまえには早い」
沙和はあっ、と口に当てた。
「そうでした。わたし、川に放りこまれて……」
「放りこまれた? 誰にだ」
「いえ、今のはお聞き逃しください」
「誰だ。言ってみろ。ここで言ったところで、そいつには聞こえん。……ふぅん、身内か。巫女失格だとでも言われたか?」
「冥府の番人さまは、心の内もお読みになるのですか……!?」
「そんなわけあるか。その格好と、霧谷の村の事情を重ね合わせればだいたいわかる。庇うのは身内ってのも鉄板だろ。反吐が出るな」
青年は吐き捨てるように言って笑ったが、沙和を笑ったのではなく、どうやら叔母の仕打ちに向けたものらしい。
その昔、神の姿は誰にとっても目に見えるものだった。八百万の神は、米粒ほどの大きさから空を覆うものまで、いずれも人々のそばにあった。
しかし時代が下るにつれて、神々の大半が人の世を去っていく。残った神も、人の目から姿を隠すようになった。
多くの人々にとって、神は不可視のものになった。
「村の事情もご存知なのですか」
「特別な祈祷で鎮守の神を巫女に降ろし、巫女の口を通じて意思を伺う。だろ?」
沙和はこくこくとうなずく。
鎮守の神の加護を得て、霧谷の村は平穏な日々を維持してきた。
「でも、鎮守様に降りていただくように、頑張ったのですが……わたしは一度もできませんでした」
沙和が巫女になってから、異変が起きた。鎮守の神が降りなくなったのだ。
加えてこの一年半ほど、村は不作続き。村人たちは困窮に喘いでいた。
そのため、沙和は一刻も早く鎮守の神を降ろして神意を得るよう迫られていた。
神を降ろすための祈祷は丸一日かかる。飲まず食わずでの祈祷は辛かったが、村のため懸命に祈祷を行なった。
でも、鎮守の神は沙和に降りない。
一昨日も、沙和は役目を果たせなかったから……こんなことになったのだ。
「わたし、死んだのでしょうか?」
「まだ早いと言っただろ。よく聞けよ。今はまだ死んじゃいない。だが、丸きり無事なわけでもない。というか、おまえは村に戻りたいか?」
尋ねられて沙和はうつむいた。自分でもどうしたいのか、よくわからない。
戻らなければ死んでしまうのだろう。それは怖い。
けれど、戻ったところでどうなるというのだろう。役目も果たせず、家では邪魔者のままで。