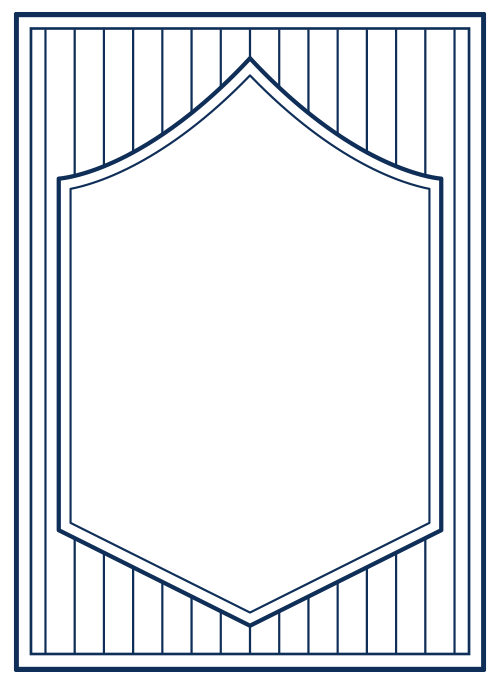抵抗するまもなく、沙和は叔母に引っ張られて境内を出る。
村へ戻るのかと思いきや、沙和は村外れの岩場に連れていかれた。
そこはちょっとした高台になっていて、谷底の川を見下ろすことができる。夏になれば子どもたちが度胸試しと称して、この岩場から川に飛びこむのが恒例だ。
ところが、今は水かさが増して流れも速さを増しているようだった。
ほどなく水の音にまじり、低く抑揚をつけた男たちの唄が川上からかすかに耳に届く。
「これは……葬送行列じゃ」
霧谷の村で古くから続く儀式を思い浮かべ、沙和は胸の前で祈りの形に両手を合わせた。
村で人死にが出ると、筵に包んだ死者をひと晩煙で燻す。その後、川に流すのだ。
村の男たちは葬送の文言を唱えながら川に沿って歩き、死者を冥府まで送り届ける。葬送行列は、夕刻に行われる。
今もちょうど山向こうに、太陽が沈むところだった。
男たちの唄が近づくとともに、燻されて薄黒く変色した筵の包みが川面を流れてくるのが目に入る。
川沿いには黒い服を着た、年齢も見た目も様々な男たちが付き添う。
「あれが昨日、この不作で死んだやつらだよ。あの筵を引く男たちは、葬送行列が終わったら、うちを襲うつもりなんですってよ! ……はっ、なんで知ってるのかって? うちの下男が怪しい動きをしてたから、問いつめたのに決まってるでしょうよ!」
沙和と同様にそちらへ目をやった叔母が、鼻を鳴らす。
その目が剣呑な光を帯び、沙和はひっと悲鳴をのみこんだ。
「ねぇ、全部あんたのせいでしょう? あんたが責任を負うべきでしょう?」
無意識に引こうとした腕が、ぐっと強くつかまれる。叔母の爪が肉に食いこむ。
沙和はあとずさろうとしたけれど、できなかった。叔母の力は思いのほか強い。
「――さあ、葬送行列に入れてもらいなさいよ。旦那様には、あんたが命でもって無能を謝罪したと伝えてあげるから。それで、あいつらもおとなしくなるでしょうよ」
言葉の意味を理解する前に、叔母の手を背中に感じた。突き落とされたのだと理解したときには、体が支えを失ったあと。
浮遊感を覚えたのを最後に、沙和の意識はそこでふつりと途切れた。
目を開けると、沙和は見知らぬ場所にいた。
頬がこけ、目元が落ちくぼんだ村人が三人、提灯を手に目の前の川を歩いている。
さっきまで、沙和が叔母と並んで見下ろしていた川だ。
筵に包まれた死者も、付き添って歩く黒服の男たちも見当たらない。
しかし沙和にはふしぎと、彼らが先ほど叔母が指した死者だとわかった。ただ、彼らがなぜ歩いていられるのかが、わからない。
それに岩場から落ちたにしては、沙和自身、どこにも痛みがないのも解せない。川に落ちたはずの沙和は、濡れてさえいなかった。
「どうして……?」
死者たちは川面を滑るように進む。
昼と夜が溶け合った色合いの空の下で、彼らは手になにか持っている。提灯かと思ったけれど、ホオズキのようだ。
ふと見れば、彼ら以外にもホオズキを手にした者たちが、川面を一列になって歩いていた。皆、口を閉ざしたままだ。
呆然と見ていたとき、低い男性の声で話しかけられた。
「なぜこんなところにいるんだ? 迷いこんだのか?」
村へ戻るのかと思いきや、沙和は村外れの岩場に連れていかれた。
そこはちょっとした高台になっていて、谷底の川を見下ろすことができる。夏になれば子どもたちが度胸試しと称して、この岩場から川に飛びこむのが恒例だ。
ところが、今は水かさが増して流れも速さを増しているようだった。
ほどなく水の音にまじり、低く抑揚をつけた男たちの唄が川上からかすかに耳に届く。
「これは……葬送行列じゃ」
霧谷の村で古くから続く儀式を思い浮かべ、沙和は胸の前で祈りの形に両手を合わせた。
村で人死にが出ると、筵に包んだ死者をひと晩煙で燻す。その後、川に流すのだ。
村の男たちは葬送の文言を唱えながら川に沿って歩き、死者を冥府まで送り届ける。葬送行列は、夕刻に行われる。
今もちょうど山向こうに、太陽が沈むところだった。
男たちの唄が近づくとともに、燻されて薄黒く変色した筵の包みが川面を流れてくるのが目に入る。
川沿いには黒い服を着た、年齢も見た目も様々な男たちが付き添う。
「あれが昨日、この不作で死んだやつらだよ。あの筵を引く男たちは、葬送行列が終わったら、うちを襲うつもりなんですってよ! ……はっ、なんで知ってるのかって? うちの下男が怪しい動きをしてたから、問いつめたのに決まってるでしょうよ!」
沙和と同様にそちらへ目をやった叔母が、鼻を鳴らす。
その目が剣呑な光を帯び、沙和はひっと悲鳴をのみこんだ。
「ねぇ、全部あんたのせいでしょう? あんたが責任を負うべきでしょう?」
無意識に引こうとした腕が、ぐっと強くつかまれる。叔母の爪が肉に食いこむ。
沙和はあとずさろうとしたけれど、できなかった。叔母の力は思いのほか強い。
「――さあ、葬送行列に入れてもらいなさいよ。旦那様には、あんたが命でもって無能を謝罪したと伝えてあげるから。それで、あいつらもおとなしくなるでしょうよ」
言葉の意味を理解する前に、叔母の手を背中に感じた。突き落とされたのだと理解したときには、体が支えを失ったあと。
浮遊感を覚えたのを最後に、沙和の意識はそこでふつりと途切れた。
目を開けると、沙和は見知らぬ場所にいた。
頬がこけ、目元が落ちくぼんだ村人が三人、提灯を手に目の前の川を歩いている。
さっきまで、沙和が叔母と並んで見下ろしていた川だ。
筵に包まれた死者も、付き添って歩く黒服の男たちも見当たらない。
しかし沙和にはふしぎと、彼らが先ほど叔母が指した死者だとわかった。ただ、彼らがなぜ歩いていられるのかが、わからない。
それに岩場から落ちたにしては、沙和自身、どこにも痛みがないのも解せない。川に落ちたはずの沙和は、濡れてさえいなかった。
「どうして……?」
死者たちは川面を滑るように進む。
昼と夜が溶け合った色合いの空の下で、彼らは手になにか持っている。提灯かと思ったけれど、ホオズキのようだ。
ふと見れば、彼ら以外にもホオズキを手にした者たちが、川面を一列になって歩いていた。皆、口を閉ざしたままだ。
呆然と見ていたとき、低い男性の声で話しかけられた。
「なぜこんなところにいるんだ? 迷いこんだのか?」