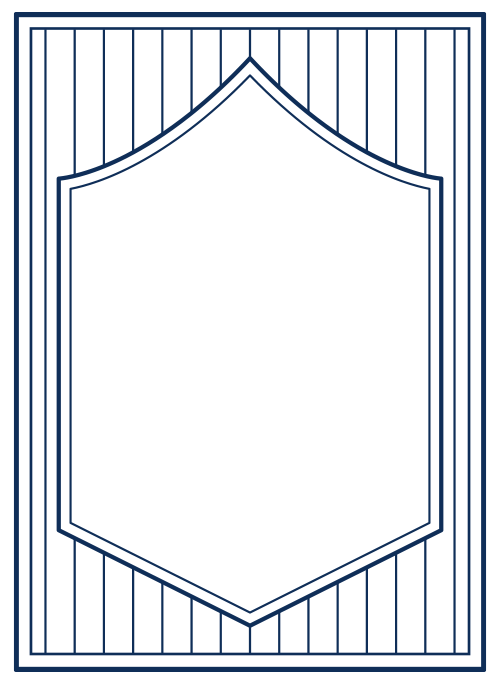「え?」
「その日、おっしゃいましたから。どなたか、そのとき旦那様を救ってくださったかたがいるそうで……誰とも結婚はしないが、そのひとのために生きると」
「そ……そうなんですか」
喜ばしいことのはずなのに、なぜだか声が沈んでしまい沙和は首をかしげる。
(そのかたのおかげで、幻夜さまは生きてくださったのに? そうよ、そのかたに感謝しましょう)
沙和は幻夜に救われて、ここにきた。だから少しでも幻夜の役に立ちたい。
(うん、まずはそこからだわ)
沙和はよし、と心の内で気を取り直した。里芋の煮物の味を見れば、出汁と醤油の味が染みてよい塩梅だ。
沙和は頬をゆるめた。若干まだ浅いけれど、幻夜が帰るころにはさらに味が染みるだろう。
辰野も、汁物の味の仕上がりを確認する。
「さあ、おつゆもできましたよ!」
「あ、わたしこの煮物に南天の葉を飾りたいから、取ってくるわね」
「まあ、細やかな。ありがとうございます」
沙和はハサミを手に土間から外に出る。辰野のつぶやきは、沙和の耳には届かなかった。
「あらやだ、旦那様が沙和様とは結婚なさるつもりでいらっしゃること、補足しそびれてしまいました……けどそれは旦那様がおっしゃいますよね!」
高階家の広い庭には、そこここに草木が植えられている。花が少ないものの、これはこれで趣がある。
(少しでも、幻夜さまの毎日が実の多いものになりますように)
庭の池近くに生えた南天には、まだ実の姿はない。けれど、沙和は願いをこめるようにして、葉の一部を切り取った。
その日の幻夜は、辰野が寝入ってから帰ってきた。
沙和はさっそく、火を入れ直した夕食を幻夜の前に並べる。上着を脱いだ幻夜が、相好を崩した。待てないとばかりに手を合わせる。
「いただきます」
幻夜の所作はひとつひとつが流れるようで美しい。帝都に広い屋敷を構えるところからいっても、上流階級の人間としての育ちを感じるけれど、それを除いても美しい。
沙和は座卓の向かいに座って、幻夜の様子にほうっと見入る。
「今日の煮物はうまいな」
「ほんとうに? 嬉しいです……! わたしが味付けと火加減を見たんですよ」
沙和が得意げに言うと、幻夜が苦笑した。
「辰野は、なんでもやわらかくしすぎるんだ。煮物も甘くすればいいと思ってる。俺をいつまでも赤ん坊扱いだ。実際、俺がぼうずのころから仕えてるわけだが」
「じゃあ、辰野が幻夜さまを味音痴だとおっしゃってたのって、もしかして……」
「辰野には言ってやるなよ。あれでも、一生懸命やってるんだ。それに漬物だけは絶品だしな」
「もちろんです」
「だが、できればこれからは、煮物はこの味付けがいいな」
幻夜が、ふたりだけの秘密だとでもいうように言う。沙和は幻夜にうなずいて笑った。
辰野の優しさも、幻夜の優しさも、あたたかい。
そのあたたかさがいつまでも続けばいいと、沙和は心から願った。それが存外早く、脅かされるなんてこのときは思いもしなかった。
「その日、おっしゃいましたから。どなたか、そのとき旦那様を救ってくださったかたがいるそうで……誰とも結婚はしないが、そのひとのために生きると」
「そ……そうなんですか」
喜ばしいことのはずなのに、なぜだか声が沈んでしまい沙和は首をかしげる。
(そのかたのおかげで、幻夜さまは生きてくださったのに? そうよ、そのかたに感謝しましょう)
沙和は幻夜に救われて、ここにきた。だから少しでも幻夜の役に立ちたい。
(うん、まずはそこからだわ)
沙和はよし、と心の内で気を取り直した。里芋の煮物の味を見れば、出汁と醤油の味が染みてよい塩梅だ。
沙和は頬をゆるめた。若干まだ浅いけれど、幻夜が帰るころにはさらに味が染みるだろう。
辰野も、汁物の味の仕上がりを確認する。
「さあ、おつゆもできましたよ!」
「あ、わたしこの煮物に南天の葉を飾りたいから、取ってくるわね」
「まあ、細やかな。ありがとうございます」
沙和はハサミを手に土間から外に出る。辰野のつぶやきは、沙和の耳には届かなかった。
「あらやだ、旦那様が沙和様とは結婚なさるつもりでいらっしゃること、補足しそびれてしまいました……けどそれは旦那様がおっしゃいますよね!」
高階家の広い庭には、そこここに草木が植えられている。花が少ないものの、これはこれで趣がある。
(少しでも、幻夜さまの毎日が実の多いものになりますように)
庭の池近くに生えた南天には、まだ実の姿はない。けれど、沙和は願いをこめるようにして、葉の一部を切り取った。
その日の幻夜は、辰野が寝入ってから帰ってきた。
沙和はさっそく、火を入れ直した夕食を幻夜の前に並べる。上着を脱いだ幻夜が、相好を崩した。待てないとばかりに手を合わせる。
「いただきます」
幻夜の所作はひとつひとつが流れるようで美しい。帝都に広い屋敷を構えるところからいっても、上流階級の人間としての育ちを感じるけれど、それを除いても美しい。
沙和は座卓の向かいに座って、幻夜の様子にほうっと見入る。
「今日の煮物はうまいな」
「ほんとうに? 嬉しいです……! わたしが味付けと火加減を見たんですよ」
沙和が得意げに言うと、幻夜が苦笑した。
「辰野は、なんでもやわらかくしすぎるんだ。煮物も甘くすればいいと思ってる。俺をいつまでも赤ん坊扱いだ。実際、俺がぼうずのころから仕えてるわけだが」
「じゃあ、辰野が幻夜さまを味音痴だとおっしゃってたのって、もしかして……」
「辰野には言ってやるなよ。あれでも、一生懸命やってるんだ。それに漬物だけは絶品だしな」
「もちろんです」
「だが、できればこれからは、煮物はこの味付けがいいな」
幻夜が、ふたりだけの秘密だとでもいうように言う。沙和は幻夜にうなずいて笑った。
辰野の優しさも、幻夜の優しさも、あたたかい。
そのあたたかさがいつまでも続けばいいと、沙和は心から願った。それが存外早く、脅かされるなんてこのときは思いもしなかった。