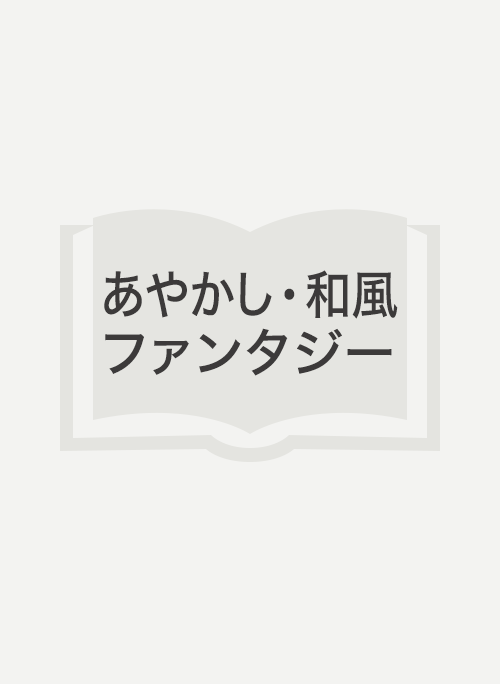千冬は灯璃に抱き上げられたまま彼の部屋に連れられていく。
先を歩いていた使用人が足を止めると両手が塞がっている灯璃のために襖を開ける。
「夕食の準備が出来次第、またお呼びします」
「ああ」
使用人は恭しくお辞儀をすると、その場を去っていく。
灯璃は革張りのソファに千冬をそっと降ろす。
(ここが灯璃さまのお部屋……)
少しだけ視線を動かすと本棚には多くの書物が、文机は書類らしきものが整理されて置かれている。
灯璃の部屋に、そもそも男性の部屋に入るのは初めてで緊張からか思わず身体に力が入ってしまう。
「緊張しているのか?」
あまり辺りをじろじろと見るのは失礼だと思い、俯いていると穏やかな声が降ってくる。
「は、はい……」
灯璃は隊服の首元のボタンを外しながら千冬の隣に座る。
そのたったひとつの所作が無垢な千冬にとって刺激的でとっさに見てはいけないと両手のひらで顔を隠す。
「何故顔を隠す?」
指と指の隙間からそっと見ると灯璃は不思議そうに首を傾げていた。
「えっと……」
自分の口から『貴方の色香で恥ずかしくなった』などととても言えない。
灯璃は普段通りに振る舞っただけで、これだけで恥ずかしさを抱いていては、この先が心配でしかない。
「もしかしてボタンを外すのを見て照れたのか?」
無意識に首元のボタンに目がいっていたのかすぐに気づかれてしまった。
「ち、違います」
図星をつかれたのに変な意地を張って誤魔化してしまう。
このままでは灯璃の調子に狂わされてしまいそうで、座る位置を一人分ずらして距離をとった。
「嘘はよくないと先ほども言っただろう?」
灯璃も負けじとこちらへ詰め寄ってくる。
もう誤魔化すのは無理だと思った千冬はソファから立ち上がろうとしたが灯璃が腕を伸ばして制止させた。
背中は肘掛けに当たり、逃げ場は無くなってしまった。
「い、意地悪です……」
何だか今日は一段と灯璃の雰囲気が違うような気がして、からかわれているようにも思える。
あまり言い返さない千冬でさえもぽろりと本音がこぼれてしまった。
「そうむくれるな」
灯璃は喉をくっと鳴らして千冬の頭に手を置いた。
それはまるで小さい子をなだめているようで……。
(何だかわたし、子どもみたい。でもすぐに恥ずかしくなって赤くなるところなんてまだまだ大人の女性には程遠いのだけれど)
年下の子の方がもっと大人びているのではと思えてしまう。
このままでは駄目だと千冬は思い切って顔を上げる。
「わたし、もっと成長できるように頑張ります」
「どうした急に」
千冬の突然の決意表明に灯璃は目を丸くしている。
物静かで冷静沈着な彼がこんな表情を浮かべるなど珍しい。
「どんなときでも落ち着いているような大人な女性になりたいです」
「表情がころころと変わる千冬も愛らしいと思うが」
「そ、それではまるで子どものようではありませんか?」
灯璃の横に立つ自分の姿を想像するが明らかに不釣り合いだ。
良妻賢母を目指すのならば、さらに行動のひとつひとつに磨きをかけなければいけない。
このままではいけないとわかっているのだが灯璃の優しく甘い言葉につい揺らぎそうになってしまう。
焦りが募って握りしめる拳に力が入る。
そこに灯璃の大きな手が重なった。
「千冬には千冬の良さがある。何事にも一生懸命なところも誰に対しても思いやりをもって接するところも私は大好きなんだ」
「でもこれから先、周囲に心ないことを言われるかもしれないですし……」
灯璃や使用人たちは親切だが他の者が何というか未知数だ。
瞳の色のこと、教養がないこと……。
そんな花嫁に他の鬼の分家やあやかしたちがついていきたいと思うだろうか。
将来について考えるたび、不安になるばかりでどうしていくべきかわからない。
灯璃は俯いていた千冬の顔に手を伸ばし顎をすくって持ち上げる。
「私がいるんだ。何も不安になる必要はない。きっと二人ならどんな壁も乗り越えていける」
「灯璃さま……」
決して揺るぐことはないまっすぐな瞳と強い想いが込められた言葉に心が楽になる。
「つらいこと、悲しいこと、不安なことをひとりで背負うことはないんだ。私は千冬には笑顔でいてほしいから」
灯璃は優しく瞳を細めると繊細な壊れものを扱うように千冬をそっと抱きしめた。
(過去のわたしは絶望しか感じられなかったけれど、誰かにこんなにも想われるなんてとても幸せなことなのね)
あのつらかった日々は一生、記憶から消えないだろう。
でもその分、自分には明るい未来が待っていたのかと思うと報われたようだ。
(もう少しこのままでいたい……)
ときどき灯璃や使用人たちに甘えてほしいと言われることがある。
でも甘え方がわからないのだ。
妹の依鈴の方が上手で考えは策士でもそれを誰も疑わずに自然と虜にさせてしまう。
こういうとき、いつもは灯璃に身を任せているけれどおそるおそる勇気を出して彼の隊服の一部を掴む。
「……!」
灯璃は掴まれた感覚に視線を動かすと千冬は耳を赤くさせていた。
抱きしめ返すまではいかなかったが、自分なりにかなり勇気を奮い起こしたのだろう。
どうしようもないほど灯璃は千冬が愛おしくなって抱きしめる腕の力を強めた。
(もう少しだけこのままでいたいと願ってもいいのかしら……)
この温もりを感じていたくて千冬はそっと瞳を閉じたのだった。
先を歩いていた使用人が足を止めると両手が塞がっている灯璃のために襖を開ける。
「夕食の準備が出来次第、またお呼びします」
「ああ」
使用人は恭しくお辞儀をすると、その場を去っていく。
灯璃は革張りのソファに千冬をそっと降ろす。
(ここが灯璃さまのお部屋……)
少しだけ視線を動かすと本棚には多くの書物が、文机は書類らしきものが整理されて置かれている。
灯璃の部屋に、そもそも男性の部屋に入るのは初めてで緊張からか思わず身体に力が入ってしまう。
「緊張しているのか?」
あまり辺りをじろじろと見るのは失礼だと思い、俯いていると穏やかな声が降ってくる。
「は、はい……」
灯璃は隊服の首元のボタンを外しながら千冬の隣に座る。
そのたったひとつの所作が無垢な千冬にとって刺激的でとっさに見てはいけないと両手のひらで顔を隠す。
「何故顔を隠す?」
指と指の隙間からそっと見ると灯璃は不思議そうに首を傾げていた。
「えっと……」
自分の口から『貴方の色香で恥ずかしくなった』などととても言えない。
灯璃は普段通りに振る舞っただけで、これだけで恥ずかしさを抱いていては、この先が心配でしかない。
「もしかしてボタンを外すのを見て照れたのか?」
無意識に首元のボタンに目がいっていたのかすぐに気づかれてしまった。
「ち、違います」
図星をつかれたのに変な意地を張って誤魔化してしまう。
このままでは灯璃の調子に狂わされてしまいそうで、座る位置を一人分ずらして距離をとった。
「嘘はよくないと先ほども言っただろう?」
灯璃も負けじとこちらへ詰め寄ってくる。
もう誤魔化すのは無理だと思った千冬はソファから立ち上がろうとしたが灯璃が腕を伸ばして制止させた。
背中は肘掛けに当たり、逃げ場は無くなってしまった。
「い、意地悪です……」
何だか今日は一段と灯璃の雰囲気が違うような気がして、からかわれているようにも思える。
あまり言い返さない千冬でさえもぽろりと本音がこぼれてしまった。
「そうむくれるな」
灯璃は喉をくっと鳴らして千冬の頭に手を置いた。
それはまるで小さい子をなだめているようで……。
(何だかわたし、子どもみたい。でもすぐに恥ずかしくなって赤くなるところなんてまだまだ大人の女性には程遠いのだけれど)
年下の子の方がもっと大人びているのではと思えてしまう。
このままでは駄目だと千冬は思い切って顔を上げる。
「わたし、もっと成長できるように頑張ります」
「どうした急に」
千冬の突然の決意表明に灯璃は目を丸くしている。
物静かで冷静沈着な彼がこんな表情を浮かべるなど珍しい。
「どんなときでも落ち着いているような大人な女性になりたいです」
「表情がころころと変わる千冬も愛らしいと思うが」
「そ、それではまるで子どものようではありませんか?」
灯璃の横に立つ自分の姿を想像するが明らかに不釣り合いだ。
良妻賢母を目指すのならば、さらに行動のひとつひとつに磨きをかけなければいけない。
このままではいけないとわかっているのだが灯璃の優しく甘い言葉につい揺らぎそうになってしまう。
焦りが募って握りしめる拳に力が入る。
そこに灯璃の大きな手が重なった。
「千冬には千冬の良さがある。何事にも一生懸命なところも誰に対しても思いやりをもって接するところも私は大好きなんだ」
「でもこれから先、周囲に心ないことを言われるかもしれないですし……」
灯璃や使用人たちは親切だが他の者が何というか未知数だ。
瞳の色のこと、教養がないこと……。
そんな花嫁に他の鬼の分家やあやかしたちがついていきたいと思うだろうか。
将来について考えるたび、不安になるばかりでどうしていくべきかわからない。
灯璃は俯いていた千冬の顔に手を伸ばし顎をすくって持ち上げる。
「私がいるんだ。何も不安になる必要はない。きっと二人ならどんな壁も乗り越えていける」
「灯璃さま……」
決して揺るぐことはないまっすぐな瞳と強い想いが込められた言葉に心が楽になる。
「つらいこと、悲しいこと、不安なことをひとりで背負うことはないんだ。私は千冬には笑顔でいてほしいから」
灯璃は優しく瞳を細めると繊細な壊れものを扱うように千冬をそっと抱きしめた。
(過去のわたしは絶望しか感じられなかったけれど、誰かにこんなにも想われるなんてとても幸せなことなのね)
あのつらかった日々は一生、記憶から消えないだろう。
でもその分、自分には明るい未来が待っていたのかと思うと報われたようだ。
(もう少しこのままでいたい……)
ときどき灯璃や使用人たちに甘えてほしいと言われることがある。
でも甘え方がわからないのだ。
妹の依鈴の方が上手で考えは策士でもそれを誰も疑わずに自然と虜にさせてしまう。
こういうとき、いつもは灯璃に身を任せているけれどおそるおそる勇気を出して彼の隊服の一部を掴む。
「……!」
灯璃は掴まれた感覚に視線を動かすと千冬は耳を赤くさせていた。
抱きしめ返すまではいかなかったが、自分なりにかなり勇気を奮い起こしたのだろう。
どうしようもないほど灯璃は千冬が愛おしくなって抱きしめる腕の力を強めた。
(もう少しだけこのままでいたいと願ってもいいのかしら……)
この温もりを感じていたくて千冬はそっと瞳を閉じたのだった。