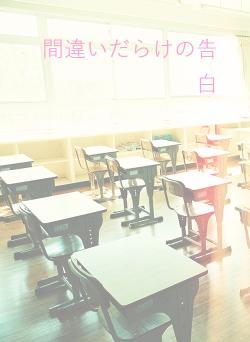私は立ち上がり、陛下の口を覆わず両手で軽くふさいだ。
不敬罪だって分かってる。分かってるけど。でもでもでもでも。こんな風に誰かに言われたことなんてないし。こんなストレートな言葉は、逆に私には強すぎる。
うううう。こんな時はどうしたらいいの? 喜ぶべきなのだろうけど。あああ、顔が顔が熱いよぅ。影武者にされた方がマシだって思えるくらい、違う意味でダメージを受けてる自分がいた。
「顔が真っ赤だぞ」
「誰のせいだと思っておられるのですか!」
「俺は見たまま、思ったままのことしか言わん」
「そ、それは! ううう。もう少し何かに包んでください」
「そういう周りくどい言い方は好きではないからな」
皇帝陛下がこんな感じでいいのかしら。いいえ、そうね。皇帝陛下だから、許されるのか。長身で線は細いのに、どこか力強い。
赤みがかった黒い瞳は私など比較にならないほど鋭く、それでいて私に微笑む姿を見ていると、どこまでが本気でどこまでが嘘なのか分からなくなってくる。
「他にもあるが、それは追々でいいさ。俺にとっては特に重要なことではない。むしろまずは蓮花の女官たちは俺の手の者で揃え、護衛を強化する。みすみす伏魔殿の餌食になんぞさせぬさ」
「……ありがとうございます」
「あとは宦官としているこの空燕も、基本的にはそなたを護る者とさせよう」
「宦官としている?」
「あああ。オレは宦官ではないんですよ、皇后さま」
「その呼び名はちょっと……。って、宦官ではないっていうのはどういうことなのですか?」
空燕は顎でクイっと、陛下を指す。基本的にこの後宮へ出入りできる男性は宦官だけ。浮気とか不義を防ぐために、ずっとそうなってきていたはず。
「空燕は元々俺の腹心であり、将軍だ。まぁ、その顔を知る者はみんな今頃あの世だからな。ちょうどいいから、宦官を演じさせている」
「えええ。えええ。演じって」
「ちゃんとまだ付いてるし、コトが片付けば元の部署に戻すつもりだ」
なんていうか、なんていうのか……無茶苦茶ね。腹心である将軍を宦官に仕立てあげるだなんて。通りで武骨だし、宦官って感じではないとは思ったのよ。
だって見た目もクマみたいだし。
「空燕様になにをさせようとなさっているのですか?」
「なに、簡単さ。そなたに頼むのと同じで、後宮の膿を出し、俺の世に必要のない者たちを排除する」
「後宮の……膿」
「皇后の下となる四妃は、家臣たちに選ばせる。元より前の政権の者たちは皆排除したものの、まだ俺の世に不満を持つ者は多いだろう」
「それをあぶり出すおつもりなのですね」
「俺と皇后に従わない者は皆、排除する。そして妃になるのはいいが、冷宮でも良いと思う者だけが娘を差し出すように言っておいてくれ」
「かしこまりました」
思った以上に責任は重大で、きっとやることは山のようにある気がする。でも陛下……暁明の言いかけた言葉も気になるし、それ以上に私は――
「引き受けてくれるか蓮花」
「賜りました暁明様」
今までただ何もない日々だった。使命や運命や人の期待も。だから一度くらい、誰かの何かのために生きてみるのも悪くない。
むしろどこか、この先の騒動を思い浮かべ、楽しみになってきた自分がいた。
不敬罪だって分かってる。分かってるけど。でもでもでもでも。こんな風に誰かに言われたことなんてないし。こんなストレートな言葉は、逆に私には強すぎる。
うううう。こんな時はどうしたらいいの? 喜ぶべきなのだろうけど。あああ、顔が顔が熱いよぅ。影武者にされた方がマシだって思えるくらい、違う意味でダメージを受けてる自分がいた。
「顔が真っ赤だぞ」
「誰のせいだと思っておられるのですか!」
「俺は見たまま、思ったままのことしか言わん」
「そ、それは! ううう。もう少し何かに包んでください」
「そういう周りくどい言い方は好きではないからな」
皇帝陛下がこんな感じでいいのかしら。いいえ、そうね。皇帝陛下だから、許されるのか。長身で線は細いのに、どこか力強い。
赤みがかった黒い瞳は私など比較にならないほど鋭く、それでいて私に微笑む姿を見ていると、どこまでが本気でどこまでが嘘なのか分からなくなってくる。
「他にもあるが、それは追々でいいさ。俺にとっては特に重要なことではない。むしろまずは蓮花の女官たちは俺の手の者で揃え、護衛を強化する。みすみす伏魔殿の餌食になんぞさせぬさ」
「……ありがとうございます」
「あとは宦官としているこの空燕も、基本的にはそなたを護る者とさせよう」
「宦官としている?」
「あああ。オレは宦官ではないんですよ、皇后さま」
「その呼び名はちょっと……。って、宦官ではないっていうのはどういうことなのですか?」
空燕は顎でクイっと、陛下を指す。基本的にこの後宮へ出入りできる男性は宦官だけ。浮気とか不義を防ぐために、ずっとそうなってきていたはず。
「空燕は元々俺の腹心であり、将軍だ。まぁ、その顔を知る者はみんな今頃あの世だからな。ちょうどいいから、宦官を演じさせている」
「えええ。えええ。演じって」
「ちゃんとまだ付いてるし、コトが片付けば元の部署に戻すつもりだ」
なんていうか、なんていうのか……無茶苦茶ね。腹心である将軍を宦官に仕立てあげるだなんて。通りで武骨だし、宦官って感じではないとは思ったのよ。
だって見た目もクマみたいだし。
「空燕様になにをさせようとなさっているのですか?」
「なに、簡単さ。そなたに頼むのと同じで、後宮の膿を出し、俺の世に必要のない者たちを排除する」
「後宮の……膿」
「皇后の下となる四妃は、家臣たちに選ばせる。元より前の政権の者たちは皆排除したものの、まだ俺の世に不満を持つ者は多いだろう」
「それをあぶり出すおつもりなのですね」
「俺と皇后に従わない者は皆、排除する。そして妃になるのはいいが、冷宮でも良いと思う者だけが娘を差し出すように言っておいてくれ」
「かしこまりました」
思った以上に責任は重大で、きっとやることは山のようにある気がする。でも陛下……暁明の言いかけた言葉も気になるし、それ以上に私は――
「引き受けてくれるか蓮花」
「賜りました暁明様」
今までただ何もない日々だった。使命や運命や人の期待も。だから一度くらい、誰かの何かのために生きてみるのも悪くない。
むしろどこか、この先の騒動を思い浮かべ、楽しみになってきた自分がいた。