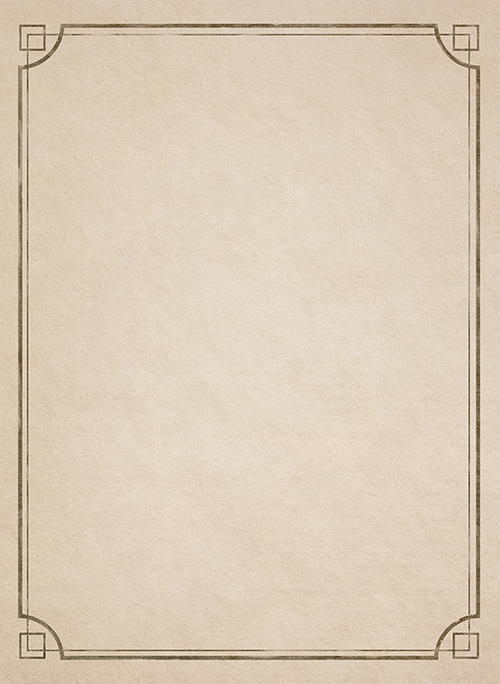一二年前の事だ。ある男が、自身の車に息子を乗せてドライブに出かけた。
彼は平日には仕事に勤しみ、妻に代わって育児を担っていた。男にとってそれは普段はあまりない息子を独占できる絶好の機会であったため、自ら子供の面倒を見ようと妻に打診したのだ。
そうしてできたのが、平日は彼の妻、休日には彼自身がメインとなって面倒を見るという生活のスタイルだった。男にとって、妻の胸裏を全て読み取れるわけではないのだが、少なくとも表面上妻はこのスタイルについて納得してくれているようだった。
だからこそ、こうして男はいつものように息子を車に乗せ、どこか遠い場所へと向かっている。
息子は二ヶ月後に小学校の入学を控えている年齢だった。もう一人で歩き回れるし、会話もできる。男はそんな息子に向かってどこへ行きたいかを尋ねた。だが息子からの返答はと言えば、昨日テレビで見た芸能人の名前を叫ぶだけである。
男は苦笑して、とりあえず家から遠く離れた場所へと車を走らせた。具体的な目的地は設定していない。そのうちに見えてきた場所に車を停めようとだけ考えた。
国道五八号線を進み、やがて右折して県道一四号線へと入る。山の中を縫うようにして通っている細い道を通り抜け、B市に入った。
そこで見つけた海沿いの公園に車を停車させ、二人仲良くあたりを散策した。
すぐそこには青い海と白い砂浜が見えた。視界を埋め尽くしそうな二つの景色の中に入り込むようにして、遠くの方に緑の山が見える。
男は息を呑んだ。自分でも気が付かないうちに口が半開きになっていて、手を繋いで歩いていた息子も似たようなリアクションを見せた。
男が凄いな、綺麗だなと言うと、息子はそれに反応して可愛らしい雄叫びのような声を上げた。こんなに小さい子供であっても魅了できる景色が、眼前に広がっているのだ。
親子二人は靴を脱いで砂浜を歩いた。まだ泳ぐには寒い季節だからなのか、付近には海水浴客の姿はない。人の姿は全く見えない。
息子が無邪気に砂山を作り、かと思えば蹴飛ばしているのを眺めているうちに時間は過ぎていった。時間が経つほどに小さな子供の遊びに対する勢いは衰えていき、やがて飽きてしまったのかその場に座り込んでしまった。
男は息子に声をかけた。
「涼太、遠くの方に灯台があるんだ。見に行かないか」
灯台が何かをよくわかっていない、と言う様子の我が子に彼は、奥の方に見える大きな白い塔を指差した。
砂浜で遊んで消費した体力は元に戻ったらしく、息子は両手をあげて「行く!」と答えた。男は微笑んで、小さな手を握って歩き出した。
砂浜を出て靴を履き再びアスファルトの地面を歩いていくと、五分ほどで灯台の足元まで来る事ができた。
しかし灯台の周囲はフェンスで囲まれており、何者かの侵入を拒んでいた。中に入るための扉には関係者以外立ち入り禁止と書かれた紙まで貼り付けてある。
「ごめんな涼太。灯台の中には入れないみたいだ」
男は下を向いて謝った。
視線の先では我が子が玩具を取り上げられた時のように泣いているのかもしれないと言う予想をした。しかしその予想に反して、息子には特に代わった様子は見受けられなかった。
小さな子供は何故か、一点のみを見つめてその場に立ち尽くしている。
「涼太?」
男が話しかけるが、反応はない。
この時彼の息子には、あるものが見えていた。
青い紐状の物体だ。それは風を受けた時の凧のように上下左右、好きなように動き回っている。半透明なのであるが、必ずそこに存在している。
どこから伸びてきたものなのか、男の子はそれを確かめるためにあたりを見回したが、持ち主らしき存在はいない。
視線を戻すが、変わらずそれはそこに存在し続けていた。
試しに手で掴んでみようとするが、握った手のひらを開いても何もなかった。つかめてはいないのだ。
「どうした、何かあったか?」
男が尋ねた。子供は首を振った。
その後も二人は歌など歌いながら、初めて見る景色を眺めたりしながら有意義な時間を過ごした。
そして一二年の月日が流れた。
あの時は小さかった子も流れていく時間の中で成長を続け、人並みの幸福を噛み締め、不幸を悲しんだりした。
高校に入学するタイミングで両親から自転車を買い与えられ、休日には最大限活用をして様々な場所へと走った。
ある日、A市の灯台へと少年は向かった。もしかすると幻が見えるようになる、と言われている灯台だ。
少年がスマートフォンで景色を撮影しようとすると、視界に青い紐状の何かが映し出された。
驚いて目を擦ってみるとそれはもう消えていた。少年は噂話が本当だったのだと喜んだが、真相は違う。
その映像は、日々絶えず積み重ねられる記憶の中から、無意識のうちに持ち上げたものだった。
昔見た景色と共通するものを目の当たりにした事で、想起されたものだ。彼自身の記憶の断片なのだ。
しかし本人はその事を覚えていない。話に聞いていた内容が真実であったのだと思い込んでいる。
少年は意気揚々とその場を後にした。これから自転車に跨りペダルを漕いで、帰路に着くのだ。
そんな彼の背後では、青い海が陽光を受けてキラキラ輝いていた。
彼は平日には仕事に勤しみ、妻に代わって育児を担っていた。男にとってそれは普段はあまりない息子を独占できる絶好の機会であったため、自ら子供の面倒を見ようと妻に打診したのだ。
そうしてできたのが、平日は彼の妻、休日には彼自身がメインとなって面倒を見るという生活のスタイルだった。男にとって、妻の胸裏を全て読み取れるわけではないのだが、少なくとも表面上妻はこのスタイルについて納得してくれているようだった。
だからこそ、こうして男はいつものように息子を車に乗せ、どこか遠い場所へと向かっている。
息子は二ヶ月後に小学校の入学を控えている年齢だった。もう一人で歩き回れるし、会話もできる。男はそんな息子に向かってどこへ行きたいかを尋ねた。だが息子からの返答はと言えば、昨日テレビで見た芸能人の名前を叫ぶだけである。
男は苦笑して、とりあえず家から遠く離れた場所へと車を走らせた。具体的な目的地は設定していない。そのうちに見えてきた場所に車を停めようとだけ考えた。
国道五八号線を進み、やがて右折して県道一四号線へと入る。山の中を縫うようにして通っている細い道を通り抜け、B市に入った。
そこで見つけた海沿いの公園に車を停車させ、二人仲良くあたりを散策した。
すぐそこには青い海と白い砂浜が見えた。視界を埋め尽くしそうな二つの景色の中に入り込むようにして、遠くの方に緑の山が見える。
男は息を呑んだ。自分でも気が付かないうちに口が半開きになっていて、手を繋いで歩いていた息子も似たようなリアクションを見せた。
男が凄いな、綺麗だなと言うと、息子はそれに反応して可愛らしい雄叫びのような声を上げた。こんなに小さい子供であっても魅了できる景色が、眼前に広がっているのだ。
親子二人は靴を脱いで砂浜を歩いた。まだ泳ぐには寒い季節だからなのか、付近には海水浴客の姿はない。人の姿は全く見えない。
息子が無邪気に砂山を作り、かと思えば蹴飛ばしているのを眺めているうちに時間は過ぎていった。時間が経つほどに小さな子供の遊びに対する勢いは衰えていき、やがて飽きてしまったのかその場に座り込んでしまった。
男は息子に声をかけた。
「涼太、遠くの方に灯台があるんだ。見に行かないか」
灯台が何かをよくわかっていない、と言う様子の我が子に彼は、奥の方に見える大きな白い塔を指差した。
砂浜で遊んで消費した体力は元に戻ったらしく、息子は両手をあげて「行く!」と答えた。男は微笑んで、小さな手を握って歩き出した。
砂浜を出て靴を履き再びアスファルトの地面を歩いていくと、五分ほどで灯台の足元まで来る事ができた。
しかし灯台の周囲はフェンスで囲まれており、何者かの侵入を拒んでいた。中に入るための扉には関係者以外立ち入り禁止と書かれた紙まで貼り付けてある。
「ごめんな涼太。灯台の中には入れないみたいだ」
男は下を向いて謝った。
視線の先では我が子が玩具を取り上げられた時のように泣いているのかもしれないと言う予想をした。しかしその予想に反して、息子には特に代わった様子は見受けられなかった。
小さな子供は何故か、一点のみを見つめてその場に立ち尽くしている。
「涼太?」
男が話しかけるが、反応はない。
この時彼の息子には、あるものが見えていた。
青い紐状の物体だ。それは風を受けた時の凧のように上下左右、好きなように動き回っている。半透明なのであるが、必ずそこに存在している。
どこから伸びてきたものなのか、男の子はそれを確かめるためにあたりを見回したが、持ち主らしき存在はいない。
視線を戻すが、変わらずそれはそこに存在し続けていた。
試しに手で掴んでみようとするが、握った手のひらを開いても何もなかった。つかめてはいないのだ。
「どうした、何かあったか?」
男が尋ねた。子供は首を振った。
その後も二人は歌など歌いながら、初めて見る景色を眺めたりしながら有意義な時間を過ごした。
そして一二年の月日が流れた。
あの時は小さかった子も流れていく時間の中で成長を続け、人並みの幸福を噛み締め、不幸を悲しんだりした。
高校に入学するタイミングで両親から自転車を買い与えられ、休日には最大限活用をして様々な場所へと走った。
ある日、A市の灯台へと少年は向かった。もしかすると幻が見えるようになる、と言われている灯台だ。
少年がスマートフォンで景色を撮影しようとすると、視界に青い紐状の何かが映し出された。
驚いて目を擦ってみるとそれはもう消えていた。少年は噂話が本当だったのだと喜んだが、真相は違う。
その映像は、日々絶えず積み重ねられる記憶の中から、無意識のうちに持ち上げたものだった。
昔見た景色と共通するものを目の当たりにした事で、想起されたものだ。彼自身の記憶の断片なのだ。
しかし本人はその事を覚えていない。話に聞いていた内容が真実であったのだと思い込んでいる。
少年は意気揚々とその場を後にした。これから自転車に跨りペダルを漕いで、帰路に着くのだ。
そんな彼の背後では、青い海が陽光を受けてキラキラ輝いていた。