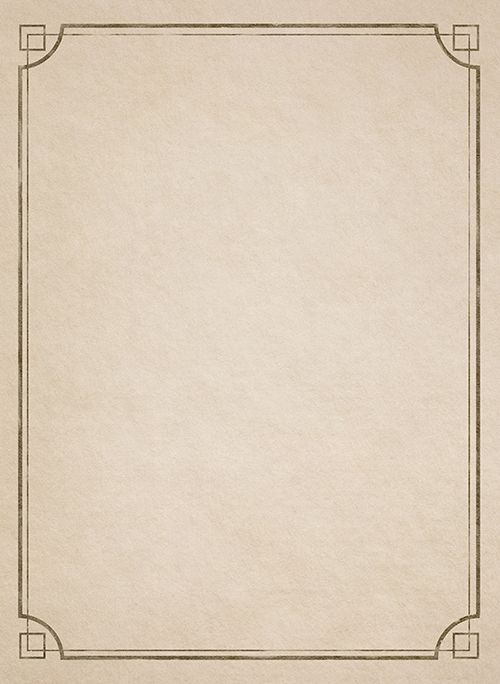終わらせたと思った瞬間には、もう二回目が始まっていた。
気づけば赤ん坊になって抱えられている。
大好きだった小説の世界でしかあり得ないと思っていた。違う世界での二回目。心が少しだけ踊る自分を嫌悪する。私にとって一回目はついさっきなのに。
――もう一度、チャンスをやる。
そう神様に言われてるような気がして、なんとなく、この時はやり直すことができる気がした。
あんなに苦しいと、死にたいと思ったいたのに別人になれたから。切り替えて、忘れて、無かったことにできて。そんな世界に救いを求められた。救われたと思い込めた。
前世の記憶を全て持って生まれたことにはきっと意味がある。この後悔を胸に刻んで、もう一度だけ生きてみよう。そう思ってしまった。
「あなたの名前はハル!」
この世界でそう名付けられた私は特別だったから。
◇
家は質素ではあったが、両親は私が生まれた時、泣いて喜んでくれた。特に母は私が女の子であったことが何よりも嬉しそうだった。
「……すごい」
両親とは似ても似つかない。白い髪に赤い瞳。
誰からみてもわかる特別な容姿。
鏡をみると可愛すぎて、自分で驚くほどだった。
これが私なんだって認識するのには時間がかかった。
そして、前世の記憶が更に私を特別にしていく。
物心ついた時には大人を含めても、村の中で私に敵う人なんて誰1人いなかった。
知識も、経験も、何もかも。この世界より遥かに進んでいる世界の記憶を持つ私はなんでもできた。だけど、それだけじゃない。
「ハル? 火をつけて」
「ママ、わかった……!」
右手を掲げて、燃えろと思うと薪はあっという間に火に包まれる。
前世の記憶なんてものが霞むほどの力。私は魔法と呼ばれる奇跡を持っていた。
王国と呼ばれているこの国で、数年に一度、生まれればいい方と言われているらしい。
左右の腕にはそれを示す刻印が生まれつき存在している。
魔法を使用したいと思うと、刻印が光り輝く。
魔法使いには一人につき、一つの能力が与えられて生まれてくる。それがこの国の常識とされているらしい。少なくとも、この辺境と呼ばれる田舎ではそう伝えられている。
だけど、私はその特別な魔法使いの中でも、さらに特別だったらしい。
火の魔法で薪を燃やす。
水の魔法で様々な用途の水を作れる。
風の魔法で空を飛び、木を切り裂く。
土の魔法で壁を作り、外敵の侵入を妨害する。
氷の魔法で食べ物を保存する。
なんでも、なんだってできた。この一回目よりも進んでいない世界では、私の力は何よりも特別で替がきかない。
だけど、最初はすぐに限界を迎えていた。この力の代償でもあるのだろう。限界を迎えると息苦しさで意識が遠くなる。心臓が痛くなって気持ち悪い。
母に言わせると、苦しそうにしてる時は少しだけ攻撃的になっているらしい。
それでも、使えば使うほど魔法を使用できる時間が伸びていく。私は大丈夫になっていく。
いつの間にか、両親に心配されることもなくなってきた。成長を能力で実感できる。私は強くなっている。
魔法の感覚は特別だ。こうしたいと思えばなんとなく使える。ただそれだけなのに。
「ハル! ありがとう!」
「うん!」
私は必要とされた。
「ハルちゃんはすごいねー!」
「そんなことないよ!」
私を特別に思ってくれた。
「今日もよろしく」
「はい!」
だから、人の役に立たなきゃ。
「いつもありがとう」
「えへへー……」
その気持ちを糧に頑張り続けた。
気づけば、私が操る五つの魔法は、ここに住む人の生活を全く別のものに変えていた。何が変わったのか説明できないほど。
私の魔法で村の人も、両親も喜んでくれる。ママは頭を撫でて、抱きしめてくれた。心はそれだけで満たされていく。
そうして生活していく中で気がついた。
「ハル〜、掃除できないから離れてー」
「やだ」
特別だけど? 特別だから?
どちらかはわからないけど、精神だけはなぜか歳相応のものとなっている。頭ではわかっていても、身体や気持ちが子供のような反応をしてしまう。
いや、元々こんなものなのかもしれない。きっと、私の心は全く成長できなかったんだろう。
それでも、本当に奇妙な感覚だった。でも、私は子供だから。それで納得させていた。それ以上に嬉しかった、誇らしかった。目を逸らしていただけなのに。
この刻印が私を特別だと示してくれる。
私は変われてる。
私は強くなっている。
私は成長できている。
私は二度と失敗しない。
私は誰よりも特別なんだ。
「あなたは将来、きっとこの国の王様になる」
それがどういう意味か全く理解していなかったが、私は大人にそう言われて育ってきた。
◇
特別な私は人の命を救うようにもなった。魔物と呼ばれている化物が存在していて、これまで多くの人を殺してきたらしい。
ここから離れた場所では多くの人が犠牲になっていると聞かされた。いてもたってもいられなかった。
これは特別な私の特別な使命だ。考えるより先に行動していた。
襲われている場所を訪れ、特別な力で人を救う。
魔物と呼ばれる存在に恐怖はない。私は違うのだから。
助けた人に声をかけて、英雄を気取る。
「大丈夫ですか?」
「ありがとう……。本当にありがとうございます……」
感謝されることは何事にも変え難い喜びで、私を突き動かしていく。幼い子供が考えるような正義の味方になれると思った。だから、風の魔法を使って移動し、周辺を見回る。
そして襲われた人を見つけては、物語のヒーローのように次々と救ってみせた。この危険な世界で物を運ぶ人、移動しなきゃならない人、集落ごと全てを奪われようとしている人。そんな人達を救って、救って。
「ありがとう……ございます……」
「どういたしまして!」
感謝されることが、本当に嬉しい。この世界で私は本当の意味で特別になれた。その誇りは確かに私を縛っていく。
ある日のこと、目の前が赤色に染まっている光景を見た。そこには、うずくまって、泣いて、絶望している人。
「ごめんな、さい……」
ある時、間に合わずに犠牲になってしまった人がいた。
私がもっとはやく、駆けつけることができれば、目の前にいる人は泣いていなかった。わからないけど、胸が張り裂けそうになる。
「……ごめんなさい」
もっとはやく、もっと魔法を使って、時間を作って。
そう願って、惜しみなく魔法を使う。変えてしまった生活を維持して、助けを求めている人を救う。それができないなら生まれた意味を失うから。だから、頑張った。
でも、ヒーローを続ければ続けるほど、犠牲が出ることは珍しくなくなっていく。
「足りなくて、ごめんなさい」
昔のことを思い出して、苦しくてもたない。胸の真ん中が痛い。
だから私は楽になるために、自分勝手を押し付けた。
「笑って!」
泣いている人には笑ってほしい。
「大丈夫だよ……!」
後悔してる人には前を向け。
そんな言葉を、失って傷ついてる人に平然と吐ける自分自身に、心底吐き気がした。
それでも魔物を、化け物を、片っ端から殺した。
私は人を救いづづけた。必死に人の役に立とうと努力した。
大好きな人達に笑顔で快適な生活をしてもらうため。
理不尽に奪われて、泣く人を一人でも少なくするため。
私の目の前で泣く人がいないように。そのためだったら、全力で闘った。
「っ、痛い……」
心臓が、心が痛い。どちらが痛いのかわからなくなっていく。息がうまく吸えない。
でも、これは治るから。誰かを救えれば人の笑顔をみれば治るから。
「はぁ、はぁ……」
感謝されて、褒められて、特別で。そんな私を支えてくれるママは、今日も「よくやったね」って褒めてくれる。この空間だけは救いで、私は間違ってないって思える。それだけで大丈夫なんだ。
でも、いつからだろう。
「ねぇ、私は頑張ったよ?」
「ハル……。偉いね……」
そう言って私の頭を撫でる母の手が震えだしたのは。
「ママ、大丈夫?」
「……大丈夫よ」
そんな痛そうな顔で笑うようなったのは。
「褒めて、抱きしめて、愛して」
暗い森で一人きりになり、呟く。
言えない。私のことで苦しませたくない。
「失敗してない、間違ってない」
抱きしめてくれることもなくなった母を思いながら。
でも、涙は流さない。流してはいけない。
何も思ってない。何も感じてない。
違う、違う、違う。だけど、ぽっかりと空いた心がつぶやく。
――私が怖いの?
そう、ママに言ってしまえって。
言えなかった。私はそれでも必死に守った。村の生活を支えて人々を救う。そんな特別な使命を持った私の生活は数年続いた。
◇
繰り返しのいつものを過ごす。
だけど、今日は少しだけ酷かった。その光景は酷すぎて目を覆いたくなる。
駆けつけた時には、一人の女の子を残して全員殺されていた。
私は最後に残された女の子を救う。
その子の顔を覗き込むと、何もかもを失っていて、あの日に鏡でみた私みたいで、その目だけは鮮明に覚えている。
だから、そんなものは見たくなくて、痛みを誤魔化すために、その子に無理矢理笑わせる。くだらない冗談を言って、それでも無理なら手をつかって口角を持ち上げて。大丈夫って言い聞かせるように呟く。これも、いつものことだから、大丈夫。
「いこう……?」
「うん」
その子が落ち着いた後は手を引いて、人のいる場所を目指す。
できるだけ明るく振る舞って、不安になってほしくないから話しかける。信用できる人に引き渡した後、その子は抱きしめられて泣いていた。
いたくて、いたくて、おかしくなりそう。
女の子は振り返って、私に何かを伝えようとする。
「あ、あの……!」
「ごめん、行かなきゃ」
だけど、その子の顔をみると泣きだしてしまいそうで。
こんな姿を見られたくなくて、その子を雑に置いて逃げてきた。そんな、いつも通りのなんて事のない日常。
ちょっと、ちょっとだけ酷かった。それだけの日。
そのはずだった。
「いたい、いたい……」
だけど、いつもとは少しだけ違ってしまった。
疲れ切って帰った後、母と喧嘩をしたんだ。
二回目の人生で、はじめての喧嘩。
きっかけは些細なことだった、と思う。
記憶が白くて、うまく思い出せない。
怒りで感情が昂り、母の手にある食器を魔法で壊してしまったのは覚えている。その時に耳に入った言葉も。
「化物……」
その瞬間、見えているもの全てが赤く染まる。
「ママ……?」
母だったものが、目の前で倒れて動かない。
いつもは綺麗に掃除されている台所は真っ赤に染まっている。そして、気づく。取り返しのつかないことをした事実に気づいてしまった。
私は魔法を全く制御できなかった。
「……え? なに、これ?」
前世の記憶があり、半端に大人を気取っていたが、感情を全く制御できなかった。
抑えきれなくなった感情が爆発し、大切な人を、ママを殺した。
自分自身がこんなにも愚かで、ただ無駄に長く生きただけのクソガキだったなんて思わなかった。
魔法がこんなに恐ろしいものだなんて知らなかったんだ。
――だから、私は悪くない。
呪文のように心の中で繰り返す。
魔法の恐ろしさは私が1番知ってるはずなのに。
目の前の赤黒い光景が目に焼き付く。
そうだ、お父さんは?
ゆっくりと振り返る。
「ぁ……、あ……ッ……!」
私を見るパパの目は、恐怖で染まっていた。
一歩踏み出した時、パパは確かに言った。
「くるな……! 化物!」
私は意識を失った。
◇
次に目を覚ました時、私は拘束されて牢屋に転がされていた。
その後のことは、よく覚えていない。意識が朦朧としていて、何も感じることができなかった。
私は、王都と呼ばれている場所に送られることになったらしい。理由はよくわからないが、私を殺すわけにはいかないと。まだ生きなきゃならないことに絶望した。
数日が経ち、迎えがきた。
村の誰にも会うことなく、拘束されたまま雑に馬車に押し込まれる。
意識がはっきりとしないまま馬車で何日も揺られ、見たこともない広い庭の大きな家で開放された。
「ここがハル様のお屋敷になります」
そして、私は家の一室に引き篭もった。
逃げるように走り込んで、知らない部屋に閉じ篭もる。
本当に静かで、なんの音もしない。
数人いるらしい使用人も、パンを部屋に放り投げる以外は化物である私が恐ろしいのか近寄ることもない。
特別な力を持っても、私の末路は同じらしい。
本当にいるのであれば神様も、さぞガッカリしていることだろう。いや、前世よりも酷い結末となったことで、力を与えたことを後悔しているはずだ。
魔法の恐ろしさは、私が一番に理解していなきゃいけないはずだった。私の腕に刻まれた特別である証は、気づけば呪いにかわっている。
それを手で引っ掻いて消そうとする。だけど、血が出て真っ赤になるだけ。
前世の記憶を持ちながらも、特別に溺れて母を殺した。
力だけは特別が与えられでも、心は何も成長してない。生きた年だけ無駄に重ねてきた、大人を気取るクズ。
それがこの世界で、ハルと呼ばれた私。
この暗い一人きりの部屋で二回目を終えるのだろう。
二回も与えられて、二回も失敗した。
化物の私は膝を抱えながら、今日もまた涙を流す。
あの赤黒い光景だけが瞼の裏に残って、他の記憶は少しずつ剥がれていった。