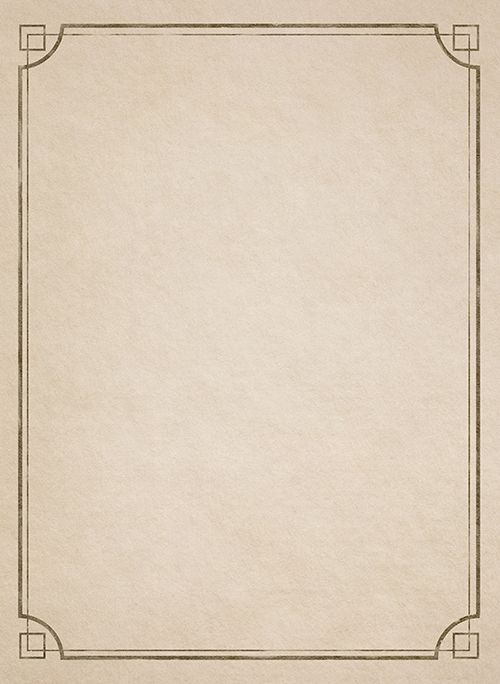1回目の人生は普通だったと思う。
ごく普通の家庭に生まれ、両親に愛された幼少期。
女の子だったからか、父からは溺愛された。
容姿はアイドル並みに可愛いとはとてもいえないが、整っていると一般的には言えるだろう。
親友なんて呼べる大切な人もできた。お互い勉強の成績では多少の上下はあったけれど、同じくらいの真ん中。
私は読書が好きで、彼女は運動が好き。
そんな少しの違いも心地よかった。
そこそこの高校とそこそこの大学を親友と一緒に卒業して、別々の会社ではあったが内定を貰い、その時にはじめて道が別れた。
特筆することの全くない人生。
何かの才能があったわけでもない。
特別な使命があったわけでもない。
でも、幼い頃は特別になりたいとは思っていたと思う。
何かになりたいっていう夢はあったし、なれるという自信も持っていた。忘れてしまったけれど、その気持ちがあったことだけは覚えている。
だけど、歳を重ねて周りを見渡した時に、みんなと同じになっている自分に気づいた。いつの間にか、人生の目標は「普通」になることへ変わっていた。
みんなという実態のないものに擬態して、幸せだって思われてる道を何も考えずに進む。
私もそうだったように、多くの人が同じだと思う。
見える世界が広がれば広がるほど、「普通」である自分の行ける道は狭いと知る。
そして、夢を諦めるのではなく忘れるのだ。諦めた理由は後付けでその場限りのもの。自分を納得させるためについた嘘。
これからは普通に仕事をして、悲しことがあればいつものように親友と愚痴を言い合って、誰もがするような恋愛をして、そこそこの年齢で結婚をする。子供を産んで育てて、役目を終えたら、大好きな人とずっと一緒にいて、大切な人達に囲まれて幸せに死ぬ。
そんな「普通」の人生を送るんだろう。それはきっと、幸せなはず。私は漠然とそう考えていた。
けれど、私はそんな普通の人生で誰にでも起こる、ありきたりな挫折に耐えられなかった。
順調に進んでいたはずの「普通」。でもはじめて、なんてことのない仕事でミスをしてしまった。それは些細なミスだったと思う。でも、私の心には傷がついた。同僚も気にするな、よくある事だ、なんて声をかけてくれて励ましてくれる。
でも私は、それからもミスをし続けた。
新入社員なら当たり前だったのかもしれない。
できていること、役に立ったことも当然あった。
褒められもしたし、感謝を言葉にしてもらった。
けれど、失敗はそれ以上にしたと思う。そして、ミスの回数を重ねるごとに減っていく励まし。反比例するように増えていく心の傷。それに私は押し潰されそうだった。
頼まれていたことをすぐに忘れてしまう。相手の名前を間違えて怒られる。物覚えが悪く、一度聞いたことを何度も確認する。数え出したらキリがない。
気づけば、心には失敗をしたということだけが残っていた。
そして、ミスをしないように恐る恐る仕事をしていた私は、それまではできていたことまで、また一つ、また一つとできなくなっていく。
何度も同じミスを繰り返して呆れられた。
人よりも時間がかかり、気づけば残業も当たり前になった。明日の仕事にいくことが怖くて眠れなくなった。
日に日に減っていく食事の量。休日は、趣味の読書をすることすらできず、意識がある中、ただ横になるだけ。
それでも大丈夫と自分に言い聞かせて、誰にも相談せず、全てを自分で抱え込んだまま過ぎていく日々。
今までだって間違いは侵してきて、それでも大丈夫だったから。無理矢理にでも身体を起こして、会社と家を往復した。
そしてなんでもない普通の日。
起き上がって会社に向かおうと、朝にシャワー浴びて、着替えをする。いつも通りの変わらない日常。
でもその日は少し違った。またミスをする。また迷惑をかけてしまう。怒られて、人に失望される。
――怖い
ドアノブに手をかけ、家を出ようとした瞬間、強烈な吐き気が私を襲った。
胃の中を全て吐き出しても止まらない吐き気。
立っていられないほどの目眩で棚にぶつかる。平衡感覚は失われて、玄関に崩れ落ちた。
会社に行くことが怖くて怖くてたまらない、全てを投げ出して逃げ出したい。心の悲鳴が確かに聞こえた。
その時、私は全てを理解した。
――あぁ、壊れてしまった。
私の人生は普通であるはずだった。この挫折だって長い人生のほんの一部で、歳を重ねた時に、そんな時もあったねって笑える時期が来るはずと信じてた。
でも、私の心は普通なんかじゃなかった。普通の人より壊れやすく脆い。本当に弱すぎて笑えてくる。
一度、壊れたら戻らない。ガラクタ以下の不良品。
それが私の心だった。身体から全てが抜け落ちていく。
残ったのは心が壊れてしまったという事実。そして、こんなことにすら耐えられない自分への失望だった。
もしかしたら、誰も怒ってなんていなかったかもしれない。失望なんてしてなかったのかも。だけど、私はこの程度のことで壊れてしまえるような人間だという事実。
それは私をひたすらに孤独にした。
それからの日々は散々だった。
月に何度か病院と自宅を往復する。
それ以外の日は家に引き篭もる。
涙すら流れなくなって、感情が動かない。
なにもしない、なにもできない。暗い部屋で横になり、閉じこもる。
怯えて、震えながら日々を過ごした。
そんなある日、親友が来てくれた。
こんな不良品である私を気にかけてくれた。
きっと、ぎこちなく笑えていたと思う。
昔の楽しかった話をいっぱいしてくれたから。
そして、真剣な表情で手を握りながら語りかけてくれる。
いつまでも側にいるよって言ってくれた。
立ち止まった私を連れ出そうとしてくれた。
こんな私を変えようとしてくれた。
何も持ってない私に手を差し伸べてくれた。
「ねぇ、これからも一緒に歩いていこう?」
私が1番欲しい言葉を言ってくれた。
でも、そんな優しさを見た時、心が急に黒く染まった。
「うるさい!」
私はその手を乱暴に振り払ってしまった。
それからひたすら、思ってもない言葉を吐き続ける。
不良品である私の心から溢れ出てしまった醜い言葉の数々は、私達の時間を終わらせるには十分すぎた。
飛び出していく前に見せた彼女の顔は忘れられない。
同じだと思ってた親友が、すごく特別に見えた。
羨ましくて妬んでしまった。
――あなたは私と同じではなかったの?
そんな醜い、身勝手で彼女を傷つけた。
私は「普通」ですらない。
成長できずに大人になれない、ずっと子供のまま。
大切な人を傷つけて、そのことで自分も傷ついて。
そんな身勝手でクズで醜い、ゴミ以下の人間だった。
洗面台の鏡で私の顔をみる。
「こいつは、死ぬべきだ」
そう思ってしまったその日に、間違いだらけの人生を終わらせた。
私は自分で自分を殺しました。
どうですか?
これが不良品である私の、失敗だらけの一回目です。
こんな人間は消えた方がいい。誰もがそう思ったと信じています。
だから、これで間違いは終わるはずだったのに……。