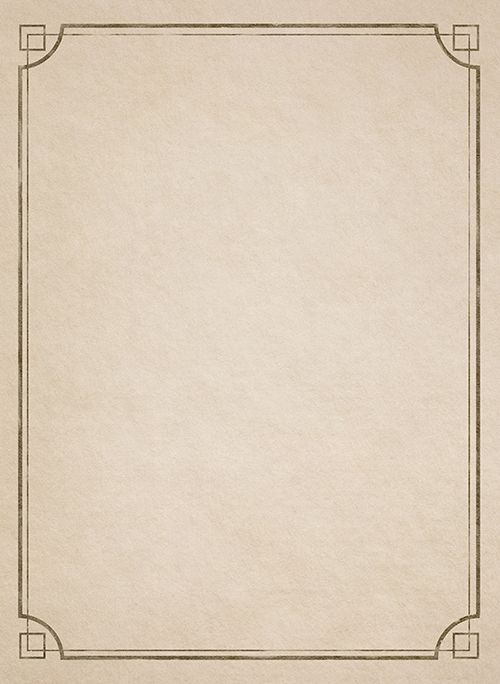「はやく逃げなさい!!!」
私を必死に逃がそうと、目の前で死んでいく人達。
そんな状況でも、全てを持ってるはずの私は、泣いて這いつくばりながら、赦しをこうことしかできなかった。
◇
私は恵まれていたと思う。
優しいお父様とお母様に大きなお家。
橙色の髪と青い瞳。誰からも羨ましがられ、褒められた容姿。家族のような従者達にいっぱいの友達。
女でありながら何をやらせても負けなしの才能。
そして神から授かったとしか思えない、大切な人を護ることができる大きな力。
それを証明する背中にある刻印。直接見みることができないけれど、それは私が特別であることの何よりの証明だった。
私は生まれてきてから何かで負けたことなんてなかった。
私は全てを持って生まれたのだと思っていた。
この力があればなんでも守れる。どんな人でも救うことができる。誰にも負けない才能を持ってる。
傲慢でわがままで、世間知らずな愚かな人間。
それが何もかも、幼い私だった。
そんな私は、王都という場所に行くと決まったらしい。
どこかって? そんなことはこの時の私も知らなかった。それぐらい物事を知らない小さな子供だったんだ。
そして、この大好きな場所を辺境と呼ぶことは後で知ることになる。
特別な役目を与えられる。誰かに求められて、選ばれて、違う場所に行くと知った時は誇らしかった。
自分が特別な人間だと確信できたから。
そして、最後になるかも知れないと、家の人達ほぼ全員と小さな旅をすることになった。馬車も新しいものを王都から借りて、大好きな人達みんなで。
何人か知らない人達も混じっていたが護衛らしい。
王様という偉い人に求められた私に何かあってはいけないから、そう言われたのを覚えている。
馬車に揺られ、楽しく会話をして。目的地に着いたと言われた時は、急いで駆け出した。
何となく覚えているのは綺麗な湖と木々。もう簡単には見られなくなるからって、両親が一番好きだという場所に連れて行ってもらった、はず。
今では風景の形しか覚えていない。匂いも、感触も、感じたことも、忘れてしまった。
楽しい時間は一瞬で、過ぎていった時に感じたことが、心の中にかすかに残るだけ。
そんな短い旅の帰り道、両親は様々なことを本音で話してくれた。
記憶にないほど幼い日々の出来事や私の知らない私について。今までの思い出を語り合った。
そして、本当はまだ行かせたくないこと。私を一人にすることが心配で、眠れない日々が続いたという両親の本音。
本当にいろんなことを話してくれた。
でも、私が娘で誇らしいと、最後は泣きながら抱きしめてくれた。
記憶の中にある思い出は絵のように綺麗で動かない。
魔物という化け物に襲われたのは、そんな時だった。
誰かの悲鳴と叫び、助けを求める声。この外では命が失われている。そう思った私は馬車から飛び出す。
両親は大きな声で、私を止めようとしていたと思う。
だけど、今は関係ない。私がこの人達を守るんだ。私じゃなきゃできないことがきた。最後の恩返しだと、そう思った。
私は特別だから、大丈夫だと。
きっと、気持ちが昂っていて周りが見えてなかったんだと思う。
私の特別は、目の前の現実に押しつぶされた。
飛び出した先に見える、とてつもない数の魔物に圧倒されて動けなくなった。足が震えて立っていられない。人生ではじめて恐怖を覚えた。
「――」
そして、次々と私を守って大切な人達が死んでいく。
私を守るために叫びながら身代わりになる、家族のように大切に思っていた従者。
そして、最愛のお父様とお母様は、私が気づいた時に殺されていた。
私はどうしようもないほどに、無力なんだと思い知らされた。けれど、現実は絶望する隙すら与えてくれない。
大切な人は、次々と殺されていった。
目の前に広がった光景を信じられない。この人達よりも大きな力を持っている。この人達を護るのは全てを持っているこの私。
けど、私は護っていると思い込んでいた人達に護られながら、無様に這いつくばることしかできなかった。
私が持っていると勘違いしていたものは、本当は持っていないと突きつけられ、あれだけ溜め込んでいた自信は価値を持たない塵のように踏みつけられる。周りを見渡せば、何も、誰も、残っていない。
化け物に私を全部奪われた。私は何もかも失ってしまった。
残されたのは、無力で無様な私だけ。
目の前に迫る真っ赤な化け物が視界を覆い尽くす。
這いつくばる私を見下ろす。それは私を嘲笑うかのようにも見えて、また、涙を流そうとする。けど、私の目からは何も出ない。
「……もう、いいかな」
まだ、ほんの少ししか生きてない。
何も成し遂げていない。
こんなところでは死ねない。
そんな思いも、もう全て涙と一緒に流れてしまった。
大切を全て失った私は、まともに生きてはいけないだろう。
だから、もう、いい。
私は目を閉じてその時を待つ。
その瞬間、私を包み込むように風が吹いた。
「もう、大丈夫」
聞いたこともない声、笑いながら目の前に立つ少女。
おそらく、私より幼いであろう小さな少女に視線が釘付けになる。
あれだけ不快な音で満たされていたのに、時間が止まったように静かだ。
「あ……、ぅえ……」
永遠と思えるような時から抜け出して周りを見る。気づけば、目の前にあった脅威は全てなくなっていた。
混乱する私に彼女は笑いながら微笑む。
私は小さな身体に包まれた。本当に、本当に小さい。だけど、暖かかった。
「頑張ったね……」
そう言って私と目線を合わせようとしゃがむ彼女。
私は安心と後悔でぐちゃぐちゃになり、涙が込み上げる。
「もう大丈夫だから、泣かないで……」
全て枯れたと思っていたのに、どうしようもなく流れて止まらない。そんな私の涙を拭って彼女は言った。
「笑って!」
彼女はこの悲惨な光景をみて、状況を理解している。
それなのに、そんなことを言う彼女。この時の感情は今でも名前をつけられない。
だけど、確かに残ってる。仕草も、会話も、表情も。彼女に触れられている感覚も。
全てが綺麗で、何一つ、忘れてない。
「みててよ〜! ……え?」
彼女は不器用ながらもなんとか私を笑わせようと、必死に試行錯誤していた。
「あれ〜でないな〜。芸には自信あるのに〜!!」
しばらく私に触れながら、あーでもない、こーでもないと何かをしようとする。
「なんにもできない!!!」
最終的に彼女はなにかを諦めた。そして、彼女の小さな手が私の顔を包み込み、左手の人差し指で涙を拭われて、右手の親指で口角を無理矢理持ち上げられる。
「そんな顔をしないで……笑ってよ……」
そう私に告げる彼女。
でも、私はもう知ってしまった。
「私は、もう笑えない……」
現実、そして自分を知りすぎてしまったから。
二度と自分を信じられなくなったから。
大切な人達を失ってしまったから。
「それでもだよ」
「なんで!!!」
感情が昂って怒鳴ってしまった。呼吸がうまくできない。辛い、痛い、苦しい。
「……うーん、そうだ!」
だけど、そんな時に困ったような顔をして、笑いながらあなたは言ったよね。
「笑った方がかわいいよ!」
「……なにそれ」
「あ、やっと笑ったね……!」
その笑顔は、生涯忘れられないと思う。
この時のことを一言一句忘れたことなんてない。
あの時に持った感情の答えは、今も見つからない。
だけど、私は私に誓ったんだ。
人生の意味はこの時に決まった。