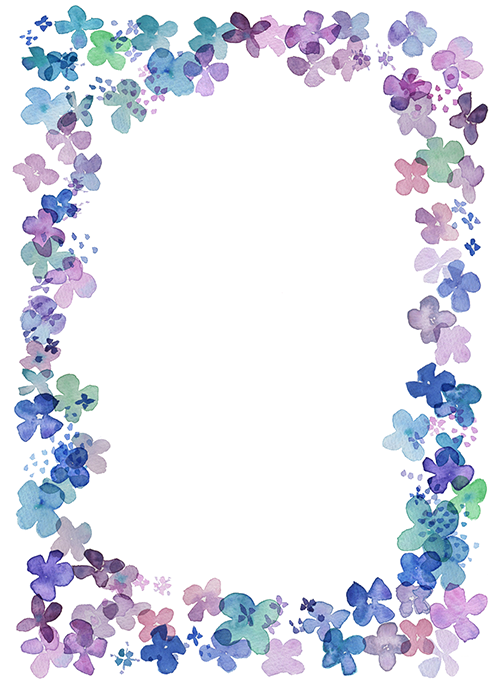「おい」
「あっせんせー」
夏休みの屋上は灼熱の地獄だ。アスファルトの上ですら暑いと言うのにそれより数十メートルも太陽に近い位置が涼しい訳がない。四階まで登るのに息切れをし、額に汗を滲ませる俺に対して、「先生」と笑いかけてきた彼女は涼し気な顔で夏風に目を細めていた。
「どうしたの?屋上になんか用?」
「どうしたの?じゃねえよ。君が何度も屋上から飛び降りようと試みるから君の担任から苦情が来てんだよ」
「えへへぇ、しょーがないよねぇ」
しょうがなくねえよ、なんてツッコミを入れる気力すら湧かない。生徒指導になって初めて分かったこの苦行。どこの誰かも知らない生徒の苦情、問題行動を俺一人で抱えるなんてあまりにも重荷が過ぎる。なおかつそれを優しい言葉で更生させようなんて……。考え出すと頭の中が気温も相まってぐちゃぐちゃに混ざって卒倒しそうになる。
しかし、この生徒は問題を起こし過ぎて幾度となく顔を合わせてきた、いわば問題行動のレジェンド、晴れて殿堂入りを果たした彼女に優しい言葉をかけるなんて気遣いはいらない。
「とっとと家に帰れー、俺も仕事あんだよ。君の飛び降りバンジージャンプに付き合ってる暇ない」
「またまた~、そんなこと言って~。さっき校舎裏に呼び出されて一年生に告白されてたの見てたよぉ」
「……」
「こんぱる先生、モテモテなんだね」
「あ゛ー、よりにもよって見られたのお前かよ……」
俺は頭を抱えてその場にうずくまる。最悪だ、他の生徒ならまだよかった。適当な言葉使ってなだめたり、叱ったり。
けど、彼女はどんな言葉を掛けたって制御不能だ。明日にでも皆に言いふらされてたら告白してくれた子に合わせる顔がない。
俺は脳みそを高速回転して今の状況を改善する方法を必死に考えた。その結果出てきた言い訳がこれだった。
「あれはアレだろ、ほら、思春期特有のさ。俺のことを好きなんじゃなくて大人の男性を好きになっちゃった自分が好き……みたいな?」
ハハッとその場を取り繕う笑みを浮かべる。
しかし目の前の少女は逡巡の間で青い絹のような髪を左右に揺らす。
「多分違うよ、それ」
「え」
「あの子、前から先生のこと好きって噂あったし」
「ま、まぁ噂って人に伝わる度に話デカくなるからな」
「先生にフラれて一人になったあと、その場で暫く固まってから号泣しだしたし」
「……本当か?」
俺が目を丸くして問いかけると、「大マジ」と一番聞きたくない言葉が返ってきた。
その言葉で一連の出来事がフラッシュバックする。
告白してくれた少女に俺はどんな顔でどんな言葉を掛けたんだっけ。
対してちゃんと言葉を受け止めもせずへらっと笑って「ありがとな」という言葉は掛けなかったような気がする。
凄く申し訳ない。けれど、生徒の俺に向けた気持ちが本物だって思えなかったのだ。生徒の言葉を信じることが先生という職業だというのに。
「ねぇ先生?」
キーンと金属が震える音が突然響いた。顔を上げれば少女がビー玉のような澄んだ瞳でこちらを見ていた。
その片足は、地上数十メートルの高さの柵に掛けられている。少し風でも吹いてしまえば、彼女の細い体はそのまま奈落に落ちてしまいそうだった。
そんな状況で君は俺に笑いかけてくる。
「もし私が告白したらどうする?」
「そりゃ……まぁ……断るしかない、だろ?」
自分で言っておきながら頭の中は何故かハテナマークでいっぱいだった。生徒と教師の間の恋愛なんて成立するわけないし、何より相手がこいつなんてありえない。それだというのに、何故躊躇う必要があるのだろう。自分でした行動だというのに自分が一番分かっていないような気がした。挙動不審な俺を見て目の前の彼女は一瞬、瞬きすら惜しんで俺の顔を穴が開くほど見つめてきた。
数秒後、すうっと目尻を下げしなやかな睫毛を震わせた彼女は一言。
「変なひと」
そう呟く口元はひどく愉快に見える。言葉とは裏腹に表情からは俺を非難するような感情は感じ取れず、むしろ少し嬉しそうだった。
「今の俺からすればお前の方こそ変な人だよ」
本当に変な人だ。屋上からバンジージャンプなんて破天荒なことをしておきながらあんな表情もできるなんて。
「今なら飛び降りれるかも、わたし」
「それは国語教師の俺だから言ってる?」
「さぁどーだろうねぇ」
君は二葉亭四迷の言葉を知っているだろうか。
彼はとあるロシアの小説を翻訳する時「愛してる」をとある言葉に訳した。
「……俺が死なれたら困るんだよ」
ボソッと呟いた言葉は誰にも届かず、自分の胸にすとんと落ちるわけでもなく。
ただ喉の奥にいつまでも苦く張り付いていた。
「あっせんせー」
夏休みの屋上は灼熱の地獄だ。アスファルトの上ですら暑いと言うのにそれより数十メートルも太陽に近い位置が涼しい訳がない。四階まで登るのに息切れをし、額に汗を滲ませる俺に対して、「先生」と笑いかけてきた彼女は涼し気な顔で夏風に目を細めていた。
「どうしたの?屋上になんか用?」
「どうしたの?じゃねえよ。君が何度も屋上から飛び降りようと試みるから君の担任から苦情が来てんだよ」
「えへへぇ、しょーがないよねぇ」
しょうがなくねえよ、なんてツッコミを入れる気力すら湧かない。生徒指導になって初めて分かったこの苦行。どこの誰かも知らない生徒の苦情、問題行動を俺一人で抱えるなんてあまりにも重荷が過ぎる。なおかつそれを優しい言葉で更生させようなんて……。考え出すと頭の中が気温も相まってぐちゃぐちゃに混ざって卒倒しそうになる。
しかし、この生徒は問題を起こし過ぎて幾度となく顔を合わせてきた、いわば問題行動のレジェンド、晴れて殿堂入りを果たした彼女に優しい言葉をかけるなんて気遣いはいらない。
「とっとと家に帰れー、俺も仕事あんだよ。君の飛び降りバンジージャンプに付き合ってる暇ない」
「またまた~、そんなこと言って~。さっき校舎裏に呼び出されて一年生に告白されてたの見てたよぉ」
「……」
「こんぱる先生、モテモテなんだね」
「あ゛ー、よりにもよって見られたのお前かよ……」
俺は頭を抱えてその場にうずくまる。最悪だ、他の生徒ならまだよかった。適当な言葉使ってなだめたり、叱ったり。
けど、彼女はどんな言葉を掛けたって制御不能だ。明日にでも皆に言いふらされてたら告白してくれた子に合わせる顔がない。
俺は脳みそを高速回転して今の状況を改善する方法を必死に考えた。その結果出てきた言い訳がこれだった。
「あれはアレだろ、ほら、思春期特有のさ。俺のことを好きなんじゃなくて大人の男性を好きになっちゃった自分が好き……みたいな?」
ハハッとその場を取り繕う笑みを浮かべる。
しかし目の前の少女は逡巡の間で青い絹のような髪を左右に揺らす。
「多分違うよ、それ」
「え」
「あの子、前から先生のこと好きって噂あったし」
「ま、まぁ噂って人に伝わる度に話デカくなるからな」
「先生にフラれて一人になったあと、その場で暫く固まってから号泣しだしたし」
「……本当か?」
俺が目を丸くして問いかけると、「大マジ」と一番聞きたくない言葉が返ってきた。
その言葉で一連の出来事がフラッシュバックする。
告白してくれた少女に俺はどんな顔でどんな言葉を掛けたんだっけ。
対してちゃんと言葉を受け止めもせずへらっと笑って「ありがとな」という言葉は掛けなかったような気がする。
凄く申し訳ない。けれど、生徒の俺に向けた気持ちが本物だって思えなかったのだ。生徒の言葉を信じることが先生という職業だというのに。
「ねぇ先生?」
キーンと金属が震える音が突然響いた。顔を上げれば少女がビー玉のような澄んだ瞳でこちらを見ていた。
その片足は、地上数十メートルの高さの柵に掛けられている。少し風でも吹いてしまえば、彼女の細い体はそのまま奈落に落ちてしまいそうだった。
そんな状況で君は俺に笑いかけてくる。
「もし私が告白したらどうする?」
「そりゃ……まぁ……断るしかない、だろ?」
自分で言っておきながら頭の中は何故かハテナマークでいっぱいだった。生徒と教師の間の恋愛なんて成立するわけないし、何より相手がこいつなんてありえない。それだというのに、何故躊躇う必要があるのだろう。自分でした行動だというのに自分が一番分かっていないような気がした。挙動不審な俺を見て目の前の彼女は一瞬、瞬きすら惜しんで俺の顔を穴が開くほど見つめてきた。
数秒後、すうっと目尻を下げしなやかな睫毛を震わせた彼女は一言。
「変なひと」
そう呟く口元はひどく愉快に見える。言葉とは裏腹に表情からは俺を非難するような感情は感じ取れず、むしろ少し嬉しそうだった。
「今の俺からすればお前の方こそ変な人だよ」
本当に変な人だ。屋上からバンジージャンプなんて破天荒なことをしておきながらあんな表情もできるなんて。
「今なら飛び降りれるかも、わたし」
「それは国語教師の俺だから言ってる?」
「さぁどーだろうねぇ」
君は二葉亭四迷の言葉を知っているだろうか。
彼はとあるロシアの小説を翻訳する時「愛してる」をとある言葉に訳した。
「……俺が死なれたら困るんだよ」
ボソッと呟いた言葉は誰にも届かず、自分の胸にすとんと落ちるわけでもなく。
ただ喉の奥にいつまでも苦く張り付いていた。