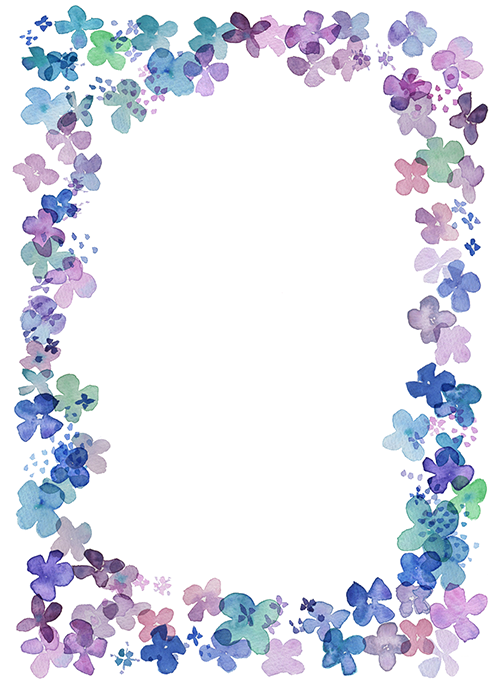私の主は心優しいニンゲンだった。
体の弱く役立たずだと罵倒され捨てられた私を拾い、育てた主は不思議な人だと思う。
石の私を戦場に向かわせず「ここにいなさい」と言い、上等な服をこしらえ、寝床を与え、自らの研究職の補佐をさせた。
私の主は私に沢山のことを教えてくれた。
私は私を捨てたニンゲンのことが憎い。それなのに主は構わず私にくしゃくしゃな笑みを浮かべる。「ワカ」と心地よい声で私の名前を呼び、頭を撫でてくれる。
目を瞑ればいつだって脳裏で主とのあたたかい思い出を再生することができた。
「失礼します、主様」
「〜、あぁワカか。どうした」
「お茶をお持ちいたしました」
一礼すると私はホコリ臭い部屋に足を踏み入れ、書類の散乱する机の端にティーカップを添える。
最近は一段と忙しいみたいで昼夜とわず頭を抱え研究に没頭している。何やらこの研究が公になれば主は伯爵の地位を授かれるそうだ。
召使いとして大変めでたいことだと私も少し浮かれてしまう。
「……ワカは少し私に気を遣い過ぎなのではないか?」
主が白いカップを片手に私に問いかける。私は片膝をたてたまま首を横に振った。
「いいえ、だって私は下僕の身です。それなのに私には寝る場所も三食のご飯もある。これ以上図々しくすることはできません」
「いいや違う。きっと君の思う図々しいことは生きる上で当たり前のことだ。君はもっと自分の欲に素直になりなさい」
私はその言葉に口ごもる。そう言われても私には我儘が分からないのだ。欲しいと思うのもは何一つなくて、私は今生きているだけで十分であって。私は役立たずなのだから、欲などあってはいけなくて……。
私が困ったように主を見上げると、主は長い髭を撫でながらいつものように優しく微笑む。
「いいかいワカ。君には言葉がある。オオカミだってクマだって象だって持っていないものを君は持っている」
言葉……。
主の言葉一つにじわりと目尻が熱くなるのは何故だろう。
「ならばその力を最大限に使うべきではないか?力は誰でも使えるが、ワカの思いから紡がれる言葉はワカだけのものだ。君は誰かを傷つける前に言葉で戦いなさい。戦わずとも自分の思いを言葉にしなさい。
ワカはもっと欲しがって良いのだと自覚しなさい」
主は蝋燭のようだヒトだ。
近づくだけであたたかくて、少し危うい。
また机に向かい資料に目を通し始めた主に私は硬直したまま微動だに出来なかった。
どれくらい時間が経ったのだろう。部屋にある立派な金時計の長い針が一番上から一番下まで動いたとき、私はもう一度空気を震わせた。
「……あ、主様」
貴方はどうして私にここまで優しくしてくれるのでしょう。
私はまだ貴方に何も恩返しできてません。
それなのにどうしてこんなにも私に与えてくれるのですか。
そして
私はどうしてこんなにも貴方に甘えたいと願ってしまうのでしょうか。
「では私も一つ、願っても良いでしょうか」
私の声に主様は再び論文から視線を逸らし、こちらを真っ直ぐ見つめる。
「明日の朝一緒にお食事してください。……ひ、一人の食事はつまらないので」
俯いたまま小さく喋る。ゆっくりと顔をあげると主は驚いたように目を見開いたあと、ゆっくり破顔した。
「一緒に食べよう。約束だ、ワカ」
「はい……!」
これが私の一番幸せな記憶だった。
「……様っ‼」
「あぁ……なんでこんなことに」
「もうすぐで……様の努力が、実を結ばれるというのに……」
朝、けたたましい声で目が覚めた。いつもは静かな家が今日は離れの使いの者の部屋まで聞こえる程に騒がしい。何かあったのだろうか。
「今日は主とのお約束の朝なのに……」
楽しみにしていた日なのに人の声で起きるなんて、残念な寝起きだ。しかし楽しみなのには変わりない。落胆した気持ちはカーテンを開けた外に広がる一面の青を見ればすぐに晴れ渡った。急がなければ主を待たせてしまうと寝間着からシャツに着替え、ネクタイを締める。一式の荷物を持ちキッチンへ移動しようとドアを開けた時、偶然廊下をせわしなく動いていた同期のメイドと鉢合わせた。
「どうしたんですか、そんなに慌てて」
「……あぁ……ワカ君……」
か細い声が私の名前をあげた瞬間、目の前の彼女は腰が抜けたようにその場にへたり込んだ。あまりに突然のことで私も動揺しながら彼女に近づく。どうしたんだ、何があったんですかと聞いても返事がない。ただ虚ろな瞳で私を見上げた。
「まさか、主様に何かあったんですか?」
彼女はその言葉にはっとして私を再度見上げる。すると突然、メイドの大きな瞳から大粒の涙が零れた。
「ワカくん、わ、ワカくん……っ‼旦那様が……っ」
お亡くなりになったの
その言葉を聞いた瞬間、私は目の前の全てがモノクロに染まった。
結果、私の主様は本当に亡くなっていた。死因は夜中に何者かに侵入されて刺殺、つまり暗殺された。目立った外傷はみぞおちの一つのことから失血死だと考えられ、刺されてから死亡までの時間はおよそ二時間らしい。
つまり私のあの優しい旦那様は刺されて痛くて苦しくて寒い中、二時間も耐えぬき息途絶えたということだ。
葬式も火葬も行われたが、私は最後会いに行くことは許されなかった。
元々、主の後ろ盾のお陰で私はこの家でニンゲンと対等に扱われていただけで所詮はただの石だ。
主が居ない今、私を庇うものなど誰もおらず、何度葬儀場に立ち入ろうとしても出禁を言い渡され、彼が灰になるのを見届けることすら叶わなかった。
「私は何故今生きているんだろう」
私は今主が私に分け与えてくれた少しの財産で上を凌いで身を隠しながら生活をしている。もし、私の存在がメイド以外のニンゲンにバレてしまえば私は今度こそ捕らえられ戦場に送り込まれてしまう。
ぼうっと小高い丘の上で空を見上げた。もう何も考えたくなかった。ニンゲンは醜い。殺し合いで何かが生まれると本気で思い込んでいる。主を殺したニンゲンは今ものうのうと生きているらしい。主が伯爵の位をもらうことが気に食わない、ただそれだけの理由で殺したようだが結局主が死んだところでそのニンゲンが何か良い地位を貰えたのか?と問われれば、何も変わっていない。
つまり、主が死んだことで生まれたものは慕っていた者の悲しみだけということだ。
「主、やはりニンゲンは愚かです。汚い心を持つものも、優しい心を持つものも、結局はどちらも同じ価値だと言います。ましてや戦場においてそんなものは関係ない。戦場での命の重さを決める唯一の判断材料は強さだ。力の強さだけが彼らの価値であり重みだ」
しかし、そんなことを言っておきながら分かっていた。
本当に醜いのは私なのだと。
「私は主の護衛なのに……使いの者なのに……貴方を命を賭しても守らなければいけないのに……生きながらえてしまいました」
どうすればいいのか分からない。私には生きる価値がない。その時、丘の下を一つの集団が横断した。その顔には見覚えがあり私はそのニンゲンが誰なのかすぐに分かった。
「主を……殺したやつ」
私は反射的に丘の上から飛び降りた。小太りの男はギトギトと脂汗をかきながら坂を上っていたが、私の姿に気づくなり驚き立ち止まる。
「誰だ?お前。それにお前……その瞳まさか人間じゃない?」
「何故貴方は暗殺など卑劣な真似ができるのですか」
「お前……まさか奴の下僕の石なのか?」
獲物を発見したように気持ちの悪い笑みを浮かべるニンゲン。その瞬間私は目にもとまらぬ速さで走り、宙を飛んだ。彼の首が月明かりで露わになると、隠し持っていたペティナイフで喉元に刃をすっと当てる。
男はあまりの速さに何が起こったのか理解できないとばかりに目を見開くだけだったが、自分が今どのような状況なのか気づくと、途端に額に汗を滲ませ泣きそうな顔で尿を漏らした。
これで私は主の仇を討てる。さぁ後は思い切り腕を横に振るだけだ。
『君は誰かを傷つける前に言葉で戦いなさい。』
刹那、誰かの声が耳を打った。疑うことのない、あたたかな声音は私の唯一大好きな人間の声。
私はもう腕に力が入らなかった。ナイフを握る握力もなくなり、銀色に光るそれは宙に舞う。
反対に私の体は、ニンゲンの護衛の矛がみぞおちを貫通していた。
救護係に手当をされる彼と腹から大量の血を垂れ流す私。向き合った時、無言でなど居られるはずがなかった。
「何故、儂を殺すのを躊躇った?」
私は最早感じることのない痛みと、体の末端から侵食する寒気に抗いながら答える。
「私は……貴方のようなニンゲンが大嫌いです。けれど同時に……この世界にいるニンゲン全員が悪ではないことも知っています」
主様、最後にどうしても貴方の言葉がよぎってしまいました。貴方が私に『誰かを傷つけてはいけない』と言ったので、私は貴方の仇を討つことはできませんでした。
けれどそれでよいのでしょう?貴方は。誰よりも優しい主様はきっと殺した相手を殺したいなんて思わないし、私に手を汚してほしくないからあんなこと言って、私を縛ったのでしょう?
「貴方は殺せません」
私はそう言い切ると笑みを浮かべた。だって、
これは主様が私にくれた大切な約束ですから。
「か……ワカ……っ!」
誰かの声でまた目覚めた。ぼんやりとする視界を三度の瞬きでピントを合わせる。そこには心配そうに私を見つめる金糸雀様がいた。
「あぁ、金糸雀様。どうしたのですか?」
「お前がずっと眠ってるからだよ‼何しても起きないからさぁ、心配したんだよ」
「安心してください、金糸雀様。私はこの通り元気ですから。しかし、確かに深い眠りについて何か夢を見ていたような……」
「どんな夢?」
うーんと記憶を蘇らせようとしても体がそれを拒否するかのようにけたたましい警告音を鳴らす。私は諦めたように首を振って金糸雀様に何も思い出せないことを伝える。
けれど本当は一つだけ思い出せそうなことがあるのだ。
顔も分からない、声も錆びれたテープのようにぎこちないのだがそれでも誰かが私の名前を呼んでくれた気がする。
あまり頑張り過ぎると良くないことが起こりそうだから、これ以上何か詮索することはないだろう。
でも、私はきっとその人物のことが大好きだ。
誰かは分からないけれど今でもずっと、心の中で忘れられないくらい大好きなのだ。
アレキサンドライト
導く者の命を守り、勇気を与える宝石
【石言葉】 秘めた思い、情熱