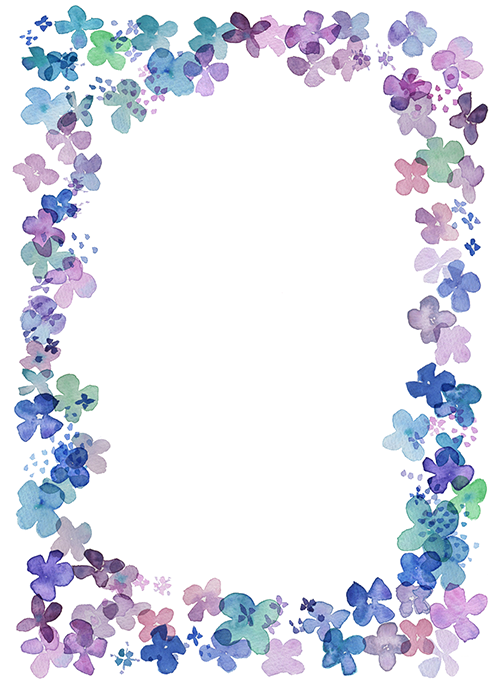酔いが回ってきて意識がふわふわと遠のく感覚がする。ここは馴染みのBarだ。ハロウィンの今日も休むことなく営業しているここはいつだって美味いカクテルを提供してくれる。今日のスペシャルメニューはカボチャとシナモンのスパイスカクテルらしい。
味は想像以上に絶品でまろやかなカボチャとピリッと舌を刺激するスパイスが口の中で解けて形容しがたい美味しさだった。
ついもう一杯と言いかけた口を閉じ、立ち上がる。今日は一人ではないからあまりダラダラと長居できない。そろそろお暇しようかと連れの子供に声を掛けた。
最近はお陰様で毎日子守で騒がしい日々を過ごしている。
大変なこともあるが、彼女がいるからこそ俺は少しずつ立ち直ることが出来てきた。
奥のテーブルで見つけた黒い艶のある髪の少女は何かを必死に描きなぐっている。
「おい、ちっちゃいの」
「ちっちゃいのじゃない!!!ゆおり!!!」
「……結織、何を描いてるんだ」
声をかけると小さい頭が俺と目線を合わせようと上を向く。細い首が折れてしまいそうだなと冷や冷やしたので俺は仕方なく彼女と同じテーブルに座った。
「どうしたんですか?こんぱるさん」
低い声音が柔らかい物腰で訪ねてきた。姿を見なくったって毎日のように顔を突き合わせ話をしているから分かる。この声はここの常勤のバーテンダー、ワカだ。
「このちっこい……じゃねぇ、結織が絵を描いてるみたいだから気になっただけだ」
「あら、そうなのですか?結織さん何を描いていらっしゃるのか私も知りたいです」
「んふふ、皆そんなにゆおの自信作知りたい……?じゃじゃーん」
そこに描いてあったのは
「っ……!!」
「これは……‼」
「「なんだ?」」
見事にワカと俺の声がハモる。微妙な反応をした俺たちに結織は小さな頬をいっぱいに膨らませて拗ねたように言い返す。
「なんだ……?じゃないでしょ!!!!!お姉ちゃんだよ!!!見たら分かるでしょ?青い髪、変なワンピース」
「結織さん、お姉ちゃんとはどなたのことですか……?」
「……だれ?ゆおもわかんない」
俺は咄嗟にしまったと思った。ワカは結織のお姉ちゃんの存在も、お姉ちゃんが誰なのかも、何も知らない。そして結織自身もお姉ちゃんが誰なのか知ることができていない。
二人のやりとりに鳥肌が立つ。結織は、今どんな表情をしている?大丈夫なのか?
覗き込もうとする前に俺の体が固まったのはレンガの床に一粒雫が零れたからだ。
「けど思い出そうとするとさみしくてなきそうになる……ゆお、へんだよね。だっていまも……」
「結織」
凍りついたその場に俺の低い声だけが響く。
「大丈夫だ、そのうち全部が分かればきっと悲しくなくなる」
「ほんとう?」
本当だよと返すと結織はまた元のように小さい子らしく顔をくしゃくしゃにして笑ってくれた。
トントンと肩を叩かれ振り向くとワカが申し訳無さそうに眉を下げていたので気にしなくて良いのにと思った。
「そんな困り顔された方が反応しづらい」
「いや……でも……本当に申し訳ありませ、」
『ばぁ!ハッピーハロウィンだね』
突然どこからか声がした。それは俺だけではなく二人にも聞こえていたようで全員でぱちぱちと瞬きをする。あまりにも浮き世離れした現象にさっきまで謝り倒していた男はその場で腰を抜かし、結織は不思議そうに俺を見上げる。
「ひぇ……お、おばけ?」
「違うこれは……」
いや、言わなくていいだろう。
あまりにもタイミングの悪いその声は何処かで聞いたことがあるなんて言葉では言い表せない。
俺が、ここの皆がずっと会いたいと願い続けている少女の声だった。
鈴を鳴らしたような、グラスに氷を一つコロンと入れたときのような可愛らしい声は懐かしくて、愛おしくて。
けれどまだ結織は彼女の存在を知るべきではない。
いつか彼女自身の力で「お姉ちゃん」の存在を知ることができたら。
その時はちゃんと今のことを教えてあげよう。
「何でもない、空耳だろう」
ワカと目配らせをすると彼も理解したように視線を落とした。穏やかな顔だった。
「帰ろう、結織。散歩がてら皆に会いに行こうか」
「えっ、おさんぽ⁉いいの⁉」
「あぁ」
小さな手を優しく包み込むとワカの柔らかな笑顔に見送られて俺たちは店を後にする。
帰ったら皆に伝えよう、酔いが回ってきて千鳥足になる前に。
今夜はあいつが脅かしに来るかもしれないよ、と。
味は想像以上に絶品でまろやかなカボチャとピリッと舌を刺激するスパイスが口の中で解けて形容しがたい美味しさだった。
ついもう一杯と言いかけた口を閉じ、立ち上がる。今日は一人ではないからあまりダラダラと長居できない。そろそろお暇しようかと連れの子供に声を掛けた。
最近はお陰様で毎日子守で騒がしい日々を過ごしている。
大変なこともあるが、彼女がいるからこそ俺は少しずつ立ち直ることが出来てきた。
奥のテーブルで見つけた黒い艶のある髪の少女は何かを必死に描きなぐっている。
「おい、ちっちゃいの」
「ちっちゃいのじゃない!!!ゆおり!!!」
「……結織、何を描いてるんだ」
声をかけると小さい頭が俺と目線を合わせようと上を向く。細い首が折れてしまいそうだなと冷や冷やしたので俺は仕方なく彼女と同じテーブルに座った。
「どうしたんですか?こんぱるさん」
低い声音が柔らかい物腰で訪ねてきた。姿を見なくったって毎日のように顔を突き合わせ話をしているから分かる。この声はここの常勤のバーテンダー、ワカだ。
「このちっこい……じゃねぇ、結織が絵を描いてるみたいだから気になっただけだ」
「あら、そうなのですか?結織さん何を描いていらっしゃるのか私も知りたいです」
「んふふ、皆そんなにゆおの自信作知りたい……?じゃじゃーん」
そこに描いてあったのは
「っ……!!」
「これは……‼」
「「なんだ?」」
見事にワカと俺の声がハモる。微妙な反応をした俺たちに結織は小さな頬をいっぱいに膨らませて拗ねたように言い返す。
「なんだ……?じゃないでしょ!!!!!お姉ちゃんだよ!!!見たら分かるでしょ?青い髪、変なワンピース」
「結織さん、お姉ちゃんとはどなたのことですか……?」
「……だれ?ゆおもわかんない」
俺は咄嗟にしまったと思った。ワカは結織のお姉ちゃんの存在も、お姉ちゃんが誰なのかも、何も知らない。そして結織自身もお姉ちゃんが誰なのか知ることができていない。
二人のやりとりに鳥肌が立つ。結織は、今どんな表情をしている?大丈夫なのか?
覗き込もうとする前に俺の体が固まったのはレンガの床に一粒雫が零れたからだ。
「けど思い出そうとするとさみしくてなきそうになる……ゆお、へんだよね。だっていまも……」
「結織」
凍りついたその場に俺の低い声だけが響く。
「大丈夫だ、そのうち全部が分かればきっと悲しくなくなる」
「ほんとう?」
本当だよと返すと結織はまた元のように小さい子らしく顔をくしゃくしゃにして笑ってくれた。
トントンと肩を叩かれ振り向くとワカが申し訳無さそうに眉を下げていたので気にしなくて良いのにと思った。
「そんな困り顔された方が反応しづらい」
「いや……でも……本当に申し訳ありませ、」
『ばぁ!ハッピーハロウィンだね』
突然どこからか声がした。それは俺だけではなく二人にも聞こえていたようで全員でぱちぱちと瞬きをする。あまりにも浮き世離れした現象にさっきまで謝り倒していた男はその場で腰を抜かし、結織は不思議そうに俺を見上げる。
「ひぇ……お、おばけ?」
「違うこれは……」
いや、言わなくていいだろう。
あまりにもタイミングの悪いその声は何処かで聞いたことがあるなんて言葉では言い表せない。
俺が、ここの皆がずっと会いたいと願い続けている少女の声だった。
鈴を鳴らしたような、グラスに氷を一つコロンと入れたときのような可愛らしい声は懐かしくて、愛おしくて。
けれどまだ結織は彼女の存在を知るべきではない。
いつか彼女自身の力で「お姉ちゃん」の存在を知ることができたら。
その時はちゃんと今のことを教えてあげよう。
「何でもない、空耳だろう」
ワカと目配らせをすると彼も理解したように視線を落とした。穏やかな顔だった。
「帰ろう、結織。散歩がてら皆に会いに行こうか」
「えっ、おさんぽ⁉いいの⁉」
「あぁ」
小さな手を優しく包み込むとワカの柔らかな笑顔に見送られて俺たちは店を後にする。
帰ったら皆に伝えよう、酔いが回ってきて千鳥足になる前に。
今夜はあいつが脅かしに来るかもしれないよ、と。