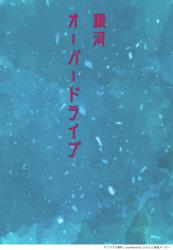この日の全ての授業が終わった。私は荷物をまとめてから、更衣室へと急ぐ。息を切らして部屋の中へと入りジャージへと着替えて、また外に出た。体育館へと向かう。体育館にたどり着くまで時間はかかったが到着すると、そこに部員は真希ちゃん一人しかいなかった。
「真希ちゃん、今日の練習は?」
「あ、今日は先生が体調悪くてお休みみたいだよ。他に見てくれる先生が誰もいなかったらしいね」
「わかった。ありがとう」
「いえいえ」
「ところで、真希ちゃんはどうしてここにいるの?」
「それは、みんな休みだって知らないだろうからここに来たみんなに休みだって伝えるためだよ」
「ありがとう! とても助かる」
「どうってことないよ。ただ、ここに居たいだけってのもあるし」
それから少しの間、真希ちゃんと他愛もないやりとりをする。私と真希ちゃんが揃って好きな流行りのアイドルや役者のこと、私が遅刻をした今日の出来事、彼女が次の土曜に少し遠くのテーマパークに出かけるということ。相槌を打ったり、打たれたり。一通り話したところで私はその場を離れることにした。
「じゃあ、今日は家に帰るね」
「わかった。気をつけてね」
「うん。じゃあね!」
「また明日」
私は彼女と別れて、体育館の全体を一瞥した。周りには私たち以外の部活が活動をしている。シュートの練習をする男子バスケ部の部員たち、掛け声を出しながらトスの練習をするバレー部、窓の外からはグラウンドでサッカー部や野球部が頑張っている。ここの体育館は広いはずなのだが、部活動のために多くの人や物が密集しているせいで、この時は狭く感じた。
「広いはずなのにな」
呟いて、私は体育館の外に出た。しばらく廊下を歩いていると、校内のいろいろな物が目についた。廊下の壁に貼られた何かの啓発ポスター。教室前の壁にあるいろいろな大学の偏差値表。教室の立て札。広場に置かれている少し大きいクリスマスツリー。
私はふと呟いてみる。
「もうすぐ、クリスマスか」
そのクリスマスツリーは頂点に大きな星飾り、全体に巻き付けられた電飾、メタリックカラーのボール、ツリーのサイズに対して少し大きいベルが取り付けられている。私はなんとなくツリーを眺めて、もうすぐ、冬休みに入って高校一年のこの年が終わるのだということを実感する。それが過ぎれば次の年が始まり、休みが明け、三年生たちはいよいよ受験本番で、二年生はいよいよ受験の準備を始める。来年、二年生になった私たちはみんな揃って修学旅行へと出かけて思い出を作り、受験に向けて動き始める。再来年、三年生になった私たちはそれぞれの進路に向けて受験をする。
それが私のこれからであり、みんなの当たり前だと思っていた。それが、私たちが手にしている唯一の未来であり、価値観でもあった。この未来であり、価値観は決して崩れることのない絶対的な物だと考えていたし、ましてや、それを覆すことは誰にもできないのだと思っていた。だが、私が抱いていたその考えはこの日、この時間、この場所から次第に崩れて行くことになる。
掲示物を眺めて歩いていると、私の正面に一人の女子が立っていることに気がついた。制服をきっちりと着ていて、スカートの丈はは膝下まである。髪はボサッとしていたが、なかなかに華奢で整った体型だったので思わず目を向けた。靴を見ると、私たちの学年が履く靴だったので、同級生だということを理解した。彼女はどこか不思議な雰囲気を全身に纏っていた。それで、私は彼女がクラスメイトの倉持咲であることに気がついた。彼女の雰囲気を感じて私は一瞬、どうして良いかがわからなくなった。動きを止める。すると、彼女の方から私に近づいてきた。顔をまじまじと見つめると化粧っ気は無かったが顔もなかなかに良かった。おそらく、身嗜みを整えれば、モデルの様な美しい人なのだろうとこの時の私は思った。空な目と私の目が合う。彼女は私の顔をじっくりと見つめてから何かに怯えるように、私の何かを見抜いたかのように小さく言葉を放った。
「……友達になってくれる?」
私はこの言葉を聞いて、どういうことか、頭の中にある言葉たちが一斉に消え去った。私はその一言がすぐには受け止められず、どう返したら良いのか分からなかった。廊下を歩いている途中で見えた時計が示していた時刻は午後の四時半。冬の夕暮れが私たちの顔に差し込む。まるで、何か見てはいけないものを見てしまったかのような気持ちになった。しばらく答えらずにいると彼女はまた小さな声で、
「どうしたの? 聞こえなかった?」
と言った。私はやっとのことで、頭の中で消え去った言葉たちを見つけ出す。
「い、いや、そんなことない、けど……」
私は自分で何を言っているのかがうまく掴めなかった。彼女は空な目で今度は私の全身を見つめた。
「あなた、バスケ部?」
「そう、だけど」
「バスケ部に石崎友美っているでしょ。私、彼女と昔からの付き合いなんだ」
「へえ…… 、そうなんだ」
彼女がなぜ、友美の名前を出したのかがこの時の私にはわからなかった。この時の私はとても混乱していた。それは、もしかすると直感的に彼女の身に何かがあることに気づいたけらなのかもしれない。それは、今となっては確かめようもないのだが。
彼女は、小さな声で話を続けた。
「ねえ、ところであなたの名前は?」
「え、ええと、佐野由香里」
「そう。私は倉持咲。よろしく」
「よろしくって、言われても、私、あなたと同じクラスのはずだけど」
「あ、そっか。同じクラスの佐野さんだとは気づかなったよ。ごめんごめん」
私は咄嗟に友美が言っていた、倉持咲には気をつけた方がいいという言葉を思い出した。でも、なぜ友美はそう言ったのかの理由はわからなかったが、私の心に警戒の念が生まれた。だが、彼女はそれを見破るかのように口を開いた。
「ねえ、あなた今、私のことを警戒しているでしょ」
「そんなことないよ……」
「嘘。顔にもろその表情が出ている」
私の頭の中はどんどんぐちゃぐちゃになってきた。ぐちゃとして、一体何のためにこんな会話をしているのだろうかと思えてきた。彼女はそんな私の事などお構いなしに言葉を続ける。
「どうせ、友美に私のことは気をつけた方がいいとでも言われたのでしょ。わかるよ。そんなことくらい」
「どうして、そんなこと言うの?」
「だって、彼女は私を妬んでいるから」
私はそれを平然と言いのけた彼女が恐ろしいと思った。
「なんか、私のことが理解できない見たいね」
彼女のこの言葉を聞いて、私は思わず、
「ええ、怖いよ。あなたの考えていることが」
と返した。これは紛れもなく本音だった。
「そう。分かった。それならば、ごめんね」
彼女はあっさりと謝った。私はますます気持ちが混乱した。
「あのさ、友達になってくれるってどういうこと?」
彼女は少しだけ考えるような仕草をしてからこう答えた。
「私には友達がいない。だから友達が欲しくなったの。それだけ」
「それだけって……」
「そういえば、友美が毎年クリスマスにパーティーをしているのだけど、今年はあなたも来る?」
友美がクリスマスパーティーを毎年開いていたというのは初めて聞いた。なぜ、彼女がパーティーを知っていたのかは、‘昔からの付き合い‘だからなのだろうか。私はまたしても何も言い切れなくなってしまう。
「行くって言っても、まだ誘われていないから何とも言えないよ」
「そうなのね」
この時、彼女が私の言葉を聞いてさらに弱々しい声になったような気がした。どうしてそうなったのか、私はこの時、計りかねたのだけど、後になって思えば、これは彼女なりの救難信号だったのかもしれない。
少しの間、私たちに静寂が訪れた。お互いにどうすることもできずにただ、時計の針だけが進んでいく。次第に彼女が近くの壁に掛けられている時計に目を向けた。それにつられて私も時計の方を見た。時刻は出会してからおおよそ十五分以上が過ぎていることを示していた。もうすぐで夕方の五時となる。
「じゃあ、今日は帰るね。私の友達になって欲しいこと、忘れないでね」
「う、うん」
「じゃあね」
彼女は踵を返して、歩いて行った。私は彼女の「じゃあね」の言葉に返事をすることができなかった。突然訪れた嵐は突然に、静かに去っていった。私はしばらくそこで一人立ち尽くした。この嵐が去った時、私にはそうすることしかできなかった。この瞬間から心の中の何かが崩れ始める音が少しずつ、少しずつ響き始めた。ようやく動けるようになった頃にはもう日が暮れて、窓の外から見える街灯の光が道を照らし始めていた。私は家に帰らなくてはいけないことをこのタイミングで思い出す。駐輪場に向かって歩き始める。
暗い暗い廊下を進むと、再び広場に出た。そこには電飾が綺麗に点灯したクリスマスツリーがあった。この時の私にはなんて場違いな物なのだろうかと思えた。そう思えたが、綺麗に光っているものだから、心が少しだけ元気になれた気がした。駐輪場に出た私は自転車に乗った。
街灯に照らされた薄暗い道を一人で進んでいく。他のみんなはまだ部活を続けている。一人の帰り道で考えた。倉持咲は何をしたいのだろうか? どうして、友美は彼女を遠ざけているのか? 考えてはみようと思ったが、この日はどうしても結論は出そうになかった。途中で考えるのを止めて無心になって家路を走った。普段見る景色が暗く澱んで見えたような気がした。
自転車を止めて、鍵をかける。階段を上がって家の玄関に着くと丁度お母さんも階段を上がってきた。
「あら、おかえり。早かったね」
「ただいま。今日は部活が無かったから」
「あらそう。じゃあ、さっきお菓子を買ってきたから食べない?」
「食べる、食べる」
私は玄関の鍵を開けた。お母さんを先に通してから中に入った。家の中はとても暗かった。お母さんがすぐに明かりをつけたから、一瞬で暗闇は消えたが、この日の私にはどうしても、印象に残った。それから、私はこの日々に少しだけ亀裂が走ったことに気がついた。この亀裂は塞げるのだろうかと考えていると、母は私の中の少しの亀裂に気づいていたのか、わからないが、こう言った。
「何かあったでしょ?」
「え?」
「何かあったんでしょ? 学校で」
「真希ちゃん、今日の練習は?」
「あ、今日は先生が体調悪くてお休みみたいだよ。他に見てくれる先生が誰もいなかったらしいね」
「わかった。ありがとう」
「いえいえ」
「ところで、真希ちゃんはどうしてここにいるの?」
「それは、みんな休みだって知らないだろうからここに来たみんなに休みだって伝えるためだよ」
「ありがとう! とても助かる」
「どうってことないよ。ただ、ここに居たいだけってのもあるし」
それから少しの間、真希ちゃんと他愛もないやりとりをする。私と真希ちゃんが揃って好きな流行りのアイドルや役者のこと、私が遅刻をした今日の出来事、彼女が次の土曜に少し遠くのテーマパークに出かけるということ。相槌を打ったり、打たれたり。一通り話したところで私はその場を離れることにした。
「じゃあ、今日は家に帰るね」
「わかった。気をつけてね」
「うん。じゃあね!」
「また明日」
私は彼女と別れて、体育館の全体を一瞥した。周りには私たち以外の部活が活動をしている。シュートの練習をする男子バスケ部の部員たち、掛け声を出しながらトスの練習をするバレー部、窓の外からはグラウンドでサッカー部や野球部が頑張っている。ここの体育館は広いはずなのだが、部活動のために多くの人や物が密集しているせいで、この時は狭く感じた。
「広いはずなのにな」
呟いて、私は体育館の外に出た。しばらく廊下を歩いていると、校内のいろいろな物が目についた。廊下の壁に貼られた何かの啓発ポスター。教室前の壁にあるいろいろな大学の偏差値表。教室の立て札。広場に置かれている少し大きいクリスマスツリー。
私はふと呟いてみる。
「もうすぐ、クリスマスか」
そのクリスマスツリーは頂点に大きな星飾り、全体に巻き付けられた電飾、メタリックカラーのボール、ツリーのサイズに対して少し大きいベルが取り付けられている。私はなんとなくツリーを眺めて、もうすぐ、冬休みに入って高校一年のこの年が終わるのだということを実感する。それが過ぎれば次の年が始まり、休みが明け、三年生たちはいよいよ受験本番で、二年生はいよいよ受験の準備を始める。来年、二年生になった私たちはみんな揃って修学旅行へと出かけて思い出を作り、受験に向けて動き始める。再来年、三年生になった私たちはそれぞれの進路に向けて受験をする。
それが私のこれからであり、みんなの当たり前だと思っていた。それが、私たちが手にしている唯一の未来であり、価値観でもあった。この未来であり、価値観は決して崩れることのない絶対的な物だと考えていたし、ましてや、それを覆すことは誰にもできないのだと思っていた。だが、私が抱いていたその考えはこの日、この時間、この場所から次第に崩れて行くことになる。
掲示物を眺めて歩いていると、私の正面に一人の女子が立っていることに気がついた。制服をきっちりと着ていて、スカートの丈はは膝下まである。髪はボサッとしていたが、なかなかに華奢で整った体型だったので思わず目を向けた。靴を見ると、私たちの学年が履く靴だったので、同級生だということを理解した。彼女はどこか不思議な雰囲気を全身に纏っていた。それで、私は彼女がクラスメイトの倉持咲であることに気がついた。彼女の雰囲気を感じて私は一瞬、どうして良いかがわからなくなった。動きを止める。すると、彼女の方から私に近づいてきた。顔をまじまじと見つめると化粧っ気は無かったが顔もなかなかに良かった。おそらく、身嗜みを整えれば、モデルの様な美しい人なのだろうとこの時の私は思った。空な目と私の目が合う。彼女は私の顔をじっくりと見つめてから何かに怯えるように、私の何かを見抜いたかのように小さく言葉を放った。
「……友達になってくれる?」
私はこの言葉を聞いて、どういうことか、頭の中にある言葉たちが一斉に消え去った。私はその一言がすぐには受け止められず、どう返したら良いのか分からなかった。廊下を歩いている途中で見えた時計が示していた時刻は午後の四時半。冬の夕暮れが私たちの顔に差し込む。まるで、何か見てはいけないものを見てしまったかのような気持ちになった。しばらく答えらずにいると彼女はまた小さな声で、
「どうしたの? 聞こえなかった?」
と言った。私はやっとのことで、頭の中で消え去った言葉たちを見つけ出す。
「い、いや、そんなことない、けど……」
私は自分で何を言っているのかがうまく掴めなかった。彼女は空な目で今度は私の全身を見つめた。
「あなた、バスケ部?」
「そう、だけど」
「バスケ部に石崎友美っているでしょ。私、彼女と昔からの付き合いなんだ」
「へえ…… 、そうなんだ」
彼女がなぜ、友美の名前を出したのかがこの時の私にはわからなかった。この時の私はとても混乱していた。それは、もしかすると直感的に彼女の身に何かがあることに気づいたけらなのかもしれない。それは、今となっては確かめようもないのだが。
彼女は、小さな声で話を続けた。
「ねえ、ところであなたの名前は?」
「え、ええと、佐野由香里」
「そう。私は倉持咲。よろしく」
「よろしくって、言われても、私、あなたと同じクラスのはずだけど」
「あ、そっか。同じクラスの佐野さんだとは気づかなったよ。ごめんごめん」
私は咄嗟に友美が言っていた、倉持咲には気をつけた方がいいという言葉を思い出した。でも、なぜ友美はそう言ったのかの理由はわからなかったが、私の心に警戒の念が生まれた。だが、彼女はそれを見破るかのように口を開いた。
「ねえ、あなた今、私のことを警戒しているでしょ」
「そんなことないよ……」
「嘘。顔にもろその表情が出ている」
私の頭の中はどんどんぐちゃぐちゃになってきた。ぐちゃとして、一体何のためにこんな会話をしているのだろうかと思えてきた。彼女はそんな私の事などお構いなしに言葉を続ける。
「どうせ、友美に私のことは気をつけた方がいいとでも言われたのでしょ。わかるよ。そんなことくらい」
「どうして、そんなこと言うの?」
「だって、彼女は私を妬んでいるから」
私はそれを平然と言いのけた彼女が恐ろしいと思った。
「なんか、私のことが理解できない見たいね」
彼女のこの言葉を聞いて、私は思わず、
「ええ、怖いよ。あなたの考えていることが」
と返した。これは紛れもなく本音だった。
「そう。分かった。それならば、ごめんね」
彼女はあっさりと謝った。私はますます気持ちが混乱した。
「あのさ、友達になってくれるってどういうこと?」
彼女は少しだけ考えるような仕草をしてからこう答えた。
「私には友達がいない。だから友達が欲しくなったの。それだけ」
「それだけって……」
「そういえば、友美が毎年クリスマスにパーティーをしているのだけど、今年はあなたも来る?」
友美がクリスマスパーティーを毎年開いていたというのは初めて聞いた。なぜ、彼女がパーティーを知っていたのかは、‘昔からの付き合い‘だからなのだろうか。私はまたしても何も言い切れなくなってしまう。
「行くって言っても、まだ誘われていないから何とも言えないよ」
「そうなのね」
この時、彼女が私の言葉を聞いてさらに弱々しい声になったような気がした。どうしてそうなったのか、私はこの時、計りかねたのだけど、後になって思えば、これは彼女なりの救難信号だったのかもしれない。
少しの間、私たちに静寂が訪れた。お互いにどうすることもできずにただ、時計の針だけが進んでいく。次第に彼女が近くの壁に掛けられている時計に目を向けた。それにつられて私も時計の方を見た。時刻は出会してからおおよそ十五分以上が過ぎていることを示していた。もうすぐで夕方の五時となる。
「じゃあ、今日は帰るね。私の友達になって欲しいこと、忘れないでね」
「う、うん」
「じゃあね」
彼女は踵を返して、歩いて行った。私は彼女の「じゃあね」の言葉に返事をすることができなかった。突然訪れた嵐は突然に、静かに去っていった。私はしばらくそこで一人立ち尽くした。この嵐が去った時、私にはそうすることしかできなかった。この瞬間から心の中の何かが崩れ始める音が少しずつ、少しずつ響き始めた。ようやく動けるようになった頃にはもう日が暮れて、窓の外から見える街灯の光が道を照らし始めていた。私は家に帰らなくてはいけないことをこのタイミングで思い出す。駐輪場に向かって歩き始める。
暗い暗い廊下を進むと、再び広場に出た。そこには電飾が綺麗に点灯したクリスマスツリーがあった。この時の私にはなんて場違いな物なのだろうかと思えた。そう思えたが、綺麗に光っているものだから、心が少しだけ元気になれた気がした。駐輪場に出た私は自転車に乗った。
街灯に照らされた薄暗い道を一人で進んでいく。他のみんなはまだ部活を続けている。一人の帰り道で考えた。倉持咲は何をしたいのだろうか? どうして、友美は彼女を遠ざけているのか? 考えてはみようと思ったが、この日はどうしても結論は出そうになかった。途中で考えるのを止めて無心になって家路を走った。普段見る景色が暗く澱んで見えたような気がした。
自転車を止めて、鍵をかける。階段を上がって家の玄関に着くと丁度お母さんも階段を上がってきた。
「あら、おかえり。早かったね」
「ただいま。今日は部活が無かったから」
「あらそう。じゃあ、さっきお菓子を買ってきたから食べない?」
「食べる、食べる」
私は玄関の鍵を開けた。お母さんを先に通してから中に入った。家の中はとても暗かった。お母さんがすぐに明かりをつけたから、一瞬で暗闇は消えたが、この日の私にはどうしても、印象に残った。それから、私はこの日々に少しだけ亀裂が走ったことに気がついた。この亀裂は塞げるのだろうかと考えていると、母は私の中の少しの亀裂に気づいていたのか、わからないが、こう言った。
「何かあったでしょ?」
「え?」
「何かあったんでしょ? 学校で」