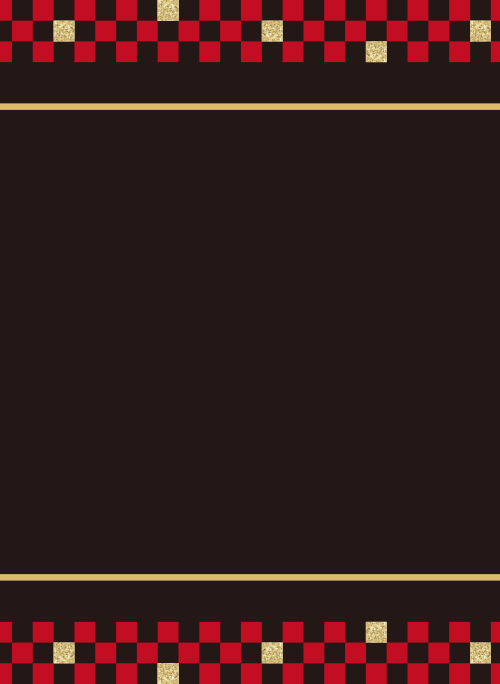(お味噌汁の香り・・・?)
雪はゆっくりまぶたを開いた。外では小鳥がさえずっている。
やわらかな布団の中で寝返りをうつ。眠気と空腹の葛藤はあったが、空腹に負けた。
雪はゆるゆる起き上がると、まぶたをこする。
「・・・ふふっ」
ふと、独り笑いしてしまった。
嬉しかったのだ。
自分で起き上がれるようになったこと。
歩けるようになったこと。
介助無しで、腹いっぱい、ごはんも食べられる。
できることが一つ一つ、増えていく。
他人にとってはなんでもない『あたりまえ』が、雪にはすべてが新鮮で、胸が踊った。
たどたどしい足取りで二階の障子を開け放つ。すこしひんやりとした空気を胸いっぱいに吸い込めば、ほろりと笑みが溢れる。
――わたしは、生きている。生きている実感がする。
雪はうなずき、踵を返すと、今度は階段へと向かった。途中、菫が眠る押し入れを覗いてみる。・・・完全に熟睡しているようだ。ぷくぷくの頬は満足げに笑っている。
雪は急な階段を見下ろし、ごくりとつばを飲んだ。
「・・・よし」
慎重に、一歩ずつ降りてみる。龍胆に見つかれば小言を言われるだろうが、頼ってばかりでは進歩がない。
壁によりかかりながら、どきどきする胸を抑え、雪は白い足を伸ばす。ハラハラする冒険だが、要領よく行けば意外と速かった。
やがて、最後の一段を踏んだとき、雪は涙が滲んだ。
(はじめて、階段を降りた・・・っ!)
思わず手を叩いて小躍りする。感動だ。
(もう、人の手を借りなくてもいいんだわ)
どこへでも行ける。自分の足で。
行きたいところに行けるのだ。
雪は上機嫌で辺りを見渡した。一階は風呂と厠を使うとき以外、探索したことはない。どこへゆこう?
(まずは・・・、厨に行きたいな。お料理をしている龍胆さまを、見てみたいもの)
情けない話だが、雪は厨に立った記憶があまりない。幼い頃寝たきりになってから、すぐに馬小屋へ放り込まれたからだ。
幸い、彼は雪が起きていることに気づいていないだろう。
(気づいていたら、すぐに飛んでくるものね)
思わず、はにかむ。頬が染まったのは気のせい。
朝餉の匂いを頼りに進めば、心地よい包丁の音が聞こえてくる。
雪は壁に隠れながら、首だけひょいと伸ばし、そっと厨の様子を伺った。
「・・・っ」
思わず、息を呑んだ。吸い込まれるように、視線が釘付けになる。
綺麗な背中だった。
黒い紐でたすき掛けしている。その後ろ姿は華奢だが、男らしい無骨さのある二の腕の筋肉がちらちら見え隠れしている。窓から差し込む朝日。白髪はきらきら輝く。いつもよりしっかり髪を束ねているから、彼の真剣な顔もよく見えた。
(鬼が・・・、大根を切っている・・・)
よくよく考えれば奇妙な光景だ。丁寧に皮を剥かれた大根は彼と引けをとらないほど白くて美しい。雪はくすりと笑った。
「ゆき。そんなところに隠れて、何か企んでいるのかね?」
顔もあげずに淡々と龍胆は言う。雪は飛び上がった。
「べ、べつになにも、企んでなどおりませんっ」
あわてて飛び出すと、彼は振り向き、腰に手を当てた。・・・意地悪く、にやりと笑う。
「ふふ。――なら、俺に見とれていたのかな?」
「う」
雪は思わず後ずさる。「うぬぼれですよ」と喉まででかけたが、なにをされるかわからない。例えばそう――・・・。
「あの。龍胆さま」
「うん?」
雪はおそるおそる胸に手を添えて尋ねる。彼は味噌汁の味見をするため、小皿を口に含んだ。
「はじめて逢ったとき、その――・・・。どうして、口づけをなさったのですか?」
「っ!?」
龍胆はブッと吹き出した。激しく咳き込む。「え。だいじょうぶ・・・?」とおろおろする雪を涙目で睨んだ。
「君ねぇっ! 朝っぱらから、若い娘がする話題じゃないだろうっ」
「龍胆さまはおいくつなのですか?」
「そういう問題じゃないっ。ちなみに二十九歳だ!」
龍胆は手近な布巾で両手を拭くと、ずかずかと娘に歩み寄る。
「いいかいっ? 誰にでも気を許すな。俺だからいいようなものの。君は男と言うものを知らなすぎる」
手を取られ、女性として見られているのだと教えられた雪はうつむいた。
「・・・だったら、なぜ?」
その小さな耳は、ほんのり染まっている。甘い香りがするようで、龍胆は反射的に手を離した。逃げるように、作りかけの鍋へ向かう。
「・・・・・・君が、あんなことを言うからだ」
「え?」
雪は首を傾げ、――途端、思い至る。
『この濁世(だくせ)に、もういたくない・・・。生きる理由が見つからない。生きながらえればながらえるほど、ひどい目にばかりあう』
(そうだ、私は。この人に、食べてくださいって頼んだんだわ)
ぎゅっと、胸が痛む。
彼は鬼であることを気にしていたのに。
(なんてことを・・・言ってしまったの)
雪は肩を落とす。勘違いしているのだ。
「はあ・・・」
ため息を付き、絞り出すように、龍胆は言った。
「あれ以上、君の口から『死にたい』なんて言わせたくなかった。だから塞いだ。・・・それだけだ」
とん、とん・・・と、彼は再び野菜を切り始める。
雪は何も言えない。
彼は何でもないことのように続ける。
「俺の作るこの食事が、雪の生きる糧になれたらと思う。大抵のことは、飯を食ったら忘れるものさ」
「――・・・」
それは、無意識の行動だったかもしれない。
土間へ降りる。裸足のまま、勢いもそのままに。
彼の背中へ抱きついていた。
「っ」
龍胆は目を見開く。彼の動揺を抑え込むように、雪はぎゅっと腕を回し、体を密着させる。頬ずりする頬は、涙で濡れていた。
着物に染み込む雫の気配に気づいた龍胆は、呆然とする。
――やめてくれ。
浮かんだ言葉は、先程とは真反対の冷たい声だった。
(もう俺になつくな。俺を慕うな。――これ以上、俺を苦しめないでくれ)
自分は鬼なのだ。もう、人間ではないのだ。長らく現世を離れれば、それだけ戻れなくなってしまうのに。
――だったらなぜ、俺は雪を連れて帰った!?
また別の声がした。
雪に取り付いた餓鬼を追い出せば、それで終わり。雪を人里へ戻すべきだろう?
なのに。帰すどころか料理まで作って、日々食べさせている。
この行動の意味は。
(雪をつなぎとめているのは、俺のほうじゃないか)
腕は力なくだらりと下がる。
わかっているはずだ。
・・・わかっている、はずだ。
彼女を本当に思うのなら、これ以上自分と関わるべきではない。
人殺しのこの手は、君を抱きしめ返すには汚れすぎている。
死体を喰う化け物なのだ。
「――ふ」
ぐしゃりと前髪をかきあげる。
(なんだ。雪にすがっているのは、俺のほうじゃないか)
この世には、二種類の人間がいる。
生きる価値のある人と、そうじゃない人。
俺は、まぎれもなく後者。
世の中のすべての人間に訪ねても、皆そう言うだろう。
龍胆はゆっくりと振り返り、雪を見下ろす。
・・・だから、かもしれない。
(せめて、たった一人。おまえに必要とされたいと、願うのは)
雪は何も言わない。
彼女もまた、ようやく見つけた居場所を失いたくないのだ。
龍胆も雪を振り払わない。・・・振り払うなど、できない。
互いに拠り所としながら、共にあることを苦しむ二人。
ただ、時間だけが過ぎていく。