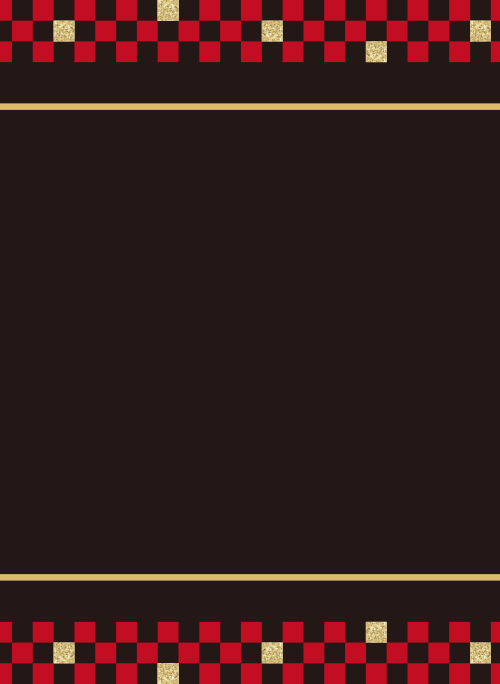「おい。聞いたかよ? 一週間前の花散里の変死事件。あれ、妖怪の仕業らしいぜ?」
暖簾を下ろしながら、小間物屋の店主は言った。
ここは花散里から少し離れた場所にある隣町。小規模だが店が並んでいる。買い物したければ、ここへ来ればだいたい事足りる。その程度には栄えていた。
だが今は夕方。日も沈みかけ、店じまいの時間帯だ。
問われた古着屋の店主は、顎に手を添え、深々とうなずいた。
「俺も噂で聞いたよ。なんでも、庄屋のオヤジの葬儀を無事に終わらせたくて生贄を選んだ結果、鬼の怒りを買って全員喰われちまったそうじゃないか。自業自得だって、みんな言ってるよ。・・・もっとも、死人に祟られたくねえなら、悪口もほどほどにするべきだが」
「そうじゃねぇ。鬼の仕業じゃなかったって話だよ!」
「えぇ?」
古着屋の店主は首を傾げた。
「鬼じゃねえなら、どいつがやったんだ?」
小間物屋の店主は「火車って化け猫だよ!」と鼻息荒く言った。まくし立てる。
「百年前から、急に花散里に出るようになったって俺の曾祖父さんが言ってた。俺も親父から聞いた話だが。・・・なんでも百年前、女ばかり消える、神隠しが頻発したらしい。隠された女は誰一人戻ってこなかったそうだ」
「ああ。それなら俺も親父から聞いたよ。あの村が『花散里』なんて呼ばれるのは、変死の異常な多さのせいだって。その化け猫も、死んだ娘の誰かの飼い猫だったんじゃねえかなぁ? 猫は飼い主の恨みを晴らしてくれる、心優しい生き物だからよ」
――ちげぇねぇ。そう言って、二人、うなずきあったときだった。
みゃおん。
野太い猫の鳴き声がした。
「ひっ!?」
男たちは縮み上がった。あわててあたりを見渡すが、猫など、どこにもいない。
代わりに、七つぐらいの男の子がほほ笑んで立っていた。
「あの・・・。おつかいできたのですが、もうお店しまっちゃいましたか・・・?」
肩上された着物はところどころほつれている。しもやけのあとも見つけて、店主たちはほっと息を吐いた。
「ごめんよ、ちょいと話し込んでたもんだから・・・。驚かせちまったな」
店主はよしよしと豪快に頭をなでた。
「ふふっ。だいじょうぶです」
男の子は気持ちよさそうに目を細める。
小間物屋の店主は腰を折ると、「なにを買いにきたんだい?」と訪ねた。
「えっと・・・。女の人の櫛と、髪油と、それから・・・?」
くしゃくしゃに握りしめた小さな紙を見て、男の子はまごつく。
「どれ。見せてみな」
「お、お手数おかけします・・・」
かわいい手から紙を受け取ると、大人たちは商売人の顔になった。見繕ってくれるらしい。
「古着も買っていくんだな。坊っちゃんのかい?」
男の子は頬を赤らめた。
「はい・・・。やぶれているから、買い直しなさいって言われました」
「そりゃ、良かったな!」
景気よく店主は言う。
やがて、必要なものは揃った。
「結構な荷物だけど、背負えるかい?」
「しんせつにありがとうございます。・・・ぼくは、こうみえて力持ちなんですよ」
礼儀正しく少年はお辞儀する。背中に背負えるように、風呂敷を結んでやった大人たちは、清々しい気持ちで「まいどぉ」と手を振った。
「今どき珍しい、いい子だったなぁ」
「ささ、今度こそ店じまいだ」
店の周りを片付け、ふと、小間物屋の店主は男の子のことが気になった。
(そういえば、こんな時間に子供一人で、大丈夫かな?)
もしものことがあれば、後味が悪い。
そう思って、男の子が消えた表通りへ走る。子供の足だ。すぐに追いつくだろう。
「あれぇ?」
だが誰も、通行人はいなかった。
真っ赤な夕日は、どっぷりと沈んでいった。
暖簾を下ろしながら、小間物屋の店主は言った。
ここは花散里から少し離れた場所にある隣町。小規模だが店が並んでいる。買い物したければ、ここへ来ればだいたい事足りる。その程度には栄えていた。
だが今は夕方。日も沈みかけ、店じまいの時間帯だ。
問われた古着屋の店主は、顎に手を添え、深々とうなずいた。
「俺も噂で聞いたよ。なんでも、庄屋のオヤジの葬儀を無事に終わらせたくて生贄を選んだ結果、鬼の怒りを買って全員喰われちまったそうじゃないか。自業自得だって、みんな言ってるよ。・・・もっとも、死人に祟られたくねえなら、悪口もほどほどにするべきだが」
「そうじゃねぇ。鬼の仕業じゃなかったって話だよ!」
「えぇ?」
古着屋の店主は首を傾げた。
「鬼じゃねえなら、どいつがやったんだ?」
小間物屋の店主は「火車って化け猫だよ!」と鼻息荒く言った。まくし立てる。
「百年前から、急に花散里に出るようになったって俺の曾祖父さんが言ってた。俺も親父から聞いた話だが。・・・なんでも百年前、女ばかり消える、神隠しが頻発したらしい。隠された女は誰一人戻ってこなかったそうだ」
「ああ。それなら俺も親父から聞いたよ。あの村が『花散里』なんて呼ばれるのは、変死の異常な多さのせいだって。その化け猫も、死んだ娘の誰かの飼い猫だったんじゃねえかなぁ? 猫は飼い主の恨みを晴らしてくれる、心優しい生き物だからよ」
――ちげぇねぇ。そう言って、二人、うなずきあったときだった。
みゃおん。
野太い猫の鳴き声がした。
「ひっ!?」
男たちは縮み上がった。あわててあたりを見渡すが、猫など、どこにもいない。
代わりに、七つぐらいの男の子がほほ笑んで立っていた。
「あの・・・。おつかいできたのですが、もうお店しまっちゃいましたか・・・?」
肩上された着物はところどころほつれている。しもやけのあとも見つけて、店主たちはほっと息を吐いた。
「ごめんよ、ちょいと話し込んでたもんだから・・・。驚かせちまったな」
店主はよしよしと豪快に頭をなでた。
「ふふっ。だいじょうぶです」
男の子は気持ちよさそうに目を細める。
小間物屋の店主は腰を折ると、「なにを買いにきたんだい?」と訪ねた。
「えっと・・・。女の人の櫛と、髪油と、それから・・・?」
くしゃくしゃに握りしめた小さな紙を見て、男の子はまごつく。
「どれ。見せてみな」
「お、お手数おかけします・・・」
かわいい手から紙を受け取ると、大人たちは商売人の顔になった。見繕ってくれるらしい。
「古着も買っていくんだな。坊っちゃんのかい?」
男の子は頬を赤らめた。
「はい・・・。やぶれているから、買い直しなさいって言われました」
「そりゃ、良かったな!」
景気よく店主は言う。
やがて、必要なものは揃った。
「結構な荷物だけど、背負えるかい?」
「しんせつにありがとうございます。・・・ぼくは、こうみえて力持ちなんですよ」
礼儀正しく少年はお辞儀する。背中に背負えるように、風呂敷を結んでやった大人たちは、清々しい気持ちで「まいどぉ」と手を振った。
「今どき珍しい、いい子だったなぁ」
「ささ、今度こそ店じまいだ」
店の周りを片付け、ふと、小間物屋の店主は男の子のことが気になった。
(そういえば、こんな時間に子供一人で、大丈夫かな?)
もしものことがあれば、後味が悪い。
そう思って、男の子が消えた表通りへ走る。子供の足だ。すぐに追いつくだろう。
「あれぇ?」
だが誰も、通行人はいなかった。
真っ赤な夕日は、どっぷりと沈んでいった。