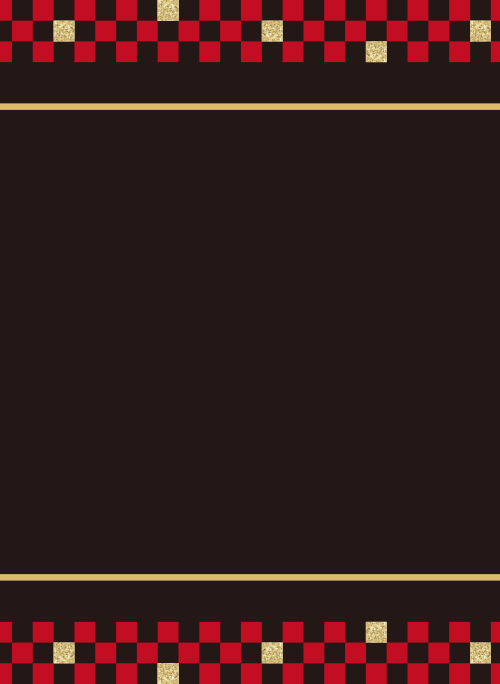穢土(えど)から遠く離れた村――花散里は、田園風景の広がる田舎だ。
そしてこの村には、『鬼』が出る。
――『屍食鬼』という、死にかけの人間や死体ばかりを食う、化け物が。
昨日、庄屋のオヤジが死んだ。
奔放な男だったから、酒飲みが過ぎたのだろう。
村が貧困にあえぐなか、贅沢で死ねるなんて、と村人たちは皮肉った。それでも、葬式は挙げてやらねばなるまい。皆、準備に取り掛かった。
「今回も出るかねぇ? 『屍食鬼』殿は」
「出るだろうよ。死人が出るたびに、葬式の最中でも死体をかっさらっていく化物だぜ。でっぷり太った男の肉はさぞうまかろうよ」
「ちげえねえ」
一方、病の娘――雪は、穀潰しとそしられながらもまだ生きていた。
梅の花がほころぶ季節だ。甘ったるい香りが鼻をくすぐってきて、雪は目を覚ました。
ボロボロにほつれた着物はドブネズミのようだ。幽霊のような長い黒髪は足首まで伸びている。青白く、痩せた体は枯れ木のようだった。
雪からは悪臭が漂っていたが、馬小屋だったからか、馬のにおいと混ざって、幸いにも指摘されることは少なかった。
・・・・・・でも、今日は違う。
「まあっ、くさい。なんだいこの娘の汚さは。まるで死にかけの猫じゃないか」
初めて聞く女の声。雪はどきっと心臓が跳ねた。
起き上がることすらままならない体、眼球だけで睨むように見上げれば、喪服に身を包んだ中年の女性が、いまわしげにこちらを見下ろしている。
「あ・・・・・・、げほっ!」
雪は声を出そうとして、激しく咳き込んだ。喋る相手ができたのはいつぶりだろうか。
女の正体はおそらく死んだ庄屋の妻だろう。絹の着物を着こなす出で立ちで見当がついた。嫌な女と評判だ。嫌味の一つくらい言ってくるだろう。
だが、気に留めてもらえるだけ、マシなのかもしれない。
――まるで空気のような存在。いてもいなくても気づかれない。それが私だから。
「哀れなもんだね」
女は着物の袖で鼻を覆う。
「親がいなくなった子供の末路は悲惨さ。遊里に売られる娘もいる。それに比べりゃ、お前は幸運な方だよ。・・・病弱だったお陰で人買いにすら相手にされなかった。本当なら山に捨てて獣の餌にするところを、馬小屋でも村においてやったんだ。あたしら夫婦に感謝すべきじゃないかい?」
――なにが感謝だ。
雪は血走った眼(まなこ)で女を睨みつける。ひゅー、ひゅー・・・と乾いた音の出る喉を押さえた。
言い返すこともできない雪を、庄屋の妻は満足げに見下ろす。
そこには下卑た笑みが浮かんでいた。
「無様だねぇ。お前の人生はせいぜい、そうやって地べたに這いつくばって物乞いするだけ。糞の役にも立たないまま終わるのさ。――だが、お前の返事次第では、死に花を咲かせてやってもいいよ」
(どういう意味?)
雪は怪訝な顔をした。すでに死を宣告されている提案など、飲めるはずがない。
女はよほど確信があるらしい。自身に満ちた声で続ける。
「あたしの旦那――・・・いや、もうただの骸になっちまったけどね。あの男の葬儀を取り仕切らなきゃいけない。屍食鬼に邪魔されたくないんだよ」
(屍食鬼・・・?)
雪は首を傾げる。やがて、女の言わんとすることがひしひしと伝わってきた。
女は構わず続ける。
「まあ、生きてるときはろくな男じゃなかったさ。女を囲って、あたしとはろくに会話すらしない旦那だった。・・・でも、あんなのでも夫は夫。葬式ぐらい、無事に終わらせてやるくらいはしてやってもいいと思ってね」
(・・・それは、つまり?)
奇妙な感じだ。雪のこめかみを、脂汗がすべる。
女はひょうひょうと、なんでもないことのように言った。
「あんた、あたしの旦那の代わりに、鬼に喰われてくれないかい?」
時が、止まった気がした。
場違いな小鳥のさえずりが、うるさいくらい耳につく。だが、不快ではない。
待ち焦がれた瞬間が、ようやく訪れた気がしたのだ。
先程まで、雪は山猫のような眼で女を睨んでいた。その言葉を聞いた今、雪は別人のような顔へ変貌した。
眉間のしわはゆるゆると穏やかになっていく。
蕾がほころぶように、噛み締めた唇が緩んでいく。
わたし――・・・・・・。
雪は、はにかんだ。
ふわり。
それは美しすぎるほど。
子供のような、無邪気な笑顔だった。
――苦しみが、終わる時が、来た。
「承諾、だね」
女は変わらぬ調子で言った。
腕を組み、煙管をふかす様子は、まったく動じた様子もない。
ひょっとしたら、心が冷たい鉄でできているのかもしれない。
女の一声で、村人たちが駆けつける。てきぱきと指示を出すと、動くこともままならない雪をおぶらせ、連れ帰った。