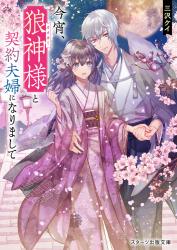始まりは、だんだんと春の心地よい風が吹き始めた頃だった。
日増しに長くなる昼間と過ごしやすい陽気に、外郭城──皇城の周囲に広がる町に住む人々も夜の行動時間が増す。
そんなある日の晩、ひとりの男がほろ酔い気分で機嫌よく川辺を歩いているとふと川の方向から物音がした。怪訝に思って近づこうとしたとき、突如川の向こうに火の玉が現れた。そしてその火の玉は川辺に沿うように空を浮き、横切ったのだという。
「春先に川辺で? それは蛍ではないでしょうか」
玲燕は真っ先に思いついた原因を告げる。
川辺で見られる光と言えば、蛍が定石だ。ほろ酔いということは、その光を見たのは酔っ払いということだ。つまり、蛍の光を火の玉だと勘違いしたのではなかろうか。
「当初は皆、酔っ払いの痴れ言(しれごと)だと笑い話で終わらせていたのだよ。玲燕の言うとおり、蛍ではないかと疑う者も多かった。しかし、その日以降も度々火の玉が目撃されるようになって、刑部にも情報が入ってきてね。ここまで目撃情報が多いと、単純に蛍を見間違えているとも思えない」
「場所は?」
日増しに長くなる昼間と過ごしやすい陽気に、外郭城──皇城の周囲に広がる町に住む人々も夜の行動時間が増す。
そんなある日の晩、ひとりの男がほろ酔い気分で機嫌よく川辺を歩いているとふと川の方向から物音がした。怪訝に思って近づこうとしたとき、突如川の向こうに火の玉が現れた。そしてその火の玉は川辺に沿うように空を浮き、横切ったのだという。
「春先に川辺で? それは蛍ではないでしょうか」
玲燕は真っ先に思いついた原因を告げる。
川辺で見られる光と言えば、蛍が定石だ。ほろ酔いということは、その光を見たのは酔っ払いということだ。つまり、蛍の光を火の玉だと勘違いしたのではなかろうか。
「当初は皆、酔っ払いの痴れ言(しれごと)だと笑い話で終わらせていたのだよ。玲燕の言うとおり、蛍ではないかと疑う者も多かった。しかし、その日以降も度々火の玉が目撃されるようになって、刑部にも情報が入ってきてね。ここまで目撃情報が多いと、単純に蛍を見間違えているとも思えない」
「場所は?」