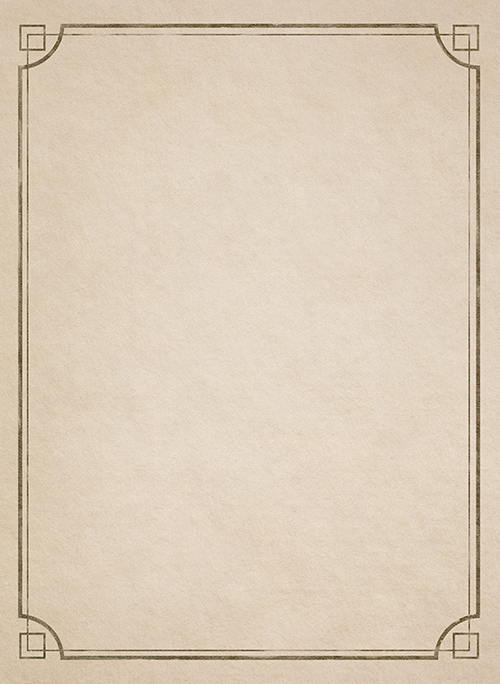「そういうわけで、瀬戸さん、俺と付き合ってください!」
――何がそういうわけなのだろうか?
心の中で思いながら瀬戸ユウリは目の前の男子を見る。
名前も知らない男子に呼び出されたからその場で終わらせてという事で用件を伝えた所いつもの事だった。
昨日の怪異の出来事が薄れぬまま、いつも通りと言えるような日常。
周りの女子達は冷めた目で、男子達は敵意を告白してきた者へ向けている。
代わり映えしない、灰色の日常。
「沈黙は肯定ってことで」
「お断り、今は付き合うつもりはないから」
「え」
告白してきた男子が呆然とした表情でこちらをみてくる。
もう終わったと判断してそのまま背を向けた。
ふと、あの時の出来事が脳裏を過る。
怪異というわけのわからない存在、そして、自分を狙う赤い死神と呼ばれた存在。
そんな奴から自分を守ってくれた新城凍真。
「なぁ、待って、待ってくれよ!」
教室内に響く大きな声と衝撃で肩を掴まれて振り返らされる。
「なんで、ダメなんだよ!そんなばっさりされるなんて俺は納得ができない!」
必死という男子生徒の顔があの赤い死神と被る。
体が恐怖に包まれそうになる。
――望んでいるものを掴む。
あの時、彼、新城凍真と話をしていた時の記憶が過った。
いつもの灰色の日常。
そんなものは欲しくない。
「私が望むのは」
「え?」
「アンタなんかに興味ない!恋愛も興味ないんだよぉ!」
叫びと共に目の前の邪魔者を追い払うべく足を前に踏み出した。
同時刻。
「目の前に現れた敵を倒して終わりならそれでハッピーエンドなんだけど、それで終わらないのが怪異なんだよな」
肩を竦める新城の傍で僕は十手を構える。
「いやぁ、流石、文献に名前が残っている怪異様だよ。あれで封印できたと思っていたらまさか、体の一部を千切って人に寄生しているなんて思わなかったよ。本当に、いや、参った、参った」
新城の目は真っすぐに目の前の女子生徒へ向けられている。
髪を染めて、ピアス等をつけた女子。
瀬戸さんのクラスにいた子だが、その目はどす黒く濁って、口は三日月に裂けて笑っている。
「新城、どうすればいいの?」
「幸いにも完全に乗っ取られたわけじゃないからな、引きはがせばなんとかなる。まぁ、乗っ取られている子は辛いだろうけれど」
「僕はどうしたら?」
「数分でいい、抑え込んでいろ。俺が祓う」
「わかった」
話し合っている間に赤い死神に寄生された女子生徒が走り出す。
両手をだらんとさせながら走ってくる姿は不気味だ。
僕も駆け出して十手を前に突き出す。
「グッ!」
十手を腹部に受けた女子生徒は苦悶の声をあげるも、すぐに両手を伸ばしてくる。
その手を払いのけながら一定の距離を保つ。
後ろで新城が赤い死神を女子生徒から引きはがす為の言葉を唱えている。
自分にとって害となる行動を新城がとっていることに気付きながらも死神は行動に移せない。いや、僕がさせない。
僕は足払いで死神を地面に倒す。
そのまま腕を掴んで起き上がれないように抑え込んだ。
暴れる死神だけど、体は女の子のもので、関節技を使って抑え込んでいるから拘束から逃れることはできない。
新城の術が効いていたのか死神が言葉を発する。
何を話しているのかわからないけれど、ジタバタと暴れていることから苦しんでいるのだろう。
しばらく痙攣をしていると思ったら動かなくなる。
「拘束、解いていいぞ」
「終わったの?」
傍まで近づいてきて新城が声をかけてくる。
「あぁ、祓った。死神の体の一部はここに封じ込めてある」
手の中に小さな瓶があって、蓋の部分に札が何枚か貼り付けられていた。
「これで終わりってこと?」
「あぁ、本当の意味で終わりだよ。お疲れさん」
そういって新城が肩を叩いてくる。
僕は安心して、手の中の十手を返そうとした。
すると新城がその手を押し戻す。
「ソイツはお前がもってろ」
「え、でも」
「その十手とお前の相性は良いみたいだからな、いつも俺が渡してっていうのも面倒だ。これからも俺の右手として動いてもらうわけだし、持っておけ」
僕は新城に戻された十手を握りしめる。
今まで何かを祓う際になってから新城に道具を渡されてばかりだった。
あまり新城は他人を信用していないに思っていた。だから、道具を新城からもらえたという事に僕は仲間として認めてもらえたように思えて嬉しい。
「そういえば、本気で拘束しちゃったけど、この子、大丈夫かな?」
「まぁ、ちょうどいい罰になったんじゃないか」
「え?」
新城は気絶している女子生徒の服の中をごそごそと漁ると携帯電話を取り出す。
止める暇もなく携帯電話を操作してあるページをみせる。
「なに、これ?」
「この女、瀬戸ユウリを賭けの対象として学校の裏サイトで儲けていたんだよ。その賭けに乗っかってアイツに告白しようとするバカが後を絶たない状況も作り上げていた」
「えぇ~」
赤い死神に寄生された人がまさか裏でそんなことをやっていたことに僕は驚きの声を上げる。
「赤い死神がどうして瀬戸ユウリに狙いを付けたのか調べていたら偶然見つけた。そうしたらまぁ、出るわ出るわ色々な恨みつらみの言葉、ま、狙っていた男子がアイツに告白して振られた逆恨みみたいだけど~」
「女子って、怖いね」
「お前も似たような経験ある癖に、まぁ、今後も似たようなことを仕出かさないようにアフターサービスでお灸をすえてやるつもりが、意外な展開だったな。さて、データも初期化したからこれでアイツに悪さをできないだろうな」
放り投げられた携帯は何をされたのか不気味な音を立てながら初期化されていっている。
目を覚ました時の女子生徒の悲鳴が浮かんでしまい、哀れに思う。
いや、そもそもこの子が原因で彼女が怪異に狙われる切欠となっているわけだから自業自得だろう。
哀れみの感情はすぐに消えて仕方ないねという気持ちになった。
「さ、行くぞ」
「うん。これで依頼達成だね」
「そうだな。あのうるさい奴の顔をみなくて済む」
ふわぁと欠伸を噛み殺す新城の後を僕は追いかける。
新城凍真は放課後、ある報告書を手に車へ乗り込む。
「よう、待っていたぞ」
「今回の報告書だ。それを提出すれば上も満足するだろうよ」
「おう、サンキュ」
受け取った封筒を開いて中身を確認する長谷川。
「しっかし、本当に赤い死神を封印してしまうなんて、陰陽塾の連中が聞いたら腰抜かすんじゃないか?」
「そうなったら面倒だからアンタに色々と誤魔化した書類を渡しているんだ」
シートに深く腰を沈めながら新城は睨む。
「わーっているよ。手柄はこちらが貰う代わりに情報を誤魔化すって話。しかし、赤い死神が狙っていた瀬戸ユウリって娘、本当に陰陽師の家系なのか?」
「元、だがな。資料を見るまで確信を持てなかったけどな」
長い歴史の中で多くの陰陽師の血が失われていた。
過去の時代は名家と言われていた者達の血は経たれ、失われた術も沢山ある。
「怪異が元陰陽師の血筋を持つあの女を狙った事で発覚したわけだが、この情報を陰陽塾の連中が知る事だけは避けたいんだよ」
「わかっているって、普通の女の子をこんなおどろおどろしい世界へようこそなんてやりたくないしな」
「……わかっているならいい。俺は帰る」
「今回は」
車を降りようとした所で長谷川が呼び止める。
「今回だけはそっちの要求を呑んでやるが、何度も元陰陽師とかの血筋発見を隠しておけるほど、こっちも余裕があるってわけじゃねぇからな、お前もわかっているだろう?怪異の発生は年々、増えている。戦力はどこも欲しがるんだよ」
「そんなこと、嫌でもわかっているさ」
会話は終わりだという意思を表すように車のドアを乱暴に閉める。
「怪異なんて、関わらない方が幸せなんだよ」
髪に隠れている眼帯に触りながら新城は去っていく。
翌日、僕はいつものように特別教室へ向かった。
怪異の事件は終わった。
いつも通りの日常が戻ってくる。
「おはよう」
筈だった。
「え、瀬戸さん?どうして、ここに?もしかして何かあった?」
「今日から特別教室に通うことになったからよろしく」
「どういうこと!?」
驚いていると寝袋に丸まっていた新城がむくりと体を起こす。
「うっさいぞ、朝から」
「え、新城、これはどういうこと!?」
「あ?チッ」
新城はちらりと瀬戸さんを見ると舌打ちをした。
「そこのバカが問題を起こして工藤の判断で特別教室移動になったんだよ」
「問題?」
「バカとは何よ!アンタの言った事を実行に移しただけよ。望むものを掴もうとしただけよ」
「え、話が見えないんだけど?」
困惑している僕にため息を零しながら新城が説明してくれた。
昨日の放課後、瀬戸さんにまたも男子の告白があったらしい。
ばっさりと断った所、逆上する男子生徒。
その男子生徒を瀬戸さんは撃退したという。
「急所を思いっきり蹴飛ばしたのよ。すっきりしたわぁ」
撃退方法がなんというか凄い。
そして、その撃退方法が色々と問題だと騒いだ教師がいたらしくて瀬戸さんを守るために工藤先生が特別教室所属に決めたのだという。
「そういうわけだから今日からよろしくね」
「うん、でも、その大丈夫?僕達と一緒にいると嫌な思い出とか」
怪異と遭遇した人達はその時の記憶を思い出すことを嫌がることがある。
瀬戸さんも守っていたとはいえ、怪異に命を狙われていたわけだから僕達と接触しない方が良いと思う。
「嫌な思い出?とんでもない!アンタ達みたいな凄い人達と一緒に居られることの方が最高だから!」
にっこりと微笑む瀬戸さんの顔に嘘はない。
「今度、怪異の事件とかあったらアタシも協力するから」
「え?」
「バカに付ける薬はなしか」
「ちょっと、さっきからバカバカって何よ!アタシの名前は瀬戸ユウリなの!ちゃんと名前で呼んでよ!新城!」
呆れた新城へ瀬戸さんが詰め寄っていく。
どうやら彼女は本気で僕達と関わっていくらしい。
日常の変化に戸惑いながらも僕は自然とそれを受け入れていくのだろう。
こうして新しく瀬戸ユウリさんを加えた日常がはじまっていく。
――何がそういうわけなのだろうか?
心の中で思いながら瀬戸ユウリは目の前の男子を見る。
名前も知らない男子に呼び出されたからその場で終わらせてという事で用件を伝えた所いつもの事だった。
昨日の怪異の出来事が薄れぬまま、いつも通りと言えるような日常。
周りの女子達は冷めた目で、男子達は敵意を告白してきた者へ向けている。
代わり映えしない、灰色の日常。
「沈黙は肯定ってことで」
「お断り、今は付き合うつもりはないから」
「え」
告白してきた男子が呆然とした表情でこちらをみてくる。
もう終わったと判断してそのまま背を向けた。
ふと、あの時の出来事が脳裏を過る。
怪異というわけのわからない存在、そして、自分を狙う赤い死神と呼ばれた存在。
そんな奴から自分を守ってくれた新城凍真。
「なぁ、待って、待ってくれよ!」
教室内に響く大きな声と衝撃で肩を掴まれて振り返らされる。
「なんで、ダメなんだよ!そんなばっさりされるなんて俺は納得ができない!」
必死という男子生徒の顔があの赤い死神と被る。
体が恐怖に包まれそうになる。
――望んでいるものを掴む。
あの時、彼、新城凍真と話をしていた時の記憶が過った。
いつもの灰色の日常。
そんなものは欲しくない。
「私が望むのは」
「え?」
「アンタなんかに興味ない!恋愛も興味ないんだよぉ!」
叫びと共に目の前の邪魔者を追い払うべく足を前に踏み出した。
同時刻。
「目の前に現れた敵を倒して終わりならそれでハッピーエンドなんだけど、それで終わらないのが怪異なんだよな」
肩を竦める新城の傍で僕は十手を構える。
「いやぁ、流石、文献に名前が残っている怪異様だよ。あれで封印できたと思っていたらまさか、体の一部を千切って人に寄生しているなんて思わなかったよ。本当に、いや、参った、参った」
新城の目は真っすぐに目の前の女子生徒へ向けられている。
髪を染めて、ピアス等をつけた女子。
瀬戸さんのクラスにいた子だが、その目はどす黒く濁って、口は三日月に裂けて笑っている。
「新城、どうすればいいの?」
「幸いにも完全に乗っ取られたわけじゃないからな、引きはがせばなんとかなる。まぁ、乗っ取られている子は辛いだろうけれど」
「僕はどうしたら?」
「数分でいい、抑え込んでいろ。俺が祓う」
「わかった」
話し合っている間に赤い死神に寄生された女子生徒が走り出す。
両手をだらんとさせながら走ってくる姿は不気味だ。
僕も駆け出して十手を前に突き出す。
「グッ!」
十手を腹部に受けた女子生徒は苦悶の声をあげるも、すぐに両手を伸ばしてくる。
その手を払いのけながら一定の距離を保つ。
後ろで新城が赤い死神を女子生徒から引きはがす為の言葉を唱えている。
自分にとって害となる行動を新城がとっていることに気付きながらも死神は行動に移せない。いや、僕がさせない。
僕は足払いで死神を地面に倒す。
そのまま腕を掴んで起き上がれないように抑え込んだ。
暴れる死神だけど、体は女の子のもので、関節技を使って抑え込んでいるから拘束から逃れることはできない。
新城の術が効いていたのか死神が言葉を発する。
何を話しているのかわからないけれど、ジタバタと暴れていることから苦しんでいるのだろう。
しばらく痙攣をしていると思ったら動かなくなる。
「拘束、解いていいぞ」
「終わったの?」
傍まで近づいてきて新城が声をかけてくる。
「あぁ、祓った。死神の体の一部はここに封じ込めてある」
手の中に小さな瓶があって、蓋の部分に札が何枚か貼り付けられていた。
「これで終わりってこと?」
「あぁ、本当の意味で終わりだよ。お疲れさん」
そういって新城が肩を叩いてくる。
僕は安心して、手の中の十手を返そうとした。
すると新城がその手を押し戻す。
「ソイツはお前がもってろ」
「え、でも」
「その十手とお前の相性は良いみたいだからな、いつも俺が渡してっていうのも面倒だ。これからも俺の右手として動いてもらうわけだし、持っておけ」
僕は新城に戻された十手を握りしめる。
今まで何かを祓う際になってから新城に道具を渡されてばかりだった。
あまり新城は他人を信用していないに思っていた。だから、道具を新城からもらえたという事に僕は仲間として認めてもらえたように思えて嬉しい。
「そういえば、本気で拘束しちゃったけど、この子、大丈夫かな?」
「まぁ、ちょうどいい罰になったんじゃないか」
「え?」
新城は気絶している女子生徒の服の中をごそごそと漁ると携帯電話を取り出す。
止める暇もなく携帯電話を操作してあるページをみせる。
「なに、これ?」
「この女、瀬戸ユウリを賭けの対象として学校の裏サイトで儲けていたんだよ。その賭けに乗っかってアイツに告白しようとするバカが後を絶たない状況も作り上げていた」
「えぇ~」
赤い死神に寄生された人がまさか裏でそんなことをやっていたことに僕は驚きの声を上げる。
「赤い死神がどうして瀬戸ユウリに狙いを付けたのか調べていたら偶然見つけた。そうしたらまぁ、出るわ出るわ色々な恨みつらみの言葉、ま、狙っていた男子がアイツに告白して振られた逆恨みみたいだけど~」
「女子って、怖いね」
「お前も似たような経験ある癖に、まぁ、今後も似たようなことを仕出かさないようにアフターサービスでお灸をすえてやるつもりが、意外な展開だったな。さて、データも初期化したからこれでアイツに悪さをできないだろうな」
放り投げられた携帯は何をされたのか不気味な音を立てながら初期化されていっている。
目を覚ました時の女子生徒の悲鳴が浮かんでしまい、哀れに思う。
いや、そもそもこの子が原因で彼女が怪異に狙われる切欠となっているわけだから自業自得だろう。
哀れみの感情はすぐに消えて仕方ないねという気持ちになった。
「さ、行くぞ」
「うん。これで依頼達成だね」
「そうだな。あのうるさい奴の顔をみなくて済む」
ふわぁと欠伸を噛み殺す新城の後を僕は追いかける。
新城凍真は放課後、ある報告書を手に車へ乗り込む。
「よう、待っていたぞ」
「今回の報告書だ。それを提出すれば上も満足するだろうよ」
「おう、サンキュ」
受け取った封筒を開いて中身を確認する長谷川。
「しっかし、本当に赤い死神を封印してしまうなんて、陰陽塾の連中が聞いたら腰抜かすんじゃないか?」
「そうなったら面倒だからアンタに色々と誤魔化した書類を渡しているんだ」
シートに深く腰を沈めながら新城は睨む。
「わーっているよ。手柄はこちらが貰う代わりに情報を誤魔化すって話。しかし、赤い死神が狙っていた瀬戸ユウリって娘、本当に陰陽師の家系なのか?」
「元、だがな。資料を見るまで確信を持てなかったけどな」
長い歴史の中で多くの陰陽師の血が失われていた。
過去の時代は名家と言われていた者達の血は経たれ、失われた術も沢山ある。
「怪異が元陰陽師の血筋を持つあの女を狙った事で発覚したわけだが、この情報を陰陽塾の連中が知る事だけは避けたいんだよ」
「わかっているって、普通の女の子をこんなおどろおどろしい世界へようこそなんてやりたくないしな」
「……わかっているならいい。俺は帰る」
「今回は」
車を降りようとした所で長谷川が呼び止める。
「今回だけはそっちの要求を呑んでやるが、何度も元陰陽師とかの血筋発見を隠しておけるほど、こっちも余裕があるってわけじゃねぇからな、お前もわかっているだろう?怪異の発生は年々、増えている。戦力はどこも欲しがるんだよ」
「そんなこと、嫌でもわかっているさ」
会話は終わりだという意思を表すように車のドアを乱暴に閉める。
「怪異なんて、関わらない方が幸せなんだよ」
髪に隠れている眼帯に触りながら新城は去っていく。
翌日、僕はいつものように特別教室へ向かった。
怪異の事件は終わった。
いつも通りの日常が戻ってくる。
「おはよう」
筈だった。
「え、瀬戸さん?どうして、ここに?もしかして何かあった?」
「今日から特別教室に通うことになったからよろしく」
「どういうこと!?」
驚いていると寝袋に丸まっていた新城がむくりと体を起こす。
「うっさいぞ、朝から」
「え、新城、これはどういうこと!?」
「あ?チッ」
新城はちらりと瀬戸さんを見ると舌打ちをした。
「そこのバカが問題を起こして工藤の判断で特別教室移動になったんだよ」
「問題?」
「バカとは何よ!アンタの言った事を実行に移しただけよ。望むものを掴もうとしただけよ」
「え、話が見えないんだけど?」
困惑している僕にため息を零しながら新城が説明してくれた。
昨日の放課後、瀬戸さんにまたも男子の告白があったらしい。
ばっさりと断った所、逆上する男子生徒。
その男子生徒を瀬戸さんは撃退したという。
「急所を思いっきり蹴飛ばしたのよ。すっきりしたわぁ」
撃退方法がなんというか凄い。
そして、その撃退方法が色々と問題だと騒いだ教師がいたらしくて瀬戸さんを守るために工藤先生が特別教室所属に決めたのだという。
「そういうわけだから今日からよろしくね」
「うん、でも、その大丈夫?僕達と一緒にいると嫌な思い出とか」
怪異と遭遇した人達はその時の記憶を思い出すことを嫌がることがある。
瀬戸さんも守っていたとはいえ、怪異に命を狙われていたわけだから僕達と接触しない方が良いと思う。
「嫌な思い出?とんでもない!アンタ達みたいな凄い人達と一緒に居られることの方が最高だから!」
にっこりと微笑む瀬戸さんの顔に嘘はない。
「今度、怪異の事件とかあったらアタシも協力するから」
「え?」
「バカに付ける薬はなしか」
「ちょっと、さっきからバカバカって何よ!アタシの名前は瀬戸ユウリなの!ちゃんと名前で呼んでよ!新城!」
呆れた新城へ瀬戸さんが詰め寄っていく。
どうやら彼女は本気で僕達と関わっていくらしい。
日常の変化に戸惑いながらも僕は自然とそれを受け入れていくのだろう。
こうして新しく瀬戸ユウリさんを加えた日常がはじまっていく。