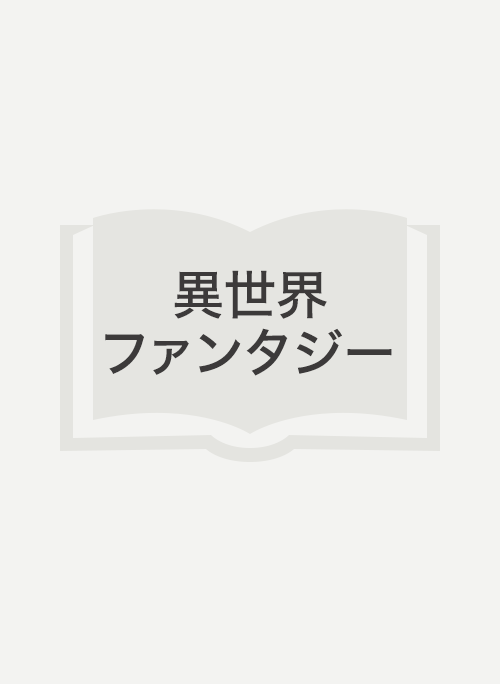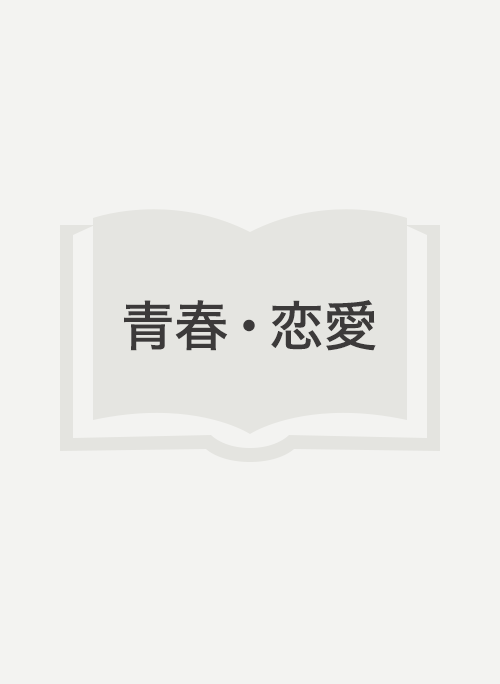あります、とはどういうことなのか。
なぜ数を答えなかったのか。
新久郎には千紗の考えていることが理解できなかった。
三のような数ではない、何かなのか。
分からない。
新久郎は老師の横顔を眺めて次の言葉を待っていた。
「やはりおぬしには見えるのであるな」と、方正斎は目を細めて千紗にうなずいてみせた。「良い目をしておるな」
新久郎は老師に詰め寄った。
「いったいどういうことですか、先生」
「平方の根を求めることは天元術(方程式)を用いればよい。ただし、そのとき、解が二つ生じてしまう。双方が正であれば良しとされるが、負であれば病題(答えのない悪い問題)とされる」
「はい」
「逆に、正であれ負であれ、二乗した数は常に正となるのが道理」
「はい。負の数を掛け合わせれば正となります」
「だが、わしは二乗して負になる数があると常々考えておるのだ」
「しかし、それでは道理に合わぬではありませんか」
「さよう」と、老師が顎をなでる。「だが、まだ見ぬ道理もあるのやもしれん」
そうですか、と新久郎は千紗に目を向けた。
口をまっすぐに結んで方正斎を見上げていた千紗は地面に描かれた円に内接する正五角形を指さした。
「むむっ」とうなると、方正斎が腕組みをして円周上にある五つの点を見つめる。「おお、そなたにはこれが解に見えるのだな。それでこの図形を描くのが好きなのか」
「はい」と、極楽から舞い降りた天女のような声で千紗はうなずいた。
「なるほど。これがそうなのか」と、老師は満足そうに何度もうなずいている。「わしにも正確には分からぬことだが、こうして見ると、そこに何かがあるのは分かる。いや、良い物を見せてもらった」
方正斎は愉快そうに笑う。
その横で新久郎は悟られぬように静かにため息を漏らした。
師匠にすらおぼろげにしか見えないものが千紗にははっきりと見えているのだ。
だが、彼にはただの五角形にしか見えない。
千紗はいったいどこにいるのか。
目の前にいるようで、どこか遠いところにいる。
川の向こう、海の向こう、それとも遙か山の向こうなのか。
新久郎の知らないどこか遠く、もしかしたら千紗は本当に天女なのかもしれない。
老師がつぶやく。
「江戸で学んでいた頃、わしの師匠は負の平方を提唱したが異端とされてな。師の師匠から破門されてもなお独学で追究しようとなされたのだが、病に倒れてしまってのう。さぞ無念であったことであろう」
老師は目を閉じた。
「わしもすでに師の齢を越えてしまったが、未だに見えぬ。天元術に算木は並べどもそこにある数は見えんのだ。もどかしゅうてならん。今ではわしもこんな田舎に引っ込んでおるが、江戸や長崎の学問がどうなっておるのか見てみたいものじゃ」
なぜ数を答えなかったのか。
新久郎には千紗の考えていることが理解できなかった。
三のような数ではない、何かなのか。
分からない。
新久郎は老師の横顔を眺めて次の言葉を待っていた。
「やはりおぬしには見えるのであるな」と、方正斎は目を細めて千紗にうなずいてみせた。「良い目をしておるな」
新久郎は老師に詰め寄った。
「いったいどういうことですか、先生」
「平方の根を求めることは天元術(方程式)を用いればよい。ただし、そのとき、解が二つ生じてしまう。双方が正であれば良しとされるが、負であれば病題(答えのない悪い問題)とされる」
「はい」
「逆に、正であれ負であれ、二乗した数は常に正となるのが道理」
「はい。負の数を掛け合わせれば正となります」
「だが、わしは二乗して負になる数があると常々考えておるのだ」
「しかし、それでは道理に合わぬではありませんか」
「さよう」と、老師が顎をなでる。「だが、まだ見ぬ道理もあるのやもしれん」
そうですか、と新久郎は千紗に目を向けた。
口をまっすぐに結んで方正斎を見上げていた千紗は地面に描かれた円に内接する正五角形を指さした。
「むむっ」とうなると、方正斎が腕組みをして円周上にある五つの点を見つめる。「おお、そなたにはこれが解に見えるのだな。それでこの図形を描くのが好きなのか」
「はい」と、極楽から舞い降りた天女のような声で千紗はうなずいた。
「なるほど。これがそうなのか」と、老師は満足そうに何度もうなずいている。「わしにも正確には分からぬことだが、こうして見ると、そこに何かがあるのは分かる。いや、良い物を見せてもらった」
方正斎は愉快そうに笑う。
その横で新久郎は悟られぬように静かにため息を漏らした。
師匠にすらおぼろげにしか見えないものが千紗にははっきりと見えているのだ。
だが、彼にはただの五角形にしか見えない。
千紗はいったいどこにいるのか。
目の前にいるようで、どこか遠いところにいる。
川の向こう、海の向こう、それとも遙か山の向こうなのか。
新久郎の知らないどこか遠く、もしかしたら千紗は本当に天女なのかもしれない。
老師がつぶやく。
「江戸で学んでいた頃、わしの師匠は負の平方を提唱したが異端とされてな。師の師匠から破門されてもなお独学で追究しようとなされたのだが、病に倒れてしまってのう。さぞ無念であったことであろう」
老師は目を閉じた。
「わしもすでに師の齢を越えてしまったが、未だに見えぬ。天元術に算木は並べどもそこにある数は見えんのだ。もどかしゅうてならん。今ではわしもこんな田舎に引っ込んでおるが、江戸や長崎の学問がどうなっておるのか見てみたいものじゃ」