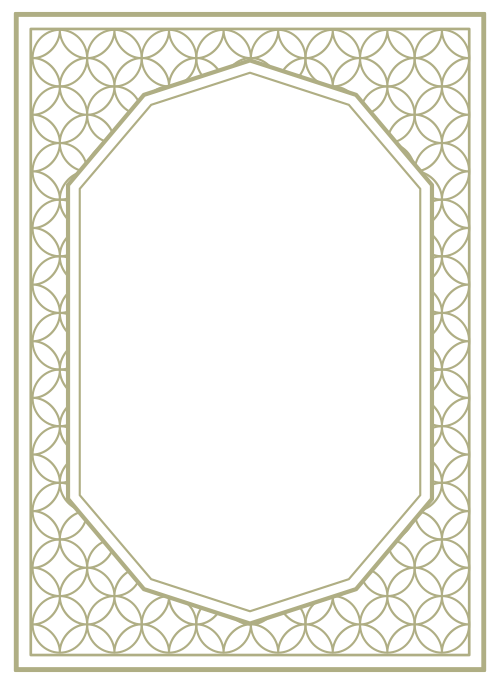購買部でも笠寺たちの姿を見なくなった。三年生は自由登校になっていたのだと知ったのは、早紀に言われたからだった。
「南校舎、寂しく見えるね……」
早紀が言うのに、曖昧に頷くことしかできない。早紀にそう見えるのは当たり前だが、小春にそう見えるのは、本当に三年生が少ないからだけのことなのか、分からなくなってしまっていたのだ。
――『無駄なことはしないほうがいいよ』
そう言った尾上の顔が忘れられない。まるで、全ての非を自分で背負って、小春にだけ穏やかな道を用意するみたいな、そんな表情。
ずるいと思う。
最初から、最後まで、尾上は小春に強い印象を植え付けてばかりだ。笠寺を横に立たせて怒った顔で校門に立っていたとき以来、本当に尾上のことを考えない日はない。小春の許を去って行こうとするのなら、もっと消えるようにいなくなってくれればいいのに。
そう思いながら、でも、そんなのは嫌だと思う自分がいることに戸惑う。
自分の記憶を否定するようなことを考えてしまうのが、嫌だった。どんな出来事でも、全部小春の経験であり、思い出だ。それを自ら否定するようなことを、したくはなかった。ましてや、自分じゃない人に否定されるべきものでは、ない。……少なくとも、そう思っていた。
「もう、先輩たち、卒業式まで来ないんだよね……」
寂しそうに、早紀が言う。小春は、自分の記憶を否定したくない一方で、これから先の道がどこに伸びているのか、見極められないでいた。
「寂しくなるね、小春も。折角尾上先輩と仲良くなったのに」
早紀の言葉が、ふっと胸の奥を突いた。
今はまだ、卒業式が控えていて、三年生はそのときには必ず登校してくるけれど、卒業式を超えてしまったら、もうこの校舎にはいなくなるのだ。
小春にとって、仲の良い人との別れと言うのは、後一年後の、早紀と別れる自分達の卒業式の日なんだと思っていた。……その寂しさが、こんなに早く来るなんて、思っていなかった。
急にその寂しさが現実味を帯びる。
もう会えないのだ。
進路も、きっと小春の進路とは全く違うことだろう。だとしたら、もう卒業式の日にしか、会えない。その日を逃したら、もうこの先二度と、会うことはない人なのだ。
短かったけど、四人で仲良くした時間。あの時間たちは確かに小春の中に息づいていて、それが今では心をあたたかくしてくれる。笠寺も、……尾上だって、本当に小春たちに良くしてくれた。ぴりぴりした雰囲気の多い三年生とは思えないようなフレンドリーさで話し掛けてくれていた。小春を見つめてくれた眼差しには、からかいの後ろに、ちゃんとした気遣いとやさしさが詰まっていた。
どこへ、行くんだろうと思う。自分の、今の気持ちは。
ただ、あの時間が過去になってしまうのが、残念だった。
……それだけは、確かだった。