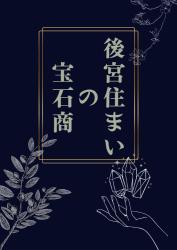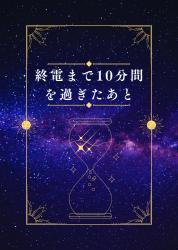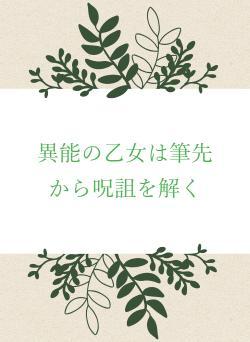その日から、一の姫はすっかり漢詩の勉強を楽しむようになった。
拙いながらも自分で漢詩を詠むようにもなった。
乳母は泣きながら喜んだ。
「何もかも夕少納言様がいらしてくださったおかげでございます! この調子で和歌も練習してくださると良いのですが……」
この時代、何はともあれ和歌を詠むのが貴族達の伝達方法である。
それならばと、夕少納言は香炉峰の雪の話をすることにした。
「一の姫様、今日は『香炉峰下新卜山居』を詠みましょう」
香炉峰というのは山の名前だ。
「これは白居易が左遷されたときに詠んだ漢詩でございます。左遷された先の住居で御簾を押し上げ、香炉峰に積もる雪を見る……という内容ですね」
一の姫はふむふむと興味深そうに何度も頷きながら夕少納言の解説を聞く。
「清少納言という人をご存知ですね?」
「ええ、もちろん」
「彼女はある雪の日、お仕えしていた中宮様からこう尋ねられます。『香炉峰の雪いかならむ』と。もちろん京の都から香炉峰など見えません。しかし清少納言は御簾を上げさせたのです。これは『香炉峰下新卜山居』を知っているからこそ通じたのです。これは和歌でも同じ事ができます。試しに白居易の漢詩を引いて和歌を詠んでみませんか」
一の姫はすっかりかつての女房の機知に感じ入り、こくこくとうなずいた。
そうして一の姫は漢詩から着想を得た和歌を詠むようになっていった。
「ああ、早く冬にならないかしら。そうしたら私、あなたに香炉峰の雪について尋ねるわ!」
「あらあら……」
夕少納言はそんな一の姫を微笑ましく思った。
夕少納言が一の姫の元に来てからというもの、式部卿宮は幾度か一の姫の元に遊びに来た。
その度に梅の花や、桜の花、桃の花を持ってきてくれた。
初めて会ったときに歌った『春風』に掛けているのだと夕少納言にはわかった。
「これは一の姫様のお部屋を照らすために、そしてこちらは……あなたの側にどうぞ、私だと思って」
そう言って式部卿宮は一の姫に渡す花束の他に、一枚の花びらを取り次ぎをする夕少納言にそっと握らせていくのであった。
「お、お、お、恐れ多いことで……」
夕少納言はそんな式部卿宮の振る舞いにすっかり参ってしまったが、きちんと立場をわきまえていた。
そもそも式部卿宮にはすでに正妻がいた。
右大臣の娘で、式部卿宮が元服した夜に共寝した添い臥しの相手で、年上の妻であった。
いつも着ている装束も、焚きしめられた香りも、すべてその妻の支度である。夜を共に過ごして、朝には仕事へ送り出す。貴人の妻とはそういうものであった。
本来なら、夕少納言の母もそれを父にするはずであったが、夕少納言が物心ついた頃には、父は他の女の元で夜を過ごし、支度もその女にさせていた。
そういったことを思い出すと、夕少納言の胸はきりきりと痛んだ。
「私は応援するわ!」
一の姫はキラキラと顔を輝かせてそう言った。
「男君など恋人の一人や二人いての甲斐性ではないの」
「……一の姫様」
夕少納言は苦笑して姫君を諫めた。
「私ごとき式部卿宮には釣り合いませんよ。あれは……それこそ、そう、恋人の……真似事でしょう」
口ではそう達観したことを言いながらも、実際に振る舞われるとすっかりのぼせ上がって顔を真っ赤にしてしまう夕少納言であったが、彼女は冷静であった。
「……私は、父の愛人に邸を追い出されました」
夕少納言は翳った顔でそう言った。
「……夕少納言」
「ですから、愛人にはなりたくないのです。……大仰な夢かもしれませぬが、それが叶わぬなら女房としてここに骨を埋めとうございます」
「不吉だから内裏に骨は埋められないけれど……わかったわ」
一の姫はうなずいた。
「……式部卿宮様のことがご迷惑なら、中宮様から主上に申し上げるようお願いしてみる?」
「い、いいえ! そんなこのような些事で主上や弘徽殿の方を動かすなどとんでもない!」
「そう……」
一の姫はふうとため息をついた。
夕少納言は寂しげに微笑んだ。
さて、一方その頃、夕少納言が内裏に上がった後、綾大輔は息子の家に退いた。
夫はすでに亡かったが、綾大輔の息子は孝行息子で綾大輔を快く邸に迎え入れた。
しかしその日々は長くは続かなかった。
綾大輔も年齢には勝てず、寝込むようになってしまった。
風の便りにそれを聞いた夕少納言は心配する文を送った。
その返事がくるのにはいささか時間がかかった。
そこにはたった一節、「久為労生事」と震える文字で書かれていた。
これは白居易が若い頃の詩『病中作』の書き出しで、若くして病気をしてしまった、長生きが出来るであろうか、という意味の漢詩であった。
一の姫が、心配そうに夕少納言の顔を見た。
「ああ、夕少納言、綾大輔はなんて?」
「……あまり、お体、かんばしくないようで……」
つっかえつっかえ夕少納言はそう言った。震える文字から、綾大輔の病状が手に取るようにわかるようであった。
「そう……。お見舞いに行く?」
夕少納言の態度から、一の姫にもその病状は伝わったのであろう。
一の姫が気遣わしげにそう言った。
「いえ……綾大輔様のご子息様にご迷惑ですから……」
「…………」
一の姫はため息をついたが、多くを語らなかった。
それからしばらく、暑さが増してきた頃、綾大輔の訃報が届いた。
夕少納言は一の姫の前では気丈に振る舞った。
しかし、夜になって、夕少納言はこっそり局を抜け出し、外でひとりシクシクと泣いた。
まだ夜は冷えたが、気にならなかった。
「……夕少納言」
そんな夕少納言に声をかける者があった。ビクリと肩を震わすと、そこには式部卿宮が立っていた。
「し、式部卿宮様……。何故、こちらに……」
「……綾大輔の事は私達の耳にも入りまして。主上と思い出話に花が咲いてしまいました」
式部卿宮からは微かに酒の香りがした。兄弟で母に仕えていた女房を偲んで酒を酌み交わしていたようだ。
「後日、私が主上の名代で綾大輔の息子のところへ、経を納めにうかがいます。何か言伝などあれば……」
「…………」
夕少納言は少し考えて、首を横に振った。
「ごめんなさい、何も思い付かない……」
「わかりました、何かありましたら、いつでも仰せ付けください」
式部卿宮は柔らかく微笑んだ。
「その様子では、今夜は寝られますまい。我らも、思い出話をしましょうか」
式部卿宮に促され、夕少納言は小さくうなずいた。
「……こちらでお仕えしていた頃の綾大輔は、どうでしたの」
「……春風は、綾大輔に習ったのです」
式部卿宮はにこりと笑ってそう言った。その目には少しの寂しさが混じっていた。
「春の花の咲く中……ああ、なんて懐かしい」
式部卿宮は近くの木を振り仰いだ。
もう花は散っていた。
「……花が散ってしまいましたね」
「……老いて香山に住せんとして初めて到る夜」
夕少納言は木より上の月を見て、そうつぶやいた。
それは香山とは白居易の親友が眠る寺のことであった。
香山に赴いて月を見、それはその日から、自分の家の月にもなるのだ、という香山への親しみを感じさせる詩であった。
「秋、白月の正に円なる時に逢う。今より便ち是れ家山の月。試みに問う、清光知るや知らずや」
涙に濡れた声で夕少納言はそう言った。
「……ええ、そうですね。我らの友ですとも、綾大輔は」
気付けば、式部卿宮は夕少納言の側近くに寄っていた。
夕少納言が何かをする暇もなく、式部卿宮は夕少納言を抱きしめた。
「……いけません、いけません」
夕少納言は力なく首を横に振った。
「三日間、こうしてあなたのもとに通いましょう」
式部卿宮は夕少納言の耳元でそう囁いた。
男が女の元に三日通うと結婚が成立する。式部卿宮が言っているのはそういうことだった。
「この内裏で餅を用意しろなどと無茶なことはもちろん申しませんとも」
くすりと式部卿宮は笑った。
三日夜餅といって、男に女が三日目の夜に餅を出す。
そうすれば婚姻は成立する。
「ただ……待っていてくだされば、それでいい」
式部卿宮はそう囁くと夕少納言を解放し、そのまま去って行ってしまった。
拙いながらも自分で漢詩を詠むようにもなった。
乳母は泣きながら喜んだ。
「何もかも夕少納言様がいらしてくださったおかげでございます! この調子で和歌も練習してくださると良いのですが……」
この時代、何はともあれ和歌を詠むのが貴族達の伝達方法である。
それならばと、夕少納言は香炉峰の雪の話をすることにした。
「一の姫様、今日は『香炉峰下新卜山居』を詠みましょう」
香炉峰というのは山の名前だ。
「これは白居易が左遷されたときに詠んだ漢詩でございます。左遷された先の住居で御簾を押し上げ、香炉峰に積もる雪を見る……という内容ですね」
一の姫はふむふむと興味深そうに何度も頷きながら夕少納言の解説を聞く。
「清少納言という人をご存知ですね?」
「ええ、もちろん」
「彼女はある雪の日、お仕えしていた中宮様からこう尋ねられます。『香炉峰の雪いかならむ』と。もちろん京の都から香炉峰など見えません。しかし清少納言は御簾を上げさせたのです。これは『香炉峰下新卜山居』を知っているからこそ通じたのです。これは和歌でも同じ事ができます。試しに白居易の漢詩を引いて和歌を詠んでみませんか」
一の姫はすっかりかつての女房の機知に感じ入り、こくこくとうなずいた。
そうして一の姫は漢詩から着想を得た和歌を詠むようになっていった。
「ああ、早く冬にならないかしら。そうしたら私、あなたに香炉峰の雪について尋ねるわ!」
「あらあら……」
夕少納言はそんな一の姫を微笑ましく思った。
夕少納言が一の姫の元に来てからというもの、式部卿宮は幾度か一の姫の元に遊びに来た。
その度に梅の花や、桜の花、桃の花を持ってきてくれた。
初めて会ったときに歌った『春風』に掛けているのだと夕少納言にはわかった。
「これは一の姫様のお部屋を照らすために、そしてこちらは……あなたの側にどうぞ、私だと思って」
そう言って式部卿宮は一の姫に渡す花束の他に、一枚の花びらを取り次ぎをする夕少納言にそっと握らせていくのであった。
「お、お、お、恐れ多いことで……」
夕少納言はそんな式部卿宮の振る舞いにすっかり参ってしまったが、きちんと立場をわきまえていた。
そもそも式部卿宮にはすでに正妻がいた。
右大臣の娘で、式部卿宮が元服した夜に共寝した添い臥しの相手で、年上の妻であった。
いつも着ている装束も、焚きしめられた香りも、すべてその妻の支度である。夜を共に過ごして、朝には仕事へ送り出す。貴人の妻とはそういうものであった。
本来なら、夕少納言の母もそれを父にするはずであったが、夕少納言が物心ついた頃には、父は他の女の元で夜を過ごし、支度もその女にさせていた。
そういったことを思い出すと、夕少納言の胸はきりきりと痛んだ。
「私は応援するわ!」
一の姫はキラキラと顔を輝かせてそう言った。
「男君など恋人の一人や二人いての甲斐性ではないの」
「……一の姫様」
夕少納言は苦笑して姫君を諫めた。
「私ごとき式部卿宮には釣り合いませんよ。あれは……それこそ、そう、恋人の……真似事でしょう」
口ではそう達観したことを言いながらも、実際に振る舞われるとすっかりのぼせ上がって顔を真っ赤にしてしまう夕少納言であったが、彼女は冷静であった。
「……私は、父の愛人に邸を追い出されました」
夕少納言は翳った顔でそう言った。
「……夕少納言」
「ですから、愛人にはなりたくないのです。……大仰な夢かもしれませぬが、それが叶わぬなら女房としてここに骨を埋めとうございます」
「不吉だから内裏に骨は埋められないけれど……わかったわ」
一の姫はうなずいた。
「……式部卿宮様のことがご迷惑なら、中宮様から主上に申し上げるようお願いしてみる?」
「い、いいえ! そんなこのような些事で主上や弘徽殿の方を動かすなどとんでもない!」
「そう……」
一の姫はふうとため息をついた。
夕少納言は寂しげに微笑んだ。
さて、一方その頃、夕少納言が内裏に上がった後、綾大輔は息子の家に退いた。
夫はすでに亡かったが、綾大輔の息子は孝行息子で綾大輔を快く邸に迎え入れた。
しかしその日々は長くは続かなかった。
綾大輔も年齢には勝てず、寝込むようになってしまった。
風の便りにそれを聞いた夕少納言は心配する文を送った。
その返事がくるのにはいささか時間がかかった。
そこにはたった一節、「久為労生事」と震える文字で書かれていた。
これは白居易が若い頃の詩『病中作』の書き出しで、若くして病気をしてしまった、長生きが出来るであろうか、という意味の漢詩であった。
一の姫が、心配そうに夕少納言の顔を見た。
「ああ、夕少納言、綾大輔はなんて?」
「……あまり、お体、かんばしくないようで……」
つっかえつっかえ夕少納言はそう言った。震える文字から、綾大輔の病状が手に取るようにわかるようであった。
「そう……。お見舞いに行く?」
夕少納言の態度から、一の姫にもその病状は伝わったのであろう。
一の姫が気遣わしげにそう言った。
「いえ……綾大輔様のご子息様にご迷惑ですから……」
「…………」
一の姫はため息をついたが、多くを語らなかった。
それからしばらく、暑さが増してきた頃、綾大輔の訃報が届いた。
夕少納言は一の姫の前では気丈に振る舞った。
しかし、夜になって、夕少納言はこっそり局を抜け出し、外でひとりシクシクと泣いた。
まだ夜は冷えたが、気にならなかった。
「……夕少納言」
そんな夕少納言に声をかける者があった。ビクリと肩を震わすと、そこには式部卿宮が立っていた。
「し、式部卿宮様……。何故、こちらに……」
「……綾大輔の事は私達の耳にも入りまして。主上と思い出話に花が咲いてしまいました」
式部卿宮からは微かに酒の香りがした。兄弟で母に仕えていた女房を偲んで酒を酌み交わしていたようだ。
「後日、私が主上の名代で綾大輔の息子のところへ、経を納めにうかがいます。何か言伝などあれば……」
「…………」
夕少納言は少し考えて、首を横に振った。
「ごめんなさい、何も思い付かない……」
「わかりました、何かありましたら、いつでも仰せ付けください」
式部卿宮は柔らかく微笑んだ。
「その様子では、今夜は寝られますまい。我らも、思い出話をしましょうか」
式部卿宮に促され、夕少納言は小さくうなずいた。
「……こちらでお仕えしていた頃の綾大輔は、どうでしたの」
「……春風は、綾大輔に習ったのです」
式部卿宮はにこりと笑ってそう言った。その目には少しの寂しさが混じっていた。
「春の花の咲く中……ああ、なんて懐かしい」
式部卿宮は近くの木を振り仰いだ。
もう花は散っていた。
「……花が散ってしまいましたね」
「……老いて香山に住せんとして初めて到る夜」
夕少納言は木より上の月を見て、そうつぶやいた。
それは香山とは白居易の親友が眠る寺のことであった。
香山に赴いて月を見、それはその日から、自分の家の月にもなるのだ、という香山への親しみを感じさせる詩であった。
「秋、白月の正に円なる時に逢う。今より便ち是れ家山の月。試みに問う、清光知るや知らずや」
涙に濡れた声で夕少納言はそう言った。
「……ええ、そうですね。我らの友ですとも、綾大輔は」
気付けば、式部卿宮は夕少納言の側近くに寄っていた。
夕少納言が何かをする暇もなく、式部卿宮は夕少納言を抱きしめた。
「……いけません、いけません」
夕少納言は力なく首を横に振った。
「三日間、こうしてあなたのもとに通いましょう」
式部卿宮は夕少納言の耳元でそう囁いた。
男が女の元に三日通うと結婚が成立する。式部卿宮が言っているのはそういうことだった。
「この内裏で餅を用意しろなどと無茶なことはもちろん申しませんとも」
くすりと式部卿宮は笑った。
三日夜餅といって、男に女が三日目の夜に餅を出す。
そうすれば婚姻は成立する。
「ただ……待っていてくだされば、それでいい」
式部卿宮はそう囁くと夕少納言を解放し、そのまま去って行ってしまった。