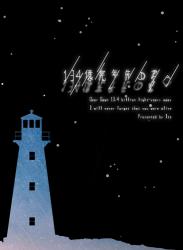どれくらい走っていたか分からない。
想太の瞳にも似たその濁りのない川を見た時、わたしはようやく足を止めた。
耳が痛いほどの静寂がわたしを包む。
想太が引き揚げられた川の水は、絹糸を束ねたような風波を立てていた。
うねり、煌めき、砕け、またひとつになって、水面に空から落ちてくる光が反射する。
涙が出るほど、綺麗だった。
胸に抱えたセーラー服を広げる。1年間着込んだ制服は、もうまっさらではないけれど、想太が望んだその形のまま、わたしの手の中にあった。
わたしは張り詰めた空気を、静かに吸い込む。
そして、セーラー服を穹に投げ捨てた。
紺のセーラー服は風にはためいて、わたしの涙と共にスローモーションで落ちていく。一刻として同じ表情を見せず、柔らかな光を纏って穹を抱いた。
それはまるで、銀の雪が降るようだった。
セーラー服は川底に沈んで、しばらくすると見えなくなった。赤のスカーフの残像だけが、目を閉じたわたしの網膜に映っていた。
想太の瞳にも似たその濁りのない川を見た時、わたしはようやく足を止めた。
耳が痛いほどの静寂がわたしを包む。
想太が引き揚げられた川の水は、絹糸を束ねたような風波を立てていた。
うねり、煌めき、砕け、またひとつになって、水面に空から落ちてくる光が反射する。
涙が出るほど、綺麗だった。
胸に抱えたセーラー服を広げる。1年間着込んだ制服は、もうまっさらではないけれど、想太が望んだその形のまま、わたしの手の中にあった。
わたしは張り詰めた空気を、静かに吸い込む。
そして、セーラー服を穹に投げ捨てた。
紺のセーラー服は風にはためいて、わたしの涙と共にスローモーションで落ちていく。一刻として同じ表情を見せず、柔らかな光を纏って穹を抱いた。
それはまるで、銀の雪が降るようだった。
セーラー服は川底に沈んで、しばらくすると見えなくなった。赤のスカーフの残像だけが、目を閉じたわたしの網膜に映っていた。