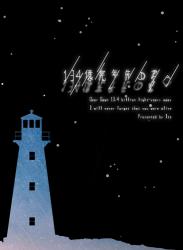花ちゃん。
想太の、わたしを呼ぶ声が好きだった。
いつでも味方でいてくれた想太。
陽だまりみたいな想太。
だけど、もういない。
どこを探しても、想太の声が聴こえない。想太は冷たい世界をわたしに遺して、ひとりで行ってしまった。
苦しかったでしょう。
冷たかったでしょう。
想太の涙をわたしだけが知っているのに、わたしはどうして今、想太を抱き締めてあげられないんだろう。
体の奥に穴が空いてしまったんじゃないかというほど、胸が苦しい。涙が、頬の上で冷たくなって痛い。
「花、戻るよ」
会場に戻ろうと、わたしの右手首を掴んだお母さんの手を、わたしは思い切り振り払う。
「わたしは……わたしは……っ」
「花」
「想太の心の1番大切な部分を、わたしは絶対に無視したくない」
お母さんの腕の中にあった自分のセーラー服を奪って、わたしはお葬式の会場を飛び出す。
花!とお母さんの呼び止める声が聞こえたけど、構わずに走り続けた。
この町は小さい。
想太と遊んだ公園、自転車の練習をした坂道に、一緒に通った幼稚園。過ぎ去る景色に、想太がいる。
走って、走って、声を上げながら泣いた。
セーラー服を抱き締めて走った。
息が吸えなくなって、足が凍ったように動かなくなって、それでもわたしは風を切った。涙が出なくなってしまっても、この体が千切れてしまっても構わないと思った。
想太の、わたしを呼ぶ声が好きだった。
いつでも味方でいてくれた想太。
陽だまりみたいな想太。
だけど、もういない。
どこを探しても、想太の声が聴こえない。想太は冷たい世界をわたしに遺して、ひとりで行ってしまった。
苦しかったでしょう。
冷たかったでしょう。
想太の涙をわたしだけが知っているのに、わたしはどうして今、想太を抱き締めてあげられないんだろう。
体の奥に穴が空いてしまったんじゃないかというほど、胸が苦しい。涙が、頬の上で冷たくなって痛い。
「花、戻るよ」
会場に戻ろうと、わたしの右手首を掴んだお母さんの手を、わたしは思い切り振り払う。
「わたしは……わたしは……っ」
「花」
「想太の心の1番大切な部分を、わたしは絶対に無視したくない」
お母さんの腕の中にあった自分のセーラー服を奪って、わたしはお葬式の会場を飛び出す。
花!とお母さんの呼び止める声が聞こえたけど、構わずに走り続けた。
この町は小さい。
想太と遊んだ公園、自転車の練習をした坂道に、一緒に通った幼稚園。過ぎ去る景色に、想太がいる。
走って、走って、声を上げながら泣いた。
セーラー服を抱き締めて走った。
息が吸えなくなって、足が凍ったように動かなくなって、それでもわたしは風を切った。涙が出なくなってしまっても、この体が千切れてしまっても構わないと思った。