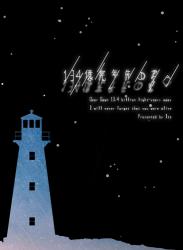◯
「花、想ちゃんのお葬式なんよ!?こんな……こんな花の制服なんて棺に入れんといて!」
お母さんはわたしの肩をきつく掴んで、酷く揺さぶる。その顔は青白く、怒っているのに血の気がない。まるで死人のようだ。
直ぐに発見された想太の遺体は、川の水が冷たかったことも相まって傷みが少なく、死化粧は想太の優しい顔立ちによく映えていた。だから、想太には光が透けるほど真っ白な花よりも、セーラー服の方が似合うと思った。
そう言うと、お母さんは怖い顔で低く声を漏らした。
「いい加減にしなさい。想ちゃんは男の子や」
違う。
違う違う違う。
想太はそんなの望んでない。
あの日涙を零した想太は、そんなことを言われるために生まれて、生きて、死んだんじゃない。
「お母さんかって知ってたやろ、ほんまは想太がスカート履きたがってたこと!なんで知らん振りするん!?」
冬の香りがする廊下に、わたしの声が響いた。
目の奥が熱い。
握り締めた手が痛い。
想太。
わたしは想太を、諦めたくない。
「なんも知らん子供が口挟むことじゃない。棺には花か手紙を入れなさい。そう決まってるから」
「決まってるって何?想太は自分が男か女か、決めさせて貰えへんかったのに!想太は最後までスカートを履かせてもらえへんの?想太の気持ちを無視するのは想太を無視するんと同じや!そうやって無視したから想太は、想太は…っ」
「花、想ちゃんのお葬式なんよ!?こんな……こんな花の制服なんて棺に入れんといて!」
お母さんはわたしの肩をきつく掴んで、酷く揺さぶる。その顔は青白く、怒っているのに血の気がない。まるで死人のようだ。
直ぐに発見された想太の遺体は、川の水が冷たかったことも相まって傷みが少なく、死化粧は想太の優しい顔立ちによく映えていた。だから、想太には光が透けるほど真っ白な花よりも、セーラー服の方が似合うと思った。
そう言うと、お母さんは怖い顔で低く声を漏らした。
「いい加減にしなさい。想ちゃんは男の子や」
違う。
違う違う違う。
想太はそんなの望んでない。
あの日涙を零した想太は、そんなことを言われるために生まれて、生きて、死んだんじゃない。
「お母さんかって知ってたやろ、ほんまは想太がスカート履きたがってたこと!なんで知らん振りするん!?」
冬の香りがする廊下に、わたしの声が響いた。
目の奥が熱い。
握り締めた手が痛い。
想太。
わたしは想太を、諦めたくない。
「なんも知らん子供が口挟むことじゃない。棺には花か手紙を入れなさい。そう決まってるから」
「決まってるって何?想太は自分が男か女か、決めさせて貰えへんかったのに!想太は最後までスカートを履かせてもらえへんの?想太の気持ちを無視するのは想太を無視するんと同じや!そうやって無視したから想太は、想太は…っ」