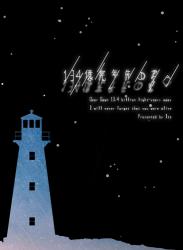◯
紺色のセーラー服。
その場で回ると、スカートのプリーツが花開くように広がる。
中学に上がる時、初めて袖を通した制服は、わたしを少しだけ大人にさせて、同時に心もとない気持ちをわたしに教えた。
姿見の前に立つわたしをじっと見ていた想太は、「花ちゃんのそれ、いいなぁ」と、鏡越しに言うと、目尻を下げて笑った。
詰襟に身を包んで、ベッドの傍に腰を下ろした想太は、膝を抱えてわたしを見上げている。
「わたしには似合わん」
「似合ってるって」
「服に着られてるみたいや」
「かわいいよ」
「だから!」
首を縦に振らない想太に、苛立ちを覚えた時だった。
想太が柔らかな笑顔を、一瞬だけ寂しそうに歪めて口を開いた。
「僕の制服にも、赤いスカーフが付いてたらいいのに」
想太はもう一度、いいなぁと言って、膝に額を落とした。
紺色のセーラー服。
その場で回ると、スカートのプリーツが花開くように広がる。
中学に上がる時、初めて袖を通した制服は、わたしを少しだけ大人にさせて、同時に心もとない気持ちをわたしに教えた。
姿見の前に立つわたしをじっと見ていた想太は、「花ちゃんのそれ、いいなぁ」と、鏡越しに言うと、目尻を下げて笑った。
詰襟に身を包んで、ベッドの傍に腰を下ろした想太は、膝を抱えてわたしを見上げている。
「わたしには似合わん」
「似合ってるって」
「服に着られてるみたいや」
「かわいいよ」
「だから!」
首を縦に振らない想太に、苛立ちを覚えた時だった。
想太が柔らかな笑顔を、一瞬だけ寂しそうに歪めて口を開いた。
「僕の制服にも、赤いスカーフが付いてたらいいのに」
想太はもう一度、いいなぁと言って、膝に額を落とした。