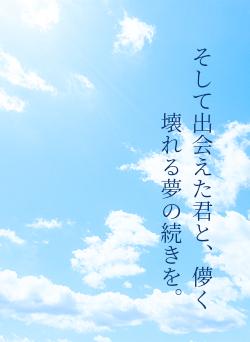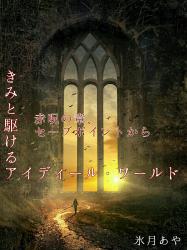「居場所の作り方とか居場所の持ち方とか、それがわからないんだ。子どものころから、居場所がなかった。家族や周囲にいじめられたわけじゃないよ。それでも、わたしは人と違うから、ここにいていいと思える場所はなかった」
「エレルギーだっけ。人工エレキに中毒を起こすから、そのへんで売ってる普通の食い物が食えない。病も呪いもよく拾う。人と同じ、まともな暮らしができない。自分は人とは違うって思っちまう」
「自分で自分を扱う術《すべ》がなかったし、みんなわたしを持て余していた。わたしは、ただ申し訳なかった。誰にも迷惑をかけない場所に行きたかった。そして京都に来て、寮で暮らすようになって、やっと居場所ができたと思ったんだけどね」
もっと張り合いがあって、もっと楽しい気持ちだった時期もあった。切石と巡野がいつもいてくれる。更紗さんから栄励気を練る術を教わって、できることが増えた。
わたしはもう無力ではない、と思っていた。居場所はここだ、と。
壊れ始めたのは、疲れたため息が増えたのは、いつだったっけ。
「沖田、きみにはわからない話だと思うんだけど、それでも聞く?」
「いいよ。聞くよ」
無力感が胸に渦巻いている。吐き出すことも断ち切ることもできない。
そもそも、無力感の正体そのものを、わたしはまだつかめていないんだろう。自分が何者なのか、一つもわかっていない。
「大学はいろんなことを学べる場所だと考えてた。探してたんだ。どこに目を向ければ、どんな力を付ければ、わたしは生きていけるのか。でも、学び続けるには、所属が必要なの。どこかの研究室を選んで、そこに所属しないといけない」
国史学、考古学、東洋史学、西南アジア史学、日本哲学、インド哲学、中国哲学、美学美術史学。
いろんな授業を受けていた。いろんなことがおもしろかった。まだまだたくさん知りたかった。知ることをおもしろいと感じ、おもしろく生きることが自分にもできそうだと感じた。
ふわふわした淡い希望の光がいくつも浮かんでいた。どれか一つなんて、選べなかった。
でも、選ばなければならなかった。枠の中に収まらなければならなかった。
「結局、国史研究室を選んだ。崩し字の演習は国史に所属していないと受けられないって言われたから。漢文演習やほかの外国語は、所属外の学生でも受けられたから」
流れの速いベルトコンベアに載せられているみたいだった。行き先は一つと定められた。立ち上がったら振り落とされる。
そのくらい速い流れでなければ間に合わないのだ、という話を聞いた。
就職活動をする間、文学部の学生はほとんど大学に出なくなる。課される選択は、彼らのスケジュールに合わせたものだった。あっという間に、彼らは学生から大人になっていくのだ。
彼らの生きるスピードはとても速くて、わたしはうまく付いていけなかった。一緒に行くのはあきらめた。わたしはわたしのペースで行けばいい、と思うことにした。
たくさん学びたい。だから大学に残って進学して、もっと勉強する。こつこつと、少しずつ。まじめにやることだけが取り柄だ。
それが自分の道だと、自分で自分を納得させた。
ところが、何もかもが裏目に出るんだ。
「いろんな分野の講義や演習に顔を出していたら、義理のない不まじめな人間だって言われた。いっぱいいっぱいだったけど、勉強には手を抜かなかったから、それで許してもらえると思ってたのに……義理って何のことだろうって、わからなくて」
ただ、嫌われたことだけはわかった。
わたしを嫌ったのは一部の人々だったかもしれない。でも、その人々は、研究室全体を担っているかのように「我々は」と言った。「我々対あなた」だった。
「所属しなければならない場所に、丸ごと嫌われた。そんな気がした。それじゃあダメだって焦って、毎日、朝いちばんに行って研究室を掃除したりとかね。ちゃんと所属するための努力をしたんだよ」
研究室の雰囲気はよかったはずだ。そこに入っていけない自分が情けなかった。努力しなければ普通に振る舞えない、努力しなければ所属することすらできない、そんな自分が悲しかった。
わたしは無理をしていたんだろうか。
なぜその程度のことが無理だったんだろうか。
「居場所、やっぱりないんだよね。去年の十一月に倒れて、そのまま大学に行けなくなって、今年は休学。復学できる気がしない。いっそ消えてなくたりたいよ。職業を選ぶどころか、自分が生き続ける将来がまったく思い描けない」
「エレルギーだっけ。人工エレキに中毒を起こすから、そのへんで売ってる普通の食い物が食えない。病も呪いもよく拾う。人と同じ、まともな暮らしができない。自分は人とは違うって思っちまう」
「自分で自分を扱う術《すべ》がなかったし、みんなわたしを持て余していた。わたしは、ただ申し訳なかった。誰にも迷惑をかけない場所に行きたかった。そして京都に来て、寮で暮らすようになって、やっと居場所ができたと思ったんだけどね」
もっと張り合いがあって、もっと楽しい気持ちだった時期もあった。切石と巡野がいつもいてくれる。更紗さんから栄励気を練る術を教わって、できることが増えた。
わたしはもう無力ではない、と思っていた。居場所はここだ、と。
壊れ始めたのは、疲れたため息が増えたのは、いつだったっけ。
「沖田、きみにはわからない話だと思うんだけど、それでも聞く?」
「いいよ。聞くよ」
無力感が胸に渦巻いている。吐き出すことも断ち切ることもできない。
そもそも、無力感の正体そのものを、わたしはまだつかめていないんだろう。自分が何者なのか、一つもわかっていない。
「大学はいろんなことを学べる場所だと考えてた。探してたんだ。どこに目を向ければ、どんな力を付ければ、わたしは生きていけるのか。でも、学び続けるには、所属が必要なの。どこかの研究室を選んで、そこに所属しないといけない」
国史学、考古学、東洋史学、西南アジア史学、日本哲学、インド哲学、中国哲学、美学美術史学。
いろんな授業を受けていた。いろんなことがおもしろかった。まだまだたくさん知りたかった。知ることをおもしろいと感じ、おもしろく生きることが自分にもできそうだと感じた。
ふわふわした淡い希望の光がいくつも浮かんでいた。どれか一つなんて、選べなかった。
でも、選ばなければならなかった。枠の中に収まらなければならなかった。
「結局、国史研究室を選んだ。崩し字の演習は国史に所属していないと受けられないって言われたから。漢文演習やほかの外国語は、所属外の学生でも受けられたから」
流れの速いベルトコンベアに載せられているみたいだった。行き先は一つと定められた。立ち上がったら振り落とされる。
そのくらい速い流れでなければ間に合わないのだ、という話を聞いた。
就職活動をする間、文学部の学生はほとんど大学に出なくなる。課される選択は、彼らのスケジュールに合わせたものだった。あっという間に、彼らは学生から大人になっていくのだ。
彼らの生きるスピードはとても速くて、わたしはうまく付いていけなかった。一緒に行くのはあきらめた。わたしはわたしのペースで行けばいい、と思うことにした。
たくさん学びたい。だから大学に残って進学して、もっと勉強する。こつこつと、少しずつ。まじめにやることだけが取り柄だ。
それが自分の道だと、自分で自分を納得させた。
ところが、何もかもが裏目に出るんだ。
「いろんな分野の講義や演習に顔を出していたら、義理のない不まじめな人間だって言われた。いっぱいいっぱいだったけど、勉強には手を抜かなかったから、それで許してもらえると思ってたのに……義理って何のことだろうって、わからなくて」
ただ、嫌われたことだけはわかった。
わたしを嫌ったのは一部の人々だったかもしれない。でも、その人々は、研究室全体を担っているかのように「我々は」と言った。「我々対あなた」だった。
「所属しなければならない場所に、丸ごと嫌われた。そんな気がした。それじゃあダメだって焦って、毎日、朝いちばんに行って研究室を掃除したりとかね。ちゃんと所属するための努力をしたんだよ」
研究室の雰囲気はよかったはずだ。そこに入っていけない自分が情けなかった。努力しなければ普通に振る舞えない、努力しなければ所属することすらできない、そんな自分が悲しかった。
わたしは無理をしていたんだろうか。
なぜその程度のことが無理だったんだろうか。
「居場所、やっぱりないんだよね。去年の十一月に倒れて、そのまま大学に行けなくなって、今年は休学。復学できる気がしない。いっそ消えてなくたりたいよ。職業を選ぶどころか、自分が生き続ける将来がまったく思い描けない」