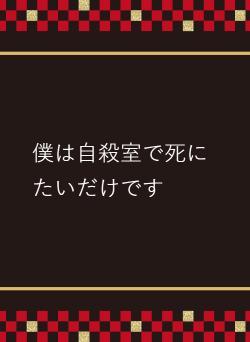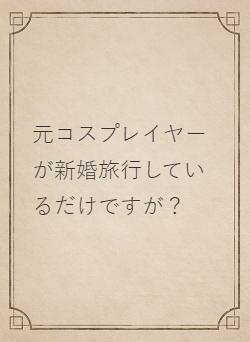・
・【差し入れの女子マネージャー】
・
僕たちは調理室をきちんと片付けて廊下に出たその時、僕たちの後ろのほうに回っていたイッチンが声を掛けてきた。
「先輩! 差し入れのおにぎりです! あのっ! 食べてくれませんかっ?」
何か急なその感じにドキッとしながら振り向いた僕たち。
少したどたどしい標準語がまた何だかドキドキした。
というか
「あの焼きおにぎりって、これをやるため用だったんだ」
「おっ、ちゃんと見とるやん、アタシのこと。やっぱ理央が一番えっちやからなぁ」
そう言ったイッチンのほうは見ず、僕のほうをガッと見てきたトールと博士。
いや!
「僕は全然エッチじゃないよ! あのホイッスルやった二人のほうが全然エッチでしょ!」
しかしトールは首を傾げながら、
「いやっ、イッチンがそう言うんだからっ、そうなんじゃないかっ?」
博士も頷きながら、
「ずっと、イッチンのことを、見ているって、そういうこと、だな」
いやいや!
「全然普通だよ! というかいつもいない人のことを見るって当たり前じゃないか!」
するとイッチンは少し物悲しそうに、
「アタシのこと警戒しとるってことやな……こんだけ一緒にいるのに寂しいわ……」
と言って俯いたので、トールと博士は僕のほうをキッと睨んできた。
いやでも
「そういうことじゃなくて、えっと、あの……」
なかなか言葉が出てこない。
なんというか、この違和感を伝えたほうがいいのか、いやそれとも、この楽し気な空間を守ったほうがいいのか。
僕が選んだほうは
「えっと、その、やっぱり僕、イッチンのこと気になっていただけかもしれない……」
「なんやねんそれ! やっぱ理央が一番えっちやん!」
トールと博士も納得した表情でそれぞれ、
「やっぱりなっ! 理央って何だかんだで一番エッチだもんなっ!」
「納得、しました、完全に」
僕はこの楽し気な雰囲気を守るほうを選択した。
だって実際に心が躍ることは本当なんだから。
そして僕たちはなんとなくイッチンが先頭になって歩いていた。
階段を上って、一階から二階に着いたその時、イッチンが振り返り、
「じゃあ最後は階段で倒れ込んで、もみくちゃになるヤツやろかっ!」
「もみくちゃっ!」
トールが嬉しそうな声を上げた。
博士もニヤニヤしながら、
「まあ、少年誌の、ラブコメ、定番だな」
と言ったが、僕は階段で倒れ込む、と聞いて一つ思い出した。
それはこの中学校の怪談だ。
そう
「昔、階段で倒れ込んで、死んだ女子生徒がいる……」
トールと博士が驚愕しながら、こっちのほうを見た。
僕の脳裏をよぎり続けた点が結び、線になり
「見知らぬ同学年の生徒。新しくできた調理室の場所は知らない。そして僕たちをやけに誘惑して、一緒にいようとするところ」
僕がボソボソとそう言うと、博士がおそるおそるこう言った。
「小生たちを、階段で、幽霊にして、一緒にいようと、している……?」
トールが震えながら、
「嘘だっ! ……いやでもっ! こんなバカな俺たちにずっと付き合って遊んでいたってことはっ! まさか!」
するとイッチンが怪しくニヤァと粘着質に笑った。
まさかこの表情、悪意に満ちたこの表情!
と思った刹那、イッチンは急に走り出した。
僕はイッチンの走った方向を見ていると、すぐさまイッチンがどこかの部屋に入っていくのが見えた。
そこに僕と、トールと博士も歩いていくと、そこは校長室だった。
「確かに校長室に入っていったよね……」
トールと博士も頷きながら、それぞれ、
「あぁっ、絶対にっ、校長室だったなっ……」
「は、入りますか、校長室に」
僕たちを顔を見合わせ、決意を固め、校長室の扉を開けると、そこには普通に校長先生がいた。
否、校長先生しかいない。
「あの……今、女子生徒が校長室に入ってきませんでしたか?」
空間の沈黙。
そりゃそうだ、もし入ってきていなければ、僕たちはおかしなことを言っているんだから。
そして校長先生は口を開いた。
「い、いやぁ……その……入ってきていないけども、どうしたのかね?」
僕たちは背筋が凍った。
というか戦慄した。
僕たちは一礼して、校長室を出て行った。
震えながらこの場所をあとにしようとした時、何か校長室から女子生徒の笑い声が聞こえた気がした。
あっ、校長先生、呪われちゃう。
とか思ったけども、それ以上のことは何もできなく、僕たちはただただ、トボトボと部室に戻り、あまり言葉も交わさず、家路に着いた。
一体何だったんだろうか、今日の放課後は。
でも確かにイッチンの体温は感じたんだ。
温かい、温かい体温を。
でも、まさか、でも、まさか……。
・【差し入れの女子マネージャー】
・
僕たちは調理室をきちんと片付けて廊下に出たその時、僕たちの後ろのほうに回っていたイッチンが声を掛けてきた。
「先輩! 差し入れのおにぎりです! あのっ! 食べてくれませんかっ?」
何か急なその感じにドキッとしながら振り向いた僕たち。
少したどたどしい標準語がまた何だかドキドキした。
というか
「あの焼きおにぎりって、これをやるため用だったんだ」
「おっ、ちゃんと見とるやん、アタシのこと。やっぱ理央が一番えっちやからなぁ」
そう言ったイッチンのほうは見ず、僕のほうをガッと見てきたトールと博士。
いや!
「僕は全然エッチじゃないよ! あのホイッスルやった二人のほうが全然エッチでしょ!」
しかしトールは首を傾げながら、
「いやっ、イッチンがそう言うんだからっ、そうなんじゃないかっ?」
博士も頷きながら、
「ずっと、イッチンのことを、見ているって、そういうこと、だな」
いやいや!
「全然普通だよ! というかいつもいない人のことを見るって当たり前じゃないか!」
するとイッチンは少し物悲しそうに、
「アタシのこと警戒しとるってことやな……こんだけ一緒にいるのに寂しいわ……」
と言って俯いたので、トールと博士は僕のほうをキッと睨んできた。
いやでも
「そういうことじゃなくて、えっと、あの……」
なかなか言葉が出てこない。
なんというか、この違和感を伝えたほうがいいのか、いやそれとも、この楽し気な空間を守ったほうがいいのか。
僕が選んだほうは
「えっと、その、やっぱり僕、イッチンのこと気になっていただけかもしれない……」
「なんやねんそれ! やっぱ理央が一番えっちやん!」
トールと博士も納得した表情でそれぞれ、
「やっぱりなっ! 理央って何だかんだで一番エッチだもんなっ!」
「納得、しました、完全に」
僕はこの楽し気な雰囲気を守るほうを選択した。
だって実際に心が躍ることは本当なんだから。
そして僕たちはなんとなくイッチンが先頭になって歩いていた。
階段を上って、一階から二階に着いたその時、イッチンが振り返り、
「じゃあ最後は階段で倒れ込んで、もみくちゃになるヤツやろかっ!」
「もみくちゃっ!」
トールが嬉しそうな声を上げた。
博士もニヤニヤしながら、
「まあ、少年誌の、ラブコメ、定番だな」
と言ったが、僕は階段で倒れ込む、と聞いて一つ思い出した。
それはこの中学校の怪談だ。
そう
「昔、階段で倒れ込んで、死んだ女子生徒がいる……」
トールと博士が驚愕しながら、こっちのほうを見た。
僕の脳裏をよぎり続けた点が結び、線になり
「見知らぬ同学年の生徒。新しくできた調理室の場所は知らない。そして僕たちをやけに誘惑して、一緒にいようとするところ」
僕がボソボソとそう言うと、博士がおそるおそるこう言った。
「小生たちを、階段で、幽霊にして、一緒にいようと、している……?」
トールが震えながら、
「嘘だっ! ……いやでもっ! こんなバカな俺たちにずっと付き合って遊んでいたってことはっ! まさか!」
するとイッチンが怪しくニヤァと粘着質に笑った。
まさかこの表情、悪意に満ちたこの表情!
と思った刹那、イッチンは急に走り出した。
僕はイッチンの走った方向を見ていると、すぐさまイッチンがどこかの部屋に入っていくのが見えた。
そこに僕と、トールと博士も歩いていくと、そこは校長室だった。
「確かに校長室に入っていったよね……」
トールと博士も頷きながら、それぞれ、
「あぁっ、絶対にっ、校長室だったなっ……」
「は、入りますか、校長室に」
僕たちを顔を見合わせ、決意を固め、校長室の扉を開けると、そこには普通に校長先生がいた。
否、校長先生しかいない。
「あの……今、女子生徒が校長室に入ってきませんでしたか?」
空間の沈黙。
そりゃそうだ、もし入ってきていなければ、僕たちはおかしなことを言っているんだから。
そして校長先生は口を開いた。
「い、いやぁ……その……入ってきていないけども、どうしたのかね?」
僕たちは背筋が凍った。
というか戦慄した。
僕たちは一礼して、校長室を出て行った。
震えながらこの場所をあとにしようとした時、何か校長室から女子生徒の笑い声が聞こえた気がした。
あっ、校長先生、呪われちゃう。
とか思ったけども、それ以上のことは何もできなく、僕たちはただただ、トボトボと部室に戻り、あまり言葉も交わさず、家路に着いた。
一体何だったんだろうか、今日の放課後は。
でも確かにイッチンの体温は感じたんだ。
温かい、温かい体温を。
でも、まさか、でも、まさか……。