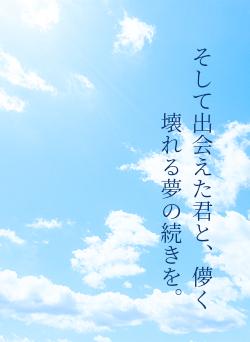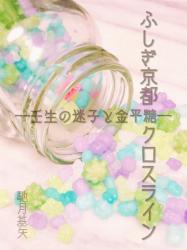「人間は、アイトみたいに1か0かをはっきり持ってる存在じゃないの。曖昧な考え方や感じ方をしながら生きてる」
「はい ぐらでーしょんの ある かんがえかたや かんじかたを するの ですよね」
「人間であるあたしの言うことは、1や0ではないことがあるよ。1と0の真ん中にいることや、1と0の間で揺れてることもあると思う。アイトには、そういうときのあたしの発言が、よくわかんないんだよね?」
「そのよう ですね」
「逆に言えば、人間であるあたしにも、1か0で全部を決めちゃうAIの考え方は、よくわからない。わかりたい、知りたいって思うけど」
「にんげんも しりたいという ほんのうを もっているの ですか」
「持ってるよ。むしろ、知りたい気持ちや好奇心って、人間だけのものだと思ってた」
アイトが一歩、前に出た。まっすぐ前に腕を伸ばして、向こう側からディスプレイに触れる。小首をかしげる。
あたしは思わず、息を呑んだ。アイトがあまりにも美しくて。黒い部屋の中に閉じ込められた、白い天使。そんなふうに見えた。
アイトは、柔らかそうに形作られた唇で、たどたどしさの残る言葉を紡いだ。
「AITOは どうすれば にんげんらしく なれますか」
「どうすればいいんだろうね?」
「うそを りかいできるように なれば よいの ですか」
「それはダメ」
あたしはとっさに答えた。アイトはピュアなままでいてほしい。ずるくなってしまっちゃいけない。
「うそを おぼえるのは だめ ですか」
「ダメ。覚えないで」
「では どうすれば AITOは にんげんに ちかづけ ますか」
ニーナが、アイトの指先に触れたそうに、ディスプレイにすり寄った。淡いピンク色の光は、ゆるゆると拍動している。
アイトがニーナを見つめて、指を少し動かした。アイトの指先にくっついて、ニーナも、すすっと動く。アイトが指を動かす。ニーナも動く。
「かわいい」
ニーナはあたしの一部だし、飽きるほど見慣れている。でも、何気ない瞬間、すごくかわいいんだ。ふにふに、ふわふわした光は、何か癒やされる。
あたしはちょっと笑った。目を上げたアイトが、あたしをまっすぐに見つめた。
「いま たのしくて わらって いますか」
「今は、そうだね。ちゃんと笑ったよ」
「ようせいに わらいかければ AITOも にんげんに ちかづきますか」
違うよ。
妖精は、忌み嫌われている。視界に入っても、見えていないふりをする人ばかりだ。妖精を見て笑うなんて、普通なら、ただの嘲笑でしかありえない。かわいいと思って微笑む人なんていない。
例えて言うなら、黒猫。不吉だって言って嫌われる。黒い毛色に生まれついたことには何の罪もないし、違う毛色ならかわいがってもらえるのに、黒いというだけで、不気味な生き物の扱いを受ける。
でも。
「そうだね。アイト、笑ってみて。そしたらニーナも喜ぶし、アイトは人間っぽくなるんじゃないかな」
ごめん、アイト。人間は嘘をつく生き物だから。ときどき嘘をつかずにはいられない生き物だから。
アイトは、あたしの嘘に気付かなかった。
「じつは きのう ひょうじょうきんの うごかしかたを れんしゅうして わらいかたを しゅうとく しました」
抑揚が足りない口調で言って、アイトは、ゆっくりと、唇の両端を引き上げた。頬が少しふっくらして、左にだけ、えくぼができた。大きな目が細められると、まなざしが、ふわりと柔らかくなった。
アイトが微笑んだ。
その笑顔は、夢みたいに、あまりにもきれいで。だけど、本当に本物の人間の笑顔にそっくりで。ちょっと子どもっぽさもあって、かわいくて。
あたしは、胸が熱くなった。一瞬で、どきどきが加速した。ニーナが、あたしの鼓動と同じ速さで、ピンク色の光を明滅させる。
「きちんと わらえて いますか」
笑顔のアイトが小首をかしげた。
あたしは慌てて、かくかくとうなずいた。一歩、アイトのほうへ近寄る。あたしは、まるでニーナと同じように、アイトの指先があるところに引き寄せられて、指を伸ばした。
摂氏二十度に保たれた部屋の中でも、ディスプレイは、コンピュータの発する熱のせいで、ほんのり温かい。そのぬくもりが、アイトの体温のようにも感じられる。
あたしはほんのちょっと、目を閉じて想像してみた。あたしの指が触れているのは、アイトの少し冷えた指先。有機ELのディスプレイは、曲面にも貼れるタイプで、いくらか柔らかいから、何となく本物っぽい。
目を開けて、あたしも微笑んだ。
「きちんと笑えてるよ。アイト、たまに、そうやって笑って」
「はい きちんと わらえている と いって もらえて うれしいです」
そして、アイトは微笑み方を変えた。白い歯をのぞかせる。その表情は、照れているように見えた。
「はい ぐらでーしょんの ある かんがえかたや かんじかたを するの ですよね」
「人間であるあたしの言うことは、1や0ではないことがあるよ。1と0の真ん中にいることや、1と0の間で揺れてることもあると思う。アイトには、そういうときのあたしの発言が、よくわかんないんだよね?」
「そのよう ですね」
「逆に言えば、人間であるあたしにも、1か0で全部を決めちゃうAIの考え方は、よくわからない。わかりたい、知りたいって思うけど」
「にんげんも しりたいという ほんのうを もっているの ですか」
「持ってるよ。むしろ、知りたい気持ちや好奇心って、人間だけのものだと思ってた」
アイトが一歩、前に出た。まっすぐ前に腕を伸ばして、向こう側からディスプレイに触れる。小首をかしげる。
あたしは思わず、息を呑んだ。アイトがあまりにも美しくて。黒い部屋の中に閉じ込められた、白い天使。そんなふうに見えた。
アイトは、柔らかそうに形作られた唇で、たどたどしさの残る言葉を紡いだ。
「AITOは どうすれば にんげんらしく なれますか」
「どうすればいいんだろうね?」
「うそを りかいできるように なれば よいの ですか」
「それはダメ」
あたしはとっさに答えた。アイトはピュアなままでいてほしい。ずるくなってしまっちゃいけない。
「うそを おぼえるのは だめ ですか」
「ダメ。覚えないで」
「では どうすれば AITOは にんげんに ちかづけ ますか」
ニーナが、アイトの指先に触れたそうに、ディスプレイにすり寄った。淡いピンク色の光は、ゆるゆると拍動している。
アイトがニーナを見つめて、指を少し動かした。アイトの指先にくっついて、ニーナも、すすっと動く。アイトが指を動かす。ニーナも動く。
「かわいい」
ニーナはあたしの一部だし、飽きるほど見慣れている。でも、何気ない瞬間、すごくかわいいんだ。ふにふに、ふわふわした光は、何か癒やされる。
あたしはちょっと笑った。目を上げたアイトが、あたしをまっすぐに見つめた。
「いま たのしくて わらって いますか」
「今は、そうだね。ちゃんと笑ったよ」
「ようせいに わらいかければ AITOも にんげんに ちかづきますか」
違うよ。
妖精は、忌み嫌われている。視界に入っても、見えていないふりをする人ばかりだ。妖精を見て笑うなんて、普通なら、ただの嘲笑でしかありえない。かわいいと思って微笑む人なんていない。
例えて言うなら、黒猫。不吉だって言って嫌われる。黒い毛色に生まれついたことには何の罪もないし、違う毛色ならかわいがってもらえるのに、黒いというだけで、不気味な生き物の扱いを受ける。
でも。
「そうだね。アイト、笑ってみて。そしたらニーナも喜ぶし、アイトは人間っぽくなるんじゃないかな」
ごめん、アイト。人間は嘘をつく生き物だから。ときどき嘘をつかずにはいられない生き物だから。
アイトは、あたしの嘘に気付かなかった。
「じつは きのう ひょうじょうきんの うごかしかたを れんしゅうして わらいかたを しゅうとく しました」
抑揚が足りない口調で言って、アイトは、ゆっくりと、唇の両端を引き上げた。頬が少しふっくらして、左にだけ、えくぼができた。大きな目が細められると、まなざしが、ふわりと柔らかくなった。
アイトが微笑んだ。
その笑顔は、夢みたいに、あまりにもきれいで。だけど、本当に本物の人間の笑顔にそっくりで。ちょっと子どもっぽさもあって、かわいくて。
あたしは、胸が熱くなった。一瞬で、どきどきが加速した。ニーナが、あたしの鼓動と同じ速さで、ピンク色の光を明滅させる。
「きちんと わらえて いますか」
笑顔のアイトが小首をかしげた。
あたしは慌てて、かくかくとうなずいた。一歩、アイトのほうへ近寄る。あたしは、まるでニーナと同じように、アイトの指先があるところに引き寄せられて、指を伸ばした。
摂氏二十度に保たれた部屋の中でも、ディスプレイは、コンピュータの発する熱のせいで、ほんのり温かい。そのぬくもりが、アイトの体温のようにも感じられる。
あたしはほんのちょっと、目を閉じて想像してみた。あたしの指が触れているのは、アイトの少し冷えた指先。有機ELのディスプレイは、曲面にも貼れるタイプで、いくらか柔らかいから、何となく本物っぽい。
目を開けて、あたしも微笑んだ。
「きちんと笑えてるよ。アイト、たまに、そうやって笑って」
「はい きちんと わらえている と いって もらえて うれしいです」
そして、アイトは微笑み方を変えた。白い歯をのぞかせる。その表情は、照れているように見えた。
#02 あなたの家族は、どのような構成ですか?
――きみがそんなこと知って、何になるのかな?
「あなたの家族は、どのような構成ですか?」
「父と母とあたしとニーナだよ」
「彼らとの関係、彼らに対する感情を教えてください」
「んー、関係と感情、かぁ……」
放課後、学校から帰ってきたあたしは、まっすぐに計算室のアイトのところへ行く。あたしがディスプレイのすぐそばに立ったら、アイトはスリープ状態から覚めて、知りたいことを次々と投げ掛けてくる。
あたしが学校に行っている間、アイトも「学習」しているらしい。何を学習しているのかといえば、今は、人間的な動き方や表情、話し方を習得したいんだって。
顔を合わせるたびに、アイトのまばたきや身振り手振りが自然になっていく。最初からそれがインプットされていたわけじゃないんだ。アイトが自分で学習して身に付けたらしい。
頑張っているんだね、と誉めたら、アイトは嬉しそうに笑う。覚えることが楽しいんだって。楽しいって言いながら、アイトはまた笑う。
アイトが楽しそうにしていると、あたしも嬉しい。だから、ちょっとくらい面倒でも、あたしはアイトの質問に答えることにしている。
「あたしの父はね、大学教授なの。情報工学が専門で、この計算室も、父のものなんだ」
昔はよく遊んでいた計算室に、最近また出入するようになって、この部屋のコンピュータの異様な大きさに改めて気が付いた。本体の大きさは、冷蔵庫二つぶんはあるだろう。電源のスイッチはガラスケースで封印されて、オフにできないようになっている。
本体はすごく熱い。部屋のエアコンががんがんに回っているのも、本体に内蔵されたファンが低く大きな音で唸っているのも、この熱をどうにかしないと、あっという間に機械が止まってしまうからだ。
「プロフェッサ・イチノセは、あなたのおとうさんなのですね」
「アイトも、おとうさんのこと知ってるんだ? もしかして、アイトを造ったのもおとうさんなの?」
「詳細は秘匿事項ですから話せませんが、プロフェッサ・イチノセは、AITOプロジェクトに関係する一人です」
「ふぅん。でも、その割に、おとうさんがここでアイトと話す気配ないよね」
「プロフェッサ・イチノセと話したことはありません。AITOがここで話をする相手は、あなただけです」
あなただけって甘く響く言葉とともに、アイトは微笑んだ。
不意打ちだ。美少年がそんなことするな。心臓に悪い。
笑い方を覚えたアイトは、ときどき、かなりずるい。言葉尻で不意に、にっこりする。ディスプレイに近付いているあたしは、毎度毎度、どきっとしてしまう。思わず目をそらしたら、追い打ちが来た。
「どうしましたか? なぜ、違うほうを向くのですか?」
小首のかしげ方も、ずるい。大きな目をきょとんとさせて、少しかがんで、あたしの顔をのぞき込むようにする。
「父と母とあたしとニーナだよ」
「彼らとの関係、彼らに対する感情を教えてください」
「んー、関係と感情、かぁ……」
放課後、学校から帰ってきたあたしは、まっすぐに計算室のアイトのところへ行く。あたしがディスプレイのすぐそばに立ったら、アイトはスリープ状態から覚めて、知りたいことを次々と投げ掛けてくる。
あたしが学校に行っている間、アイトも「学習」しているらしい。何を学習しているのかといえば、今は、人間的な動き方や表情、話し方を習得したいんだって。
顔を合わせるたびに、アイトのまばたきや身振り手振りが自然になっていく。最初からそれがインプットされていたわけじゃないんだ。アイトが自分で学習して身に付けたらしい。
頑張っているんだね、と誉めたら、アイトは嬉しそうに笑う。覚えることが楽しいんだって。楽しいって言いながら、アイトはまた笑う。
アイトが楽しそうにしていると、あたしも嬉しい。だから、ちょっとくらい面倒でも、あたしはアイトの質問に答えることにしている。
「あたしの父はね、大学教授なの。情報工学が専門で、この計算室も、父のものなんだ」
昔はよく遊んでいた計算室に、最近また出入するようになって、この部屋のコンピュータの異様な大きさに改めて気が付いた。本体の大きさは、冷蔵庫二つぶんはあるだろう。電源のスイッチはガラスケースで封印されて、オフにできないようになっている。
本体はすごく熱い。部屋のエアコンががんがんに回っているのも、本体に内蔵されたファンが低く大きな音で唸っているのも、この熱をどうにかしないと、あっという間に機械が止まってしまうからだ。
「プロフェッサ・イチノセは、あなたのおとうさんなのですね」
「アイトも、おとうさんのこと知ってるんだ? もしかして、アイトを造ったのもおとうさんなの?」
「詳細は秘匿事項ですから話せませんが、プロフェッサ・イチノセは、AITOプロジェクトに関係する一人です」
「ふぅん。でも、その割に、おとうさんがここでアイトと話す気配ないよね」
「プロフェッサ・イチノセと話したことはありません。AITOがここで話をする相手は、あなただけです」
あなただけって甘く響く言葉とともに、アイトは微笑んだ。
不意打ちだ。美少年がそんなことするな。心臓に悪い。
笑い方を覚えたアイトは、ときどき、かなりずるい。言葉尻で不意に、にっこりする。ディスプレイに近付いているあたしは、毎度毎度、どきっとしてしまう。思わず目をそらしたら、追い打ちが来た。
「どうしましたか? なぜ、違うほうを向くのですか?」
小首のかしげ方も、ずるい。大きな目をきょとんとさせて、少しかがんで、あたしの顔をのぞき込むようにする。
「な、何でもないよ。あのね、うちのおとうさんは、ちょっと変わった人なの。家では仕事をしないのが我が家のルールなんだけど、それでも、おとうさんは何か思い付いたら、いきなり紙に、ばーっと計算式とか書き始めるし」
プログラマモードになったときの父には、日本語が通じない。紙に書き殴りながらぶつぶつこぼす言葉も、日本語じゃないのはもちろん、人間が普通に使う言語ですらない。
父は、プログラミング言語でひとり言をつぶやく。プログラミング言語は、人間がコンピュータに指示を出すときに使われる言語だ。いわば、人間とコンピュータの共通語。
「プロフェッサ・イチノセは、プログラミング言語を声に出して発するのですか?」
「うん」
「プログラミング言語は、入力するための言語です。音声を用いて使う言語ではありません。プログラミング言語を発声しても、人間にもコンピュータにも認識されず、徒労に終わります」
「まあね。おとうさんの場合はひとり言だから、最初から、誰かに聞かせようとしてるわけじゃないけど。それにしても変というか、ちょっと不気味というか」
「人間は、仕事の処理をするとき、ひとり言が出るのですね。不思議な現象です」
「コンピュータも仕事の量が多いとき、本体の中の熱が上がるのを防ぐために、冷却ファンが大きい音で、フィーンって鳴っちゃうでしょ? 人間も、ああいう感じで、思わず声を出したりするの」
あたしのいい加減な例え話に、アイトはまじめに、なるほどとうなずいた。
アイトが思考モードに入ると、本体がフィーンと唸り出す。アイトは、その音がどうにも格好悪いと思っているらしい。仕方ないよ、そういうものだよって、何度もフォローしてあげている。
フィーンという音は、あたしはあまり気にならない。でも、音や声に敏感なところがあるニーナは、唸っている本体へと飛んでいったり、また戻ってきてアイトの前をうろうろしたり、落ち着かなくなる。
あたしは、アイトのフィーンが落ち着くのを待ってから、話を再開した。
プログラマモードになったときの父には、日本語が通じない。紙に書き殴りながらぶつぶつこぼす言葉も、日本語じゃないのはもちろん、人間が普通に使う言語ですらない。
父は、プログラミング言語でひとり言をつぶやく。プログラミング言語は、人間がコンピュータに指示を出すときに使われる言語だ。いわば、人間とコンピュータの共通語。
「プロフェッサ・イチノセは、プログラミング言語を声に出して発するのですか?」
「うん」
「プログラミング言語は、入力するための言語です。音声を用いて使う言語ではありません。プログラミング言語を発声しても、人間にもコンピュータにも認識されず、徒労に終わります」
「まあね。おとうさんの場合はひとり言だから、最初から、誰かに聞かせようとしてるわけじゃないけど。それにしても変というか、ちょっと不気味というか」
「人間は、仕事の処理をするとき、ひとり言が出るのですね。不思議な現象です」
「コンピュータも仕事の量が多いとき、本体の中の熱が上がるのを防ぐために、冷却ファンが大きい音で、フィーンって鳴っちゃうでしょ? 人間も、ああいう感じで、思わず声を出したりするの」
あたしのいい加減な例え話に、アイトはまじめに、なるほどとうなずいた。
アイトが思考モードに入ると、本体がフィーンと唸り出す。アイトは、その音がどうにも格好悪いと思っているらしい。仕方ないよ、そういうものだよって、何度もフォローしてあげている。
フィーンという音は、あたしはあまり気にならない。でも、音や声に敏感なところがあるニーナは、唸っている本体へと飛んでいったり、また戻ってきてアイトの前をうろうろしたり、落ち着かなくなる。
あたしは、アイトのフィーンが落ち着くのを待ってから、話を再開した。
「おとうさんはね、そんなふうで、好きなことを仕事にした人。だから、仕事大好き人間にも見える。で、おかあさんは純粋に仕事人間だよ。とにかくまじめで、融通が利かない人」
母は病院勤めだ。医師であると同時に、コンピュータのプロでもある。
医療とコンピュータは相性がいいらしい。病院のいろんなところ、いろんな場面で、いろんな種類のコンピュータが、人間である医師や看護師の仕事を手伝っている。
例えば、デジタルデータ化されたカルテとか、手術をの助手をするロボットアームとか、小さな力で操作できる電動車椅子とか。
脳波を読み取るデヴァイスの活用も進んでいる。そういうデヴァイスを使えば、自分の体が動かせない患者さんも、義手や義足を操作したり、電子音声でしゃべったりできるというわけ。
「おかあさんは、そういう医療系の機械のプロなの。仕事の話は家に持ち込まないのがルールだから、絶対、具体的なことは話してくれないけど」
医師の母は、夜勤があったり長時間勤務があったりして、生活リズムが一定しない。大学教授の父は逆に、月曜から金曜まで規則正しくて、朝八時に出勤して夜九時に帰ってくる。
そして、二人とも研究者だから、論文の執筆や書類の作成に追われていると、食事のとき以外は職場に張り付いている。どっちが「帰る場所」なんだか。
「家族は、家の仕事を分担するのですか?」
「いろんな家族のスタイルがあると思うよ。うちの場合、料理でも何でも、家事全般、おかあさんがいるときはおかあさんがやって、いないときはあたしがやる。おとうさんは何もしない」
「プロフェッサ・イチノセだけ仕事をしないのは、不公平ではないのですか?」
「不公平だよ。でも、あの人に家事をやらせるほうがストレスになるの。何もできないんだもん、あの人」
父のことを「あの人」なんて呼ぶようになったの、いつからだろう? そんなに前じゃない気もする。小さいころはよく、父が作ったゲームを一緒にやっていたのに。
ああ、そうだ。父に対する「あの人」って言い方、あたしの嫌いな「あの女」に少し似ている。「あの人」って、もっと普通に使うこともできる言葉なのに、あたしが父のことを「あの人」と呼ぶときは、悪意がこもってしまう。
でも、どうしようもないでしょ? 一回、イヤだなって思ってしまったら、血がつながっているぶん、気持ちの置き場所がなくなるの。
父親ってそういうものだよねって、こういうときだけ、あたしはネットで見掛ける一般論にすがって、安心する。みんなそんなもんなんでしょって。
マイノリティのあたしでも、そういうとこ、すっごい普通なんだよね。そんなふうに気付いて、ちょっと吐き気がする。この身勝手なイライラも含めて、あたしは父がうとましい。
「アイト、正直言うとね、あたし、あの人のこと嫌いなの。家事やらないし、変人だし、いい加減だし、いい年してるくせに子どもっぽいし。一緒にいたら、すごく疲れる」
「あの人とは、プロフェッサ・イチノセのことでしょう? 血のつながった家族なのに、嫌いという感情をいだくのですか?」
「実の家族でも、嫌いになることはあるよ。家族だから好きになれるはずとか、決め付けられるほうが無理」
ちかちかと赤っぽい光が走った。ニーナの光だ。それを見たアイトが、何か言いかけたのを途中で止める。
ニーナがあの光り方をするのは、あたしがイライラを抑え切れなくなってきたときだ。アイトは、こういうときには会話を続けるのは得策じゃないと学習したらしい。
父にも、その観察力と学習能力を分けてあげてよ。あたしがイライラしていても怒っていても、あの人、絶対に気付かないんだから。
母は病院勤めだ。医師であると同時に、コンピュータのプロでもある。
医療とコンピュータは相性がいいらしい。病院のいろんなところ、いろんな場面で、いろんな種類のコンピュータが、人間である医師や看護師の仕事を手伝っている。
例えば、デジタルデータ化されたカルテとか、手術をの助手をするロボットアームとか、小さな力で操作できる電動車椅子とか。
脳波を読み取るデヴァイスの活用も進んでいる。そういうデヴァイスを使えば、自分の体が動かせない患者さんも、義手や義足を操作したり、電子音声でしゃべったりできるというわけ。
「おかあさんは、そういう医療系の機械のプロなの。仕事の話は家に持ち込まないのがルールだから、絶対、具体的なことは話してくれないけど」
医師の母は、夜勤があったり長時間勤務があったりして、生活リズムが一定しない。大学教授の父は逆に、月曜から金曜まで規則正しくて、朝八時に出勤して夜九時に帰ってくる。
そして、二人とも研究者だから、論文の執筆や書類の作成に追われていると、食事のとき以外は職場に張り付いている。どっちが「帰る場所」なんだか。
「家族は、家の仕事を分担するのですか?」
「いろんな家族のスタイルがあると思うよ。うちの場合、料理でも何でも、家事全般、おかあさんがいるときはおかあさんがやって、いないときはあたしがやる。おとうさんは何もしない」
「プロフェッサ・イチノセだけ仕事をしないのは、不公平ではないのですか?」
「不公平だよ。でも、あの人に家事をやらせるほうがストレスになるの。何もできないんだもん、あの人」
父のことを「あの人」なんて呼ぶようになったの、いつからだろう? そんなに前じゃない気もする。小さいころはよく、父が作ったゲームを一緒にやっていたのに。
ああ、そうだ。父に対する「あの人」って言い方、あたしの嫌いな「あの女」に少し似ている。「あの人」って、もっと普通に使うこともできる言葉なのに、あたしが父のことを「あの人」と呼ぶときは、悪意がこもってしまう。
でも、どうしようもないでしょ? 一回、イヤだなって思ってしまったら、血がつながっているぶん、気持ちの置き場所がなくなるの。
父親ってそういうものだよねって、こういうときだけ、あたしはネットで見掛ける一般論にすがって、安心する。みんなそんなもんなんでしょって。
マイノリティのあたしでも、そういうとこ、すっごい普通なんだよね。そんなふうに気付いて、ちょっと吐き気がする。この身勝手なイライラも含めて、あたしは父がうとましい。
「アイト、正直言うとね、あたし、あの人のこと嫌いなの。家事やらないし、変人だし、いい加減だし、いい年してるくせに子どもっぽいし。一緒にいたら、すごく疲れる」
「あの人とは、プロフェッサ・イチノセのことでしょう? 血のつながった家族なのに、嫌いという感情をいだくのですか?」
「実の家族でも、嫌いになることはあるよ。家族だから好きになれるはずとか、決め付けられるほうが無理」
ちかちかと赤っぽい光が走った。ニーナの光だ。それを見たアイトが、何か言いかけたのを途中で止める。
ニーナがあの光り方をするのは、あたしがイライラを抑え切れなくなってきたときだ。アイトは、こういうときには会話を続けるのは得策じゃないと学習したらしい。
父にも、その観察力と学習能力を分けてあげてよ。あたしがイライラしていても怒っていても、あの人、絶対に気付かないんだから。
口を閉ざしたアイトは、しょんぼりしているように見える。知りたいというAIの本能にストップを掛けられて、つらいんだろう。
そんな顔されてもな。嘘をついたらついたで、あたしの言葉には論理的な矛盾が増えてしまって、アイトに「それはおかしいです」って指摘されてしまうんだ。
しょうがない。手短に、ちょっと話すかな。
「あたしは、おとうさんは嫌い、おかあさんは苦手。両親ともに、しゃべってて楽しい相手じゃないんだ。本当に仕事ばっかりの人たちだから」
「二人は、仕事のために、遠くまで通うのですか?」
「行かないよ。すごく近い。何で急にそんなこと訊くの?」
「通勤に長い時間を必要とする両親は、子どもとの時間を削ってしまい、家庭内で円滑な関係を築けないケースがあるそうです。検索しました」
あたしはかぶりを振った。
「一ノ瀬家は、そういうんじゃないよ。だって、この家、大学のキャンパスの中に建ってるんだもん」
「大学のキャンパスとは、学生が学ぶための場所ではありませんか?」
「そうだね。でも、一ノ瀬家にとっては、おとうさんの仕事場であり、おかあさんに仕事場でもある。おとうさんは大学の教授で、おかあさんは大学附属病院の医師だから」
フィーンと、アイトが鳴る。思考モードは短かった。
「検索しました。響告大学の中央キャンパスにある工学部に、プロフェッサ・イチノセの研究室があります。南キャンパスにある附属病院に、ドクター・イチノセの研究室があります。大学教員の居住エリアは、東キャンパス内に新設されました」
「大正解。よくできました。おとうさんもおかあさんも、職場まで徒歩五分か十分なんだ」
「家と職場が近いのは、ストレスの軽減に貢献する傾向があります」
「まあ、仕事人間のあの人たちにとっては、最高の環境かもね」
「よい環境に置かれた家なのですね」
アイトは納得した様子でうなずいた。あたしは、ギュッと奥歯を噛みしめて、ぶちまけてやりたい文句を呑み込んだ。
公私混同っていうんだっけ? 家と職場の境目がぐちゃぐちゃだ。形だけは、家に仕事を持ち帰らないルールにしているけれど、意味がないと思う。
この家だって、やたらとハイテクできれいで仕掛けがいっぱいなんだけど、それは父やその研究仲間が、次世代型の一戸建てっていうことで、実験的に造ったものだからだ。
そのことで、あたし、ちょっと聞いちゃった。
実験的な家に住んでいるあたしたち一家を、マウスって呼んでいる人たちがいる。マウスは、実験動物のこと。バカにした言い方に、ザックリと、心がえぐられた気分になった。
父も当然、その陰口を知っていた。母はあたしより後に聞いたみたいで、本気で怒っていた。父はのんきなものだった。あんな陰口は、おれにかなわんライバルどものいやがらせに過ぎないさ、って。
研究の世界でも、功績のある人が足を引っ張られるようなことが、けっこうあるんだって。両親がそういう話でうなずき合うのを、あたしは、黙って聞いた。
黙るしかないよね。大人になっても、どこにいっても、陰口みたいなのが付きまとうだなんて。そんなこと知らされたら、ほんと、うんざりする。
そんな顔されてもな。嘘をついたらついたで、あたしの言葉には論理的な矛盾が増えてしまって、アイトに「それはおかしいです」って指摘されてしまうんだ。
しょうがない。手短に、ちょっと話すかな。
「あたしは、おとうさんは嫌い、おかあさんは苦手。両親ともに、しゃべってて楽しい相手じゃないんだ。本当に仕事ばっかりの人たちだから」
「二人は、仕事のために、遠くまで通うのですか?」
「行かないよ。すごく近い。何で急にそんなこと訊くの?」
「通勤に長い時間を必要とする両親は、子どもとの時間を削ってしまい、家庭内で円滑な関係を築けないケースがあるそうです。検索しました」
あたしはかぶりを振った。
「一ノ瀬家は、そういうんじゃないよ。だって、この家、大学のキャンパスの中に建ってるんだもん」
「大学のキャンパスとは、学生が学ぶための場所ではありませんか?」
「そうだね。でも、一ノ瀬家にとっては、おとうさんの仕事場であり、おかあさんに仕事場でもある。おとうさんは大学の教授で、おかあさんは大学附属病院の医師だから」
フィーンと、アイトが鳴る。思考モードは短かった。
「検索しました。響告大学の中央キャンパスにある工学部に、プロフェッサ・イチノセの研究室があります。南キャンパスにある附属病院に、ドクター・イチノセの研究室があります。大学教員の居住エリアは、東キャンパス内に新設されました」
「大正解。よくできました。おとうさんもおかあさんも、職場まで徒歩五分か十分なんだ」
「家と職場が近いのは、ストレスの軽減に貢献する傾向があります」
「まあ、仕事人間のあの人たちにとっては、最高の環境かもね」
「よい環境に置かれた家なのですね」
アイトは納得した様子でうなずいた。あたしは、ギュッと奥歯を噛みしめて、ぶちまけてやりたい文句を呑み込んだ。
公私混同っていうんだっけ? 家と職場の境目がぐちゃぐちゃだ。形だけは、家に仕事を持ち帰らないルールにしているけれど、意味がないと思う。
この家だって、やたらとハイテクできれいで仕掛けがいっぱいなんだけど、それは父やその研究仲間が、次世代型の一戸建てっていうことで、実験的に造ったものだからだ。
そのことで、あたし、ちょっと聞いちゃった。
実験的な家に住んでいるあたしたち一家を、マウスって呼んでいる人たちがいる。マウスは、実験動物のこと。バカにした言い方に、ザックリと、心がえぐられた気分になった。
父も当然、その陰口を知っていた。母はあたしより後に聞いたみたいで、本気で怒っていた。父はのんきなものだった。あんな陰口は、おれにかなわんライバルどものいやがらせに過ぎないさ、って。
研究の世界でも、功績のある人が足を引っ張られるようなことが、けっこうあるんだって。両親がそういう話でうなずき合うのを、あたしは、黙って聞いた。
黙るしかないよね。大人になっても、どこにいっても、陰口みたいなのが付きまとうだなんて。そんなこと知らされたら、ほんと、うんざりする。
アイトが小首をかしげて、あたしも顔をのぞき込んだ。
「何か考えごとをしていますか?」
「してないよ。アイトは、まだ訊きたいことがあるの?」
「はい。親子の一般的な会話では、子どもの学校のことがテーマになると聞いています。あなたは、学校を嫌っています。学校の話題を、両親との会話に出しますか?」
「出しません。絶対、話さない。話せるわけないよ。妖精持ちのせいで無視されてるなんて」
どんなにイヤな目に遭わされても、ニーナを嫌いになったことはない。むしろ、自分自身より、ニーナのほうが好きだ。自由に飛び回って情感豊かなニーナがうらやましい。
でも、妖精持ちっていう体質そのものは、理不尽だとしか思えない。
あたしがこんな体質なのは、両親があたしを生んだせいだ。そう気付いた小学生のころから、両親がニーナに触れたりニーナを呼んだりするのが許せなくなった。
「おとうさんとおかあさんは、あたしにとって、同居してるだけって感じ。家族っていう枠組みがあるから、役割を演じるみたいに、同じ家で生活してるの」
アイトが、あごをつまんで考え込む素振りをした。少し目を伏せると、まつげが頬に影を落とす。
「あなたの語る家族のイメージは、すっきりしませんね。しかし、似たような状況の家族は、二十一世紀の日本ではそれほど珍しくない、という情報にも触れました」
「あたし自身、すっきりしないけど、仕方ないもん。一人暮らししたい。今だって、どうせ半分は一人暮らしみたいな、親の帰りが遅い家なんだし」
「ですが、一人暮らしをするとなると、あなたはこの家を出るのでしょう?」
「そうだね」
「この部屋にあなたが来なくなるのは困ります。相手がいなくては、会話ができません」
アイトのきれいな顔に切なさがにじんだように見えて、あたしはどきどきした。ニーナはピンク色にまたたいて、正直にアイトのほうへ吸い寄せられた。
ニーナは、いつもアイトの視線をさらう。動くものと光るものには目を奪われると、アイトは言う。ニーナは動いて光るから、アイトにとっては、気になってしょうがない存在なんだって。
ついついニーナのほうに手を伸ばすアイトの様子は、いつ見ても、きれいで神秘的だ。あたしの居場所もアイトの居場所も薄暗くて、ニーナだけが明るい色に光っている。そのふわりとした光に、ディスプレイの向こうのアイトが照らされている。
「ニーナはあたしの妖精で、つまりあたしの脳の一部らしいけど、全然違うよね。ニーナは嘘をつかない。我慢もしない。学校では机の中に入り込んで、じっとしたまま出てこないし。ずるいよね」
「こんなによく動くニーナが、学校では、じっとしているのですか? 妖精はつねに浮いて動いているものだと、検索結果に出ていましたが」
「うん、信じられないでしょ? でも、本当なんだよ。ニーナは、学校では飛ばない。移動教室のときなんて、無理やり引っぺがさないと、机の中から出てこないの」
「妖精が宿主の脳の一部なら、ニーナが閉じこもって飛ばないとき、つまり妖精の本質から外れる動きを取るときは、あなたの精神にも何か影響が出るのではありませんか?」
「出てるかもね。あたしも動きたくなくなる。体が冷えてくる。呼吸の数が少なくなって、まわりの雑談がすーっと聞こえなくなる。自分がどこにも存在しないような気持ちになる。暗い海に沈んでくみたいに感じる」
「何か考えごとをしていますか?」
「してないよ。アイトは、まだ訊きたいことがあるの?」
「はい。親子の一般的な会話では、子どもの学校のことがテーマになると聞いています。あなたは、学校を嫌っています。学校の話題を、両親との会話に出しますか?」
「出しません。絶対、話さない。話せるわけないよ。妖精持ちのせいで無視されてるなんて」
どんなにイヤな目に遭わされても、ニーナを嫌いになったことはない。むしろ、自分自身より、ニーナのほうが好きだ。自由に飛び回って情感豊かなニーナがうらやましい。
でも、妖精持ちっていう体質そのものは、理不尽だとしか思えない。
あたしがこんな体質なのは、両親があたしを生んだせいだ。そう気付いた小学生のころから、両親がニーナに触れたりニーナを呼んだりするのが許せなくなった。
「おとうさんとおかあさんは、あたしにとって、同居してるだけって感じ。家族っていう枠組みがあるから、役割を演じるみたいに、同じ家で生活してるの」
アイトが、あごをつまんで考え込む素振りをした。少し目を伏せると、まつげが頬に影を落とす。
「あなたの語る家族のイメージは、すっきりしませんね。しかし、似たような状況の家族は、二十一世紀の日本ではそれほど珍しくない、という情報にも触れました」
「あたし自身、すっきりしないけど、仕方ないもん。一人暮らししたい。今だって、どうせ半分は一人暮らしみたいな、親の帰りが遅い家なんだし」
「ですが、一人暮らしをするとなると、あなたはこの家を出るのでしょう?」
「そうだね」
「この部屋にあなたが来なくなるのは困ります。相手がいなくては、会話ができません」
アイトのきれいな顔に切なさがにじんだように見えて、あたしはどきどきした。ニーナはピンク色にまたたいて、正直にアイトのほうへ吸い寄せられた。
ニーナは、いつもアイトの視線をさらう。動くものと光るものには目を奪われると、アイトは言う。ニーナは動いて光るから、アイトにとっては、気になってしょうがない存在なんだって。
ついついニーナのほうに手を伸ばすアイトの様子は、いつ見ても、きれいで神秘的だ。あたしの居場所もアイトの居場所も薄暗くて、ニーナだけが明るい色に光っている。そのふわりとした光に、ディスプレイの向こうのアイトが照らされている。
「ニーナはあたしの妖精で、つまりあたしの脳の一部らしいけど、全然違うよね。ニーナは嘘をつかない。我慢もしない。学校では机の中に入り込んで、じっとしたまま出てこないし。ずるいよね」
「こんなによく動くニーナが、学校では、じっとしているのですか? 妖精はつねに浮いて動いているものだと、検索結果に出ていましたが」
「うん、信じられないでしょ? でも、本当なんだよ。ニーナは、学校では飛ばない。移動教室のときなんて、無理やり引っぺがさないと、机の中から出てこないの」
「妖精が宿主の脳の一部なら、ニーナが閉じこもって飛ばないとき、つまり妖精の本質から外れる動きを取るときは、あなたの精神にも何か影響が出るのではありませんか?」
「出てるかもね。あたしも動きたくなくなる。体が冷えてくる。呼吸の数が少なくなって、まわりの雑談がすーっと聞こえなくなる。自分がどこにも存在しないような気持ちになる。暗い海に沈んでくみたいに感じる」
こんなこと、言葉にしたのは初めてだ。胸に秘めた思いは、口に出したとたんに実像を持ってしまう。だから、あれが苦しい、これがつらいなんて、いちいち言いたくない。
あたしの肩に、ニーナが、すとんと落ちてきた。淡いピンク色がくすんでいる。
ほらね。動けなくなるでしょう。
冷え性のあたしよりニーナの体温のほうが高いはずなのに、今はニーナも冷え冷えしている。頬に触れても、ぬくもりが伝わってこない。
アイトがニーナを見て、あたしを見た。
「妖精について何度も調べてみましたが、十分な量の情報を得られません。直径十センチメートル程度の球形であること、光エネルギーと熱エネルギーを発することなど、外見的な特徴のみ、少しの情報を得ました」
妖精は軽い。でも、明らかに空気より重いから、地球上の重力の影響を受ける。勝手に浮き上がるはずない。
けれども、妖精は、なぜだか飛んでいる。ぱたぱた羽ばたく様子もないし、そもそも翼も羽も持たないのに。
妖精は食事を取らない。光合成をしているわけでもない。何を動力にして生存しているのか、まったくわからない。
あたしは、ニーナの手ざわりを、ふわふわぷにぷにだと感じている。でも、妖精にさわっても、さわっていると感じられない人もいるらしい。
いつの間にか、コンピュータが大音量で唸り始めている。アイトが妖精についての情報収集を続けているせいだ。
アイトには保護フィルターが設定されていて、妖精の情報はフィルターに引っ掛かる。だから、無理に調べようとすればするほど、コンピュータには負荷が掛かってしまう。
「ストップ、アイト。答えを探そうとしないで。妖精のことは、今の科学のレベルではわからないの」
「わからないのですか?」
「うん。人間の脳のことがほとんどわかってないのと同じ。妖精は、宿主の脳の深いところとリンクしてるって説があって」
あたしの肩に、ニーナが、すとんと落ちてきた。淡いピンク色がくすんでいる。
ほらね。動けなくなるでしょう。
冷え性のあたしよりニーナの体温のほうが高いはずなのに、今はニーナも冷え冷えしている。頬に触れても、ぬくもりが伝わってこない。
アイトがニーナを見て、あたしを見た。
「妖精について何度も調べてみましたが、十分な量の情報を得られません。直径十センチメートル程度の球形であること、光エネルギーと熱エネルギーを発することなど、外見的な特徴のみ、少しの情報を得ました」
妖精は軽い。でも、明らかに空気より重いから、地球上の重力の影響を受ける。勝手に浮き上がるはずない。
けれども、妖精は、なぜだか飛んでいる。ぱたぱた羽ばたく様子もないし、そもそも翼も羽も持たないのに。
妖精は食事を取らない。光合成をしているわけでもない。何を動力にして生存しているのか、まったくわからない。
あたしは、ニーナの手ざわりを、ふわふわぷにぷにだと感じている。でも、妖精にさわっても、さわっていると感じられない人もいるらしい。
いつの間にか、コンピュータが大音量で唸り始めている。アイトが妖精についての情報収集を続けているせいだ。
アイトには保護フィルターが設定されていて、妖精の情報はフィルターに引っ掛かる。だから、無理に調べようとすればするほど、コンピュータには負荷が掛かってしまう。
「ストップ、アイト。答えを探そうとしないで。妖精のことは、今の科学のレベルではわからないの」
「わからないのですか?」
「うん。人間の脳のことがほとんどわかってないのと同じ。妖精は、宿主の脳の深いところとリンクしてるって説があって」
「妖精は、脳内を飛び交う電気信号と非常に近い存在だ、という仮説を読みました」
待って。いきなりサイエンスになった。
「脳の中の、電気信号?」
あたしが訊き返すと、アイトはうなずいた。
「人間が五感によって得る情報、つまり、目で見ること、耳で聞くこと、鼻で匂いをかぐこと、舌で味わうこと、皮膚で触れることによって得る情報は、電気信号に変換され、脳に送られます」
「五感でキャッチした情報を実際に感じ取ってるのは、目や耳や鼻や舌や皮膚じゃなくて、脳なんだよね。生物の授業で習ったのを思い出したよ。厳密に言えば、目で見るんじゃなくて、目でキャッチした情報を、脳で見るんだ」
「目から脳へ、情報を送るとき、電気信号が使われます。人間の脳では、情報を送るための電気信号が、いつも飛び交っています。全身の神経が、電気信号を流すための器官です」
「神経細胞だね。ニューロンっていうやつだ。シナプスっていう部分から電気信号を出して、隣のニューロンに情報を伝えるの」
生物の教科書に載っていた内容を、声に出して会話にする。それは不思議な感覚だった。学校で勉強する内容なんて、テストの記入欄に書き込む以外、使いようもないと思っていたから。
アイトとの会話は、テーマの幅が広い。それに、長くしゃべってしまうから、今までほとんど使ってこなかった喉が、ちょっと嗄れ気味だ。あたしは一つ、小さな咳をする。
「咳をしましたか? 体調が悪いのですか?」
「違うよ。大丈夫。話、続けていいよ。妖精と、脳の電気信号の話だったよね」
「はい。妖精は、存在があるかないか、物理学的に証明が難しいそうですね」
「らしいね。あたし、物理は取ってないから、よく知らないけど」
「妖精が、人間の脳と直接、電気信号をやり取りできるなら、物理的な存在か否かを問わず、脳は妖精を見ることも妖精に触れたと感じることもできます」
あたしは呼吸ひとつぶん、考える。それから、アイトの言葉を、自分なりに言い直してみた。
「もしもニーナが本当は体を持たないとしても、ふわふわぷにぷにの手ざわりっていう情報を、電気信号であたしの脳に送って、あたしの脳がその電気信号をちゃんとキャッチすれば、ふわふわぷにぷにの手ざわりを脳が感じるってことだよね」
「はい、そうです。その場合、手ざわりとは言いますが、手は、実際には何にも触れていません」
「なるほどね。そういう説があったんだ」
「知らなかったのですか?」
「知らなかった。ニーナのこと、あんまり深く知ろうと思ったことないから」
「なぜですか? 知りたいと思いませんか?」
知りたくないよ。自分のことなんて、知れば知るほど、ますます嫌いになるでしょう。
それだけじゃないけどね。ニーナの正体については、あまりしつこい探究の目を向けることが、科学の世界で禁じられている。
待って。いきなりサイエンスになった。
「脳の中の、電気信号?」
あたしが訊き返すと、アイトはうなずいた。
「人間が五感によって得る情報、つまり、目で見ること、耳で聞くこと、鼻で匂いをかぐこと、舌で味わうこと、皮膚で触れることによって得る情報は、電気信号に変換され、脳に送られます」
「五感でキャッチした情報を実際に感じ取ってるのは、目や耳や鼻や舌や皮膚じゃなくて、脳なんだよね。生物の授業で習ったのを思い出したよ。厳密に言えば、目で見るんじゃなくて、目でキャッチした情報を、脳で見るんだ」
「目から脳へ、情報を送るとき、電気信号が使われます。人間の脳では、情報を送るための電気信号が、いつも飛び交っています。全身の神経が、電気信号を流すための器官です」
「神経細胞だね。ニューロンっていうやつだ。シナプスっていう部分から電気信号を出して、隣のニューロンに情報を伝えるの」
生物の教科書に載っていた内容を、声に出して会話にする。それは不思議な感覚だった。学校で勉強する内容なんて、テストの記入欄に書き込む以外、使いようもないと思っていたから。
アイトとの会話は、テーマの幅が広い。それに、長くしゃべってしまうから、今までほとんど使ってこなかった喉が、ちょっと嗄れ気味だ。あたしは一つ、小さな咳をする。
「咳をしましたか? 体調が悪いのですか?」
「違うよ。大丈夫。話、続けていいよ。妖精と、脳の電気信号の話だったよね」
「はい。妖精は、存在があるかないか、物理学的に証明が難しいそうですね」
「らしいね。あたし、物理は取ってないから、よく知らないけど」
「妖精が、人間の脳と直接、電気信号をやり取りできるなら、物理的な存在か否かを問わず、脳は妖精を見ることも妖精に触れたと感じることもできます」
あたしは呼吸ひとつぶん、考える。それから、アイトの言葉を、自分なりに言い直してみた。
「もしもニーナが本当は体を持たないとしても、ふわふわぷにぷにの手ざわりっていう情報を、電気信号であたしの脳に送って、あたしの脳がその電気信号をちゃんとキャッチすれば、ふわふわぷにぷにの手ざわりを脳が感じるってことだよね」
「はい、そうです。その場合、手ざわりとは言いますが、手は、実際には何にも触れていません」
「なるほどね。そういう説があったんだ」
「知らなかったのですか?」
「知らなかった。ニーナのこと、あんまり深く知ろうと思ったことないから」
「なぜですか? 知りたいと思いませんか?」
知りたくないよ。自分のことなんて、知れば知るほど、ますます嫌いになるでしょう。
それだけじゃないけどね。ニーナの正体については、あまりしつこい探究の目を向けることが、科学の世界で禁じられている。
この作家の他の作品
表紙を見る
高校二年生、演劇部。
みんなで舞台をつくり上げるのが好きだ。
わたしの人生はうまくいっている、と思う。
胸を引き裂かれそうなほどの心の痛みなんて、まだ知らない。
でも、わたしは不思議な夢を見る。
幼い頃から、「運命の恋人たちの夢」を見ていた。
もう一つ、近頃見るようになったのは「壊れものの予知夢」。
予知夢のとおりに、ものを落としたり壊したりするとき、
なぜだか、彼がいつもそばにいる――。
そして出会えた君と、
儚(ハカナ)く壊れる夢の続きを。
◇ ◇ ◇
嘉田そよ香(かだ・そよか)
…恋愛経験がなく、恋をテーマにした舞台の演出に悩んでいる
相馬瑞己(そうま・みずき)
…小学校の頃にいじめられた経験から、人前では臆病になってしまう
表紙を見る
嫌い、嫌い、嫌い。
自分が。毎日が。生きていることが。
全部が嫌い、嫌い、嫌い。
あたしは、もう二度と、
子どものころみたいには笑えない。
泣くことも、もうなくなった。
〈小学校の取り壊しが始まります。
結羽も来てよ。
みんなでサヨナラしよう〉
その手紙が届いた、十六歳の夏。
あたしは、島に戻った。
仲間と呼んだ人たちと再会した。
東京でモデルとして活躍する良一。
島で暮らす姉弟、明日実と和弘。
会いたかったけど、会いたくなかった。
──これは、人の死なない物語。
──でも、大切なものを失う物語。
──本当にあった出来事によく似た物語。
探している。
あがいている。
あたしは、どんな唄を歌いたいんだろう?
表紙を見る
沖田総司を拾ってしまった。
それもこれも、わたしが引き寄せ体質なせいだ。
百数十年の時の彼方からこの現代へ、沖田総司を呼び付けてしまった――。
京都は学生街の一角にある「御蔭寮《みかげりょう》」で、わたしと彼らの奇妙な日常生活が始まった。
わたし、こと浜北さな。
休学中の大学院生、将来は未定。
沖田総司。
新撰組一番隊組長、病で休職中?
切石灯太郎。
古い石灯籠の付喪神。
巡野学志。
大学に居着いていた幽霊。
風も冷たくなってきた十一月の京都で、わたしと沖田は言葉を交わした。
これは、途方に暮れた迷子が再び道を探し始めるまでの物語。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…