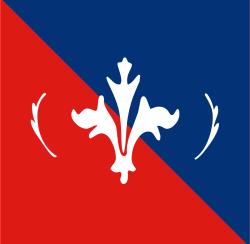私以外の同級生とたくさん出会って、話して、笑って。人の輪の中心になって。
颯はいつも、籠からとき放たれた鳥のように、楽しそうに世界を眺めていた。
本当はもう、大嫌いなんかじゃないって。
『俺のことほんとに大事にしてくれてる奴もいるんだなってわかって、もっと自分以外の世界も大事にしようって思った』
私は、知ってる。
私の言葉に、颯は眉を寄せて「わかってるよ……」と弱々しい声で返した。
「でも、もうぜんぶ消えた。あの高校に、理央以外に俺のこと覚えてる奴はいない。無理なんだよ、今更。俺はここで生きてくしかないんだ」
「無理じゃない」
いつかにも、こうやって彼の言葉を否定した。
颯がハッとして、顔をあげる。
私は彼をまっすぐ見つめた。この心が、まるごと伝わるように。
「颯が諦めなきゃ、いくらでもチャンスはある。だってまだ私がいるから。颯のこと、ひとりになんかしない。ここに閉じこもったままになんか絶対させない」
言いながら、また涙が溢れた。
今度は構わず言葉を続ける。喉の奥が痛くなって、声が震えたけれど、気にしなかった。