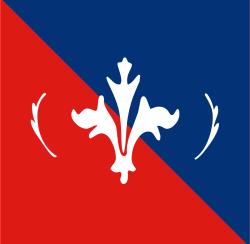涙で視界がぐにゃりと歪んだとき、風が私の身体を通り抜けた。
目元を拭って、顔をあげる。
病室は消えていた。
透明な世界で、高校二年生の颯はぽつんとひとりで立っていた。
彼は私に気づくと、眉を下げて微笑んだ。
「……いいんだよ、理央。俺はもう、充分満足した。あとはもう、この狭い世界で過ごすだけだ」
ここには、色がない。風もない。景色もない。
あるのは、透明だけだ。
どんなものも受け入れられるけれど、その実、どんなものより排他的で、他との交わりを許さない。
「理央には、理央の世界がある。俺なんかに付き合ってたら、外の世界と関われなくなっちゃうよ」
「………颯」
気づけば声は出るようになっていた。
呼べば、彼は目を細める。この世でいちばん愛しいものを見るような目で、私を見つめる。
目があって、喉の奥が痛んだ。
『俺の世界のまんなかにいんのは、理央だよ』
涙が込み上げたけれど、必死にこらえる。
泣きたくても、笑おう。前を向こう。
何度も私を慰めてくれた、颯のように。