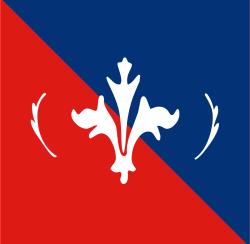こんな大きな世界が外には広がっているのに、彼はあの小さな世界にひとりきり。
なんだ、私と同じじゃないか。
大きな歯車が動かすこの世界で、私は本当にちっぽけな存在でしかなくて。
それが寂しくて寂しくてたまらなかった。
誰かの心に残る私でいたかった。
颯も、私と同じだったんだ。
苦しくなって、過去の自分を後悔した。どうして行かなくなってしまったんだろう。
この人に見せるためにいくら風景を上手くなったって、この人に会う以上に大事なことなんてなかったのに。
だんだんと潤む瞳も無視して、黙って颯の背中を見つめ続けた。
すると颯が振り返って、私を見つめて笑った。
「どうせなら、少しの間でいいから理央と同じ学校に通って、理央と同じ普通の高校生をしてみたいって思った。理央が一緒に行こうって言ってくれた場所に行きたいって」
颯は普段通り、楽しいことを語るみたいな口調で話す。
彼の笑顔を照らすのは、月明かりだけだ。
「そしたら去年の夏、病室に理央の姿をした幻が現れたんだ。まるで妖精みたいだったから、夏の妖精って俺は呼んでる」
信じられる?と颯が笑う。
………私の姿の、幻。
それが本物だったとしても、幻影だったとしても。
颯がそれをその目で見たんだってことを、疑う必要は私にはなかった。