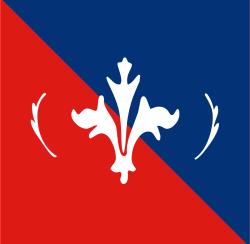「たぶん、ほとんど」
月明かりの逆光で、颯が暗闇の中微笑む。
彼は「そっか」と静かに返事をして、門の向こう側に降り立った。
「こっち来れる?」
「…………………」
言われて、おずおずと門に足をかける。
ゆっくりと移動して校門を越えると、颯に手を引かれて歩き始めた。
夜の学校に忍び込むなんて初めてで、少しドキドキした。
驚くことに校舎は施錠させていなくて、私はまたポカンとした。
颯はまるですべて知っていたかのように、迷いなく昇降口の扉を開けて、中へ入った。
そのまま階段を上がっていく。懐かしい景色がいくつも視界に入ってきて、それを颯と一緒に見ているのが、どうにも不思議だった。
「………え」
颯が再び立ち止まったのは、屋上の扉の前だった。
普段は立ち入り禁止のはずだから、当然鍵は開いていない。
そう思ったのに、彼は躊躇いなくドアノブに手をかけて、それはあっさりと開いた。
「………うそ」
「理央、屋上に行ってみたいって言ってたじゃん」
「………いつ………?」
「えーと、三年前?」
颯は指折り数えて言った。
三年前。私が中学一年生のとき。
ああ、言った気がする。
この学校のことを颯に話す中で、『屋上に入ってみたいのに開いてない』と不満を漏らした覚えがある。