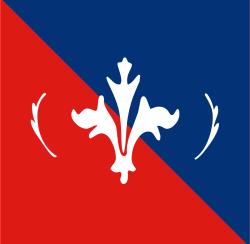「颯、すごいなつかれてたもんね」
「はは。まあ、子供は好きだからいいけど」
「疲れた?」
「ほどほどにな。つーか理央、絵見せてよ」
地面に置いたままの絵を拾い上げて、颯が頭上に掲げた。
彼は目を細める。慈しむようなその視線に、まるで私が見られているかのように思えて、少し心がざわついた。
「やっぱ上手いなあ、理央」
「……ありがと」
気恥ずかしくて、颯の方は見れなかった。
それから広げていた画材たちを片付けて、店主のおばあちゃんに挨拶して、駄菓子屋を出た。
日も暮れていない、まだ帰るには早い時間。私たちはひとまず街の方へ歩き始めた。
今だ照りつける太陽の下、颯が私の二歩前を歩く。
坂道を下り始めると、普段は見えない彼の頭のつむじが見えた。
しばらくお互いに無言で坂を下った。颯はときどき周りの景色を見回しては、目を細めていた。
そして坂が終わり、平坦な道に足を踏み出したとき、颯の横顔がぽつりと呟いた。
「………もーすぐ、夏が来るなあ」
もうすっかり色づいた緑たちが、さわさわと風に揺れる。