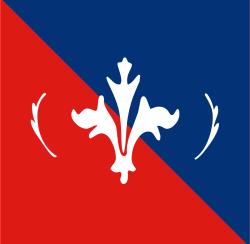「理央の目で、俺がどんな風に映ってるのか見てみたい。理央の絵の中にいる俺を、もっと見たいんだよ」
彼の茶色の混じった瞳が、こちらを向く。目があって、また私の身体が震えた。
怯えじゃない。背筋を走る電流。
私の目に映る颯は、いつも綺麗だ。
綺麗で、きらきらしている。
だけどそれでいて、どこか儚かった。だから私は焦るように、彼の姿を形に残したいと思ったんだ。
「………じゃあ理央は、なんで俺を描いてくれたの?」
颯の問いに、私は思わずその場に立ち止まった。
住宅街を抜けて、木々が生い茂る緩やかな坂道の前。
オレンジのカーブミラーが、颯の後ろ姿を映していた。
「………描きたいって、思ったから」
理由なら、探せばたくさんあった。
だけどそれをぜんぶ伝えるには、私の持つ言葉では不十分だ。
『描きたい』という衝動が私を襲った。一言でいうなら、それだけだ。