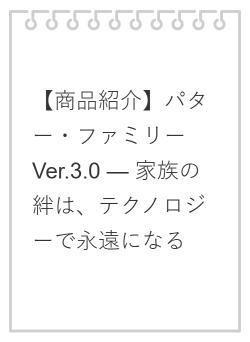「小野寺さん」
昼休み。
以前から現在に至るまで起き続けている不思議な出来事を思い出していると、急に目の前で大きく手を振られた。突然のことに驚いていると、手を振った張本人は笑いながらも申し訳なさそうに眉を下げた。
「ごめん。そんなに驚かす気はなかったんだけど…」
声をかけてきたのはクラスの…いや、学年の人気者にして完璧な学級委員長である『永田(ながた) 晴人(はると)』だ。
彼はそのすらりとした長身や整った顔立ちを始めとして、全てにおいて絵に描いたようなイケメンだった。成績は常にトップ層に入る上に、運動神経も抜群。誰に対しても優しく、困っている人がいれば真っ先に手を差し伸べる。女子からの黄色い声が飛ぶのは日常茶飯事で、男子からも慕われる。まさに皆の憧れの人だった。
そんな彼が私に何の用だろうか。
「私こそ、無駄に驚いちゃってごめんね。どうしたの?」
「小野寺さんのことを呼んでほしいって言われたんだ」
永田君の指さす方向には数人の男子がいた。1人の男子は顔を赤くしており、周囲の友人らしき人たちは顔を赤くしている彼に何かを言っていた。
…うーん、見覚えのない人だ。自分で言っていて悲しいが、生憎交友関係は狭いのだ。どこかで知り合ったかもしれないが、まともに話した記憶はない。
「知り合い?」
急に永田君は真剣な目でそう問うてきた。突然のことに驚いて、何も考えずに素で首を横に振ってしまう。すると彼は「だよね。ちょっと待ってて」とだけ言うと、彼らの元に歩いていき、何か話し始めた。
(ん?今、『だよね』って言った?)
一瞬流しかけたが違和感を感じる。『だよね』ということは、私とあの男子生徒が知り合いではないことを知っていたことにならない…?
そんな違和感がまとまる前に、顔を赤くしていた男子生徒は悲しそうな表情で周囲の友人と共に去っていった。何があったのだろうかと不思議に思っていると、永田君は爽やかな笑顔を浮かべて戻って来た。
「あの、」
「ああ、人違いだったらしいよ。図書室で落とし物を拾ったから小野寺さんのかと思ったんだってさ」
図書室…。確かに昨日の放課後に図書室で本を借りたからその時のことだろうか。人違いというのならば、それまでだ。現に私は何も落とし物をしていない。
「そっか。わざわざありがとう」
「これぐらいいいよ」
そう言うと、永田君はまた爽やかに笑った。その時にはもうあの違和感は綺麗に消え去っていた。
そんな些細なやり取りをきっかけに、私たちは日常的に話すようになっていた。
気づけば数週間経っており、彼と話すことが私の日常の一部となっていた。
好きな色の話
趣味の話
昨日の夕飯の話
最近読んだ小説の話 などなど
毎日何かしらの会話をする。
基本的には永田君から質問を投げてくれることが多かったため、私としては話しやすかった。話術もさながらのこと、心の底から楽しそうに笑う永田君を見る度に人に好かれる笑顔をしているなと感じる。
彼に魅せられる人の気持ちがほんの少しだけ分かったような気がした。
昼休み。
以前から現在に至るまで起き続けている不思議な出来事を思い出していると、急に目の前で大きく手を振られた。突然のことに驚いていると、手を振った張本人は笑いながらも申し訳なさそうに眉を下げた。
「ごめん。そんなに驚かす気はなかったんだけど…」
声をかけてきたのはクラスの…いや、学年の人気者にして完璧な学級委員長である『永田(ながた) 晴人(はると)』だ。
彼はそのすらりとした長身や整った顔立ちを始めとして、全てにおいて絵に描いたようなイケメンだった。成績は常にトップ層に入る上に、運動神経も抜群。誰に対しても優しく、困っている人がいれば真っ先に手を差し伸べる。女子からの黄色い声が飛ぶのは日常茶飯事で、男子からも慕われる。まさに皆の憧れの人だった。
そんな彼が私に何の用だろうか。
「私こそ、無駄に驚いちゃってごめんね。どうしたの?」
「小野寺さんのことを呼んでほしいって言われたんだ」
永田君の指さす方向には数人の男子がいた。1人の男子は顔を赤くしており、周囲の友人らしき人たちは顔を赤くしている彼に何かを言っていた。
…うーん、見覚えのない人だ。自分で言っていて悲しいが、生憎交友関係は狭いのだ。どこかで知り合ったかもしれないが、まともに話した記憶はない。
「知り合い?」
急に永田君は真剣な目でそう問うてきた。突然のことに驚いて、何も考えずに素で首を横に振ってしまう。すると彼は「だよね。ちょっと待ってて」とだけ言うと、彼らの元に歩いていき、何か話し始めた。
(ん?今、『だよね』って言った?)
一瞬流しかけたが違和感を感じる。『だよね』ということは、私とあの男子生徒が知り合いではないことを知っていたことにならない…?
そんな違和感がまとまる前に、顔を赤くしていた男子生徒は悲しそうな表情で周囲の友人と共に去っていった。何があったのだろうかと不思議に思っていると、永田君は爽やかな笑顔を浮かべて戻って来た。
「あの、」
「ああ、人違いだったらしいよ。図書室で落とし物を拾ったから小野寺さんのかと思ったんだってさ」
図書室…。確かに昨日の放課後に図書室で本を借りたからその時のことだろうか。人違いというのならば、それまでだ。現に私は何も落とし物をしていない。
「そっか。わざわざありがとう」
「これぐらいいいよ」
そう言うと、永田君はまた爽やかに笑った。その時にはもうあの違和感は綺麗に消え去っていた。
そんな些細なやり取りをきっかけに、私たちは日常的に話すようになっていた。
気づけば数週間経っており、彼と話すことが私の日常の一部となっていた。
好きな色の話
趣味の話
昨日の夕飯の話
最近読んだ小説の話 などなど
毎日何かしらの会話をする。
基本的には永田君から質問を投げてくれることが多かったため、私としては話しやすかった。話術もさながらのこと、心の底から楽しそうに笑う永田君を見る度に人に好かれる笑顔をしているなと感じる。
彼に魅せられる人の気持ちがほんの少しだけ分かったような気がした。