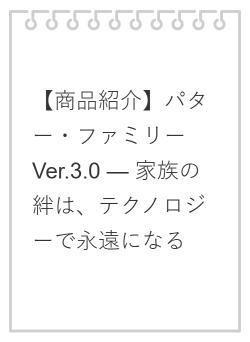「私より先に死なせないから」
その言葉は、放課後の生徒会室に突如として落とされたものだった。
窓の外では運動部の掛け声やボールを蹴る鈍い音が響いているのに、この部屋だけが分厚いガラスに守られた水槽のように静かだ。その中で発された言葉を、聞き間違えるわけない。
振り返るも、会長の視線は手元の書類に向けられたまま。ペン先だけが規則正しく紙の上を滑っている。
窓からグラウンドを見下ろしていた僕の視線に気づいているはずなのに、それ以上は何も言わない。言わないのなら、こちらか聞くだけだ。
「何ですか。藪から棒に」
「自殺念慮を抱えてる後輩に先手を打っておこうと思って」
ようやくペンを止めた会長は、ゆっくりと顔を上げた。夕日を受けた瞳はいつ見ても美しい。でも、その奥にある感情が、どうしても読み取れない。心配なのか、面白がっているのか。はたまた、別の感情か。
「失礼な。僕は自殺念慮ではなく、希死念慮を抱えているんです」
「同じようなものじゃない」
「全く違いますよ。希死念慮は『死にたいという漠然とした思い』です。で、自殺念慮は『死にたい理由や方法を考え始めている状態』です」
「へぇー、知らなかった」
あまりにもさっぱりとした反応に、思わず笑いが漏れた。命の話をしているはずなのに、空気は妙に軽い。
会長はおもむろに椅子から立ち上がると、僕の隣へと並んだ。肘が触れそうな距離。体温がやけに近い。
「じゃあ私は自殺念慮か」
独り言のような言葉に驚いた。思わず顔を見るも、視線は合わない。
「……会長、死にたかったんですか」
「若気の至りだよ」
呆気からんと返される言葉。思わずツッコんでしまう。
「いやいや。それで済まされる思考じゃないですよ」
「そう?でも、いいでしょ。誰だって死にたい中生きてるんだから」
さも当然のように言われてしまえば、言葉は喉の奥で溶けて消える。
反論できない。自分もまた、死にたい気持ちを抱えたまま息をしているのだから。
「知らなかったです」
「何が」
「会長が死にたがってたこと」
「あははっ、寧ろ生きたがっているように見える?」
ようやく浮かんだ笑みは可愛らしいのに、内容は重い。そんなに朗らかに言うことじゃないだろう、と言いかけてやめる。代わりに小さく頷いた。
その肯定は予想外だったらしい。会長の眉がわずかに上がる。
「だって会長、生徒会長やってるし、」
「暇つぶしだもん」
「部活でもキャプテンだったし、」
「推薦されたら断れないよ」
「……今もこうやって生きてるし」
「死ぬのに失敗してるだけだよ。……ほら」
何の前触れもなく、カッターシャツの襟元のボタンが外された。白い喉元に、うっすらと残る線。皺のようにも見えるが、目を凝らせばそれが紐の痕だと分かる。
それに気づくと同時に、心臓が一瞬だけ強く脈打った。それでも、驚きをぐっと押し込んだ。代わりに、棒読みに驚いてみせる。
「わぁ」
「反応薄いな~」
「大袈裟にしましょうか?」
「ううん、いいや」
ボタンを閉じ直す仕草が、やけに丁寧だった。その様子を見つめていれば、会長は何事もなかったかのように欠伸をする。目じりに浮かんだ涙が、長い指で拭われた。
「僕だって」
グラウンドに視線を戻したまま、言葉を絞り出す。隣から、確かにこちらを見る気配がした。
「僕だって、会長のことを僕より先に死なせたりしません」
ちょうどその瞬間、サッカー部の1人がシュートを決めた。甲高いホイッスルに、弾ける歓声。土煙が舞い上がる様子は青春そのものだ。その眩しさに、思わず目を細めてしまう。
その喧騒を、静まり返った生徒会室から見下ろす。ここだけ別世界。日はまだ高いのに、薄暗い海の底に沈んでいるような錯覚に襲われる。
「じゃあ一緒に死ぬ?」
弾かれたように隣を見た。いつもと変わらない表情。けれど綺麗な目だけが、冗談ではないと告げている。
「心中。私はやぶさかではないよ」
「……僕でいいんですか」
「なんかプロポーズ受けた人みたいな言葉だね」
会長は幼さを孕んだ声で笑い、筆箱を漁った。取り出されたのは、1本のカッターナイフ。蛍光灯の光を受けて、仕舞われている刃が鈍く光ったように見えた。
生徒会の備品整理に使うためのもの。そう分かっているのに、用途が別のものへとすり替わる。
「私たちさ、案外相性いいと思うんだよ。こんな第三者が聞いたらドン引きしそうな話でも淡々と話せるし」
「それは否定しません。僕もこんな話ができるのは先輩ぐらいですよ」
「嬉しいこと言ってくれるね。ありがと」
ふわりと風が吹いた。開け放たれた窓から入り込んだ風がカーテンを膨らませ、先輩の肩を覆う。薄い布越しに透ける輪郭は、まるで花嫁のベールのようだった。
プロポーズのような言葉。
ベールを被った先輩。
向かい合う2人。
そして、鈍く光る1本のカッターナイフ。
「どっちからにする?」
「今日の今日で死にます?」
「思い立ったが吉日かなって」
「多分その言葉を作った人も、自殺に当てはめては無いと思いますよ」
クスリと笑った先輩は、ふと目を細める。その目が、ほんの一瞬だけ寂しそうに揺れた気がした。
「でも、そっか。君が抱えているものは『希死念慮』だったね」
「……いつか『自殺念慮』に変わるかもしれません」
僕の言葉に、先輩は吹き出した。ケラケラと楽しげに笑う。その無邪気さが酷く残酷だ。
「ふふっ、なら待ってあげないとね。君が『自殺念慮』を抱く、その日まで」
カッターナイフを片手に、先輩はそれはそれは綺麗に笑った。
女神ではなく、死神。
救済ではなく、共犯。
僕の目には、そう映った。
その言葉は、放課後の生徒会室に突如として落とされたものだった。
窓の外では運動部の掛け声やボールを蹴る鈍い音が響いているのに、この部屋だけが分厚いガラスに守られた水槽のように静かだ。その中で発された言葉を、聞き間違えるわけない。
振り返るも、会長の視線は手元の書類に向けられたまま。ペン先だけが規則正しく紙の上を滑っている。
窓からグラウンドを見下ろしていた僕の視線に気づいているはずなのに、それ以上は何も言わない。言わないのなら、こちらか聞くだけだ。
「何ですか。藪から棒に」
「自殺念慮を抱えてる後輩に先手を打っておこうと思って」
ようやくペンを止めた会長は、ゆっくりと顔を上げた。夕日を受けた瞳はいつ見ても美しい。でも、その奥にある感情が、どうしても読み取れない。心配なのか、面白がっているのか。はたまた、別の感情か。
「失礼な。僕は自殺念慮ではなく、希死念慮を抱えているんです」
「同じようなものじゃない」
「全く違いますよ。希死念慮は『死にたいという漠然とした思い』です。で、自殺念慮は『死にたい理由や方法を考え始めている状態』です」
「へぇー、知らなかった」
あまりにもさっぱりとした反応に、思わず笑いが漏れた。命の話をしているはずなのに、空気は妙に軽い。
会長はおもむろに椅子から立ち上がると、僕の隣へと並んだ。肘が触れそうな距離。体温がやけに近い。
「じゃあ私は自殺念慮か」
独り言のような言葉に驚いた。思わず顔を見るも、視線は合わない。
「……会長、死にたかったんですか」
「若気の至りだよ」
呆気からんと返される言葉。思わずツッコんでしまう。
「いやいや。それで済まされる思考じゃないですよ」
「そう?でも、いいでしょ。誰だって死にたい中生きてるんだから」
さも当然のように言われてしまえば、言葉は喉の奥で溶けて消える。
反論できない。自分もまた、死にたい気持ちを抱えたまま息をしているのだから。
「知らなかったです」
「何が」
「会長が死にたがってたこと」
「あははっ、寧ろ生きたがっているように見える?」
ようやく浮かんだ笑みは可愛らしいのに、内容は重い。そんなに朗らかに言うことじゃないだろう、と言いかけてやめる。代わりに小さく頷いた。
その肯定は予想外だったらしい。会長の眉がわずかに上がる。
「だって会長、生徒会長やってるし、」
「暇つぶしだもん」
「部活でもキャプテンだったし、」
「推薦されたら断れないよ」
「……今もこうやって生きてるし」
「死ぬのに失敗してるだけだよ。……ほら」
何の前触れもなく、カッターシャツの襟元のボタンが外された。白い喉元に、うっすらと残る線。皺のようにも見えるが、目を凝らせばそれが紐の痕だと分かる。
それに気づくと同時に、心臓が一瞬だけ強く脈打った。それでも、驚きをぐっと押し込んだ。代わりに、棒読みに驚いてみせる。
「わぁ」
「反応薄いな~」
「大袈裟にしましょうか?」
「ううん、いいや」
ボタンを閉じ直す仕草が、やけに丁寧だった。その様子を見つめていれば、会長は何事もなかったかのように欠伸をする。目じりに浮かんだ涙が、長い指で拭われた。
「僕だって」
グラウンドに視線を戻したまま、言葉を絞り出す。隣から、確かにこちらを見る気配がした。
「僕だって、会長のことを僕より先に死なせたりしません」
ちょうどその瞬間、サッカー部の1人がシュートを決めた。甲高いホイッスルに、弾ける歓声。土煙が舞い上がる様子は青春そのものだ。その眩しさに、思わず目を細めてしまう。
その喧騒を、静まり返った生徒会室から見下ろす。ここだけ別世界。日はまだ高いのに、薄暗い海の底に沈んでいるような錯覚に襲われる。
「じゃあ一緒に死ぬ?」
弾かれたように隣を見た。いつもと変わらない表情。けれど綺麗な目だけが、冗談ではないと告げている。
「心中。私はやぶさかではないよ」
「……僕でいいんですか」
「なんかプロポーズ受けた人みたいな言葉だね」
会長は幼さを孕んだ声で笑い、筆箱を漁った。取り出されたのは、1本のカッターナイフ。蛍光灯の光を受けて、仕舞われている刃が鈍く光ったように見えた。
生徒会の備品整理に使うためのもの。そう分かっているのに、用途が別のものへとすり替わる。
「私たちさ、案外相性いいと思うんだよ。こんな第三者が聞いたらドン引きしそうな話でも淡々と話せるし」
「それは否定しません。僕もこんな話ができるのは先輩ぐらいですよ」
「嬉しいこと言ってくれるね。ありがと」
ふわりと風が吹いた。開け放たれた窓から入り込んだ風がカーテンを膨らませ、先輩の肩を覆う。薄い布越しに透ける輪郭は、まるで花嫁のベールのようだった。
プロポーズのような言葉。
ベールを被った先輩。
向かい合う2人。
そして、鈍く光る1本のカッターナイフ。
「どっちからにする?」
「今日の今日で死にます?」
「思い立ったが吉日かなって」
「多分その言葉を作った人も、自殺に当てはめては無いと思いますよ」
クスリと笑った先輩は、ふと目を細める。その目が、ほんの一瞬だけ寂しそうに揺れた気がした。
「でも、そっか。君が抱えているものは『希死念慮』だったね」
「……いつか『自殺念慮』に変わるかもしれません」
僕の言葉に、先輩は吹き出した。ケラケラと楽しげに笑う。その無邪気さが酷く残酷だ。
「ふふっ、なら待ってあげないとね。君が『自殺念慮』を抱く、その日まで」
カッターナイフを片手に、先輩はそれはそれは綺麗に笑った。
女神ではなく、死神。
救済ではなく、共犯。
僕の目には、そう映った。