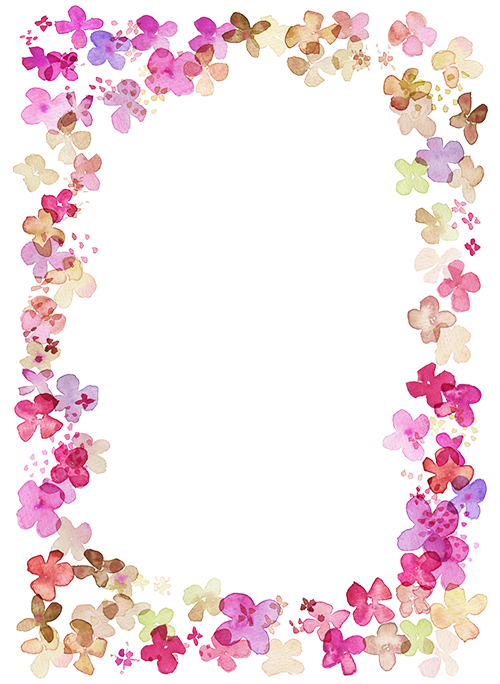花火大会が終わるとお盆まであっという間だった。夏休みが過ぎ、九月に入ると暑さは少し和らいだ。
九月の下旬を過ぎると夏服は出番を終える頃になった。
「俺らがガキの頃は、九月はもっと暑かったよな」
衣替えをして紺色のブレザーに緑と白色のチェック柄のネクタイ、同じチェックのズボンに身を包んだ勇が言った。
その隣では優作がブレザーの下にべージュ色のカーディガンを着用して、彼の横顔を見つめている。勇の高く形の整った鼻に見惚れたことは、本人には恥ずかしくて言えない。
「多分、地球温暖化で気候が変わったんじゃないかな。いっとき秋が無かった時もあったし」
真っ青な空のキャンバスを、飛行機が白い雲を引いて飛んでいる。
恋愛感情としてお互いに好きだと自覚し、打ち明けてからは以前のように身体が熱くなり、激しい思いに心臓が突き動かされることはなくなった。
もっと自分の想いに早く気が付いていればと、二人は思った。
「あ、そうだ。今日は少し寄り道してもいいかな?」
「おう、それは構わないが。優作が帰りに寄り道なんて珍しいな。どこへ行きたいんだ?」
勇が小さな頭を斜めに傾けて不思議そうに聞くと、優作はふふっと目を細めて微笑えんだ。頬が少し赤く染っているように見える。
「それは着いてからのお楽しみだよ」その顔は女子より誰よりこの世で一番、可愛い笑顔だった。
九月の下旬を過ぎると夏服は出番を終える頃になった。
「俺らがガキの頃は、九月はもっと暑かったよな」
衣替えをして紺色のブレザーに緑と白色のチェック柄のネクタイ、同じチェックのズボンに身を包んだ勇が言った。
その隣では優作がブレザーの下にべージュ色のカーディガンを着用して、彼の横顔を見つめている。勇の高く形の整った鼻に見惚れたことは、本人には恥ずかしくて言えない。
「多分、地球温暖化で気候が変わったんじゃないかな。いっとき秋が無かった時もあったし」
真っ青な空のキャンバスを、飛行機が白い雲を引いて飛んでいる。
恋愛感情としてお互いに好きだと自覚し、打ち明けてからは以前のように身体が熱くなり、激しい思いに心臓が突き動かされることはなくなった。
もっと自分の想いに早く気が付いていればと、二人は思った。
「あ、そうだ。今日は少し寄り道してもいいかな?」
「おう、それは構わないが。優作が帰りに寄り道なんて珍しいな。どこへ行きたいんだ?」
勇が小さな頭を斜めに傾けて不思議そうに聞くと、優作はふふっと目を細めて微笑えんだ。頬が少し赤く染っているように見える。
「それは着いてからのお楽しみだよ」その顔は女子より誰よりこの世で一番、可愛い笑顔だった。