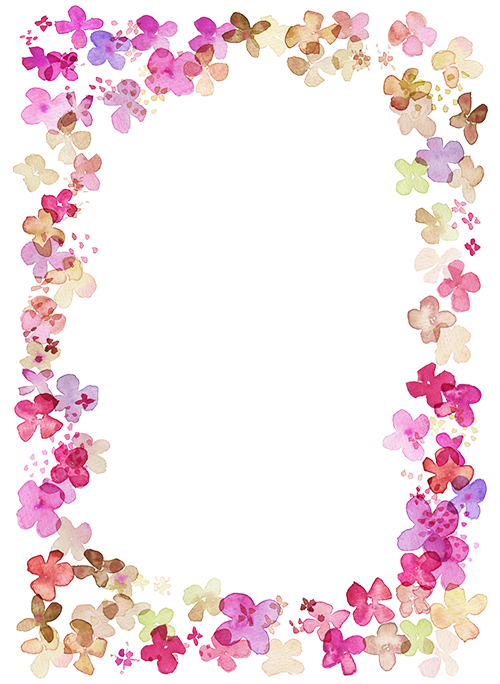「つまり俺達は両想い、ってことでいいんだよな」
勇の漆黒の瞳が真っ直ぐに射るように優作を見つめる。
その力強い眼差しに、優作の心臓がトクトクと加速した。
でもそれは以前のように激しさを増すことなく、緩やかにどこか心地よく胸に響く。
「そうだね。僕達は幼馴染で親友から、両想いになったんだ」
優作がしみじみと言った、次の瞬間。勇が両手で優作の頬を包むと、一気に顔を近づけて彼の唇を塞いだ。
「……!」
優作の驚く声は漏れず、やがてアーモンド型の目を閉じる。
目を閉じた彼の耳に花火が打ち上がるヒュルルという音。そして夜空に花火が咲く盛大な音が響く。
それらもどこか遠くに聞こえ、まるで世界に二人だけのようだと優作は思った。
「今年の花火大会はもう終わっちゃったね」
花火大会が終わると、二人はエレベーターで降りて勇の部屋の前に来た。
優作がしょんぼりした子犬のような目と声音で言う。
勇の胸にまた「可愛い」が込み上げ、彼を抱きしめたくなったがぐっと堪える。
「また来年があるだろう。俺と優作なら、その先もずっとな」
言い終わってから勇はふいに気恥ずかしくなり、顔が赤くなる。
「じ、じゃあまたな。夏風邪とかひくなよ」
素っ気なく言いながら勇は鍵を開けて部屋に入る。
「うん、君も体調には気を付けてね。おやすみ!」
優作の柔らかく穏やかで耳に心地よい声が、部屋のドアを閉めても勇の耳にいつまでもリフレインする。
勇は玄関にしゃがみ込み、真っ赤な顔で自分の唇を人差し指でなぞった。
勇の漆黒の瞳が真っ直ぐに射るように優作を見つめる。
その力強い眼差しに、優作の心臓がトクトクと加速した。
でもそれは以前のように激しさを増すことなく、緩やかにどこか心地よく胸に響く。
「そうだね。僕達は幼馴染で親友から、両想いになったんだ」
優作がしみじみと言った、次の瞬間。勇が両手で優作の頬を包むと、一気に顔を近づけて彼の唇を塞いだ。
「……!」
優作の驚く声は漏れず、やがてアーモンド型の目を閉じる。
目を閉じた彼の耳に花火が打ち上がるヒュルルという音。そして夜空に花火が咲く盛大な音が響く。
それらもどこか遠くに聞こえ、まるで世界に二人だけのようだと優作は思った。
「今年の花火大会はもう終わっちゃったね」
花火大会が終わると、二人はエレベーターで降りて勇の部屋の前に来た。
優作がしょんぼりした子犬のような目と声音で言う。
勇の胸にまた「可愛い」が込み上げ、彼を抱きしめたくなったがぐっと堪える。
「また来年があるだろう。俺と優作なら、その先もずっとな」
言い終わってから勇はふいに気恥ずかしくなり、顔が赤くなる。
「じ、じゃあまたな。夏風邪とかひくなよ」
素っ気なく言いながら勇は鍵を開けて部屋に入る。
「うん、君も体調には気を付けてね。おやすみ!」
優作の柔らかく穏やかで耳に心地よい声が、部屋のドアを閉めても勇の耳にいつまでもリフレインする。
勇は玄関にしゃがみ込み、真っ赤な顔で自分の唇を人差し指でなぞった。