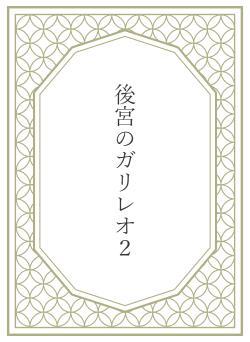File:1
メール 野月→出版社
宛先:S出版 編集部 S様
件名:青春小説の企画書修正案をお送りいたします
お世話になっております。
先日は打ち合わせにてありがとうございました。
いただいた案などを盛り込みまして、企画書の修正をいたしました。
以下URLよりダウンロードをお願いいたします。
URL:※※※※※※
お手すきのタイミングでご確認いただけますと幸いです。
引き続き、よろしくお願いいたします。
企画書修正案
◆タイトル案
『青の証明』『十七歳の答え』など
◆コンセプト
思春期の「まっすぐさ」「不器用さ」を描く。
大人がかつて信じたもの、そして失ったものを、中高生たちの姿を通しても見つめなおす青春小説。
◆あらすじ
県立高校の吹奏楽部が舞台。
全国大会常連校という華々しい肩書きの裏で、練習は厳しく、常に空気は重かった。
二年生の藤堂(とうどう)遥(はるか)はフルートの担当。
まじめで優等生、だが人間関係の軋(きし)みに疲れ、音楽を苦しいものと感じ始めていた。
ある日、教室でギターを弾いていた転校生・朝倉(あさくら)陸(りく)と出会う。
自由奔放で、部活に縛られない彼の姿に、遥は次第に惹かれていく。
「音楽は誰の許可もいらない。音を楽しまずになにが音楽だ」
その言葉に背中を押され、遥は初めて吹奏楽部を辞めるという選択肢を考える。
部員や家族との衝突、進路の悩みなどの障害を乗り越え、遥と陸はお互いに惹かれ合っていく。
そんな中、陸は留学を決める。
彼は自分の音楽を究めるために、海外へ旅立つのだという。
「お前も一緒に行かないか」と誘われ、迷う遥。
夏の終わり。吹奏楽の県大会で金賞を取り、全国大会への切符を手に入れた遥たち。
同じタイミングで、遥に音楽大学への推薦の話が出る。
このまま音楽大学へと進むと、留学はできなくなってしまう。
約束された未来、挑戦が必要な未来のはざまで揺れ動く遥。
しかし、彼女は自分の心に嘘はつけないからと、次の全国大会を最後に部活を辞め、留学をするという選択をした。
彼女は部員の前で頭を下げる。
「私は賞を取るための音楽じゃなくて、人に届く音を奏でたい」
部活を辞めた遥は今度こそ自分の音楽を奏でるために、陸とともに海外へと旅立った。
メール 出版社→野月
宛先:野月様
件名:Re:青春小説の企画書修正案をお送りいたします
お世話になっております。
企画書の件、ありがとうございます。
さっそく拝見いたしました。
いただいた修正案、とても素敵なのですが、
このままGOを出すのは正直難しいというのが現状です。
理由といたしましては、リアリティの薄さが挙げられます。
今の中高生の考えていることというよりは、
野月様の中高生の理想像が前面に出ているように見受けられました。
価値観の押し付けと思われてしまうと大変残念なので、
可能であれば、もう少しリアリティラインを上げられますでしょうか。
また、特定の部活に属していないほうが、リーチ先が広がると思います。
一度打ち合わせていただいた件はご放念いただき、
再度ゼロベースで案をいただいたほうがよろしいかもしれません。
数行の素案で結構ですので、もし他の案をいただけるようであれば、
ぜひお願いできたらと思います。
お手数をおかけいたしますが、ご検討いただけますと幸いです。
引き続き、よろしくお願いいたします。
メール 野月→出版社
宛先:S出版 編集部 S様
件名:Re:Re:青春小説の企画書修正案をお送りいたします
お世話になっております。
ご確認いただきましてありがとうございます!
また、ご指摘いただきましてありがとうございます。
おっしゃる通りだと思いますので、今一度、再考いたします。
何度もご確認いただき、お手数をおかけしてしまって申し訳ございません。
少々お待ちいただけますと幸いです。
引き続き、よろしくお願いいたします。
リアリティと言われても、学生時代なんて何年前だ。
その言葉をかろうじて飲み込んで、私はメール返信を終えた。
またボツだ。もう何度目だろう。企画のあまりの通らなさに、ため息が止まらない。
S社は、私がメインで取引している出版社である。
この出版社の公募に応募し、運よく受賞してデビューが決まったときは、跳び上がるほど喜んだ。
一年目は大人向けの恋愛小説を。二年目には古典作品を現代の青春恋愛に置き換えた小説を書いた。
そして三年目、オリジナルの青春小説を書かないか、と打診があったのである。
S社は青春小説に強いことで有名な出版社だ。映画化の実績を持っているのも魅力的である。
もしここで青春小説を出すことができ、そして、それがヒットすれば、自身のキャリアに箔がつく。
しかし、何度企画を練っても、担当さんからはOKが出ない。
価値観の押し付けと言われても困ってしまう。
今の若い子がなにを考えているのかなんて正直わからない。
でも、書かなければ。
デビューして三年。たった三年だが、この業界に身を置いてみて身に染みたことがある。
努力を怠ったらあっという間に失業するのが小説家だ。
一本でも多く原稿を書き、販売ルートに乗せ、表舞台に立たなければ読者のみなさんに忘れられてしまう。
そこに舞い込んだ、S社の青春小説の話。なんとしても企画を通さなければ。
チャンスはもうすぐそこにある。あとは私がどんな案を出せるか、それ次第で、今後の命運が決まるのだ。
私はスマホを握りしめる。
実を言うと、私には奥の手があった。それは、過去の交友関係のつてである。
卒業した大学は、数多くの教員を輩出していることで有名だった。
私の友人たちも例に漏れず、教職についている者が多い。
友人に、学校を紹介してもらおう。
取材をさせてもらって、今の中高生のリアルを知っておこう。
想像で書くには、あまりにも自分の中の情報が古すぎる。
スマホを開き、トークルームを表示した。
AとのLINE
野月「ひさしぶり」
野月「いきなりごめん!」
A「どした~?」
野月「Aって今、中学校の先生やってたよね」
A「そうだけど」
野月「その中学校って取材可能だったりするかな?」
野月「実は次の作品で、中高生を書きたいなって考えているんだけど」
野月「リアルな学生の声とか、学校の雰囲気とかを聞きたくて」
A「マジ? いいじゃん!」
A「取材大丈夫だと思う! 前も取材で雑誌の人とか来たことあるし」
A「一応、明日確認するよ! ちょっと待ってて~」
野月「(ありがとう、と猫がおじぎしているスタンプ)」
そして翌日、Aより取材OKの連絡をもらった。
こうして私はAの勤める中学校、『朝日ヶ森中学校』に向かうこととなった。
メール 野月→出版社
宛先:S出版 編集部 S様
件名:青春小説の企画書修正案をお送りいたします
お世話になっております。
先日は打ち合わせにてありがとうございました。
いただいた案などを盛り込みまして、企画書の修正をいたしました。
以下URLよりダウンロードをお願いいたします。
URL:※※※※※※
お手すきのタイミングでご確認いただけますと幸いです。
引き続き、よろしくお願いいたします。
企画書修正案
◆タイトル案
『青の証明』『十七歳の答え』など
◆コンセプト
思春期の「まっすぐさ」「不器用さ」を描く。
大人がかつて信じたもの、そして失ったものを、中高生たちの姿を通しても見つめなおす青春小説。
◆あらすじ
県立高校の吹奏楽部が舞台。
全国大会常連校という華々しい肩書きの裏で、練習は厳しく、常に空気は重かった。
二年生の藤堂(とうどう)遥(はるか)はフルートの担当。
まじめで優等生、だが人間関係の軋(きし)みに疲れ、音楽を苦しいものと感じ始めていた。
ある日、教室でギターを弾いていた転校生・朝倉(あさくら)陸(りく)と出会う。
自由奔放で、部活に縛られない彼の姿に、遥は次第に惹かれていく。
「音楽は誰の許可もいらない。音を楽しまずになにが音楽だ」
その言葉に背中を押され、遥は初めて吹奏楽部を辞めるという選択肢を考える。
部員や家族との衝突、進路の悩みなどの障害を乗り越え、遥と陸はお互いに惹かれ合っていく。
そんな中、陸は留学を決める。
彼は自分の音楽を究めるために、海外へ旅立つのだという。
「お前も一緒に行かないか」と誘われ、迷う遥。
夏の終わり。吹奏楽の県大会で金賞を取り、全国大会への切符を手に入れた遥たち。
同じタイミングで、遥に音楽大学への推薦の話が出る。
このまま音楽大学へと進むと、留学はできなくなってしまう。
約束された未来、挑戦が必要な未来のはざまで揺れ動く遥。
しかし、彼女は自分の心に嘘はつけないからと、次の全国大会を最後に部活を辞め、留学をするという選択をした。
彼女は部員の前で頭を下げる。
「私は賞を取るための音楽じゃなくて、人に届く音を奏でたい」
部活を辞めた遥は今度こそ自分の音楽を奏でるために、陸とともに海外へと旅立った。
メール 出版社→野月
宛先:野月様
件名:Re:青春小説の企画書修正案をお送りいたします
お世話になっております。
企画書の件、ありがとうございます。
さっそく拝見いたしました。
いただいた修正案、とても素敵なのですが、
このままGOを出すのは正直難しいというのが現状です。
理由といたしましては、リアリティの薄さが挙げられます。
今の中高生の考えていることというよりは、
野月様の中高生の理想像が前面に出ているように見受けられました。
価値観の押し付けと思われてしまうと大変残念なので、
可能であれば、もう少しリアリティラインを上げられますでしょうか。
また、特定の部活に属していないほうが、リーチ先が広がると思います。
一度打ち合わせていただいた件はご放念いただき、
再度ゼロベースで案をいただいたほうがよろしいかもしれません。
数行の素案で結構ですので、もし他の案をいただけるようであれば、
ぜひお願いできたらと思います。
お手数をおかけいたしますが、ご検討いただけますと幸いです。
引き続き、よろしくお願いいたします。
メール 野月→出版社
宛先:S出版 編集部 S様
件名:Re:Re:青春小説の企画書修正案をお送りいたします
お世話になっております。
ご確認いただきましてありがとうございます!
また、ご指摘いただきましてありがとうございます。
おっしゃる通りだと思いますので、今一度、再考いたします。
何度もご確認いただき、お手数をおかけしてしまって申し訳ございません。
少々お待ちいただけますと幸いです。
引き続き、よろしくお願いいたします。
リアリティと言われても、学生時代なんて何年前だ。
その言葉をかろうじて飲み込んで、私はメール返信を終えた。
またボツだ。もう何度目だろう。企画のあまりの通らなさに、ため息が止まらない。
S社は、私がメインで取引している出版社である。
この出版社の公募に応募し、運よく受賞してデビューが決まったときは、跳び上がるほど喜んだ。
一年目は大人向けの恋愛小説を。二年目には古典作品を現代の青春恋愛に置き換えた小説を書いた。
そして三年目、オリジナルの青春小説を書かないか、と打診があったのである。
S社は青春小説に強いことで有名な出版社だ。映画化の実績を持っているのも魅力的である。
もしここで青春小説を出すことができ、そして、それがヒットすれば、自身のキャリアに箔がつく。
しかし、何度企画を練っても、担当さんからはOKが出ない。
価値観の押し付けと言われても困ってしまう。
今の若い子がなにを考えているのかなんて正直わからない。
でも、書かなければ。
デビューして三年。たった三年だが、この業界に身を置いてみて身に染みたことがある。
努力を怠ったらあっという間に失業するのが小説家だ。
一本でも多く原稿を書き、販売ルートに乗せ、表舞台に立たなければ読者のみなさんに忘れられてしまう。
そこに舞い込んだ、S社の青春小説の話。なんとしても企画を通さなければ。
チャンスはもうすぐそこにある。あとは私がどんな案を出せるか、それ次第で、今後の命運が決まるのだ。
私はスマホを握りしめる。
実を言うと、私には奥の手があった。それは、過去の交友関係のつてである。
卒業した大学は、数多くの教員を輩出していることで有名だった。
私の友人たちも例に漏れず、教職についている者が多い。
友人に、学校を紹介してもらおう。
取材をさせてもらって、今の中高生のリアルを知っておこう。
想像で書くには、あまりにも自分の中の情報が古すぎる。
スマホを開き、トークルームを表示した。
AとのLINE
野月「ひさしぶり」
野月「いきなりごめん!」
A「どした~?」
野月「Aって今、中学校の先生やってたよね」
A「そうだけど」
野月「その中学校って取材可能だったりするかな?」
野月「実は次の作品で、中高生を書きたいなって考えているんだけど」
野月「リアルな学生の声とか、学校の雰囲気とかを聞きたくて」
A「マジ? いいじゃん!」
A「取材大丈夫だと思う! 前も取材で雑誌の人とか来たことあるし」
A「一応、明日確認するよ! ちょっと待ってて~」
野月「(ありがとう、と猫がおじぎしているスタンプ)」
そして翌日、Aより取材OKの連絡をもらった。
こうして私はAの勤める中学校、『朝日ヶ森中学校』に向かうこととなった。