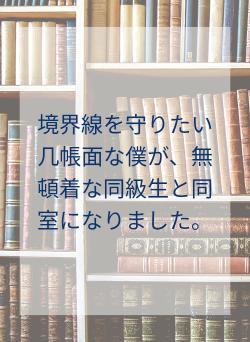***
ホテルのロビーに着いた日向は、場違いなほど高級そうな空間に少し萎縮していた。
下に到着したら連絡して、と流星からのメッセージには書かれていたが、やはり体調が悪くなったと嘘をついて帰ってしまおうか。
そんなことを考えながら回れ右をすると、誰かに腕をつかまれた。驚いて顔を上げれば、マスクにサングラス姿の長身の男が立っていた。
「ねえ、君。……ひょっとして『ヒナタ』?」
サングラスをそっと外した男は、流星と同じアイドルグループ「Meteoroids」のメンバーであるカイだった。何故か自分の存在を知られていることに日向が焦っていると、カイがガシッと肩を組んできた。そのままエレベーターの方へと強引に引っ張られていく。
「ちょっ……ちょっと、待ってください」
「リュウセイに会いに来たんだろ? 逃げないで会ってやってよ。今日のライブ、君が関係者席に来てなかったから、リュウセイめちゃくちゃ不機嫌だったんだよ」
「いや、あ、はい。……すみません」
流星からは事前に関係者席のライブチケットが送られてきていたのだが、日向は自分で苦労して入手していた一般席のチケットを使った。もしかしたら、今日のライブに来ていないと勘違いされている可能性があった。
それに、もう一つ気になることがある。
「あの、カイさん。……なんで僕のことを?」
「自分の親友がどんなに可愛くて素晴らしいのか、頻繁にプレゼンしてくる自惚れバカがメンバーにいんだよ。奴のスマホには推しの君の写真が死ぬ程入ってる。アイツが頻繁に眺めてるから、顔覚えちゃった」
日向は軽いめまいを覚えた。まさかメンバーにまで自分のことを話しているとは思わなかった。
「お~い、リュウセイ、ちょっといいか?」
ホテルのエレベーターを降りて部屋に辿り着くや否や、カイは扉を叩いて大声で流星を呼んだ。その瞬間、扉が勢いよく開き、眉を吊り上げた流星が飛び出してきた。
「うっせえぞ! 去れ!! 俺は今から大事な用事があって忙し……」
カイを怒鳴ろうとした口が途中で止まった。流星の視線が一点に固定され、次の瞬間、カイから奪い取るような勢いで、視線の先に佇んでいた日向の身体を抱き寄せた。
「テメエ、何で日向に触ってんだよ!?」
「おいおい、気おくれして帰ろうとしていたヒナタ君を捕獲してきたヒーローだぜ俺は」
「日向……来てくれたんだな」
「……うん。久しぶり、流星」
「会いたかった」
「お~い、リュウセイさーん? 俺のこと見えなくなった系?」
流星が日向を腕の中に抱き締めたまま、カイの方を見た。
「おー、サンキュ。あとは二人で話すからさっさと退散しろ。日向に近づいたらぶっ殺す」
「お前なあ……そういうとこ、ファンに知られないようにしろよ? じゃあなヒナタくん、またね」
「あっ、はい……ありがとうございました」
カイが出ていった後、日向と流星の間に沈黙が流れた。しばらくすると、逃亡を阻止するかのように流星が日向の持っている手荷物を取り上げ、部屋のソファの上に置いた。大きな窓の外には、ライブ会場から帰宅する人々の頭上に広がる星空が輝いている。
流星は、日向の手を握りしめ、顔を覗き込んできた。その表情には、安堵と、そして拗ねた子どものような色が混じっている。
ステージ上でスポットライトを浴びながら輝いていた銀色の光の化身のような「アイドル」ではない。少し幼くて、昔のままの、日向のよく知っている素直な「流星」の顔だった。
「日向は、俺に会いたくなかった?」
流星が、弱々しい声で問いかける。その問いかけに、日向の心がぎゅっと痛んだ。会いたくなかった訳じゃない。ただ、目の当たりにした圧倒的な彼の輝きに、自分の居場所を見失ってしまっただけで。
「そんなことない」
「帰ろうとしてたんだろ? 俺が送ったチケットも使ってくれなかったみたいだし……」
「あ……それは、ごめん。でも、チケットは自分で用意してたから、今日のライブはちゃんと観たよ。凄く良かった」
「……知ってる。見えてたから」
「え? わかったの?」
日向は軽く驚いた。流星は嘘をつかないから、本当に日向を見つけてくれたのだろう。あんなに広い会場で、遠くの、たくさんの観客がいる中でも。
「ステージから、観客席は想像以上によく見えるんだ。笑顔を向けて応援してくれる子はめちゃくちゃ楽しませてあげたいし、つまんなそうに俯いてる奴とかは、ゼッテー顔上げさせてやろうって力が湧いてくる」
天性のアイドル気質なのだろう。日向は隣の席にいた女の子を思い出していた。ちゃんと、君の想いは届いてるよ、と伝えたくなる。
「なあ、日向。あれ何?」
「ああ、ライブ中に降ってきた銀テープだよ。隣の子が欲しそうにしてたから一度あげたんだけど、その後スタッフさんに貰ったからって返してくれたんだ」
日向は、自分の元へ戻ってきた銀テープを袋から取り出して流星に見せた。流星はテープを手に取り、裏側に印字された自分のサインを指でそっと撫でる。
「……お前、隣の子と仲良く話してたもんな」
唇を尖らせながら、ブツブツ呟いている。本当によく見えてるんだと感心するのと同時に、そんな些細なことで嫉妬してしまう流星が少しおかしくて、愛おしく感じてしまう。
「あの子、流星のファンだった。ライブ凄く楽しんでたよ」
「それも分かってる。でも感情が追いつかないんだから、仕方ねぇだろ」
流星があまりにも素直に自分の気持ちを語るから、少しだけ日向も気が緩んでしまう。
「……なんかさ、ステージに立っている流星は、手の届かない王子様みたいで凄く綺麗で輝いてた。みんなの視線を集めて、みんなに愛されて、みんなを愛して……。住む世界が違うっていうか、遠い存在になってるんだなって、もう一緒にいられないんだなって感じて……」
「……お前が、そんなこと言うなよ」
「だって……」
流星が苦しげな表情で、日向の言葉を遮る。何か言おうとしても、うまく言葉にならない。
「日向、両手出せ」
流星の命令に、戸惑いながら日向が両手を差し出すと、流星は愛の言葉が印字された銀テープを、何故か日向の両手首にグルグルと巻きつけはじめた。優しく、だけどしっかりと。
日向はポカンとしながら、それを眺めた。
「流星? 何してんの?」
「日向が、俺から逃げないように縛ってる」
「ええっ?」
「……あのさ、俺は日向がいたから、辛くても頑張れたんだよ。今の俺がステージに立てるのは日向のおかげでもあるんだ。お前が一番最初に言ってくれたんだろ? 流星なら絶対出来るよ、ずっと応援しててやるって。今さら俺を放り出さないでくれ」
流星の瞳が揺れている。それは、皆のアイドルではなく、日向にしか見せない、弱くて甘えたような彼本来の光だった。
日向は目を瞬かせた。大げさだよと軽く笑えなかった。自分の言葉が、存在が、こんな風に彼を支えていたなんて、正直全く自覚がなかった。
「頼むから、俺のそばからいなくならないでくれよ」
流星の切羽詰まった声に、日向は思わず息を飲んだ。ああ、そうか。自分が勝手に線を引いて、諦めて手を離そうとしていただけで、流星はずっと自分を想っていてくれていたんだ。
スポットライトを浴びていた時はあんなに派手に輝いていた銀テープが、今は日向の肌に白く冷たく反射して、まるで「銀の枷」のように見える。でも、手首に巻き付けられたその執着と束縛の証は、不快なものではなかった。むしろ、それこそが彼の確かな想いであり、自分という存在を必要としてくれている証明に思えた。
「流星」
「うん?」
「逃げないよ。僕は流星のそばにいるから」
「……うん」
「愛してるよ」
日向が小さくそう告げると、流星は安堵したように目を細めた。「俺も」 と短く返し、日向の顔を見つめながら笑った。
それは、日向だけが知る、いつも一緒にいたあの頃の流星と同じ柔らかい笑顔だった。
【終】
ホテルのロビーに着いた日向は、場違いなほど高級そうな空間に少し萎縮していた。
下に到着したら連絡して、と流星からのメッセージには書かれていたが、やはり体調が悪くなったと嘘をついて帰ってしまおうか。
そんなことを考えながら回れ右をすると、誰かに腕をつかまれた。驚いて顔を上げれば、マスクにサングラス姿の長身の男が立っていた。
「ねえ、君。……ひょっとして『ヒナタ』?」
サングラスをそっと外した男は、流星と同じアイドルグループ「Meteoroids」のメンバーであるカイだった。何故か自分の存在を知られていることに日向が焦っていると、カイがガシッと肩を組んできた。そのままエレベーターの方へと強引に引っ張られていく。
「ちょっ……ちょっと、待ってください」
「リュウセイに会いに来たんだろ? 逃げないで会ってやってよ。今日のライブ、君が関係者席に来てなかったから、リュウセイめちゃくちゃ不機嫌だったんだよ」
「いや、あ、はい。……すみません」
流星からは事前に関係者席のライブチケットが送られてきていたのだが、日向は自分で苦労して入手していた一般席のチケットを使った。もしかしたら、今日のライブに来ていないと勘違いされている可能性があった。
それに、もう一つ気になることがある。
「あの、カイさん。……なんで僕のことを?」
「自分の親友がどんなに可愛くて素晴らしいのか、頻繁にプレゼンしてくる自惚れバカがメンバーにいんだよ。奴のスマホには推しの君の写真が死ぬ程入ってる。アイツが頻繁に眺めてるから、顔覚えちゃった」
日向は軽いめまいを覚えた。まさかメンバーにまで自分のことを話しているとは思わなかった。
「お~い、リュウセイ、ちょっといいか?」
ホテルのエレベーターを降りて部屋に辿り着くや否や、カイは扉を叩いて大声で流星を呼んだ。その瞬間、扉が勢いよく開き、眉を吊り上げた流星が飛び出してきた。
「うっせえぞ! 去れ!! 俺は今から大事な用事があって忙し……」
カイを怒鳴ろうとした口が途中で止まった。流星の視線が一点に固定され、次の瞬間、カイから奪い取るような勢いで、視線の先に佇んでいた日向の身体を抱き寄せた。
「テメエ、何で日向に触ってんだよ!?」
「おいおい、気おくれして帰ろうとしていたヒナタ君を捕獲してきたヒーローだぜ俺は」
「日向……来てくれたんだな」
「……うん。久しぶり、流星」
「会いたかった」
「お~い、リュウセイさーん? 俺のこと見えなくなった系?」
流星が日向を腕の中に抱き締めたまま、カイの方を見た。
「おー、サンキュ。あとは二人で話すからさっさと退散しろ。日向に近づいたらぶっ殺す」
「お前なあ……そういうとこ、ファンに知られないようにしろよ? じゃあなヒナタくん、またね」
「あっ、はい……ありがとうございました」
カイが出ていった後、日向と流星の間に沈黙が流れた。しばらくすると、逃亡を阻止するかのように流星が日向の持っている手荷物を取り上げ、部屋のソファの上に置いた。大きな窓の外には、ライブ会場から帰宅する人々の頭上に広がる星空が輝いている。
流星は、日向の手を握りしめ、顔を覗き込んできた。その表情には、安堵と、そして拗ねた子どものような色が混じっている。
ステージ上でスポットライトを浴びながら輝いていた銀色の光の化身のような「アイドル」ではない。少し幼くて、昔のままの、日向のよく知っている素直な「流星」の顔だった。
「日向は、俺に会いたくなかった?」
流星が、弱々しい声で問いかける。その問いかけに、日向の心がぎゅっと痛んだ。会いたくなかった訳じゃない。ただ、目の当たりにした圧倒的な彼の輝きに、自分の居場所を見失ってしまっただけで。
「そんなことない」
「帰ろうとしてたんだろ? 俺が送ったチケットも使ってくれなかったみたいだし……」
「あ……それは、ごめん。でも、チケットは自分で用意してたから、今日のライブはちゃんと観たよ。凄く良かった」
「……知ってる。見えてたから」
「え? わかったの?」
日向は軽く驚いた。流星は嘘をつかないから、本当に日向を見つけてくれたのだろう。あんなに広い会場で、遠くの、たくさんの観客がいる中でも。
「ステージから、観客席は想像以上によく見えるんだ。笑顔を向けて応援してくれる子はめちゃくちゃ楽しませてあげたいし、つまんなそうに俯いてる奴とかは、ゼッテー顔上げさせてやろうって力が湧いてくる」
天性のアイドル気質なのだろう。日向は隣の席にいた女の子を思い出していた。ちゃんと、君の想いは届いてるよ、と伝えたくなる。
「なあ、日向。あれ何?」
「ああ、ライブ中に降ってきた銀テープだよ。隣の子が欲しそうにしてたから一度あげたんだけど、その後スタッフさんに貰ったからって返してくれたんだ」
日向は、自分の元へ戻ってきた銀テープを袋から取り出して流星に見せた。流星はテープを手に取り、裏側に印字された自分のサインを指でそっと撫でる。
「……お前、隣の子と仲良く話してたもんな」
唇を尖らせながら、ブツブツ呟いている。本当によく見えてるんだと感心するのと同時に、そんな些細なことで嫉妬してしまう流星が少しおかしくて、愛おしく感じてしまう。
「あの子、流星のファンだった。ライブ凄く楽しんでたよ」
「それも分かってる。でも感情が追いつかないんだから、仕方ねぇだろ」
流星があまりにも素直に自分の気持ちを語るから、少しだけ日向も気が緩んでしまう。
「……なんかさ、ステージに立っている流星は、手の届かない王子様みたいで凄く綺麗で輝いてた。みんなの視線を集めて、みんなに愛されて、みんなを愛して……。住む世界が違うっていうか、遠い存在になってるんだなって、もう一緒にいられないんだなって感じて……」
「……お前が、そんなこと言うなよ」
「だって……」
流星が苦しげな表情で、日向の言葉を遮る。何か言おうとしても、うまく言葉にならない。
「日向、両手出せ」
流星の命令に、戸惑いながら日向が両手を差し出すと、流星は愛の言葉が印字された銀テープを、何故か日向の両手首にグルグルと巻きつけはじめた。優しく、だけどしっかりと。
日向はポカンとしながら、それを眺めた。
「流星? 何してんの?」
「日向が、俺から逃げないように縛ってる」
「ええっ?」
「……あのさ、俺は日向がいたから、辛くても頑張れたんだよ。今の俺がステージに立てるのは日向のおかげでもあるんだ。お前が一番最初に言ってくれたんだろ? 流星なら絶対出来るよ、ずっと応援しててやるって。今さら俺を放り出さないでくれ」
流星の瞳が揺れている。それは、皆のアイドルではなく、日向にしか見せない、弱くて甘えたような彼本来の光だった。
日向は目を瞬かせた。大げさだよと軽く笑えなかった。自分の言葉が、存在が、こんな風に彼を支えていたなんて、正直全く自覚がなかった。
「頼むから、俺のそばからいなくならないでくれよ」
流星の切羽詰まった声に、日向は思わず息を飲んだ。ああ、そうか。自分が勝手に線を引いて、諦めて手を離そうとしていただけで、流星はずっと自分を想っていてくれていたんだ。
スポットライトを浴びていた時はあんなに派手に輝いていた銀テープが、今は日向の肌に白く冷たく反射して、まるで「銀の枷」のように見える。でも、手首に巻き付けられたその執着と束縛の証は、不快なものではなかった。むしろ、それこそが彼の確かな想いであり、自分という存在を必要としてくれている証明に思えた。
「流星」
「うん?」
「逃げないよ。僕は流星のそばにいるから」
「……うん」
「愛してるよ」
日向が小さくそう告げると、流星は安堵したように目を細めた。「俺も」 と短く返し、日向の顔を見つめながら笑った。
それは、日向だけが知る、いつも一緒にいたあの頃の流星と同じ柔らかい笑顔だった。
【終】