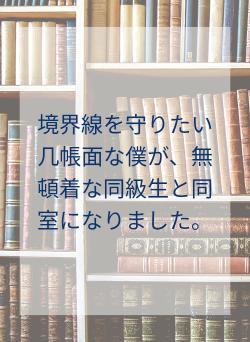会場の照明がゆっくりと落ち、大歓声が一瞬の静寂に変わる。暗闇の中、心臓だけが不規則なリズムを刻んでいた。
『5、4、3、2、1、───』
スクリーンにカウントダウンの数字が映し出され、それがゼロになった瞬間。
爆発音にも似た特効が炸裂し、ステージいっぱいに眩い光が降り注ぐ。日向の全身を揺らすほどの重低音が響き渡り、視界が一気に銀色の世界に塗り替えられた。
スポットライトの中心。煙が渦巻くステージの奥から、五人の影が浮かび上がる。
頼れるリーダーのタイキ、ムードメーカーのカイ、クールなアマネ、そしてダンス担当のリク。けれど、日向の目はただ一人を追っていた。
──流星。
煌びやかな銀色の衣装を身につけた『リュウセイ』は、まるで夜空を切り取ってきたかのような輝きを放っていた。彼の登場を告げるかのように、ひときわ強い光が彼を捉える。
一歩足を踏み出すたびに、衣装に縫い付けられたスパンコールやビジューが、会場の光を吸い込んで万華鏡のようにキラキラと反射する。その姿は、まさに流星群の中心を征くたった一つの星だった。
彼がマイクを握り、歌い始める。その声は、甘くも力強く、日向が知る昔の『流星』の面影を宿しながらも、さらに何倍も磨き上げられ、大勢の心を掴むための『リュウセイ』の声になっていた。
「Meteoroidsです! 今日は来てくれてありがとう!!」
タイキのその言葉とともに、五人が一糸乱れぬフォーメーションで踊り出す。指の先、つま先まで神経の行き届いた完璧なパフォーマンス。その中心にいるリュウセイの笑顔はどこまでも爽やかで完璧で、彼は観客席に「愛」を振り撒きながら、皆を魅了していく。
日向は息をすることさえ忘れて、ただその光景に見入っていた。
隣の席では、初めてライブに来たらしい女の子が、ペンライトを振り回しながら「リュウセイ!」と嬉しそうに叫んでいる。
────この光は、もう僕だけのものではないんだ。
その視線、その指先、その吐息。すべてが「みんなのもの」だ。
ステージ上の彼は、誰よりも美しく輝いていて、そして誰よりも遠い。
かつて同じ放課後を過ごし、同じコンビニのアイスを分け合い、同じ夜空の星を見上げながら、くだらないことで笑い合っていた日々が、急に薄いガラス細工のように脆く儚く感じられた。
目の前に広がるのは、非現実的なほどに美しい夢の世界。そして自分は、その世界の一ファンとして、何千人の中の一人として、彼の放つ光に照らされているに過ぎない。その事実が、胸の奥を鈍く深く抉っていく。
喜びと興奮の中で、けれど確かに滲むのは、孤独感にも似た底なしの切なさだった。
ボンヤリと別世界のステージを眺めていると、不意に隣の女の子の腕が日向の肩をパチンと叩いて、現実に引き戻された。
「あっ! ごめんなさい!!」
興奮しすぎてつい腕が当たってしまったらしい。慌てて謝る女の子に、日向は苦笑いで返した。
「いや、全然。気にしないで」
少し年下、高校生くらいだろうか? 先ほどから楽しくてたまらないという様子で、リュウセイの名前を必死で叫びながら、届けとばかりに全力でペンライトを振っている。可愛らしい女の子だった。純粋で、一生懸命で、その姿は見ていて微笑ましい。
「……すごく、カッコいいね、リュウセイくん」
幕間に日向がぽつりと呟けば、女の子は顔をぱっと明るくして日向の腕を掴んだ。その瞳はキラキラと輝いている。
「でしょ!? 絶対一番カッコいいもん! リュウセイ、ダンスも歌もめちゃくちゃ上手いし。けど凄く努力してるの!! ファンのことも大切にしてくれる。嫌なことがあっても、いつもリュウセイに元気貰えて……だから私、今日凄く楽しみにしてたの!!」
弾丸のようにリュウセイへの想いを語る女の子。その熱量に押されつつも、日向はリュウセイの影響力に驚いていた。誰かの心の糧になり、誰かの明日を支える存在。流星が夢見た「アイドル」に、彼は確かに成りきっているのだ。隣の子にとって、リュウセイは人生に彩りを与えてくれるような存在なのかもしれない。
ステージの上のリュウセイは、そんな無数の思いを一身に受け止め、満面の笑みで踊り続けていた。彼がファンサービスで投げキッスを飛ばせば、会場からは黄色い悲鳴が上がり、誰もが彼の視線を求めて手を伸ばしている。
誰一人見逃さないような視線の動き。計算された表情。完璧なパフォーマンスは、見る者全てを夢中にさせた。その光景はあまりにも眩しく、日向は思わず目を細めた。
銀色の雨が降ってきたのは、ライブが最高潮に達した時だった。
曲がサビに入り、パンッ、という破裂音とともに、天井から無数の銀テープが一斉に放たれる。照明を反射してキラキラと舞い落ちるそれは、日向には自分と彼を隔てる分厚いカーテンのように見えた。
観客達は皆そのテープを掴もうと躍起になって手を伸ばしていた。女の子もキャアキャア言いながら腕を伸ばし、頭上から降ってくるテープを掴もうとしている。
日向は指一本動かせず、その銀の雨を見つめていた。無邪気に伸びるあの腕の数だけ、彼を必要とする人間がいるのだと、その光景を見て無理やり理解させられる。
そんな日向の目の前に、突然、一枚の銀テープがふわりと落ちてきた。思わず掴んだそれは冷たく、手の中でひどく軽い。これが何の価値を持つのか、今の日向には全く分からなかった。リュウセイの甘い歌声が耳朶を打つ。
銀テープには、Meteoroidsのメンバーのサインが印字されているようだった。日向が手に入れたそれには、リュウセイのサインも書かれていた。ファンに向けた言葉と一緒に。日向は小さく苦笑する。
──もう、住む世界が違うのだ。
この先もずっと一緒に、などと簡単に言える関係ではないと、思い知らされてしまった。
ふと、隣を見れば、先ほどまで笑顔ではしゃいでいたはずの女の子が、少し俯きながら唇を噛み締めていた。その肩は僅かに震えており、目尻には涙が滲んでいる。どうやら、銀テープが取れなかったらしい。
日向は、自分が手にしていた銀テープを見た。
そこにはリュウセイのサインと、『愛してるよ』の文字が、しっかりと印刷されていた。これは、日向自身ではなく、ここにいる無数の「誰か」へ向けられた愛なのだ。少しクセのある懐かしいその筆跡は、日向がよく知っている流星のものだ。けれど、日向が欲しかった感情は、そこに描かれている形では決してない。それを突きつけられたような気がして、なんとも言えない気持ちになる。
日向はその銀テープをそっと隣の女の子に差し出した。
「え……?」
「君ならきっと大事にしてくれそうだから」
「い……いんですか!? だって、せっかく取れたのに……!」
戸惑う少女の手にテープを滑り込ませると、日向は小さく微笑んだ。彼女は、日向の手をぎゅっと握りながら、笑顔を見せた。
「ありがとう! 大切にする!!」
その笑顔を見て、日向も少しだけ救われたような気がした。
彼女から視線をステージに戻せば、流星と視線が交わったような気がした。それはほんの一瞬だったが、まるでスローモーションのようにゆっくりと時間が流れ、流星の瞳に吸い込まれていく。
全身の血液が沸騰し、息が詰まりそうになる。彼との距離がどれだけ離れていても、たった一瞬視線が合っただけで、こうも簡単に心を掻き乱されるなんて。自分自身の浅ましさに辟易した。
***
「あの、お兄さん。これ思い出になるからやっぱり返します!」
アンコールが終わると同時にスタッフの所へ駆けて行った隣の席の子が、終演後、何かを持って戻ってきた。キョトンとした顔で女の子を見つめていると、彼女は小さな袋を差し出してきた。中にはさっき日向があげた銀テープがきちんと収められている。
「私の分はさっきスタッフさんからいただけたので」
「あぁ、そういうこともあるんだ」
「はい。だからこれはお兄さんに返さないとと思って」
日向は差し出された袋を受け取る。リュウセイのサインは変わらずそこにあった。さっきまでの軽さとは異なり、妙にずっしりと感じる気がした。
「それに、お兄さんもきっと大切にしてくれると思うから」
「……どうして?」
「だって、お兄さんもリュウセイ推しでしょう? ライブが始まった瞬間から、ずっとリュウセイのことを見ていたもの」
日向はハッとした。無意識に、視線は流星ばかりを追っていたのだろうか。そんなに分かりやすかったのか。
じゃあ! と勢いよくお辞儀をして笑顔で帰っていく女の子に日向は小さく手を振って見送る。その背中を見つめながら、軽くため息を吐いた。