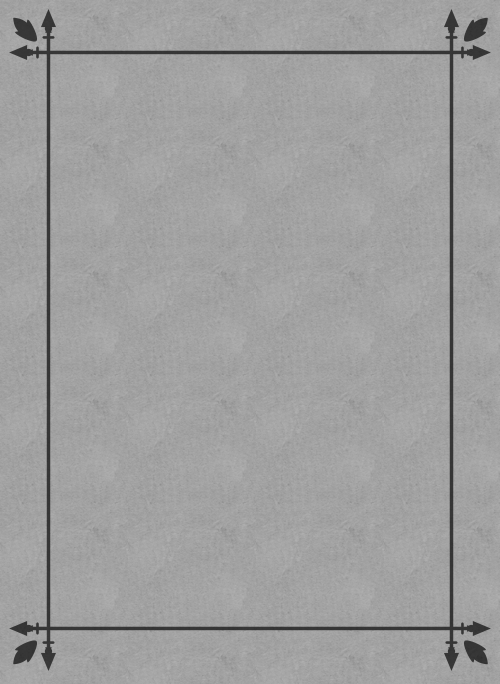入学式って、もっとこう――人生の新章が始まるぞ!みたいなイベントだと思ってた。
体育館の床はきちんとワックスで光ってて、壇上の校長先生はマイク越しに「可能性」という単語を二十回くらい言って、親はスマホで写真を撮って、同級生はすでにクラスのLINEを作っていた。
で、当の俺――青山朔(あおやま・さく)、高校一年生はというと。
(……可能性って、どこに売ってんだろ)
中学の卒業文集に「将来の夢」を書けって言われたときも、俺は最後まで空欄だった。
なりたい職業もない。熱中できるものも、夢中になれるものも、今のところ見当たらない。
だから、入学式の「これからだ!」って空気が、俺には眩しすぎた。
制服の襟がまだ硬い。ネクタイの結び目も、鏡の前で練習したほどきれいじゃない。
桜の花びらが、練馬の風に吹かれて歩道を滑っていくのを見ながら、俺は校門を出た。
練馬。住み慣れた街。
西武線の高架、商店街の八百屋の呼び込み、交差点の信号待ち。全部いつも通りで、だからこそ胸の奥がじわっと冷えた。
(このまま、高校も「いつも通り」で終わるのかな)
(部活?友だち?恋?……なんか、どれも他人事)
入学式の帰り道なのに、なぜか卒業式みたいな気分だ。
俺の青春、まだ始まってもいないのに、もう「平凡でした」って締めのナレーションが流れそう。
家へ向かういつもの道は、今日は使わない。
新しい通学路。入学式の日だけの、ちょっとした冒険。
俺は目白通りの一本裏を曲がって、住宅街のほうへ足を向けた。
春の午後の住宅街は、妙に明るい。
玄関先の花壇のパンジー、干したばかりの洗濯物の匂い、犬の散歩の足音。
平和。平和すぎて、逆に怖い。
(平和って、退屈と紙一重だな……)
そう思った瞬間――
カン、という乾いた金属音が、路地の奥からした。
カン。カン。
何かを叩く音。硬いものがぶつかる音。
俺は思わず足を止めて、音のするほうを見た。
古い三階建てのビルの一階。ガラス戸の向こうに、白い床と、細長い影がいくつも揺れている。
ビルの外壁には昔のテナントの跡が残っていて、「学習塾」とか「クリーニング」とか、消えかけた文字の上に新しい看板が貼り付けられていた。
『NERIMA FENCING CLUB』
「……フェンシング?」
テレビでしか見たことないやつ。
白い服着て、顔に網みたいなマスクして、ピッ、って刺したら光るやつ。たぶん。
(ルール、知らない。剣道みたいに「面!」とか言うの?)
(いや、言わないか。フェンシングで「面!」は無理がある)
(ていうかフェンシングって、刺すの?突くの?どっちも怖いんだけど)
ガラス越しに覗こうとすると、室内の照明が金属に反射してきらっと光った。
その瞬間だけ、俺の中の「退屈」が、針でつつかれたみたいに動いた。
――興味。
俺がその言葉を自分に認める前に。
ガチャ、と扉が開いて、熱気が外へ漏れた。
同時に、汗と柔軟剤とゴムマットの匂いが混ざった空気が顔に当たる。
「おっ、見学?」
出てきたのは、同い年くらいの男子だった。
髪は短めで、目がやけに真っすぐ。ジャージの袖を肘までまくって、手には細長い剣――いや、剣っていうより、金属の棒を持ってる。
その棒の先端が、俺の心臓のあたりを指した。
「……え、俺?」
「そう。君。今、うちの看板見たでしょ」
「いや、見たっていうか、音がして……」
「音に釣られて来た。つまり、興味ある」
結論が早い。
俺が口を開く前に、彼はもう満面の笑みを作っていた。
「俺、赤羽慎太郎(あかばね・しんたろう)。今日から高校一年。君は?」
「……青山朔、俺も今日から高校一年」
「よし。同い年。運命。はい、握手」
握手を求められて、反射で手を出してしまった。
手のひらが熱い。汗ばんでるのに、妙に気持ちいい。
(なんだこのテンション。……太陽系の人だ)
「朔っていい名前。新月の朔でしょ。始まりって感じする」
「……始まり、ね」
「始まりだよ。君のフェンシング人生の」
「いや、まだ俺の人生に採用してないんだけど」
「採用しよう。今、ここで」
勝手に採用を決めるなよ……。
「ていうかさ、朔って練馬?」
「練馬。ずっと」
「俺も。あ、でも苗字は赤羽だけど北区じゃないからね。よく言われるんだ。『赤羽って、赤羽駅?』って」
「……言われそう」
「言われる。駅前で『家、北区?』って聞かれて『練馬です』って答えるたびに、俺の心が一回刺さる」
「……そうなんだ」
「でも、フェンシングやってるから耐性ある」
「耐性の使い道、違うだろ」
俺が初めてちゃんとツッコむと、赤羽は嬉しそうに笑った。
なんだよ、ツッコミ歓迎タイプかよ。厄介だな。
「で、朔。入学式帰り?制服きれいだもん」
「そう。帰り……の途中」
「最高の途中だよ。ちょうどいい。今、うち、体験やってる。入って!」
赤羽の手が、俺の背中に軽く触れた。
軽いのに、押しが強い。まるで手のひらが「断る」の選択肢を消してくる。
「いや、でも、俺――」
「大丈夫。フェンシングって、思ってるより怖くない。刺さないから」
「刺さないの?」
「突く」
「そこ、言い換えても怖いんだけど」
「突くのも、先っぽはボタンみたいになってるから。ほら、触ってみ」
赤羽は俺の指先に、金属の先端をちょん、と当てた。
冷たい。軽い。……思ったより、怖くない。
(……あれ。ちょっと、かっこいい)
(いや、かっこよさで人生は変わらない。はず)
(でも今、変わりかけてない?俺の進路)
「一回だけ!一回だけやって、合わなかったら帰っていい。約束」
「約束って、信用していいやつ?」
「俺、赤羽慎太郎。約束は守る男」
「さっき『運命』って言った人の約束、重いな……」
俺が小さくため息をついた瞬間、赤羽は勝利を確信したみたいに親指を立てた。
「よし、決まり!ようこそ練馬フェンシングクラブへ!」
「まだ入ってない!」
「入ってる入ってる。心がもう半分入ってる」
「俺の心、勝手に分割しないで」
「じゃ、残り半分も今から入れよう」
そんなやり取りをしているうちに、俺はビルの中へ押し込まれていた。
中は、思ったより広い。
白いマットの上に、細長いレーンが何本か引かれている。壁には大会のポスター。『東京都ジュニア選手権』。『全国高校総体予選』。
天井の蛍光灯が少しだけ唸っていて、床のゴムマットが足裏に柔らかく沈む。
そして、何より――金属の音が、胸の骨まで響いてくる。
カン!カン!
ぶつかる音が、会話みたいにテンポよく続く。
(……なんだこれ。音だけで、ちょっとワクワクする)
(俺の中に、こんなスイッチ残ってたんだ)
「おーい、慎太郎!新入生、また連れてきたのか!」
奥から声がした。
顔を出したのは、二十代後半くらいの男性。黒いポロシャツに、ホイッスル。目が鋭いのに、口元は笑ってる。
「コーチ!入学式帰りの新星です!」
「新星って勝手に言うな。こんにちは。体験?」
「……はい。たぶん」
「たぶんって何。まあいい。私はコーチの三枝(さえぐさ)。君は?」
「青山朔です」
「朔くんね。制服のままでもいいけど、汗かくよ」
「汗は、たぶん、すでに……」
赤羽に絡まれて、俺の手のひらはもう汗ばんでいる。
「ほら朔、こっち!まずは着替え!」
「え、着替え?」
「これ。体験用ジャージ。サイズ、たぶんいける」
「さっきから『たぶん』多くない?」
「人生はたぶんでできてる。俺たちの未来も、たぶん明るい」
「明るさの根拠が薄い」
赤羽が差し出したのは、青いジャージだった。チーム名のロゴが入ってる。
俺はそれを受け取って、ロッカーのほうへ歩いた。
(……俺、なんで着替えようとしてるんだ)
(入学式の帰り道に、知らないクラブでジャージに着替える高校一年。情報量が多い)
(でも、ちょっとだけ、楽しいって思ってる自分がいるのが一番怖い)
ロッカーの鏡の前で、俺は自分の顔を見た。
いつもと同じ顔。なのに、目が少しだけ、いつもより生きている気がした。
(これが青春ってやつ?いや、まだ。たぶん違う)
(でも、制服よりは似合ってる気がする。ジャージが)
戻ると、赤羽が待ちきれない犬みたいに足踏みしていた。
「朔!準備OK?じゃ、まずは武器紹介!」
「武器って言うな」
「えっとね、フェンシングには三種類あって――フルーレ、エペ、サーブル。うちは主にフルーレ」
「フルーレ……」
「ルール簡単。ここ、胴体だけが有効面。先に突いたほうがポイント。ピコーンって光ったら勝ち」
「ゲームみたいだな」
「そう!しかもヒット判定が機械で出る。言い訳できない」
「言い訳するつもりだったの?」
「する。負けたら『回線が』って言う」
「そんなこと言うの!?」
例えが雑なのに、わかりやすいのが腹立つ。
「で、これがフルーレ。軽いよ。ほら、持ってみ」
「……軽っ」
受け取った瞬間、手首がふわっと浮く感じがした。
金属なのに、重さがない。剣というより、筆みたいだ。
「どう?かっこよくない?」
「……かっこいいかも」
「よし!出た!『かっこいい』!これで君はもう逃げられない!」
「逃げたらどうなるの」
「追いかける」
「ストーカー宣言やめろ」
「剣を持つ者は執念も持つ」
「その台詞、少年漫画の悪役っぽい」
赤羽は「褒めてる?」って顔をした。褒めてない。
すると、レーンの端から、無表情の男子が一人近づいてきた。
俺より背が高くて、髪が少し長い。目が眠そう。ジャージの胸に、赤羽と同じロゴ。
「慎太郎、また勧誘成功?」
「成功っていうか、運命が連れてきた」
「運命って便利だね」
「便利だよ。これ、朔。で、こっちは白石(しらいし)先輩。二年」
「……どうも」
「どうも。初心者?」
「初心者です」
「よかった。慎太郎は初心者にだけ優しいから」
「ちょっと待て先輩!俺は全人類に優しい!」
「全人類に話しかける、の間違い」
「会話は愛だろ!」
白石先輩はため息をついて、俺の剣先をちょい、と指で押した。
「持ち方、力入りすぎ。親指と人差し指で挟んで、他は添える」
「……こうですか」
「そう。剣は軽い。軽いものほど、力むと重くなる」
「……哲学?」
「ただの物理」
なんだ、ここ。思ったより居心地がいい。
「次はマスク。顔、守るやつ。はい」
網目のマスクを被ると、視界が一気に「格子」になる。
世界が細かい四角に区切られたみたいで、ちょっと不思議だ。
(……あ、音が近い)
(カン、っていう音が、さっきより鮮明になってる)
(俺の耳、そんなに性能よかったっけ)
「怖い?」
「ちょっと。でも……変な感じ」
「いい感じってことだね」
「勝手に解釈するな」
赤羽は自分もマスクを被って、俺の前に立った。
彼の目が、網の向こうで笑っている。
「じゃ、立ち方。ここがオンガード。足はこう。前足、軽く。後ろ足、斜め。ほら、真似して」
「……こう?」
「そうそう!いい!朔、飲み込み早い!」
「早いっていうか、必死」
「必死は最高。必死は才能」
「才能の方向性がおかしい」
俺は足を動かしてみる。前へ。後ろへ。
体育の授業でやるダンスのステップとは違う。足裏が床を「擦る」感じ。静かに、でも確実に距離を詰める。
(これ、意外と難しい)
(でも、難しいって、なんか嬉しい。俺、今まで簡単なことしかしてこなかったのかも)
「ほら、進んで、戻って。進んで、戻って。リズム」
「リズム……」
「そう。音楽だと思え。フェンシングはダンスだ」
「ダンスで人を突くの、怖い」
「突かないダンスもあるけど、うちは突く」
赤羽の言葉が矛盾だらけなのに、なぜか頭に入ってくる。
俺の身体が、ちょっとずつ「いつも」と違う動きを覚えていく。
赤羽が、剣先を俺の胴に向ける。
「いくよ。突く。――えい」
「うわ」
反射で身を引いた。
赤羽の剣先は、俺のジャージに触れる寸前で止まる。
「今の、避けた。いい」
「いや、怖いから避けただけ」
「怖いを避ける。才能だよ」
「才能って便利な言葉だな」
「便利だよ。運命と同じくらい」
白石先輩が小さく笑った気がした。気のせいかもしれない。
「今度は君。俺の――胸じゃない、胴。胴を狙って」
「胸って言いかけた」
「フェンシングでは胸も胴のうち」
「そういう問題じゃない」
「いいからいけ。青春は胸だ」
俺は剣を構えて、赤羽の正面に立った。
呼吸が浅くなる。指先が冷える。
(……やるだけ。刺さない。突く)
(『刺さない』って思うから怖いんだ。『突く』って言い換えても怖いけど)
「せーの、でいってみ」
「せーの……!」
俺は一歩踏み込んで、剣先を伸ばした。
カン!
赤羽の剣とぶつかって、音が鳴った。
同時に、肩から腕にかけて、ビリッと電気みたいなものが走る。
(……今の音、好きだ)
(心臓が、音に合わせて速くなる)
(退屈って、こうやって壊れるのか)
赤羽が笑う。
「今の、いい!ぶつかったけど、踏み込みがちゃんと前に出た」
「わかんないけど、なんか……」
「なんか?」
「……ちょっと楽しい」
俺が言った瞬間、赤羽は「よっしゃあ!」って叫んだ。
体育館じゃなくてよかった。入学式の校長先生より声がでかい。
「よし、じゃ次は本当にポイント取ろう。ここ、機械に繋ぐ。突いたら光るやつ」
「本当に光るんだ」
「光る。青春みたいに」
「青春、万能すぎ」
俺はコードを腰に付けられて、剣にも線を繋がれて、完全にゲームの主人公みたいになった。
胸の前の装置が、かすかに「ピ…」って鳴っている。
白石先輩が手慣れた動きでコードの接続を確認してくれた。
「これ外れると判定出ない。慎太郎、また回線言い訳するなよ」
「言い訳じゃない、戦略!」
「戦略って言うなら勝て」
「うるさい!」
赤羽は先輩に突っかかって、先輩は涼しい顔。平和だ。だけど退屈じゃない平和。
「じゃ、いくぞ。ルールは簡単。先に当てたほうが勝ち。合図はコーチが『アレ!』って言う」
「アレ?」
「フランス語。たぶん『行け』みたいな意味」
「たぶん?」
「大丈夫、大体で生きてるから」
「俺は大体が苦手なんだが」
三枝コーチがホイッスルを口に咥えた。
「二人とも、プレッ。――アレ!」
ピーッ!
俺の足が勝手に動いた。
前へ。踏み込む。剣先が伸びる。
赤羽も同時に動く。速い。けど、怖くない。
さっきまでの「知らない世界」が、今は「入っていい世界」に変わっている。
(……あ、俺、今――)
(退屈じゃない)
カン!
剣がぶつかった。
赤羽の肩が僅かに沈む。隙――なのか。
俺は自分でも驚くくらい自然に、もう一歩踏み込んだ。
ピカッ。
赤。
「え」
「え?」
「今、光った?」
「光った!朔、当てた!初ポイント!」
赤羽がマスクのまま、肩を揺らして笑った。
俺も、なんか笑ってしまう。笑い方を忘れてたみたいに、ぎこちないのに、止まらない。
「当てた……?」
「当てた!君、すごい。入学式帰りに初ポイント。記念日だよ。今日は『朔ポイント記念日』」
「ネーミング、適当すぎる」
「適当って言うな。大事にしろ。人生で初めて、何かが『当たった日』だぞ」
その言葉に、胸の奥が少しだけ痛んだ。
俺の人生、今まで何も当たってこなかったみたいじゃん。
でも、否定できないのが悔しい。
だから、俺は話をそらすみたいに聞いた。
「……赤羽は、なんでフェンシングやってんの」
「え?」
「こんなに楽しそうに。理由あるの?」
「理由?うーん……」
赤羽は少しだけ黙って、マスクを外した。
汗で濡れた前髪を指でかき上げて、笑ったまま言う。
「単純。剣ってかっこいいから」
「それだけ?」
「それだけで十分じゃん」
赤羽の言葉が、胸の奥に刺さる。いや、突く。
俺はまだ、世界に味方されたことなんてないと思ってた。
でも今、ほんの一瞬だけ、俺のほうに光が点いた。
体育館の床はきちんとワックスで光ってて、壇上の校長先生はマイク越しに「可能性」という単語を二十回くらい言って、親はスマホで写真を撮って、同級生はすでにクラスのLINEを作っていた。
で、当の俺――青山朔(あおやま・さく)、高校一年生はというと。
(……可能性って、どこに売ってんだろ)
中学の卒業文集に「将来の夢」を書けって言われたときも、俺は最後まで空欄だった。
なりたい職業もない。熱中できるものも、夢中になれるものも、今のところ見当たらない。
だから、入学式の「これからだ!」って空気が、俺には眩しすぎた。
制服の襟がまだ硬い。ネクタイの結び目も、鏡の前で練習したほどきれいじゃない。
桜の花びらが、練馬の風に吹かれて歩道を滑っていくのを見ながら、俺は校門を出た。
練馬。住み慣れた街。
西武線の高架、商店街の八百屋の呼び込み、交差点の信号待ち。全部いつも通りで、だからこそ胸の奥がじわっと冷えた。
(このまま、高校も「いつも通り」で終わるのかな)
(部活?友だち?恋?……なんか、どれも他人事)
入学式の帰り道なのに、なぜか卒業式みたいな気分だ。
俺の青春、まだ始まってもいないのに、もう「平凡でした」って締めのナレーションが流れそう。
家へ向かういつもの道は、今日は使わない。
新しい通学路。入学式の日だけの、ちょっとした冒険。
俺は目白通りの一本裏を曲がって、住宅街のほうへ足を向けた。
春の午後の住宅街は、妙に明るい。
玄関先の花壇のパンジー、干したばかりの洗濯物の匂い、犬の散歩の足音。
平和。平和すぎて、逆に怖い。
(平和って、退屈と紙一重だな……)
そう思った瞬間――
カン、という乾いた金属音が、路地の奥からした。
カン。カン。
何かを叩く音。硬いものがぶつかる音。
俺は思わず足を止めて、音のするほうを見た。
古い三階建てのビルの一階。ガラス戸の向こうに、白い床と、細長い影がいくつも揺れている。
ビルの外壁には昔のテナントの跡が残っていて、「学習塾」とか「クリーニング」とか、消えかけた文字の上に新しい看板が貼り付けられていた。
『NERIMA FENCING CLUB』
「……フェンシング?」
テレビでしか見たことないやつ。
白い服着て、顔に網みたいなマスクして、ピッ、って刺したら光るやつ。たぶん。
(ルール、知らない。剣道みたいに「面!」とか言うの?)
(いや、言わないか。フェンシングで「面!」は無理がある)
(ていうかフェンシングって、刺すの?突くの?どっちも怖いんだけど)
ガラス越しに覗こうとすると、室内の照明が金属に反射してきらっと光った。
その瞬間だけ、俺の中の「退屈」が、針でつつかれたみたいに動いた。
――興味。
俺がその言葉を自分に認める前に。
ガチャ、と扉が開いて、熱気が外へ漏れた。
同時に、汗と柔軟剤とゴムマットの匂いが混ざった空気が顔に当たる。
「おっ、見学?」
出てきたのは、同い年くらいの男子だった。
髪は短めで、目がやけに真っすぐ。ジャージの袖を肘までまくって、手には細長い剣――いや、剣っていうより、金属の棒を持ってる。
その棒の先端が、俺の心臓のあたりを指した。
「……え、俺?」
「そう。君。今、うちの看板見たでしょ」
「いや、見たっていうか、音がして……」
「音に釣られて来た。つまり、興味ある」
結論が早い。
俺が口を開く前に、彼はもう満面の笑みを作っていた。
「俺、赤羽慎太郎(あかばね・しんたろう)。今日から高校一年。君は?」
「……青山朔、俺も今日から高校一年」
「よし。同い年。運命。はい、握手」
握手を求められて、反射で手を出してしまった。
手のひらが熱い。汗ばんでるのに、妙に気持ちいい。
(なんだこのテンション。……太陽系の人だ)
「朔っていい名前。新月の朔でしょ。始まりって感じする」
「……始まり、ね」
「始まりだよ。君のフェンシング人生の」
「いや、まだ俺の人生に採用してないんだけど」
「採用しよう。今、ここで」
勝手に採用を決めるなよ……。
「ていうかさ、朔って練馬?」
「練馬。ずっと」
「俺も。あ、でも苗字は赤羽だけど北区じゃないからね。よく言われるんだ。『赤羽って、赤羽駅?』って」
「……言われそう」
「言われる。駅前で『家、北区?』って聞かれて『練馬です』って答えるたびに、俺の心が一回刺さる」
「……そうなんだ」
「でも、フェンシングやってるから耐性ある」
「耐性の使い道、違うだろ」
俺が初めてちゃんとツッコむと、赤羽は嬉しそうに笑った。
なんだよ、ツッコミ歓迎タイプかよ。厄介だな。
「で、朔。入学式帰り?制服きれいだもん」
「そう。帰り……の途中」
「最高の途中だよ。ちょうどいい。今、うち、体験やってる。入って!」
赤羽の手が、俺の背中に軽く触れた。
軽いのに、押しが強い。まるで手のひらが「断る」の選択肢を消してくる。
「いや、でも、俺――」
「大丈夫。フェンシングって、思ってるより怖くない。刺さないから」
「刺さないの?」
「突く」
「そこ、言い換えても怖いんだけど」
「突くのも、先っぽはボタンみたいになってるから。ほら、触ってみ」
赤羽は俺の指先に、金属の先端をちょん、と当てた。
冷たい。軽い。……思ったより、怖くない。
(……あれ。ちょっと、かっこいい)
(いや、かっこよさで人生は変わらない。はず)
(でも今、変わりかけてない?俺の進路)
「一回だけ!一回だけやって、合わなかったら帰っていい。約束」
「約束って、信用していいやつ?」
「俺、赤羽慎太郎。約束は守る男」
「さっき『運命』って言った人の約束、重いな……」
俺が小さくため息をついた瞬間、赤羽は勝利を確信したみたいに親指を立てた。
「よし、決まり!ようこそ練馬フェンシングクラブへ!」
「まだ入ってない!」
「入ってる入ってる。心がもう半分入ってる」
「俺の心、勝手に分割しないで」
「じゃ、残り半分も今から入れよう」
そんなやり取りをしているうちに、俺はビルの中へ押し込まれていた。
中は、思ったより広い。
白いマットの上に、細長いレーンが何本か引かれている。壁には大会のポスター。『東京都ジュニア選手権』。『全国高校総体予選』。
天井の蛍光灯が少しだけ唸っていて、床のゴムマットが足裏に柔らかく沈む。
そして、何より――金属の音が、胸の骨まで響いてくる。
カン!カン!
ぶつかる音が、会話みたいにテンポよく続く。
(……なんだこれ。音だけで、ちょっとワクワクする)
(俺の中に、こんなスイッチ残ってたんだ)
「おーい、慎太郎!新入生、また連れてきたのか!」
奥から声がした。
顔を出したのは、二十代後半くらいの男性。黒いポロシャツに、ホイッスル。目が鋭いのに、口元は笑ってる。
「コーチ!入学式帰りの新星です!」
「新星って勝手に言うな。こんにちは。体験?」
「……はい。たぶん」
「たぶんって何。まあいい。私はコーチの三枝(さえぐさ)。君は?」
「青山朔です」
「朔くんね。制服のままでもいいけど、汗かくよ」
「汗は、たぶん、すでに……」
赤羽に絡まれて、俺の手のひらはもう汗ばんでいる。
「ほら朔、こっち!まずは着替え!」
「え、着替え?」
「これ。体験用ジャージ。サイズ、たぶんいける」
「さっきから『たぶん』多くない?」
「人生はたぶんでできてる。俺たちの未来も、たぶん明るい」
「明るさの根拠が薄い」
赤羽が差し出したのは、青いジャージだった。チーム名のロゴが入ってる。
俺はそれを受け取って、ロッカーのほうへ歩いた。
(……俺、なんで着替えようとしてるんだ)
(入学式の帰り道に、知らないクラブでジャージに着替える高校一年。情報量が多い)
(でも、ちょっとだけ、楽しいって思ってる自分がいるのが一番怖い)
ロッカーの鏡の前で、俺は自分の顔を見た。
いつもと同じ顔。なのに、目が少しだけ、いつもより生きている気がした。
(これが青春ってやつ?いや、まだ。たぶん違う)
(でも、制服よりは似合ってる気がする。ジャージが)
戻ると、赤羽が待ちきれない犬みたいに足踏みしていた。
「朔!準備OK?じゃ、まずは武器紹介!」
「武器って言うな」
「えっとね、フェンシングには三種類あって――フルーレ、エペ、サーブル。うちは主にフルーレ」
「フルーレ……」
「ルール簡単。ここ、胴体だけが有効面。先に突いたほうがポイント。ピコーンって光ったら勝ち」
「ゲームみたいだな」
「そう!しかもヒット判定が機械で出る。言い訳できない」
「言い訳するつもりだったの?」
「する。負けたら『回線が』って言う」
「そんなこと言うの!?」
例えが雑なのに、わかりやすいのが腹立つ。
「で、これがフルーレ。軽いよ。ほら、持ってみ」
「……軽っ」
受け取った瞬間、手首がふわっと浮く感じがした。
金属なのに、重さがない。剣というより、筆みたいだ。
「どう?かっこよくない?」
「……かっこいいかも」
「よし!出た!『かっこいい』!これで君はもう逃げられない!」
「逃げたらどうなるの」
「追いかける」
「ストーカー宣言やめろ」
「剣を持つ者は執念も持つ」
「その台詞、少年漫画の悪役っぽい」
赤羽は「褒めてる?」って顔をした。褒めてない。
すると、レーンの端から、無表情の男子が一人近づいてきた。
俺より背が高くて、髪が少し長い。目が眠そう。ジャージの胸に、赤羽と同じロゴ。
「慎太郎、また勧誘成功?」
「成功っていうか、運命が連れてきた」
「運命って便利だね」
「便利だよ。これ、朔。で、こっちは白石(しらいし)先輩。二年」
「……どうも」
「どうも。初心者?」
「初心者です」
「よかった。慎太郎は初心者にだけ優しいから」
「ちょっと待て先輩!俺は全人類に優しい!」
「全人類に話しかける、の間違い」
「会話は愛だろ!」
白石先輩はため息をついて、俺の剣先をちょい、と指で押した。
「持ち方、力入りすぎ。親指と人差し指で挟んで、他は添える」
「……こうですか」
「そう。剣は軽い。軽いものほど、力むと重くなる」
「……哲学?」
「ただの物理」
なんだ、ここ。思ったより居心地がいい。
「次はマスク。顔、守るやつ。はい」
網目のマスクを被ると、視界が一気に「格子」になる。
世界が細かい四角に区切られたみたいで、ちょっと不思議だ。
(……あ、音が近い)
(カン、っていう音が、さっきより鮮明になってる)
(俺の耳、そんなに性能よかったっけ)
「怖い?」
「ちょっと。でも……変な感じ」
「いい感じってことだね」
「勝手に解釈するな」
赤羽は自分もマスクを被って、俺の前に立った。
彼の目が、網の向こうで笑っている。
「じゃ、立ち方。ここがオンガード。足はこう。前足、軽く。後ろ足、斜め。ほら、真似して」
「……こう?」
「そうそう!いい!朔、飲み込み早い!」
「早いっていうか、必死」
「必死は最高。必死は才能」
「才能の方向性がおかしい」
俺は足を動かしてみる。前へ。後ろへ。
体育の授業でやるダンスのステップとは違う。足裏が床を「擦る」感じ。静かに、でも確実に距離を詰める。
(これ、意外と難しい)
(でも、難しいって、なんか嬉しい。俺、今まで簡単なことしかしてこなかったのかも)
「ほら、進んで、戻って。進んで、戻って。リズム」
「リズム……」
「そう。音楽だと思え。フェンシングはダンスだ」
「ダンスで人を突くの、怖い」
「突かないダンスもあるけど、うちは突く」
赤羽の言葉が矛盾だらけなのに、なぜか頭に入ってくる。
俺の身体が、ちょっとずつ「いつも」と違う動きを覚えていく。
赤羽が、剣先を俺の胴に向ける。
「いくよ。突く。――えい」
「うわ」
反射で身を引いた。
赤羽の剣先は、俺のジャージに触れる寸前で止まる。
「今の、避けた。いい」
「いや、怖いから避けただけ」
「怖いを避ける。才能だよ」
「才能って便利な言葉だな」
「便利だよ。運命と同じくらい」
白石先輩が小さく笑った気がした。気のせいかもしれない。
「今度は君。俺の――胸じゃない、胴。胴を狙って」
「胸って言いかけた」
「フェンシングでは胸も胴のうち」
「そういう問題じゃない」
「いいからいけ。青春は胸だ」
俺は剣を構えて、赤羽の正面に立った。
呼吸が浅くなる。指先が冷える。
(……やるだけ。刺さない。突く)
(『刺さない』って思うから怖いんだ。『突く』って言い換えても怖いけど)
「せーの、でいってみ」
「せーの……!」
俺は一歩踏み込んで、剣先を伸ばした。
カン!
赤羽の剣とぶつかって、音が鳴った。
同時に、肩から腕にかけて、ビリッと電気みたいなものが走る。
(……今の音、好きだ)
(心臓が、音に合わせて速くなる)
(退屈って、こうやって壊れるのか)
赤羽が笑う。
「今の、いい!ぶつかったけど、踏み込みがちゃんと前に出た」
「わかんないけど、なんか……」
「なんか?」
「……ちょっと楽しい」
俺が言った瞬間、赤羽は「よっしゃあ!」って叫んだ。
体育館じゃなくてよかった。入学式の校長先生より声がでかい。
「よし、じゃ次は本当にポイント取ろう。ここ、機械に繋ぐ。突いたら光るやつ」
「本当に光るんだ」
「光る。青春みたいに」
「青春、万能すぎ」
俺はコードを腰に付けられて、剣にも線を繋がれて、完全にゲームの主人公みたいになった。
胸の前の装置が、かすかに「ピ…」って鳴っている。
白石先輩が手慣れた動きでコードの接続を確認してくれた。
「これ外れると判定出ない。慎太郎、また回線言い訳するなよ」
「言い訳じゃない、戦略!」
「戦略って言うなら勝て」
「うるさい!」
赤羽は先輩に突っかかって、先輩は涼しい顔。平和だ。だけど退屈じゃない平和。
「じゃ、いくぞ。ルールは簡単。先に当てたほうが勝ち。合図はコーチが『アレ!』って言う」
「アレ?」
「フランス語。たぶん『行け』みたいな意味」
「たぶん?」
「大丈夫、大体で生きてるから」
「俺は大体が苦手なんだが」
三枝コーチがホイッスルを口に咥えた。
「二人とも、プレッ。――アレ!」
ピーッ!
俺の足が勝手に動いた。
前へ。踏み込む。剣先が伸びる。
赤羽も同時に動く。速い。けど、怖くない。
さっきまでの「知らない世界」が、今は「入っていい世界」に変わっている。
(……あ、俺、今――)
(退屈じゃない)
カン!
剣がぶつかった。
赤羽の肩が僅かに沈む。隙――なのか。
俺は自分でも驚くくらい自然に、もう一歩踏み込んだ。
ピカッ。
赤。
「え」
「え?」
「今、光った?」
「光った!朔、当てた!初ポイント!」
赤羽がマスクのまま、肩を揺らして笑った。
俺も、なんか笑ってしまう。笑い方を忘れてたみたいに、ぎこちないのに、止まらない。
「当てた……?」
「当てた!君、すごい。入学式帰りに初ポイント。記念日だよ。今日は『朔ポイント記念日』」
「ネーミング、適当すぎる」
「適当って言うな。大事にしろ。人生で初めて、何かが『当たった日』だぞ」
その言葉に、胸の奥が少しだけ痛んだ。
俺の人生、今まで何も当たってこなかったみたいじゃん。
でも、否定できないのが悔しい。
だから、俺は話をそらすみたいに聞いた。
「……赤羽は、なんでフェンシングやってんの」
「え?」
「こんなに楽しそうに。理由あるの?」
「理由?うーん……」
赤羽は少しだけ黙って、マスクを外した。
汗で濡れた前髪を指でかき上げて、笑ったまま言う。
「単純。剣ってかっこいいから」
「それだけ?」
「それだけで十分じゃん」
赤羽の言葉が、胸の奥に刺さる。いや、突く。
俺はまだ、世界に味方されたことなんてないと思ってた。
でも今、ほんの一瞬だけ、俺のほうに光が点いた。