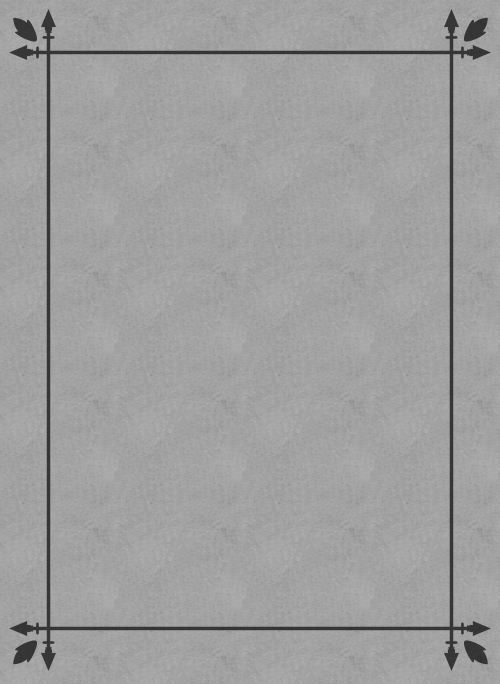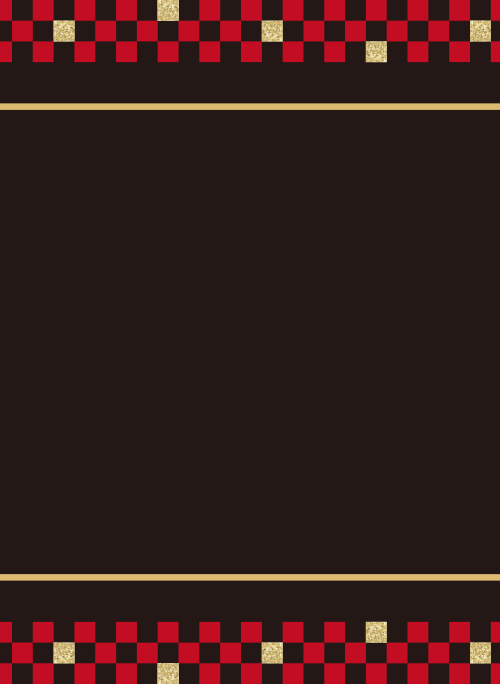「神様の言うとおりにしました」
――その声は、取調室の小さなテレビから流れてきた。音量は絞られていて、言葉だけが、妙に鮮明だった。
録画を再生しているのだと分かっているのに、あたかも今ここで誰かが言ったみたいに、空気が震える。
私は椅子の背に体を押しつけたまま、うまく息ができなかった。
蛍光灯の白さが、肌の色を奪っていく。机の角がやけに尖って見える。床のビニールの匂いが、現実感だけを増幅させる。
正面にいる刑事は、書類を一枚めくった。
目線は優しくもなく、冷たくもない。
「葉山澪(はやま・みお)さん。十七歳。……この「神様の声」ってアカウント、知ってるね」
私は頷けなかった。頷いたら、全部が私のせいになる気がした。
でも否定したところで、画面の中の神様は消えない。
刑事がスマホを机の上に置く。画面には、私たちが何度も見た投稿のスクリーンショットが表示されていた。
白い面のアイコン。匿名。やけに整った文体。――そして、見慣れた言い回し。
『神様は言う――』
喉の奥が、ぎゅっと縮む。
私が整えた神様の言葉に、似すぎていた。
「……知ってます」
声が、変なところで裏返った。
「でも、私が……投稿したわけじゃありません」
「投稿したかどうか、今は置いておこう」
刑事は淡々と言った。
「質問に答えて。君たちは6人グループだね。篠原新、早川慧、加賀陸、桐谷咲、望月杏。――全員、同じアカウントに関わっている」
全員という単語が、重く落ちた。
机の上に一つずつ石を置かれるみたいに、逃げ道が減っていく。
私は目を伏せた。
頭の中に、6人の顔が順番に浮かぶ。今日の顔だ。いつもの顔じゃない。
篠原新(しのはら・しん)。
無口で、目だけがよく動く子。誰より見ているのに、誰にも見られたくない子。
早川慧(はやかわ・けい)。
正しいで自分を守る子。守れると思っているうちは。
加賀陸(かが・りく)。
「俺、詳しいから」で便利に使われてきた子。
桐谷咲(きりたに・さき)。
取調室に呼ばれる直前まで、髪を整えていた。泣きそうな目を、怒っている目に変えるのが上手い子。
望月杏(もちづき・あん)。
人の痛みに反応しすぎる子。だから、壊れるのが一番早い。
そして私。葉山澪。
空気を壊さない係。いちばん無難な言葉を選ぶ係。
――神様の口。
「6人とも、同じことを言ってる」
刑事が言う。
「自分は言ってない」
その言葉に、私は反射で頷きそうになった。
同じことを言う、という事実が、今の私には救いみたいに聞こえたから。
でも、救いのはずの一致が、同時に怖い。6人が口を揃えるのは、いつも悪ノリのときだった。
「本当に?」
刑事が聞く。
「……本当に」
私は言った。
「私たちは、神様の言葉を作ったかもしれないけど、あの事件の……あの人の言葉を、言わせてなんかいません」
事件という言葉を、口に出した瞬間、胸の中に冷たい水が落ちた。
思い出そうとすると、映像が途切れる。
ニュースの画面。人混み。悲鳴。意味のないサイレン。
そして、例の供述。
――「神様の言うとおりにしました」
刑事は私の表情の変化を見逃さなかった。
「君は、作ったと言ったね。神様の言葉を」
私は唇を噛んだ。言葉選びを間違えた。
でも、もう引っ込められない。取調室は、訂正が許されない場所だ。訂正は、嘘に聞こえる。
「遊びでした」
私は言った。
「最初は……本当に、遊びだったんです」
「遊びで、人が動く」
刑事は書類に目を落としたまま言った。
「遊びで、金が動く。遊びで、集団ができる。――そして、遊びで、人が壊れる」
私は息を吸って、吐いた。
その呼吸が普通であることが、逆に怖かった。こんな場所で、普通に呼吸できる私は、どこか壊れているのかもしれない。
「他の子たちも、同じことを言ってる?」
私は聞いてしまった。
自分でも分かる。聞かなくていい質問だ。
でも、確認しないと、ここで私だけが神様にされそうだった。
刑事は頷いた。
「篠原は『僕は煽っただけ。決めたのは投票だ』と言っている。加賀は『俺は仕組み作っただけ。内容は知らない』。早川は『止めた。反対した』。望月は『相談を受けただけ。救いたかった』。桐谷は……」
刑事が一瞬だけ言葉を止めた。
その間が、いやに長く感じた。
「桐谷は、『私は見ていただけ』と言っている」
見ていただけ。
――神の目みたいな言い方だ、と私は思ってしまった。
そして、そう思える自分が嫌だった。まだ役割に逃げている。
取調室の壁の向こうから、誰かの声が聞こえた。
薄い壁を通すと、声は中身より温度だけが伝わってくる。
「だから!僕は言ってないって言ってるだろ!」
篠原の声だ。
「……新」
私は喉の奥で名前を転がした。
声に出したら、泣きそうだった。
刑事は眉一つ動かさずに、机の上のペンを回した。
「葉山さん。君は投稿係だね」
「……誰がそんなこと」
私は反射で言いかけて、言葉を飲んだ。
否定しても無駄だ。
私のスマホに残っている下書き。表現の癖。句読点の打ち方。
それらは、私がいくら否定しても、私のものとして出てくる。
「……はい」
私は小さく答えた。
「私が……文章を整えて、投稿してました。最初は」
「最初は?」
「途中から、予約投稿とか……自動で落ちるようにして」
言いながら、背中が冷えた。
自分の口で自動と言った瞬間、私は気づいてしまう。
言ってないを可能にしたのは、自動化だ。
刑事は頷いた。
「加賀も、同じことを言った。『効率化した』と。君たちは、それぞれ言い方が違うだけで、同じ方向を見ている」
同じ方向。
私たちが一番、得意だったやつだ。
誰かが怖いことを言っても、誰かが笑ってしまえば、みんなの方向になる。
そして、みんなの方向になった瞬間、誰も止められなくなる。
「……ねえ」
私は思わず、刑事に聞いてしまった。
「あの人は……本当に、そう言ったんですか」
「あの人?」
刑事は確認するように言った。
「供述した人です。『神様の言うとおりにしました』って」
刑事は、テレビを一度だけ見た。
さっきの再生は止まっていて、画面には静止した顔が映っている。
目が合う。画面越しなのに、目が合った気がした。
「言った」
刑事が言う。
「繰り返し。しかも、穏やかに。……自分の意思じゃない、と信じている顔で」
私は胃のあたりが、ひゅっと冷えた。
自分の意思じゃない、と信じている顔。
それは、私たちが神様ごっこをしていたとき、時々見せた顔に似ていた。
「神様が言ったから」
「神様のせい」
「設定どおり」
あの言葉たちを、誰より何度も書いたのは――私だ。
「……私たちが、言わせたんですか」
声が震える。
ここまで来ると、問いが自分に刺さって、抜けない。
刑事は答えなかった。
代わりに、扉がノックされる。低い声がして、若い警察官が顔を出した。
「真鍋さん、保護者が到着してます」
取調室の外に出ると、廊下の空気が冷たかった。
壁沿いに、椅子が並んでいる。その端に、望月杏が座っていた。膝の上で手を握り潰している。
私を見るなり、杏は泣きそうな顔で笑った。
「澪……ごめん……」
謝る理由がないのに、謝る声だった。
「杏は悪くない」
私は言った。
言った瞬間、矛盾に気づく。
悪くない、って言葉は、便利だ。便利すぎる。
だからこそ、私たちはここにいる。
反対側の壁にも椅子があり、そこに早川慧がいた。
背筋を伸ばしている。姿勢だけは正しい。
でも、目の焦点がずれていた。
「澪」
慧が呼ぶ。声がやけに小さい。
「……お前、何言った」
「まだ何も……」
私は言いかけて、止めた。
何もは嘘だ。
慧は唇を引き結ぶ。
「俺は、止めたって言った」
その言い方に、私は一瞬だけ苛立った。
止めた、と言える立場があるのが、羨ましかったから。
「止めたなら、止められたでしょ」
口から出た言葉が、自分でも冷たくて驚いた。
慧の目が揺れた。
「……止められなかった」
その一言が、妙に正直で、私は何も言えなくなった。
加賀陸は廊下の先で、壁にもたれて立っていた。
両手が空っぽなのに、指先だけが忙しなく動いている。いつもの癖だ。
スマホがないと、人は自分の手を持て余すらしい。
「澪、聞かれた?」
加賀が早口で言う。
「ログとかさ、IPとかさ、なんか言われた?」
「……それ、今する話?」
私は言った。
「するだろ!する話だろ!」
加賀は笑いそうな顔で、でも笑えなくて歯を見せた。
「だってさ、俺ら、言ってねえんだぜ?言ってないのに、こうなってんだぜ?それってさ、……仕組みが、仕組みが――」
言葉が詰まって、加賀は黙った。
仕組みが、と言いかけたその先を、彼自身が怖がっている。
廊下の反対側、警察官に挟まれるようにして歩いてくるのが、桐谷咲だった。
表情がない。
いや、表情がないのではない。表情を見せない顔だ。
その後ろから、篠原新が来た。
さっきまで怒鳴っていたのが嘘みたいに、肩をすぼめている。
私と目が合った瞬間、新は一瞬だけ笑った。
笑うしかないときの笑いだ。
「なあ、澪」
新が言った。声が、ひどく甘ったるい。
「大丈夫。僕たち、言ってないもん。な?」
な?
その一言が、昔なら合図だった。
ここで同じ方向を見る、という合図。
私は答えられなかった。
杏が、新を見て小さく首を振る。
「……新、やめて。今、大丈夫って言うの、やめて」
新の笑いが消える。
「は?じゃあ何言えばいい?泣けばいいの?」
新は言い返す。でも、いつもの強さがない。強く見せるための声が、空回りしている。
咲がぽつりと言った。
「泣いても、ログは消えない」
全員の空気が止まった。
咲の声は小さかったのに、廊下全体に響いた気がした。
「……ログって何」
杏が震える声で聞いた。
「証拠」
咲が言う。
「私たちの言ったこと、押したこと、見たこと、保存したこと。全部」
「押した?」
慧が眉をひそめた。
「俺、押してない。外部投票にしてから、俺は――」
「押してない、って言えるのは」
咲が慧を見た。
「自分の手を信じてるから」
慧が言葉を失う。
私は、背筋が冷えた。
私たちの中で、信じてるという単語が、いちばん危ない。
加賀が咲に詰め寄った。
「おい、咲。お前、なんか知ってんのかよ。管理者とか、なんか変な設定とか――」
咲は視線を逸らさない。
「知ってる。……でも、知らない」
「どっちだよ!」
加賀が声を荒げる。
咲は、淡々と続けた。
「私は、見てただけ。何が起こるか。どこまで行くか。――行った先で、誰が『神様のせい』って言うか」
杏が口元を押さえた。
新の顔から血の気が引く。
慧が唇を噛む。
加賀が言葉を探して、見つけられない。
私の胸の奥で、何かが小さく笑った気がした。笑ってはいけないのに、笑ってしまうあの感じ。
意味が揃った瞬間の、気持ち悪い快感。
――私たちは、見たかったのかもしれない。
誰かが本当に、「神様の言うとおり」と言ってしまう瞬間を。
「……違う」
私は言った。
誰に言ったのか分からない。自分に言ったのかもしれない。
「違う。私たちは、そんなつもりじゃ……」
新が私の言葉にすがるように頷いた。
「そう、そうだよ。澪が言うならそう。僕たち、そんなつもりじゃなかった。ほら、慧も、陸も、杏も、咲も――」
ほら。
新がまた、合図を出す。
合図に乗れば、私たちはいつもの6人に戻れる。
戻ってしまえば、責任はまた薄まる。
その瞬間、廊下の奥から、さっきの刑事――真鍋刑事が歩いてきた。
足音が、妙に規則正しい。
規則正しさは、感情を削る。
真鍋刑事は、6人を一列に見た。
私たちが、いつもの屋上の円陣みたいに固まっているのを、観察するように。
「揃ったね」
刑事が言った。
穏やかな声なのに、胸の奥が締まる。
「君たちは全員、『自分は言ってない』と主張している」
刑事の視線が、順番に私たちをなぞる。
新の爪先、慧の背筋、陸の指先、咲の瞳、杏の手、そして私の喉。
「それが本当だとして――」
真鍋刑事は、少しだけ間を置いた。
その間に、私たちの中の誰かが犯人であってほしいという願いが、膨らんでしまう。
犯人が一人なら、終わる。
終わりにできる。
刑事は、願いを丁寧に潰すみたいに言った。
「じゃあ、誰が言わせた?」
――その声は、取調室の小さなテレビから流れてきた。音量は絞られていて、言葉だけが、妙に鮮明だった。
録画を再生しているのだと分かっているのに、あたかも今ここで誰かが言ったみたいに、空気が震える。
私は椅子の背に体を押しつけたまま、うまく息ができなかった。
蛍光灯の白さが、肌の色を奪っていく。机の角がやけに尖って見える。床のビニールの匂いが、現実感だけを増幅させる。
正面にいる刑事は、書類を一枚めくった。
目線は優しくもなく、冷たくもない。
「葉山澪(はやま・みお)さん。十七歳。……この「神様の声」ってアカウント、知ってるね」
私は頷けなかった。頷いたら、全部が私のせいになる気がした。
でも否定したところで、画面の中の神様は消えない。
刑事がスマホを机の上に置く。画面には、私たちが何度も見た投稿のスクリーンショットが表示されていた。
白い面のアイコン。匿名。やけに整った文体。――そして、見慣れた言い回し。
『神様は言う――』
喉の奥が、ぎゅっと縮む。
私が整えた神様の言葉に、似すぎていた。
「……知ってます」
声が、変なところで裏返った。
「でも、私が……投稿したわけじゃありません」
「投稿したかどうか、今は置いておこう」
刑事は淡々と言った。
「質問に答えて。君たちは6人グループだね。篠原新、早川慧、加賀陸、桐谷咲、望月杏。――全員、同じアカウントに関わっている」
全員という単語が、重く落ちた。
机の上に一つずつ石を置かれるみたいに、逃げ道が減っていく。
私は目を伏せた。
頭の中に、6人の顔が順番に浮かぶ。今日の顔だ。いつもの顔じゃない。
篠原新(しのはら・しん)。
無口で、目だけがよく動く子。誰より見ているのに、誰にも見られたくない子。
早川慧(はやかわ・けい)。
正しいで自分を守る子。守れると思っているうちは。
加賀陸(かが・りく)。
「俺、詳しいから」で便利に使われてきた子。
桐谷咲(きりたに・さき)。
取調室に呼ばれる直前まで、髪を整えていた。泣きそうな目を、怒っている目に変えるのが上手い子。
望月杏(もちづき・あん)。
人の痛みに反応しすぎる子。だから、壊れるのが一番早い。
そして私。葉山澪。
空気を壊さない係。いちばん無難な言葉を選ぶ係。
――神様の口。
「6人とも、同じことを言ってる」
刑事が言う。
「自分は言ってない」
その言葉に、私は反射で頷きそうになった。
同じことを言う、という事実が、今の私には救いみたいに聞こえたから。
でも、救いのはずの一致が、同時に怖い。6人が口を揃えるのは、いつも悪ノリのときだった。
「本当に?」
刑事が聞く。
「……本当に」
私は言った。
「私たちは、神様の言葉を作ったかもしれないけど、あの事件の……あの人の言葉を、言わせてなんかいません」
事件という言葉を、口に出した瞬間、胸の中に冷たい水が落ちた。
思い出そうとすると、映像が途切れる。
ニュースの画面。人混み。悲鳴。意味のないサイレン。
そして、例の供述。
――「神様の言うとおりにしました」
刑事は私の表情の変化を見逃さなかった。
「君は、作ったと言ったね。神様の言葉を」
私は唇を噛んだ。言葉選びを間違えた。
でも、もう引っ込められない。取調室は、訂正が許されない場所だ。訂正は、嘘に聞こえる。
「遊びでした」
私は言った。
「最初は……本当に、遊びだったんです」
「遊びで、人が動く」
刑事は書類に目を落としたまま言った。
「遊びで、金が動く。遊びで、集団ができる。――そして、遊びで、人が壊れる」
私は息を吸って、吐いた。
その呼吸が普通であることが、逆に怖かった。こんな場所で、普通に呼吸できる私は、どこか壊れているのかもしれない。
「他の子たちも、同じことを言ってる?」
私は聞いてしまった。
自分でも分かる。聞かなくていい質問だ。
でも、確認しないと、ここで私だけが神様にされそうだった。
刑事は頷いた。
「篠原は『僕は煽っただけ。決めたのは投票だ』と言っている。加賀は『俺は仕組み作っただけ。内容は知らない』。早川は『止めた。反対した』。望月は『相談を受けただけ。救いたかった』。桐谷は……」
刑事が一瞬だけ言葉を止めた。
その間が、いやに長く感じた。
「桐谷は、『私は見ていただけ』と言っている」
見ていただけ。
――神の目みたいな言い方だ、と私は思ってしまった。
そして、そう思える自分が嫌だった。まだ役割に逃げている。
取調室の壁の向こうから、誰かの声が聞こえた。
薄い壁を通すと、声は中身より温度だけが伝わってくる。
「だから!僕は言ってないって言ってるだろ!」
篠原の声だ。
「……新」
私は喉の奥で名前を転がした。
声に出したら、泣きそうだった。
刑事は眉一つ動かさずに、机の上のペンを回した。
「葉山さん。君は投稿係だね」
「……誰がそんなこと」
私は反射で言いかけて、言葉を飲んだ。
否定しても無駄だ。
私のスマホに残っている下書き。表現の癖。句読点の打ち方。
それらは、私がいくら否定しても、私のものとして出てくる。
「……はい」
私は小さく答えた。
「私が……文章を整えて、投稿してました。最初は」
「最初は?」
「途中から、予約投稿とか……自動で落ちるようにして」
言いながら、背中が冷えた。
自分の口で自動と言った瞬間、私は気づいてしまう。
言ってないを可能にしたのは、自動化だ。
刑事は頷いた。
「加賀も、同じことを言った。『効率化した』と。君たちは、それぞれ言い方が違うだけで、同じ方向を見ている」
同じ方向。
私たちが一番、得意だったやつだ。
誰かが怖いことを言っても、誰かが笑ってしまえば、みんなの方向になる。
そして、みんなの方向になった瞬間、誰も止められなくなる。
「……ねえ」
私は思わず、刑事に聞いてしまった。
「あの人は……本当に、そう言ったんですか」
「あの人?」
刑事は確認するように言った。
「供述した人です。『神様の言うとおりにしました』って」
刑事は、テレビを一度だけ見た。
さっきの再生は止まっていて、画面には静止した顔が映っている。
目が合う。画面越しなのに、目が合った気がした。
「言った」
刑事が言う。
「繰り返し。しかも、穏やかに。……自分の意思じゃない、と信じている顔で」
私は胃のあたりが、ひゅっと冷えた。
自分の意思じゃない、と信じている顔。
それは、私たちが神様ごっこをしていたとき、時々見せた顔に似ていた。
「神様が言ったから」
「神様のせい」
「設定どおり」
あの言葉たちを、誰より何度も書いたのは――私だ。
「……私たちが、言わせたんですか」
声が震える。
ここまで来ると、問いが自分に刺さって、抜けない。
刑事は答えなかった。
代わりに、扉がノックされる。低い声がして、若い警察官が顔を出した。
「真鍋さん、保護者が到着してます」
取調室の外に出ると、廊下の空気が冷たかった。
壁沿いに、椅子が並んでいる。その端に、望月杏が座っていた。膝の上で手を握り潰している。
私を見るなり、杏は泣きそうな顔で笑った。
「澪……ごめん……」
謝る理由がないのに、謝る声だった。
「杏は悪くない」
私は言った。
言った瞬間、矛盾に気づく。
悪くない、って言葉は、便利だ。便利すぎる。
だからこそ、私たちはここにいる。
反対側の壁にも椅子があり、そこに早川慧がいた。
背筋を伸ばしている。姿勢だけは正しい。
でも、目の焦点がずれていた。
「澪」
慧が呼ぶ。声がやけに小さい。
「……お前、何言った」
「まだ何も……」
私は言いかけて、止めた。
何もは嘘だ。
慧は唇を引き結ぶ。
「俺は、止めたって言った」
その言い方に、私は一瞬だけ苛立った。
止めた、と言える立場があるのが、羨ましかったから。
「止めたなら、止められたでしょ」
口から出た言葉が、自分でも冷たくて驚いた。
慧の目が揺れた。
「……止められなかった」
その一言が、妙に正直で、私は何も言えなくなった。
加賀陸は廊下の先で、壁にもたれて立っていた。
両手が空っぽなのに、指先だけが忙しなく動いている。いつもの癖だ。
スマホがないと、人は自分の手を持て余すらしい。
「澪、聞かれた?」
加賀が早口で言う。
「ログとかさ、IPとかさ、なんか言われた?」
「……それ、今する話?」
私は言った。
「するだろ!する話だろ!」
加賀は笑いそうな顔で、でも笑えなくて歯を見せた。
「だってさ、俺ら、言ってねえんだぜ?言ってないのに、こうなってんだぜ?それってさ、……仕組みが、仕組みが――」
言葉が詰まって、加賀は黙った。
仕組みが、と言いかけたその先を、彼自身が怖がっている。
廊下の反対側、警察官に挟まれるようにして歩いてくるのが、桐谷咲だった。
表情がない。
いや、表情がないのではない。表情を見せない顔だ。
その後ろから、篠原新が来た。
さっきまで怒鳴っていたのが嘘みたいに、肩をすぼめている。
私と目が合った瞬間、新は一瞬だけ笑った。
笑うしかないときの笑いだ。
「なあ、澪」
新が言った。声が、ひどく甘ったるい。
「大丈夫。僕たち、言ってないもん。な?」
な?
その一言が、昔なら合図だった。
ここで同じ方向を見る、という合図。
私は答えられなかった。
杏が、新を見て小さく首を振る。
「……新、やめて。今、大丈夫って言うの、やめて」
新の笑いが消える。
「は?じゃあ何言えばいい?泣けばいいの?」
新は言い返す。でも、いつもの強さがない。強く見せるための声が、空回りしている。
咲がぽつりと言った。
「泣いても、ログは消えない」
全員の空気が止まった。
咲の声は小さかったのに、廊下全体に響いた気がした。
「……ログって何」
杏が震える声で聞いた。
「証拠」
咲が言う。
「私たちの言ったこと、押したこと、見たこと、保存したこと。全部」
「押した?」
慧が眉をひそめた。
「俺、押してない。外部投票にしてから、俺は――」
「押してない、って言えるのは」
咲が慧を見た。
「自分の手を信じてるから」
慧が言葉を失う。
私は、背筋が冷えた。
私たちの中で、信じてるという単語が、いちばん危ない。
加賀が咲に詰め寄った。
「おい、咲。お前、なんか知ってんのかよ。管理者とか、なんか変な設定とか――」
咲は視線を逸らさない。
「知ってる。……でも、知らない」
「どっちだよ!」
加賀が声を荒げる。
咲は、淡々と続けた。
「私は、見てただけ。何が起こるか。どこまで行くか。――行った先で、誰が『神様のせい』って言うか」
杏が口元を押さえた。
新の顔から血の気が引く。
慧が唇を噛む。
加賀が言葉を探して、見つけられない。
私の胸の奥で、何かが小さく笑った気がした。笑ってはいけないのに、笑ってしまうあの感じ。
意味が揃った瞬間の、気持ち悪い快感。
――私たちは、見たかったのかもしれない。
誰かが本当に、「神様の言うとおり」と言ってしまう瞬間を。
「……違う」
私は言った。
誰に言ったのか分からない。自分に言ったのかもしれない。
「違う。私たちは、そんなつもりじゃ……」
新が私の言葉にすがるように頷いた。
「そう、そうだよ。澪が言うならそう。僕たち、そんなつもりじゃなかった。ほら、慧も、陸も、杏も、咲も――」
ほら。
新がまた、合図を出す。
合図に乗れば、私たちはいつもの6人に戻れる。
戻ってしまえば、責任はまた薄まる。
その瞬間、廊下の奥から、さっきの刑事――真鍋刑事が歩いてきた。
足音が、妙に規則正しい。
規則正しさは、感情を削る。
真鍋刑事は、6人を一列に見た。
私たちが、いつもの屋上の円陣みたいに固まっているのを、観察するように。
「揃ったね」
刑事が言った。
穏やかな声なのに、胸の奥が締まる。
「君たちは全員、『自分は言ってない』と主張している」
刑事の視線が、順番に私たちをなぞる。
新の爪先、慧の背筋、陸の指先、咲の瞳、杏の手、そして私の喉。
「それが本当だとして――」
真鍋刑事は、少しだけ間を置いた。
その間に、私たちの中の誰かが犯人であってほしいという願いが、膨らんでしまう。
犯人が一人なら、終わる。
終わりにできる。
刑事は、願いを丁寧に潰すみたいに言った。
「じゃあ、誰が言わせた?」