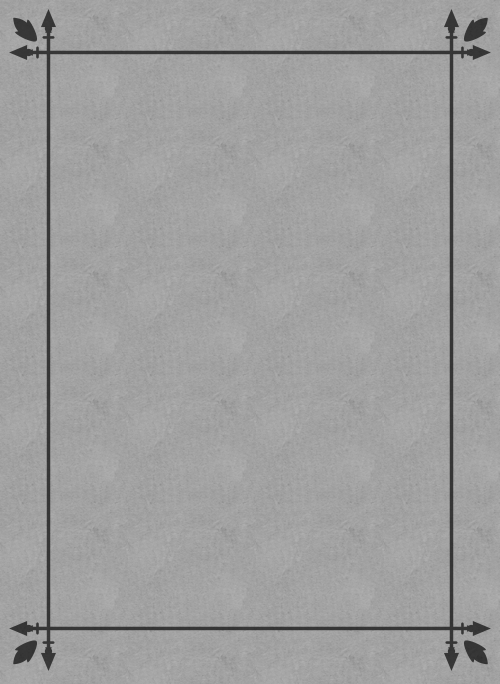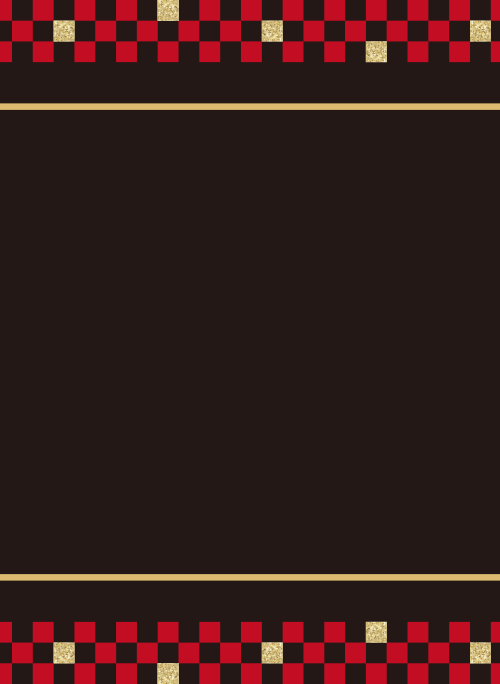パンケーキが、一口だけ消えていた。
家庭科室のドアは、確かに鍵がかかっていた。
回した鍵が「こつ」と乾いた音を立てて、静かな廊下にやけに大げさに響く。早朝の校舎は冷蔵庫みたいに冷たくて、息を吸うと喉の奥がきゅっと縮んだ。
照明を点ける。蛍光灯が一拍遅れて白く明るくなり、ステンレスの調理台が無表情に光った。
誰もいないはずなのに、ここだけ空気が薄い。いや、薄いというより――音がない。
静かすぎて、僕の心臓の音だけがうるさい。
どく、どく、どく。まるで「ここにいるのはお前だけじゃない」と言われているみたいだった。
冷蔵庫に近づいて、取っ手に指をかける。ひんやりした金属の感触に、昨夜の熱が一気に遠のいた気がした。
扉を開けると、冷気が頬をなでた。中段に、タッパーがひとつ。ラップを二重にして、さらに蓋まできっちり閉めたやつ。
僕はそのタッパーを取り出して、調理台に置いた。手が震えているのが、自分でも分かる。
蓋を開ける。
ラップをはがす。
――そこにあったパンケーキは、欠けていた。
丸いはずの縁が、指でつまんだみたいにきれいに一口ぶん消えている。
切り口は、妙に整っていた。フォークでちぎったでもない。落としたでもない。最初からそこだけ存在しなかったみたいに、自然に欠けている。
「……そんなわけ、ないだろ」
声が、自分の耳に届くのに一瞬遅れた。
寒さのせいじゃない。
怖いという感情が、言葉の速度まで奪っていく。
昨日、僕はこのパンケーキに手をつけていない。
これは食べないと決めて、冷蔵庫に入れた。ラップも蓋も、二重にした。念のため、タッパーの横に小さく付箋まで貼った。
――『結衣のぶん』
その付箋が、今も貼られている。
つまり、これは僕の見間違いでも、記憶違いでもない。
パンケーキは、たしかに、誰かに食べられた。
一口だけ。
そして、家庭科室は鍵がかかっていた。
昨夜のことを思い出すだけで、胃のあたりが重くなる。
重いのに、なぜか甘い匂いも一緒に蘇ってくるから厄介だ。
今日は、結衣の誕生日だ。
――白石結衣。僕の幼なじみ。
二ヶ月前、突然学校に来なくなった。転校だとか、入院だとか、勝手な噂は流れたけど、本人の声はどこにもなかった。僕のスマホにも、既読はつかない。電話も繋がらない。
それでも、誕生日だけは覚えている。
というより、忘れられるわけがない。
今日は彼女の誕生日だったから、僕は二人の思い出があるパンケーキを焼いた。
結衣が好きだったから。いや、正確には――結衣が焼くパンケーキが好きだったから、だ。
ふわっとして、バターの香りがして、焼き目がきれいで、口に入れると不思議な塩気が一瞬だけ走る。甘さが引き締まって、二枚目、三枚目が勝手に消える、あの味。
「隠し味、なに?」って聞いたら、結衣は毎年同じ顔をした。
得意げに笑って、でも教える気はあまりなくて、最後にこう言うのだ。
『秘密』
昨日、放課後の家庭科室に残ったのは、誰のためでもない。
僕の、意地のためだ。
結衣がいない誕生日なんて、なかったことにするべきなのに、僕はそうできなかった。
せめてパンケーキだけでも焼けば、誕生日が誕生日として存在する気がした。
粉と卵と牛乳を混ぜて、焼く。
レシピは覚えている。火加減も、返すタイミングも。
なのに、焼き上がったそれは、見た目だけがそれっぽくて――味は、別物だった。
ひと口だけ食べて、僕は思わず笑ってしまった。笑えるくらい違った。
「……美味しくないな」
誰もいない家庭科室で、ひとりで悪口を言って、ひとりで傷つく。最悪だ。
それでも捨てることはできなくて、僕は二枚焼いた。
一枚は自分の失敗作。もう一枚は、結衣のぶん――ということにした。
食べない。味見もしない。
結衣のぶんは、結衣が帰ってくるまで手をつけない。
そう決めて、タッパーに入れてラップを二重にして、蓋をして、冷蔵庫にしまった。
鍵を閉めて、校舎を出た。
僕は、ちゃんと帰った。
そして――ちゃんと眠った、はずだった。
夢を見た。
ダイニングテーブルの向かいに、結衣が座っていた。
制服じゃない。いつもの部屋着で、髪を耳にかける癖までそのままだった。
テーブルの上には、皿。湯気。バターの匂い。
パンケーキだ。
結衣はフォークで一口ぶん切り分けて、口に運んだ。
噛んで、飲み込むまでの一瞬がやけに長い。
それから、結衣は不機嫌そうな顔をした。
でも、その目だけは――どこか困ったみたいで、やさしい。
『一言で言って、まずい』
それを聞いた瞬間、僕は息を呑んだ。
聞き慣れたはずの声なのに、胸の奥に針が刺さる。
「待って、結衣――!」
名前を呼んだところで、目が覚めた。
暗い部屋。枕元のスマホが、冷たい光を放っている。
時刻は、五時過ぎ。外はまだ薄青い。
登校時間にはまだ早い。
でも、眠れる気がしなかった。
夢の中の結衣が、あまりにもいつも通りだったせいだ。
まるで本当に、どこかで僕のパンケーキを食べたみたいに――
その考えが頭をよぎって、背中に汗がにじんだ。
「……バカか」
自分にそう言いながら、僕はベッドから起き上がった。
制服に着替えて、鞄を持って、家を出る。足が勝手に学校へ向かう。
家庭科室の鍵は、僕が持っている。
結衣がいなくなってからも、僕は家庭科部を辞めていない。
辞めてないというより、辞められないままの幽霊部員だ。――笑えない冗談だと思う。
校舎に着く。
人気のない廊下を進み、家庭科室の前で立ち止まる。鍵穴に鍵を差し込む手が、少しだけ震えた。
そして今。
冷蔵庫から取り出したタッパーの中で、パンケーキは一口ぶん欠けていた。
僕は欠けた形を見つめたまま、しばらく動けなかった。
冷気が指先の感覚を奪っていくのに、胸の奥だけが熱い。
――誰が?
――いつ?
――どうやって、鍵のかかったこの部屋で?
そして、いちばん欲しかった答えが、頭の中で勝手に形を取る。
「……結衣?」
声が震えた。
返事はない。あるのは、静けさと、冷蔵庫のモーター音だけ。
それなのに、欠けた一口の形だけが、やけに誰かの存在を主張していた。
家庭科室のドアは、確かに鍵がかかっていた。
回した鍵が「こつ」と乾いた音を立てて、静かな廊下にやけに大げさに響く。早朝の校舎は冷蔵庫みたいに冷たくて、息を吸うと喉の奥がきゅっと縮んだ。
照明を点ける。蛍光灯が一拍遅れて白く明るくなり、ステンレスの調理台が無表情に光った。
誰もいないはずなのに、ここだけ空気が薄い。いや、薄いというより――音がない。
静かすぎて、僕の心臓の音だけがうるさい。
どく、どく、どく。まるで「ここにいるのはお前だけじゃない」と言われているみたいだった。
冷蔵庫に近づいて、取っ手に指をかける。ひんやりした金属の感触に、昨夜の熱が一気に遠のいた気がした。
扉を開けると、冷気が頬をなでた。中段に、タッパーがひとつ。ラップを二重にして、さらに蓋まできっちり閉めたやつ。
僕はそのタッパーを取り出して、調理台に置いた。手が震えているのが、自分でも分かる。
蓋を開ける。
ラップをはがす。
――そこにあったパンケーキは、欠けていた。
丸いはずの縁が、指でつまんだみたいにきれいに一口ぶん消えている。
切り口は、妙に整っていた。フォークでちぎったでもない。落としたでもない。最初からそこだけ存在しなかったみたいに、自然に欠けている。
「……そんなわけ、ないだろ」
声が、自分の耳に届くのに一瞬遅れた。
寒さのせいじゃない。
怖いという感情が、言葉の速度まで奪っていく。
昨日、僕はこのパンケーキに手をつけていない。
これは食べないと決めて、冷蔵庫に入れた。ラップも蓋も、二重にした。念のため、タッパーの横に小さく付箋まで貼った。
――『結衣のぶん』
その付箋が、今も貼られている。
つまり、これは僕の見間違いでも、記憶違いでもない。
パンケーキは、たしかに、誰かに食べられた。
一口だけ。
そして、家庭科室は鍵がかかっていた。
昨夜のことを思い出すだけで、胃のあたりが重くなる。
重いのに、なぜか甘い匂いも一緒に蘇ってくるから厄介だ。
今日は、結衣の誕生日だ。
――白石結衣。僕の幼なじみ。
二ヶ月前、突然学校に来なくなった。転校だとか、入院だとか、勝手な噂は流れたけど、本人の声はどこにもなかった。僕のスマホにも、既読はつかない。電話も繋がらない。
それでも、誕生日だけは覚えている。
というより、忘れられるわけがない。
今日は彼女の誕生日だったから、僕は二人の思い出があるパンケーキを焼いた。
結衣が好きだったから。いや、正確には――結衣が焼くパンケーキが好きだったから、だ。
ふわっとして、バターの香りがして、焼き目がきれいで、口に入れると不思議な塩気が一瞬だけ走る。甘さが引き締まって、二枚目、三枚目が勝手に消える、あの味。
「隠し味、なに?」って聞いたら、結衣は毎年同じ顔をした。
得意げに笑って、でも教える気はあまりなくて、最後にこう言うのだ。
『秘密』
昨日、放課後の家庭科室に残ったのは、誰のためでもない。
僕の、意地のためだ。
結衣がいない誕生日なんて、なかったことにするべきなのに、僕はそうできなかった。
せめてパンケーキだけでも焼けば、誕生日が誕生日として存在する気がした。
粉と卵と牛乳を混ぜて、焼く。
レシピは覚えている。火加減も、返すタイミングも。
なのに、焼き上がったそれは、見た目だけがそれっぽくて――味は、別物だった。
ひと口だけ食べて、僕は思わず笑ってしまった。笑えるくらい違った。
「……美味しくないな」
誰もいない家庭科室で、ひとりで悪口を言って、ひとりで傷つく。最悪だ。
それでも捨てることはできなくて、僕は二枚焼いた。
一枚は自分の失敗作。もう一枚は、結衣のぶん――ということにした。
食べない。味見もしない。
結衣のぶんは、結衣が帰ってくるまで手をつけない。
そう決めて、タッパーに入れてラップを二重にして、蓋をして、冷蔵庫にしまった。
鍵を閉めて、校舎を出た。
僕は、ちゃんと帰った。
そして――ちゃんと眠った、はずだった。
夢を見た。
ダイニングテーブルの向かいに、結衣が座っていた。
制服じゃない。いつもの部屋着で、髪を耳にかける癖までそのままだった。
テーブルの上には、皿。湯気。バターの匂い。
パンケーキだ。
結衣はフォークで一口ぶん切り分けて、口に運んだ。
噛んで、飲み込むまでの一瞬がやけに長い。
それから、結衣は不機嫌そうな顔をした。
でも、その目だけは――どこか困ったみたいで、やさしい。
『一言で言って、まずい』
それを聞いた瞬間、僕は息を呑んだ。
聞き慣れたはずの声なのに、胸の奥に針が刺さる。
「待って、結衣――!」
名前を呼んだところで、目が覚めた。
暗い部屋。枕元のスマホが、冷たい光を放っている。
時刻は、五時過ぎ。外はまだ薄青い。
登校時間にはまだ早い。
でも、眠れる気がしなかった。
夢の中の結衣が、あまりにもいつも通りだったせいだ。
まるで本当に、どこかで僕のパンケーキを食べたみたいに――
その考えが頭をよぎって、背中に汗がにじんだ。
「……バカか」
自分にそう言いながら、僕はベッドから起き上がった。
制服に着替えて、鞄を持って、家を出る。足が勝手に学校へ向かう。
家庭科室の鍵は、僕が持っている。
結衣がいなくなってからも、僕は家庭科部を辞めていない。
辞めてないというより、辞められないままの幽霊部員だ。――笑えない冗談だと思う。
校舎に着く。
人気のない廊下を進み、家庭科室の前で立ち止まる。鍵穴に鍵を差し込む手が、少しだけ震えた。
そして今。
冷蔵庫から取り出したタッパーの中で、パンケーキは一口ぶん欠けていた。
僕は欠けた形を見つめたまま、しばらく動けなかった。
冷気が指先の感覚を奪っていくのに、胸の奥だけが熱い。
――誰が?
――いつ?
――どうやって、鍵のかかったこの部屋で?
そして、いちばん欲しかった答えが、頭の中で勝手に形を取る。
「……結衣?」
声が震えた。
返事はない。あるのは、静けさと、冷蔵庫のモーター音だけ。
それなのに、欠けた一口の形だけが、やけに誰かの存在を主張していた。