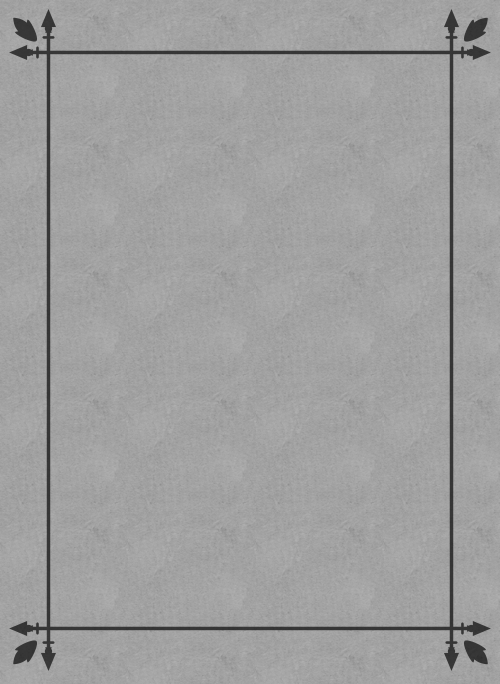昔々——そう語り出せば、たぶん、こんな物語になる。
春の宵、桜がひらひらと舞う城下町。薬師の家に生まれた娘は、絹の小袖をまとい、髪に艶やかな簪を挿す。今夜は藩主の御前で、病を癒す妙薬を献じる日。娘の名は「姫」のように呼ばれ、誰もが頬を染めて見送った。
……けれど現実は、少しも甘くない。
私の指先が触れているのは絹ではなく、煤のついた鉄瓶だった。
「小夜!まだ湯が沸かぬのかい!」
板間に響く継母の声に、私は火箸を握り直す。囲炉裏の灰がふわりと舞い、目がしばしばする。黒くなった袖口を見れば、自分が灰でできているみたいで——そこだけは、童話に似ているのかもしれない。
「すぐに。……今、火を強くします」
「口答えはいらないよ。千景の支度が先だ。今日はお屋敷へ献薬に行くんだからね」
千景——妹の名が出るだけで、家の空気がふっと華やぐ。
私の家は薬師だ。代々、藩に薬を納める家柄で、店先の暖簾には「朝霧堂」と染め抜かれている。町医者も、寺の僧も、薬が必要になればここへ来る。
けれどその繁盛の中心にいるのは、いつだって姉だった。
座敷では、千景が鏡台の前に座っている。白粉の薄い香り、紅の色。女中が髪を梳き、簪箱を開けるたびに、細工がきらりと光った。
「さすが千景だ。今度の処方は、城中でも評判になろう」
父が満足げに頷くと、千景は目を細めて笑う。
「まあ、お父さま。……小夜お姉さまにも教えてあげたらよろしいのに。覚えられるかしら」
優しい声で、棘を隠して。
私は湯桶を抱えて敷居の外に立つだけだ。教わる資格すらない、と言われているのと同じだった。
継母は私を見もしないまま言う。
「小夜は火の番と掃除をしていればいい。家の恥を外へ出さないだけでも助かるよ」
父も、視線を逸らす。
昔は父も、私の頭を撫でてくれた。薬草の名を一つ覚えるたび「よくやった」と褒めてくれた。けれど、母が亡くなってから——家の期待は千景へ、私の役目は雑用へと、静かに移っていった。
私は湯を運び、簪箱を持ち、着物の裾を整える。千景が今夜、城で披露する薬師の姫の衣装は桜の色に染められた小袖だった。袖口の刺繍は細やかで、見ていると胸が少しだけ疼く。
——私だって、同じ家に生まれたのに。
その時、表戸が荒々しく叩かれた。
「朝霧堂!薬師殿はおられるか!」
飛び込んできたのは藩の足軽だ。顔が青い。汗が光っている。
「城下で流行り病が出た。高熱と咳、そして……朝に良くなったと思った者が、夕に急に——。急ぎ、薬を」
座敷の空気が一斉に冷えた。
父が立ち上がり、千景がすぐさま口を開く。
「わかりました。解熱の処方を。……小夜、葛根と黄芩を。量は——」
私は反射的に動いた。棚から薬草を取り、臼に入れる。薬草の匂いが鼻に入る。土と日差しと、遠い山の気配。私はこの匂いが好きだった。好きなのに、好きと言うことすら許されない気がした。
千景はすらすらと指示を出し、父はそれを確認し、継母は「さすが千景」と何度も頷く。私はただ、手を動かす。
——けれど。
薬草を砕く音の中に、ひとつだけ混じる匂いがあった。
甘い。焦げた蜜のようで、鼻の奥に残る。薬草の香りとは違う、どこか人の記憶をくすぐるような香。
(……変だ)
私は臼の縁を覗き込む。粉の色はいつも通りだ。けれど、目を細めると——粉の中に、墨を落としたような黒い筋が見えた。糸のように細く、ゆらりと揺れている。
(毒?)
胸が冷える。私は思わず、臼を止めた。
「お姉さま、手が止まっている」
千景の声。私は咄嗟に口を開く。
「千景さま、この香り……。何か、混ざっています。いつもの薬草じゃ——」
「またそんなことを。妬みはみっともないわよ、小夜」
千景は微笑んだまま、臼を覗きもせずに言う。
「急ぎなの。あなたの勘より、私の処方のほうが信じられるでしょう?」
父も頷いた。
「千景の薬は城でも通っている。小夜、余計な口を挟むな」
継母が溜息をつく。
「ほら見なさい。大事な時に限って足を引っ張る」
私は唇を噛んだ。言い返せば、さらに泥を塗るだけだ。だから、手を動かした。
粉を包みに分け、煎じ薬を作り、足軽に渡す。けれど、黒い糸は、私の目から消えなかった。
その夜、城下の小さな長屋に薬が配られた。
翌朝、熱が引いたと喜ぶ声が上がった。——そして夕方、鐘が鳴った。
「死人が出た!」
店の外が騒がしい。私は裏で桶を洗っていたが、声の方向へ駆けた。近所の者が押し寄せ、顔を歪めて叫ぶ。
「朝霧堂の薬を飲んだ婆さまが、夕に血を吐いて死んだ!」
「子どももだ!さっきまで笑っていたのに——」
父の顔色が変わる。千景は眉をひそめるだけで、取り乱さない。
「おかしいわ。処方に間違いなんて」
私は人波の隙間から、運ばれてきた遺体の口元を見た。唇の端に、黒ずんだ泡。鼻に届く甘い焦げ香。——あの匂いだ。
(やっぱり……)
視界がにじむ。遺体の胸元に、黒い糸が絡みついているのが見えた。まるで蜘蛛の巣みたいに、心臓を縛っている。
「……妖毒」
ぽつり、と私の口が勝手に言った。言ってしまった瞬間、継母の視線が鋭く刺さる。
「今なんて言った?」
「い、いえ……。でもこの匂いは、薬じゃなくて——」
「口を慎みなさい!」
父の声が飛ぶ。けれど、その時、もう一つの声が店先から入ってきた。
「朝霧堂の薬で死人が出たと聞いた」
背の高い男。羽織の裾が揺れ、帯に差した刀の柄が光る。——誠一郎。私の、元婚約者だった人。
かつて父同士が決めた縁談で、私は嫁ぐはずだった。けれど千景の才が知れ渡るにつれ、縁はいつの間にか妹へと移り、私はなかったことになった。
誠一郎は今、千景の隣に立ち、当然のように彼女を守る位置にいる。
「千景、君は大丈夫か。……小夜、君はまた余計なことを言ったそうだな」
「余計、なこと……?」
「病が広がっている時に妖毒などと口にすれば、人心は乱れる。君は昔から、現実を見ないところがある」
違う。私が見ているのは、現実よりずっと、生々しいものだ。
「誠一郎さま、でも——」
「小夜お姉さま」
千景が私の名を呼ぶ。柔らかな声で、逃げ道を塞ぐ。
「あなたが粉を分けたわよね。臼を扱ったのもあなた。……もし、あなたがどこかで量を間違えたのなら、正直に言って。皆を救うために」
一瞬、世界が静かになった。皆の目が私に集まる。父の眉が寄る。継母の口元が吊り上がる。
——そうか。これが、千景のやり方。
自分は善意の顔をして、私を悪にする。
「私は……量は、間違えていません。けれど、香りが……」
「香り?また勘?」
誠一郎が吐き捨てるように言い、継母が畳みかける。
「小夜、認めな。あんたが失敗したんだよ。家に泥を塗ったんだ。どうせ役に立たないんだから、せめて責任くらい——」
「やめろ!」
父が声を上げる。……けれど、止めたのは継母の口ではなく、私の言葉だった。
「小夜。……しばらく、店を離れろ」
父はそう言った。店の名を守るために。千景の名を守るために。私を切るために。
「城下を出なさい。境の森の手前まで行けば、寺がある。……そこで身を落ち着けろ」
境の森。妖が出ると噂される、あの場所。
(追放、だ)
膝が震えた。私は必死に息を吸う。泣けば負ける。けれど、涙は勝手に熱くなる。
「お父さま……私は、毒を——」
「もういい!」
父が叫ぶ。私の言葉は、途中で折れた。
その夜、私は荷を一つだけ背負わされ、裏口から出された。見送りは誰もいない。春の宵のはずなのに、風は冷たい。通りの提灯は遠く、桜の匂いも届かない。
門前まで来たところで、足軽が二人、私を挟むように立った。
「ここから先は、勝手に戻るな。……薬師の家の恥さらし」
恥さらし。無能。疫病を広げた女。——そういう札を首から下げられた気分だった。
そのとき、闇の奥から、かすれた咳が聞こえた。
「……たすけ、て……」
道端の陰に、男が倒れている。目は虚ろで、唇が紫に変わり、喉元が引きつったように痙攣していた。近づけば、甘い焦げ香が強くなる。
足軽が顔をしかめる。
「触るな。流行り病だ」
「でも……!」
私は駆け寄りかけて止まった。男の胸元に、黒い糸が絡みついている。……病ではない。あれは、妖毒が喉を縛っている。
(このままじゃ死ぬ)
私の袖には、さっきまで扱っていた薬草の粉が少しだけ残っている。葛根、黄芩、甘草。——そして、母が遺してくれた小袋の中の解毒の丸薬。本当は、家の誰にも見せるなと継母に言われていたもの。
私は迷って、結局、その小袋に手を伸ばした。
「おい、やめろ!」
足軽の手が私の腕を掴む。次の瞬間——
蹄の音が、夜を割った。
ひとつ。ふたつ。規則正しい音。近づくにつれ、空気が重くなる。人々が息を呑む気配。提灯の火が、風もないのに揺れた。
現れたのは黒塗りの馬。背には黒の鎧を着た男が跨り、面頬の隙間から月光のような瞳が覗いていた。
——朔夜。
噂だけは知っている。藩の最強武将。妖を斬り、呪いを封じ、その代わりに自ら禍を抱える人。近づく者は皆、何かを失うと言われていた。
足軽たちが慌てて頭を下げる。
「朔夜さま……!何用で」
朔夜は馬上から、倒れた男を一瞥した。ほんの一瞬。けれど、その一瞬で、状況を飲み込んだ顔だった。
「それは病ではない」
低い声が、夜気を切る。
「……妖毒だ」
私の胸が跳ねた。私と同じ言葉を、朔夜が言った。
足軽が狼狽える。
「で、ですが……流行り病と——」
「病なら、息はこうは臭わぬ」
朔夜の鼻がわずかに動く。獲物の匂いを嗅ぎ取る獣のように。
「甘い焦げ香がする。……薬の香りに似せた、呪いの匂いだ」
朔夜は馬を下り、倒れた男の前に膝をついた。鎧が擦れる音がして、周囲の空気がさらに重くなる。
朔夜の指先が男の額に触れた瞬間、黒い糸がぴくりと跳ねた。
(禍が……朔夜さまに向かう)
黒い糸が、朔夜の腕へ伸びる。まるで餌にすがりつくように。朔夜は眉ひとつ動かさず、黒い糸を自分の中へ引き受けた。
——その代わり、朔夜の腕の内側に黒い筋が走った。脈に沿って滲むように。痛みを隠す顔。けれど、確かに苦しいはずだ。
「……っ」
短い息。誰にも聞かせないための、最小の声。
私は足軽の手を振りほどいた。
「待ってください。……それ以上、禍を抱えると」
朔夜の瞳が私を射抜く。怖い。けれど、目を逸らせなかった。
「お前は誰だ」
「朝霧堂の……小夜と申します」
「朝霧堂……薬師の家か」
朔夜の視線が、私の首に下がる札に落ちる。「恥さらし」と書かれた札が、夜目にもはっきり読める。
朔夜の指が、私の札をつまみ、ひらりと外した。
「その札は不要だ。——この場では」
足軽が口を挟む。
「し、しかし……この者は追放の——」
「追放するな。俺が預かる」
朔夜の声は冷たく、揺るがなかった。足軽が黙る。刀に触れたわけでもないのに、空気が刃になったみたいに感じた。
朔夜は倒れた男の口元に手をかざし、禍の流れを押さえる。だが、黒い筋は朔夜の腕でさらに濃くなり、肩へと広がり始めた。
(だめ……朔夜さまが)
私は小袋を取り出し、丸薬を砕いて掌に乗せた。薬草の粉を混ぜ、唾液で練る。恥ずかしいほど原始的なやり方——けれど、私は家で処方を許されていない。これしかない。
朔夜がこちらを見る。
「何をする」
「禍を……毒として、ほどきます」
口にした瞬間、自分でも驚いた。ほどく?毒を?そんな言葉、教わったことがないのに。
けれど、私の目には見えている。朔夜の腕の黒い筋が、糸の束のように絡まっているのが。流れを塞いで、血を汚しているのが。
私は薬を指先でつまみ、朔夜の腕の黒い筋の“根元”へ塗った。冷たい皮膚。硬い筋肉。……その奥で、禍がじたばたと暴れる。
(ここ……ここを、緩めれば)
黒い糸が、ゆるりとほどけた。錯覚ではない。私の目の前で、黒が薄くなる。
朔夜の呼吸が、わずかに整った。
「……お前」
驚きと、警戒と、そして——ほんの少しの安堵が混じった声。
倒れた男の喉の痙攣が止まり、薄く目が開く。甘い焦げ香も、少しだけ弱まった。
私は膝をついたまま、息を吐いた。指先が震える。手のひらに残る黒い影が、まだ消えない。
朔夜が立ち上がり、倒れた男を足軽に渡す。
「城へ運べ。陰陽寮に回せ。——この匂いは、意図して混ぜられている」
足軽が慌てて頷き、男を担ぎ上げる。
朔夜は私に向き直った。
「お前、何を見た」
私は小さく唾を飲み、答えようとして——また、朔夜の腕の黒が蠢いた。抱えた禍が、まだ完全には落ち着いていない。
(この人は……いつも、こうして一人で)
孤独。それが、匂いみたいに伝わってくる。
私の家族が私を遠ざけたのとは違う。彼は、近づく者を遠ざけるしかない孤独だ。
朔夜の瞳が細くなる。
「怖がるな。見えるのだろう」
私は、頷くしかなかった。
——目。
私の目は、いつだって家族の期待するものを見られなかった。薬師として見えるべき“効き目”ではなく、見たくもないものばかり。
黒い糸。黒い靄。黒い筋。
夜風が吹き、提灯の火が揺れる。その揺らぎの中で、私は確信した。
薬師の家に生まれたのに、私が見つけるのは、いつも——
「薬師の家に生まれたのに、私は毒しか見えなかった。」
春の宵、桜がひらひらと舞う城下町。薬師の家に生まれた娘は、絹の小袖をまとい、髪に艶やかな簪を挿す。今夜は藩主の御前で、病を癒す妙薬を献じる日。娘の名は「姫」のように呼ばれ、誰もが頬を染めて見送った。
……けれど現実は、少しも甘くない。
私の指先が触れているのは絹ではなく、煤のついた鉄瓶だった。
「小夜!まだ湯が沸かぬのかい!」
板間に響く継母の声に、私は火箸を握り直す。囲炉裏の灰がふわりと舞い、目がしばしばする。黒くなった袖口を見れば、自分が灰でできているみたいで——そこだけは、童話に似ているのかもしれない。
「すぐに。……今、火を強くします」
「口答えはいらないよ。千景の支度が先だ。今日はお屋敷へ献薬に行くんだからね」
千景——妹の名が出るだけで、家の空気がふっと華やぐ。
私の家は薬師だ。代々、藩に薬を納める家柄で、店先の暖簾には「朝霧堂」と染め抜かれている。町医者も、寺の僧も、薬が必要になればここへ来る。
けれどその繁盛の中心にいるのは、いつだって姉だった。
座敷では、千景が鏡台の前に座っている。白粉の薄い香り、紅の色。女中が髪を梳き、簪箱を開けるたびに、細工がきらりと光った。
「さすが千景だ。今度の処方は、城中でも評判になろう」
父が満足げに頷くと、千景は目を細めて笑う。
「まあ、お父さま。……小夜お姉さまにも教えてあげたらよろしいのに。覚えられるかしら」
優しい声で、棘を隠して。
私は湯桶を抱えて敷居の外に立つだけだ。教わる資格すらない、と言われているのと同じだった。
継母は私を見もしないまま言う。
「小夜は火の番と掃除をしていればいい。家の恥を外へ出さないだけでも助かるよ」
父も、視線を逸らす。
昔は父も、私の頭を撫でてくれた。薬草の名を一つ覚えるたび「よくやった」と褒めてくれた。けれど、母が亡くなってから——家の期待は千景へ、私の役目は雑用へと、静かに移っていった。
私は湯を運び、簪箱を持ち、着物の裾を整える。千景が今夜、城で披露する薬師の姫の衣装は桜の色に染められた小袖だった。袖口の刺繍は細やかで、見ていると胸が少しだけ疼く。
——私だって、同じ家に生まれたのに。
その時、表戸が荒々しく叩かれた。
「朝霧堂!薬師殿はおられるか!」
飛び込んできたのは藩の足軽だ。顔が青い。汗が光っている。
「城下で流行り病が出た。高熱と咳、そして……朝に良くなったと思った者が、夕に急に——。急ぎ、薬を」
座敷の空気が一斉に冷えた。
父が立ち上がり、千景がすぐさま口を開く。
「わかりました。解熱の処方を。……小夜、葛根と黄芩を。量は——」
私は反射的に動いた。棚から薬草を取り、臼に入れる。薬草の匂いが鼻に入る。土と日差しと、遠い山の気配。私はこの匂いが好きだった。好きなのに、好きと言うことすら許されない気がした。
千景はすらすらと指示を出し、父はそれを確認し、継母は「さすが千景」と何度も頷く。私はただ、手を動かす。
——けれど。
薬草を砕く音の中に、ひとつだけ混じる匂いがあった。
甘い。焦げた蜜のようで、鼻の奥に残る。薬草の香りとは違う、どこか人の記憶をくすぐるような香。
(……変だ)
私は臼の縁を覗き込む。粉の色はいつも通りだ。けれど、目を細めると——粉の中に、墨を落としたような黒い筋が見えた。糸のように細く、ゆらりと揺れている。
(毒?)
胸が冷える。私は思わず、臼を止めた。
「お姉さま、手が止まっている」
千景の声。私は咄嗟に口を開く。
「千景さま、この香り……。何か、混ざっています。いつもの薬草じゃ——」
「またそんなことを。妬みはみっともないわよ、小夜」
千景は微笑んだまま、臼を覗きもせずに言う。
「急ぎなの。あなたの勘より、私の処方のほうが信じられるでしょう?」
父も頷いた。
「千景の薬は城でも通っている。小夜、余計な口を挟むな」
継母が溜息をつく。
「ほら見なさい。大事な時に限って足を引っ張る」
私は唇を噛んだ。言い返せば、さらに泥を塗るだけだ。だから、手を動かした。
粉を包みに分け、煎じ薬を作り、足軽に渡す。けれど、黒い糸は、私の目から消えなかった。
その夜、城下の小さな長屋に薬が配られた。
翌朝、熱が引いたと喜ぶ声が上がった。——そして夕方、鐘が鳴った。
「死人が出た!」
店の外が騒がしい。私は裏で桶を洗っていたが、声の方向へ駆けた。近所の者が押し寄せ、顔を歪めて叫ぶ。
「朝霧堂の薬を飲んだ婆さまが、夕に血を吐いて死んだ!」
「子どももだ!さっきまで笑っていたのに——」
父の顔色が変わる。千景は眉をひそめるだけで、取り乱さない。
「おかしいわ。処方に間違いなんて」
私は人波の隙間から、運ばれてきた遺体の口元を見た。唇の端に、黒ずんだ泡。鼻に届く甘い焦げ香。——あの匂いだ。
(やっぱり……)
視界がにじむ。遺体の胸元に、黒い糸が絡みついているのが見えた。まるで蜘蛛の巣みたいに、心臓を縛っている。
「……妖毒」
ぽつり、と私の口が勝手に言った。言ってしまった瞬間、継母の視線が鋭く刺さる。
「今なんて言った?」
「い、いえ……。でもこの匂いは、薬じゃなくて——」
「口を慎みなさい!」
父の声が飛ぶ。けれど、その時、もう一つの声が店先から入ってきた。
「朝霧堂の薬で死人が出たと聞いた」
背の高い男。羽織の裾が揺れ、帯に差した刀の柄が光る。——誠一郎。私の、元婚約者だった人。
かつて父同士が決めた縁談で、私は嫁ぐはずだった。けれど千景の才が知れ渡るにつれ、縁はいつの間にか妹へと移り、私はなかったことになった。
誠一郎は今、千景の隣に立ち、当然のように彼女を守る位置にいる。
「千景、君は大丈夫か。……小夜、君はまた余計なことを言ったそうだな」
「余計、なこと……?」
「病が広がっている時に妖毒などと口にすれば、人心は乱れる。君は昔から、現実を見ないところがある」
違う。私が見ているのは、現実よりずっと、生々しいものだ。
「誠一郎さま、でも——」
「小夜お姉さま」
千景が私の名を呼ぶ。柔らかな声で、逃げ道を塞ぐ。
「あなたが粉を分けたわよね。臼を扱ったのもあなた。……もし、あなたがどこかで量を間違えたのなら、正直に言って。皆を救うために」
一瞬、世界が静かになった。皆の目が私に集まる。父の眉が寄る。継母の口元が吊り上がる。
——そうか。これが、千景のやり方。
自分は善意の顔をして、私を悪にする。
「私は……量は、間違えていません。けれど、香りが……」
「香り?また勘?」
誠一郎が吐き捨てるように言い、継母が畳みかける。
「小夜、認めな。あんたが失敗したんだよ。家に泥を塗ったんだ。どうせ役に立たないんだから、せめて責任くらい——」
「やめろ!」
父が声を上げる。……けれど、止めたのは継母の口ではなく、私の言葉だった。
「小夜。……しばらく、店を離れろ」
父はそう言った。店の名を守るために。千景の名を守るために。私を切るために。
「城下を出なさい。境の森の手前まで行けば、寺がある。……そこで身を落ち着けろ」
境の森。妖が出ると噂される、あの場所。
(追放、だ)
膝が震えた。私は必死に息を吸う。泣けば負ける。けれど、涙は勝手に熱くなる。
「お父さま……私は、毒を——」
「もういい!」
父が叫ぶ。私の言葉は、途中で折れた。
その夜、私は荷を一つだけ背負わされ、裏口から出された。見送りは誰もいない。春の宵のはずなのに、風は冷たい。通りの提灯は遠く、桜の匂いも届かない。
門前まで来たところで、足軽が二人、私を挟むように立った。
「ここから先は、勝手に戻るな。……薬師の家の恥さらし」
恥さらし。無能。疫病を広げた女。——そういう札を首から下げられた気分だった。
そのとき、闇の奥から、かすれた咳が聞こえた。
「……たすけ、て……」
道端の陰に、男が倒れている。目は虚ろで、唇が紫に変わり、喉元が引きつったように痙攣していた。近づけば、甘い焦げ香が強くなる。
足軽が顔をしかめる。
「触るな。流行り病だ」
「でも……!」
私は駆け寄りかけて止まった。男の胸元に、黒い糸が絡みついている。……病ではない。あれは、妖毒が喉を縛っている。
(このままじゃ死ぬ)
私の袖には、さっきまで扱っていた薬草の粉が少しだけ残っている。葛根、黄芩、甘草。——そして、母が遺してくれた小袋の中の解毒の丸薬。本当は、家の誰にも見せるなと継母に言われていたもの。
私は迷って、結局、その小袋に手を伸ばした。
「おい、やめろ!」
足軽の手が私の腕を掴む。次の瞬間——
蹄の音が、夜を割った。
ひとつ。ふたつ。規則正しい音。近づくにつれ、空気が重くなる。人々が息を呑む気配。提灯の火が、風もないのに揺れた。
現れたのは黒塗りの馬。背には黒の鎧を着た男が跨り、面頬の隙間から月光のような瞳が覗いていた。
——朔夜。
噂だけは知っている。藩の最強武将。妖を斬り、呪いを封じ、その代わりに自ら禍を抱える人。近づく者は皆、何かを失うと言われていた。
足軽たちが慌てて頭を下げる。
「朔夜さま……!何用で」
朔夜は馬上から、倒れた男を一瞥した。ほんの一瞬。けれど、その一瞬で、状況を飲み込んだ顔だった。
「それは病ではない」
低い声が、夜気を切る。
「……妖毒だ」
私の胸が跳ねた。私と同じ言葉を、朔夜が言った。
足軽が狼狽える。
「で、ですが……流行り病と——」
「病なら、息はこうは臭わぬ」
朔夜の鼻がわずかに動く。獲物の匂いを嗅ぎ取る獣のように。
「甘い焦げ香がする。……薬の香りに似せた、呪いの匂いだ」
朔夜は馬を下り、倒れた男の前に膝をついた。鎧が擦れる音がして、周囲の空気がさらに重くなる。
朔夜の指先が男の額に触れた瞬間、黒い糸がぴくりと跳ねた。
(禍が……朔夜さまに向かう)
黒い糸が、朔夜の腕へ伸びる。まるで餌にすがりつくように。朔夜は眉ひとつ動かさず、黒い糸を自分の中へ引き受けた。
——その代わり、朔夜の腕の内側に黒い筋が走った。脈に沿って滲むように。痛みを隠す顔。けれど、確かに苦しいはずだ。
「……っ」
短い息。誰にも聞かせないための、最小の声。
私は足軽の手を振りほどいた。
「待ってください。……それ以上、禍を抱えると」
朔夜の瞳が私を射抜く。怖い。けれど、目を逸らせなかった。
「お前は誰だ」
「朝霧堂の……小夜と申します」
「朝霧堂……薬師の家か」
朔夜の視線が、私の首に下がる札に落ちる。「恥さらし」と書かれた札が、夜目にもはっきり読める。
朔夜の指が、私の札をつまみ、ひらりと外した。
「その札は不要だ。——この場では」
足軽が口を挟む。
「し、しかし……この者は追放の——」
「追放するな。俺が預かる」
朔夜の声は冷たく、揺るがなかった。足軽が黙る。刀に触れたわけでもないのに、空気が刃になったみたいに感じた。
朔夜は倒れた男の口元に手をかざし、禍の流れを押さえる。だが、黒い筋は朔夜の腕でさらに濃くなり、肩へと広がり始めた。
(だめ……朔夜さまが)
私は小袋を取り出し、丸薬を砕いて掌に乗せた。薬草の粉を混ぜ、唾液で練る。恥ずかしいほど原始的なやり方——けれど、私は家で処方を許されていない。これしかない。
朔夜がこちらを見る。
「何をする」
「禍を……毒として、ほどきます」
口にした瞬間、自分でも驚いた。ほどく?毒を?そんな言葉、教わったことがないのに。
けれど、私の目には見えている。朔夜の腕の黒い筋が、糸の束のように絡まっているのが。流れを塞いで、血を汚しているのが。
私は薬を指先でつまみ、朔夜の腕の黒い筋の“根元”へ塗った。冷たい皮膚。硬い筋肉。……その奥で、禍がじたばたと暴れる。
(ここ……ここを、緩めれば)
黒い糸が、ゆるりとほどけた。錯覚ではない。私の目の前で、黒が薄くなる。
朔夜の呼吸が、わずかに整った。
「……お前」
驚きと、警戒と、そして——ほんの少しの安堵が混じった声。
倒れた男の喉の痙攣が止まり、薄く目が開く。甘い焦げ香も、少しだけ弱まった。
私は膝をついたまま、息を吐いた。指先が震える。手のひらに残る黒い影が、まだ消えない。
朔夜が立ち上がり、倒れた男を足軽に渡す。
「城へ運べ。陰陽寮に回せ。——この匂いは、意図して混ぜられている」
足軽が慌てて頷き、男を担ぎ上げる。
朔夜は私に向き直った。
「お前、何を見た」
私は小さく唾を飲み、答えようとして——また、朔夜の腕の黒が蠢いた。抱えた禍が、まだ完全には落ち着いていない。
(この人は……いつも、こうして一人で)
孤独。それが、匂いみたいに伝わってくる。
私の家族が私を遠ざけたのとは違う。彼は、近づく者を遠ざけるしかない孤独だ。
朔夜の瞳が細くなる。
「怖がるな。見えるのだろう」
私は、頷くしかなかった。
——目。
私の目は、いつだって家族の期待するものを見られなかった。薬師として見えるべき“効き目”ではなく、見たくもないものばかり。
黒い糸。黒い靄。黒い筋。
夜風が吹き、提灯の火が揺れる。その揺らぎの中で、私は確信した。
薬師の家に生まれたのに、私が見つけるのは、いつも——
「薬師の家に生まれたのに、私は毒しか見えなかった。」