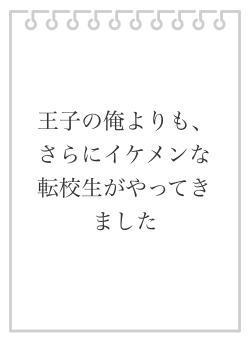「あれ…?」
「ここをこうだよ」
星藍は田舎で育っていたからか、作法に疎い。そして、生贄ということもあり、服の着方も知らないようだ。
そんな星藍を俺はにこにこに笑顔で見つめる。微笑ましくて仕方がない。
星藍と話し合って、祝言は作法などを一通り覚えてからにしようとなった。
俺は一応この国の皇帝。妻には作法をしっかりしてもらわなければならない。
この結婚には、父や母に反対されたが、俺は無理矢理押し通した。
「鬼帝様、今日のお仕事はお済みになったのですか?」
炎にそう聞かれて、
「あぁ」
と答える。宮殿の中だと、こんな風に"冷徹"だと言われる俺が完成している。
しかし、部屋に戻ると、
「星藍、ただいま」
「おかえりなさいませ、冷様」
と星藍が出迎えてくれる。俺は速攻星藍に抱きつく。
「今日も星藍がいると思うと、頑張れたよ〜!」
そう言うと、星藍も抱きしめ返してくれた。
「私も、冷様がいると思うと、作法の勉強を頑張れました!」
そう言ってくすっと笑う俺たち。
「そうかそうか」
俺は星藍を撫でる。すると、星藍は頬を少し赤くして、俺のことを見つめてくる。
「子供扱いはやめてくださいねっ」
そう言って、星藍はそっぽを向く。でも、俺が名前を呼ぶと、パッとこっちを向く。
「冷様って世間じゃ冷徹って言われていますけど、全然そうじゃないですよね」
にこにこの笑顔でそう言われて、俺は心にじーんとくる。
嬉しくて涙が出そうだ。
「ありがとう」
俺はそう言って、星藍を再度抱きしめた。
私が冷様の花嫁になるに当たって、幾つか知ったことがある。
鬼帝というのは称号で、本名は日之影冷。冷と呼んでほしいと言われた。
そして、世間で呼ばれている"冷徹"というのは嘘だ。
私のことをずっとずっと愛してくれている。本来なら生贄として湖に沈むはずだったこの命を。
冷様は、私のことをすごく溺愛してくる。それはもう信じられないくらいに。
私は今までそんなに重い愛を受けたことがなかった。物心ついたときから両親はいなく、隅の方でご飯を食べていた。
(そういえば、冷様、私のことを見て可愛らしいと……)
この家に来てから何回も自分の顔を見つめたが、可愛らいいと感じる点なんて一つもない。
「はぁ……」
私は考えるのをやめた。すると、扉がこんこんと叩かれる。
(えっと、こういうときは…)
私は冷様が手配してくれた作法教室を毎日受けている。よって、作法も少しましになったと思う。
「はい」
そう返事をすると、私の専属女中の真澄が入ってきた。
真澄とは友達のような関係になりたいと、会った時に伝えた。私は友達がいたためしがなかったので、どんなものなのか体験してみたいのだ。
「真澄!」
私がそう言うと、真澄は柔らかい雰囲気を周りに纏って、こちらにくる。
「星藍様、お夕食のお時間です」
にっこりと笑ってそう言う真澄。その一言を聞いて、私は不満顔になる。
「2人のときは、敬語なしだよ」
そう言うと、真澄は、はいはいと言って、
「星藍、夕食の準備ができたから行きましょう?」
と言ってくれた。私は大きく頷いて、真澄と一緒に食堂へゆく。この家はやっぱり異常なほど広い。
習った作法を思い出して食堂に入ると、そこにはもう冷様が席についていた。
「冷様!」
私が笑顔で言うと、冷様も笑ってくれた。そして、私はいつもの席に座る。
「いただきます」
二人で挨拶をして、夕食を食べる。今日もとても美味しい。
(毎日ご飯を食べれるなんて幸せね)
私がしみじみとしながら夕食を食べていると、冷様がこちらを向く。
すると、
「この家に来て、はや三週間。そろそろ、社交界にデビューしてもいいと思うんだが…」
そう言われて私はいろいろなところに疑問を抱く。
社交界?
デビュー?
私の疑問を読み取ったのか、冷様は、
「今度、俺の友達がパーティを開くらしい。そこに行ってみないか?」
その誘いに私は、興味を持つ。初めて行くところにはできるだけ行ってみたい。
それが私の思いだった。
「行ってみます…!」
そう言うと、冷様は笑って、
「元気があるな。これなら大丈夫だ」
と言ってくれた。
その次の日からパーティに向けての作法の授業が増えた。今までは着物のときの作法、食事の作法が多かったが、今回からは洋装のときの作法も混じるんだとか。
「星藍様、ここはこちらに持ち帰るんですよ」
西洋の食事の作法に体がうまくなれない。
(これじゃ冷様の妻としてやっていけないじゃない…!)
私は私自身を奮い立たせて、作法の授業に挑む。
「こうでしょうか…?」
私がおそるおそる聞くと、先生はにっこりと笑って、
「うまいですね」
と言ってくれた。私はそれが嬉しくて、他の作法も頑張って覚えた。
時々冷様が授業の様子を見に来てくれる。
「星藍、やってるか?」
「はい!」
私がそう言うと、冷様は私をギュッと抱きしめてくれる。すると、先生が、
「鬼帝様、それでは授業になりません」
「だって、星藍が可愛いんですもん」
私はそのやりとりを横で見て、くすくすと笑う。そして、その日の授業が終わり、私は部屋に戻った。
「ふふ」
私のことを極限まで愛してくれる冷様を想像すると、嬉しくてたまらない。
でも、私には忘れてはいけないことが一つある。
私は精神破壊の異能を持っていて、村では忌み嫌われていたことだ。それは、仕方ないことなのだ。でも、私だって異能を持ちたくて持っていたわけじゃない。
気づいたら自分の周りはこんなふうになっていたのだ。
「パーティ、うまくやれるかな…」
私の心はいつも不安でいっぱいだ。もし、パーティの場で異能が開花してしまったら…。
私が不安に押しつぶされそうになっているとき、ドアがノックされた。
私は急いで扉を開ける。細く開けた扉の隙間から見えた顔は真澄だった。
「真澄…。用は後ででもいいかしら…?」
と聞くと、真澄は、頷いた。そして、
「日之影様が明日、パーティ用の服を買いましょうとのことです。パーティまで後一週間、星藍なら大丈夫だろうとおっしゃっていました!」
笑顔でそう言う真澄に、私は頬が綻ぶ。
「ありがとう」
私は、そう言って扉を閉めた。そして、どっと布団に倒れ込む。私はそのまま眠りに落ちてしまった。
パーティ用の服を買いに行く日となった。私はとりあえず、洋装を準備してもらう。
「真澄、髪の毛は…」
私がおずおずと尋ねる。髪の毛ぐらい、普通の人なら結べるだが、私は今まで結んだことがほとんどない。
「私がやります!」
真澄が元気よく答えてくれた。私が髪の毛を結べないことには何も思っていないようだった。
私は鏡の前に座らされる。そして、十分もしないうちに美しい髪型が完成した。服によくあっている。
「わぁ……!」
私が喜びで声が出なくなっていると、真澄は、
「そんな驚くことじゃないですよ」
と言った。でも、きっと一般人が見ても綺麗だと思うだろう。
真澄に感謝しながら、私は玄関に向かう。そこにはすでに冷様がいた。
「星藍…!」
冷様は何故か驚いた顔をしている。
「何か変でしたか…?」
おそるおそるそう聞くと、冷様は、笑って私に抱きついてくる。
「星藍が可愛すぎるんだよぉ〜」
と言った。
(また、"可愛い"…)
私は最近、冷様の言葉一つ一つにドキッとするようになった。
「では、行こう」
こうやって突然、真剣になるところも、いい。
(これって、好き…?)
まだ、よくわからなくて自信がないが、これが好きって感情だろう。冷様に手を引かれて、車に乗り込む。
(車なんて高いのに…)
冷様の財力には毎回毎回驚いてしまう。私の持っていたお金など、小さな塵に思えてきた。
そんなことを考えながら車に揺られていると、いつの間にか服屋についていた。
「鬼帝様、お待ちしておりました」
深々と頭を下げる店員たち。
「失礼しますが、そちらの方は…?」
初めに挨拶を言った一人が尋ねる。すると、冷様はゾワっと殺気を放つ。
「貴様、無礼だぞ。店長はどこだ」
そう一言言った。すると、その人は、
「店長は体調を崩してしまってあいにく休んでおります」
あわあわしながらそう告げる店員さんが可哀想に見えてきた。
「そうか…、それはすまなかった。店長から話は聞いていないのか?」
冷様が謝ってそう尋ねる。すると、従業員の人たちは皆頭を左右に振った。
「すまない。この娘は私の婚約者だ」
そう冷様がいうと、みんなはぱあっと顔を輝かせて、
「おめでとうございます!」
と口々にいった。しかし、その一方で、
「…噂通り"冷徹"だな」
にやにやとそう話す店員もいた。私はその人たちに怒りを覚えつつも、冷様に向き直る。
「どんな服を買うのでしょうか?」
私がそう尋ねると、冷様は、ニコッと笑って、
「洋装かな」
と言った。
洋装?何それ?
私の頭の中は疑問でいっぱいだ。初めて聞く単語に困惑してしまう。
「洋装…ですか」
私が復唱すると、店員さんに腕を掴まれる。
「では、こちらで試着を行いましょう」
私はそう言われて、店の奥へと引っ張られる。
(何が起こるの…?!)
私が困惑でいっぱいになっている中、冷様は私に向かって手をひらひらと振るだけだった。
そして、奥に入れられて、私は服を脱がされる。そして、服を見せられる。
「こちらとこちらどちらを先に着たいですか?」
そう聞かれて私は迷う。一つは桜色の服。もう一つは水色の服。私は迷った末に桜色を選ぶ。
すると、店員さんは慣れた手つきで私に服を着せてくる。
「鬼帝様、こちらでどうでしょうか」
試着室の扉が突然開けられ、私の姿が晒される。すると、冷様は目を輝かせて、
「可愛い!これは買おう」
と言った。この勢いだと全部買いかねないと思った私は、
「そんなにたくさんお洋服は入りませんからね」
と念押しした。しかし、本人には全く聴こえている気配がなく、顔を輝かせているだけだった。
結局その後、私は二十着以上を着せられ、そのうちの十五着を買うことになった。
いくらなんでも買いすぎだと主張したが、冷様は断固として譲らなかった。
そして、いよいよパーティ当日ーー。
「ここをこうだよ」
星藍は田舎で育っていたからか、作法に疎い。そして、生贄ということもあり、服の着方も知らないようだ。
そんな星藍を俺はにこにこに笑顔で見つめる。微笑ましくて仕方がない。
星藍と話し合って、祝言は作法などを一通り覚えてからにしようとなった。
俺は一応この国の皇帝。妻には作法をしっかりしてもらわなければならない。
この結婚には、父や母に反対されたが、俺は無理矢理押し通した。
「鬼帝様、今日のお仕事はお済みになったのですか?」
炎にそう聞かれて、
「あぁ」
と答える。宮殿の中だと、こんな風に"冷徹"だと言われる俺が完成している。
しかし、部屋に戻ると、
「星藍、ただいま」
「おかえりなさいませ、冷様」
と星藍が出迎えてくれる。俺は速攻星藍に抱きつく。
「今日も星藍がいると思うと、頑張れたよ〜!」
そう言うと、星藍も抱きしめ返してくれた。
「私も、冷様がいると思うと、作法の勉強を頑張れました!」
そう言ってくすっと笑う俺たち。
「そうかそうか」
俺は星藍を撫でる。すると、星藍は頬を少し赤くして、俺のことを見つめてくる。
「子供扱いはやめてくださいねっ」
そう言って、星藍はそっぽを向く。でも、俺が名前を呼ぶと、パッとこっちを向く。
「冷様って世間じゃ冷徹って言われていますけど、全然そうじゃないですよね」
にこにこの笑顔でそう言われて、俺は心にじーんとくる。
嬉しくて涙が出そうだ。
「ありがとう」
俺はそう言って、星藍を再度抱きしめた。
私が冷様の花嫁になるに当たって、幾つか知ったことがある。
鬼帝というのは称号で、本名は日之影冷。冷と呼んでほしいと言われた。
そして、世間で呼ばれている"冷徹"というのは嘘だ。
私のことをずっとずっと愛してくれている。本来なら生贄として湖に沈むはずだったこの命を。
冷様は、私のことをすごく溺愛してくる。それはもう信じられないくらいに。
私は今までそんなに重い愛を受けたことがなかった。物心ついたときから両親はいなく、隅の方でご飯を食べていた。
(そういえば、冷様、私のことを見て可愛らしいと……)
この家に来てから何回も自分の顔を見つめたが、可愛らいいと感じる点なんて一つもない。
「はぁ……」
私は考えるのをやめた。すると、扉がこんこんと叩かれる。
(えっと、こういうときは…)
私は冷様が手配してくれた作法教室を毎日受けている。よって、作法も少しましになったと思う。
「はい」
そう返事をすると、私の専属女中の真澄が入ってきた。
真澄とは友達のような関係になりたいと、会った時に伝えた。私は友達がいたためしがなかったので、どんなものなのか体験してみたいのだ。
「真澄!」
私がそう言うと、真澄は柔らかい雰囲気を周りに纏って、こちらにくる。
「星藍様、お夕食のお時間です」
にっこりと笑ってそう言う真澄。その一言を聞いて、私は不満顔になる。
「2人のときは、敬語なしだよ」
そう言うと、真澄は、はいはいと言って、
「星藍、夕食の準備ができたから行きましょう?」
と言ってくれた。私は大きく頷いて、真澄と一緒に食堂へゆく。この家はやっぱり異常なほど広い。
習った作法を思い出して食堂に入ると、そこにはもう冷様が席についていた。
「冷様!」
私が笑顔で言うと、冷様も笑ってくれた。そして、私はいつもの席に座る。
「いただきます」
二人で挨拶をして、夕食を食べる。今日もとても美味しい。
(毎日ご飯を食べれるなんて幸せね)
私がしみじみとしながら夕食を食べていると、冷様がこちらを向く。
すると、
「この家に来て、はや三週間。そろそろ、社交界にデビューしてもいいと思うんだが…」
そう言われて私はいろいろなところに疑問を抱く。
社交界?
デビュー?
私の疑問を読み取ったのか、冷様は、
「今度、俺の友達がパーティを開くらしい。そこに行ってみないか?」
その誘いに私は、興味を持つ。初めて行くところにはできるだけ行ってみたい。
それが私の思いだった。
「行ってみます…!」
そう言うと、冷様は笑って、
「元気があるな。これなら大丈夫だ」
と言ってくれた。
その次の日からパーティに向けての作法の授業が増えた。今までは着物のときの作法、食事の作法が多かったが、今回からは洋装のときの作法も混じるんだとか。
「星藍様、ここはこちらに持ち帰るんですよ」
西洋の食事の作法に体がうまくなれない。
(これじゃ冷様の妻としてやっていけないじゃない…!)
私は私自身を奮い立たせて、作法の授業に挑む。
「こうでしょうか…?」
私がおそるおそる聞くと、先生はにっこりと笑って、
「うまいですね」
と言ってくれた。私はそれが嬉しくて、他の作法も頑張って覚えた。
時々冷様が授業の様子を見に来てくれる。
「星藍、やってるか?」
「はい!」
私がそう言うと、冷様は私をギュッと抱きしめてくれる。すると、先生が、
「鬼帝様、それでは授業になりません」
「だって、星藍が可愛いんですもん」
私はそのやりとりを横で見て、くすくすと笑う。そして、その日の授業が終わり、私は部屋に戻った。
「ふふ」
私のことを極限まで愛してくれる冷様を想像すると、嬉しくてたまらない。
でも、私には忘れてはいけないことが一つある。
私は精神破壊の異能を持っていて、村では忌み嫌われていたことだ。それは、仕方ないことなのだ。でも、私だって異能を持ちたくて持っていたわけじゃない。
気づいたら自分の周りはこんなふうになっていたのだ。
「パーティ、うまくやれるかな…」
私の心はいつも不安でいっぱいだ。もし、パーティの場で異能が開花してしまったら…。
私が不安に押しつぶされそうになっているとき、ドアがノックされた。
私は急いで扉を開ける。細く開けた扉の隙間から見えた顔は真澄だった。
「真澄…。用は後ででもいいかしら…?」
と聞くと、真澄は、頷いた。そして、
「日之影様が明日、パーティ用の服を買いましょうとのことです。パーティまで後一週間、星藍なら大丈夫だろうとおっしゃっていました!」
笑顔でそう言う真澄に、私は頬が綻ぶ。
「ありがとう」
私は、そう言って扉を閉めた。そして、どっと布団に倒れ込む。私はそのまま眠りに落ちてしまった。
パーティ用の服を買いに行く日となった。私はとりあえず、洋装を準備してもらう。
「真澄、髪の毛は…」
私がおずおずと尋ねる。髪の毛ぐらい、普通の人なら結べるだが、私は今まで結んだことがほとんどない。
「私がやります!」
真澄が元気よく答えてくれた。私が髪の毛を結べないことには何も思っていないようだった。
私は鏡の前に座らされる。そして、十分もしないうちに美しい髪型が完成した。服によくあっている。
「わぁ……!」
私が喜びで声が出なくなっていると、真澄は、
「そんな驚くことじゃないですよ」
と言った。でも、きっと一般人が見ても綺麗だと思うだろう。
真澄に感謝しながら、私は玄関に向かう。そこにはすでに冷様がいた。
「星藍…!」
冷様は何故か驚いた顔をしている。
「何か変でしたか…?」
おそるおそるそう聞くと、冷様は、笑って私に抱きついてくる。
「星藍が可愛すぎるんだよぉ〜」
と言った。
(また、"可愛い"…)
私は最近、冷様の言葉一つ一つにドキッとするようになった。
「では、行こう」
こうやって突然、真剣になるところも、いい。
(これって、好き…?)
まだ、よくわからなくて自信がないが、これが好きって感情だろう。冷様に手を引かれて、車に乗り込む。
(車なんて高いのに…)
冷様の財力には毎回毎回驚いてしまう。私の持っていたお金など、小さな塵に思えてきた。
そんなことを考えながら車に揺られていると、いつの間にか服屋についていた。
「鬼帝様、お待ちしておりました」
深々と頭を下げる店員たち。
「失礼しますが、そちらの方は…?」
初めに挨拶を言った一人が尋ねる。すると、冷様はゾワっと殺気を放つ。
「貴様、無礼だぞ。店長はどこだ」
そう一言言った。すると、その人は、
「店長は体調を崩してしまってあいにく休んでおります」
あわあわしながらそう告げる店員さんが可哀想に見えてきた。
「そうか…、それはすまなかった。店長から話は聞いていないのか?」
冷様が謝ってそう尋ねる。すると、従業員の人たちは皆頭を左右に振った。
「すまない。この娘は私の婚約者だ」
そう冷様がいうと、みんなはぱあっと顔を輝かせて、
「おめでとうございます!」
と口々にいった。しかし、その一方で、
「…噂通り"冷徹"だな」
にやにやとそう話す店員もいた。私はその人たちに怒りを覚えつつも、冷様に向き直る。
「どんな服を買うのでしょうか?」
私がそう尋ねると、冷様は、ニコッと笑って、
「洋装かな」
と言った。
洋装?何それ?
私の頭の中は疑問でいっぱいだ。初めて聞く単語に困惑してしまう。
「洋装…ですか」
私が復唱すると、店員さんに腕を掴まれる。
「では、こちらで試着を行いましょう」
私はそう言われて、店の奥へと引っ張られる。
(何が起こるの…?!)
私が困惑でいっぱいになっている中、冷様は私に向かって手をひらひらと振るだけだった。
そして、奥に入れられて、私は服を脱がされる。そして、服を見せられる。
「こちらとこちらどちらを先に着たいですか?」
そう聞かれて私は迷う。一つは桜色の服。もう一つは水色の服。私は迷った末に桜色を選ぶ。
すると、店員さんは慣れた手つきで私に服を着せてくる。
「鬼帝様、こちらでどうでしょうか」
試着室の扉が突然開けられ、私の姿が晒される。すると、冷様は目を輝かせて、
「可愛い!これは買おう」
と言った。この勢いだと全部買いかねないと思った私は、
「そんなにたくさんお洋服は入りませんからね」
と念押しした。しかし、本人には全く聴こえている気配がなく、顔を輝かせているだけだった。
結局その後、私は二十着以上を着せられ、そのうちの十五着を買うことになった。
いくらなんでも買いすぎだと主張したが、冷様は断固として譲らなかった。
そして、いよいよパーティ当日ーー。