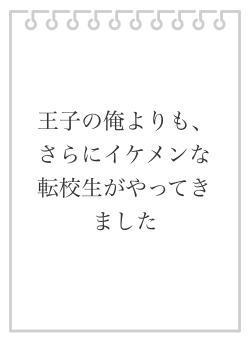「鬼帝様」
昔馴染みの従者にそう言われた。俺はそいつとは友達だと思っていたので、
「よせ、本名でいい。お飾りの称号など、聞くだけでうんざりする」
すると、そいつはため息をして、頷いた。
「では、日之影様」
そう、鬼帝というのはお飾りの称号で本名は日之影冷。本当はもっと自由に生きるはずだった哀れな青年だ。
(多分哀れだ…)
自分で思って、うんうんと頷く。
生まれたときから俺に自由などない。
学校の成績は必ず一位。
全国テストも必ず一位。
スポーツも必ず一位。
何でも1番上に立たなくてはならなかった。いずれ1番上に立つものとして。
俺はそれが嫌だった。もっと、俺のことを全面に見てくれる人が欲しいと思っていた。
母や父は、俺の成績、順位しか見ていない。俺がどう思っているかなんて、一切見ていないのだ。
(そろそろ結婚だ…。父や母が選ばないような人を選んで驚かせるのもありかな…)
そう思っていると、従者の炎が聞いてます?と言ってきた。
俺は全く話を聞いていなかったので、
「すまぬ。聞いていなかった」
と言う。すると、炎ははぁっとため息を一つ。
「貴方は王です。そろそろ結婚を考える時期です。それで、今度、ここから少し離れたところにある村の祭りに行ってみませんか?」
「なぜだ?なぜそこを選ぶ」
俺は疑問だった。なぜ村の祭りに行かなければならないのか。
「そこには、年頃の女性がたくさんいるんだそうです。そこに、一人くらいは日之影様の気にいる方がいらっしゃるでしょう?」
俺はそう言われて、うーんと唸る。
確かにいるかもしれないが、まず結婚したくないという思いがある。
俺はこの話にあまり乗り気になれない。
「わかった。行くだけ行くとしよう」
どうせ炎のことだから俺の両親には許可を取ってあるのだろう。そうすれば、俺は断ることができない。
ずるいやつだ。
「はぁ…」
俺はため息を一つついて、部屋を後にする炎の背中を見送った。
やがて、祭りに行く日となった。
俺はあまり気が進まず、全身からめんどくさいオーラを放つ。
「鬼帝様が来るとみなさん楽しみにしていらっしゃるんですから、そんなめんどくさいオーラ放たないでください」
炎にきっぱり言われる。
でもやりたくないし、行きたくもないのだから仕方ない。
「行った先での目標はなんですか?」
炎にそう問われて俺は、はぁっとため息をつく。
「結婚相手を発見すること」
俺がそう言うと、炎はにっこり笑って、
「では行きましょう」
と言った。
村までは馬車でいく。俺の馬車は三つの馬車に囲まれながら走る。村までは一日もかからずしてつくので、そんな大荷物は必要ないと言ったものの、炎が服などを張り切ったせいで、馬車三つにもなったのだ。
「あれ、鬼帝様の馬車だー!」
「ほら、静かに。とんでもなく冷徹な方が乗っているのだから…」
子供の親はそう言っているようだった。
(とんでもなく冷徹な方か……)
俺は自分自身のことを少しも冷徹だと思わない。自分はそう思っていても、周りからは逆に見えてしまうのだろうか。
心が苦しくてたまらない。
俺はその後、少しうとうとしてしまって、気づけば眠りに落ちていた。
「…様、鬼帝様!」
炎にペシペシと叩かれて、俺は起きる。もう着いたようだ。
「もう着いたのか?」
俺は大きなあくびをしながら、そう尋ねる。すると、炎は頷いた。
「皆様が集会所で鬼帝様のお出迎えの準備をしてくれています。急いで向かいましょう」
まだ半寝の俺を、炎は急いで準備させる。豪華な服、髪の毛……。
みるみるうちに世間で呼ばれている"とんでもなく冷徹な方"が完成する。
俺は、服の裾を少し持ちながら、急いで集会所へ向かう。みんなを待たせては申し訳ない。
「鬼帝様、お待ちしておりました」
村長が俺に頭を下げる。俺はそれに対して、堂々と胸を張るだけ。
よくないとわかっていても、長年染みついた行動を今更直すことは難しい。
「こちらに」
村長は集会所の中心に俺を案内してきた。そして、一言話すように促す。
「俺は今日、ここに花嫁を探しにきた。二日ほど滞在する予定だから、よろしく頼む」
そう言うと、みんなは歓声を上げることも、悪口を言うこともせず、俺に関わりたくないという目で見ていた。
今まで多くの人に向けられてきたその視線。
(もういい…)
俺は花嫁探しを諦めて、祭りを楽しむことに専念することを決めた。
色々な女性が俺に声をかけてくる。
「鬼帝様、ぜひ私と一緒にいかがです?」
「いえ、私と一緒に」
笑顔を作って俺にべたべたと近づいてくる人たち。
俺は少しうんざりしながらも、適当に受け流す。
そんな中、俺の目は一人の少女に留まる。
俺のことをチラチラ見ながらも、料理に集中している少女。
俺は席を立って、少女の方へ向かう。少女は驚いて固まっているようだった。
「その料理は美味いのか?」
俺がそう尋ねると、少女はこくこくと頷いた。
俺が一口食べると、口の中にはジューシーな肉汁。
(これは美味い…)
「これはなんて料理だ?」
俺が少女に質問すると、少女はあわあわとしながら、
「…煮鶏だよ」
その声は予想以上に小さくて、透き通っていた。
彼女はそっぽを向いてしまった。
よく見たら彼女は、年頃の女性に入る感じだった。
おそらく十七、八歳だろう。
俺がさらに彼女に声をかけようとすると、彼女は席を立って、走り去っていった。
(遅かったか…)
俺は俺に全く媚びないあの子を花嫁にしたいと思った。
人生で初めて、相手のことを好きになった瞬間だ。
「二日目のお祭りも鬼帝様の為に頑張りましょう」
村長の大きな掛け声でみんなもおぉっと言うのかと思いきや、言わない。
やっぱり俺は冷徹だということで、嫌われているのだろうか。
だとしたら結構ショックだ。
「では鬼帝様から一言お願いします」
村長に一言話すように促されて、俺は壇上に立つ。
「俺は、花嫁にしたい少女を昨日、見つけた。今日、その少女を誘うつもりだ」
みんなは一気にざわざわし始める。
俺に気になる人ができたと言うのが、それほど驚きなのだろう。
俺は集会所を見渡すが、昨日の少女はどこにもいない。
(もう来ないのか…?)
一気に不安が押し寄せてくる。俺が集会所をまたぐるりと見渡すと、隅の方に昨日の少女がいた。
「!」
俺は嬉しさで頬が緩む。一応鬼帝と呼ばれるこの国の皇帝だ。人前で笑みを漏らすなど、王の威厳が無くなってしまう。
俺が急いで笑みを消すと、あの少女は少し笑っていた。
(また、昨日の場所へ行けば会えるだろうか…)
俺はうきうきの気分で集会所を後にした。
昨日と同じように祭りを散策していると、人がたくさん集まってきた。
「鬼帝様、誰なんですか?」
「誰のことがそんなに気に入ったんですか?」
何回も同じようなことを聞いてくる村の女性たち。
俺はその中に昨日の少女を見つける。そして、手を引く。
「この子だ」
俺がその少女の手を掴んで言うと、みんなはざわつき始める。
少女は救いを求めるような俺で一瞬見たが、すぐにいつもの表情に戻ってしまった。
(なんだ…?)
「村長を呼んできます」
女性の1人が走り去っていった。なぜ村長を呼ぶ必要があるのだろうか。
すると、先程の女性が帰ってきた。村長も一緒だ。
「この子なのですかい…?」
おそるおそる尋ねてくる村長に俺は力強く頷く。すると、村長は俺を睨みつける。
「此奴は異能の家族の末裔です。一週間後、神へ生贄として捧げ、駆逐する予定だったのですが…」
村長は一切悪いと思っていないような口調でそう話す。俺は信じられなかった。
(この時代に生贄…?それより異能とは…?)
「異能とは…?」
俺が尋ねると、村長はニヤリと笑って、
「精神破壊の異能です。対象者の精神を粉々にして殺す。そういう一族でしたから」
少し笑いながらそういう村長に俺は怒りが頂点に達した。
「とりあえず、この子は俺の花嫁だ」
きっぱり言い切って、俺はその場を立ち去った。
その直前、村長は、
「異能の少女、手に入れし者、悪染まりけり」
と言った。
俺はそれを聞き流した。
帰りの馬車の中、俺は少女に質問した。
「名前は?」
少女はおじおじと、
「星藍…です」
と答えた。俺はすかさず次の質問を問いかける。
「星藍は俺の花嫁になる気はあるか?」
そう尋ねると、星藍は頷いた。俺は星藍の頬を撫でる。そして、
「俺が冷徹だと思うか?」
と尋ねる。すると、星藍はおそるおそるだが、頷く。俺はあははと笑ってしまう。
「冷徹じゃない。俺は星藍を見た時から大好きだ」
すると、星藍は頬を真っ赤にする。これからこの少女と未来を歩むと思うと、嬉しくて仕方がない。
「星藍、もう一度言う。俺の花嫁になってくれ」
「…はい」
出会ってから初めて星藍の笑みを見た。
昔馴染みの従者にそう言われた。俺はそいつとは友達だと思っていたので、
「よせ、本名でいい。お飾りの称号など、聞くだけでうんざりする」
すると、そいつはため息をして、頷いた。
「では、日之影様」
そう、鬼帝というのはお飾りの称号で本名は日之影冷。本当はもっと自由に生きるはずだった哀れな青年だ。
(多分哀れだ…)
自分で思って、うんうんと頷く。
生まれたときから俺に自由などない。
学校の成績は必ず一位。
全国テストも必ず一位。
スポーツも必ず一位。
何でも1番上に立たなくてはならなかった。いずれ1番上に立つものとして。
俺はそれが嫌だった。もっと、俺のことを全面に見てくれる人が欲しいと思っていた。
母や父は、俺の成績、順位しか見ていない。俺がどう思っているかなんて、一切見ていないのだ。
(そろそろ結婚だ…。父や母が選ばないような人を選んで驚かせるのもありかな…)
そう思っていると、従者の炎が聞いてます?と言ってきた。
俺は全く話を聞いていなかったので、
「すまぬ。聞いていなかった」
と言う。すると、炎ははぁっとため息を一つ。
「貴方は王です。そろそろ結婚を考える時期です。それで、今度、ここから少し離れたところにある村の祭りに行ってみませんか?」
「なぜだ?なぜそこを選ぶ」
俺は疑問だった。なぜ村の祭りに行かなければならないのか。
「そこには、年頃の女性がたくさんいるんだそうです。そこに、一人くらいは日之影様の気にいる方がいらっしゃるでしょう?」
俺はそう言われて、うーんと唸る。
確かにいるかもしれないが、まず結婚したくないという思いがある。
俺はこの話にあまり乗り気になれない。
「わかった。行くだけ行くとしよう」
どうせ炎のことだから俺の両親には許可を取ってあるのだろう。そうすれば、俺は断ることができない。
ずるいやつだ。
「はぁ…」
俺はため息を一つついて、部屋を後にする炎の背中を見送った。
やがて、祭りに行く日となった。
俺はあまり気が進まず、全身からめんどくさいオーラを放つ。
「鬼帝様が来るとみなさん楽しみにしていらっしゃるんですから、そんなめんどくさいオーラ放たないでください」
炎にきっぱり言われる。
でもやりたくないし、行きたくもないのだから仕方ない。
「行った先での目標はなんですか?」
炎にそう問われて俺は、はぁっとため息をつく。
「結婚相手を発見すること」
俺がそう言うと、炎はにっこり笑って、
「では行きましょう」
と言った。
村までは馬車でいく。俺の馬車は三つの馬車に囲まれながら走る。村までは一日もかからずしてつくので、そんな大荷物は必要ないと言ったものの、炎が服などを張り切ったせいで、馬車三つにもなったのだ。
「あれ、鬼帝様の馬車だー!」
「ほら、静かに。とんでもなく冷徹な方が乗っているのだから…」
子供の親はそう言っているようだった。
(とんでもなく冷徹な方か……)
俺は自分自身のことを少しも冷徹だと思わない。自分はそう思っていても、周りからは逆に見えてしまうのだろうか。
心が苦しくてたまらない。
俺はその後、少しうとうとしてしまって、気づけば眠りに落ちていた。
「…様、鬼帝様!」
炎にペシペシと叩かれて、俺は起きる。もう着いたようだ。
「もう着いたのか?」
俺は大きなあくびをしながら、そう尋ねる。すると、炎は頷いた。
「皆様が集会所で鬼帝様のお出迎えの準備をしてくれています。急いで向かいましょう」
まだ半寝の俺を、炎は急いで準備させる。豪華な服、髪の毛……。
みるみるうちに世間で呼ばれている"とんでもなく冷徹な方"が完成する。
俺は、服の裾を少し持ちながら、急いで集会所へ向かう。みんなを待たせては申し訳ない。
「鬼帝様、お待ちしておりました」
村長が俺に頭を下げる。俺はそれに対して、堂々と胸を張るだけ。
よくないとわかっていても、長年染みついた行動を今更直すことは難しい。
「こちらに」
村長は集会所の中心に俺を案内してきた。そして、一言話すように促す。
「俺は今日、ここに花嫁を探しにきた。二日ほど滞在する予定だから、よろしく頼む」
そう言うと、みんなは歓声を上げることも、悪口を言うこともせず、俺に関わりたくないという目で見ていた。
今まで多くの人に向けられてきたその視線。
(もういい…)
俺は花嫁探しを諦めて、祭りを楽しむことに専念することを決めた。
色々な女性が俺に声をかけてくる。
「鬼帝様、ぜひ私と一緒にいかがです?」
「いえ、私と一緒に」
笑顔を作って俺にべたべたと近づいてくる人たち。
俺は少しうんざりしながらも、適当に受け流す。
そんな中、俺の目は一人の少女に留まる。
俺のことをチラチラ見ながらも、料理に集中している少女。
俺は席を立って、少女の方へ向かう。少女は驚いて固まっているようだった。
「その料理は美味いのか?」
俺がそう尋ねると、少女はこくこくと頷いた。
俺が一口食べると、口の中にはジューシーな肉汁。
(これは美味い…)
「これはなんて料理だ?」
俺が少女に質問すると、少女はあわあわとしながら、
「…煮鶏だよ」
その声は予想以上に小さくて、透き通っていた。
彼女はそっぽを向いてしまった。
よく見たら彼女は、年頃の女性に入る感じだった。
おそらく十七、八歳だろう。
俺がさらに彼女に声をかけようとすると、彼女は席を立って、走り去っていった。
(遅かったか…)
俺は俺に全く媚びないあの子を花嫁にしたいと思った。
人生で初めて、相手のことを好きになった瞬間だ。
「二日目のお祭りも鬼帝様の為に頑張りましょう」
村長の大きな掛け声でみんなもおぉっと言うのかと思いきや、言わない。
やっぱり俺は冷徹だということで、嫌われているのだろうか。
だとしたら結構ショックだ。
「では鬼帝様から一言お願いします」
村長に一言話すように促されて、俺は壇上に立つ。
「俺は、花嫁にしたい少女を昨日、見つけた。今日、その少女を誘うつもりだ」
みんなは一気にざわざわし始める。
俺に気になる人ができたと言うのが、それほど驚きなのだろう。
俺は集会所を見渡すが、昨日の少女はどこにもいない。
(もう来ないのか…?)
一気に不安が押し寄せてくる。俺が集会所をまたぐるりと見渡すと、隅の方に昨日の少女がいた。
「!」
俺は嬉しさで頬が緩む。一応鬼帝と呼ばれるこの国の皇帝だ。人前で笑みを漏らすなど、王の威厳が無くなってしまう。
俺が急いで笑みを消すと、あの少女は少し笑っていた。
(また、昨日の場所へ行けば会えるだろうか…)
俺はうきうきの気分で集会所を後にした。
昨日と同じように祭りを散策していると、人がたくさん集まってきた。
「鬼帝様、誰なんですか?」
「誰のことがそんなに気に入ったんですか?」
何回も同じようなことを聞いてくる村の女性たち。
俺はその中に昨日の少女を見つける。そして、手を引く。
「この子だ」
俺がその少女の手を掴んで言うと、みんなはざわつき始める。
少女は救いを求めるような俺で一瞬見たが、すぐにいつもの表情に戻ってしまった。
(なんだ…?)
「村長を呼んできます」
女性の1人が走り去っていった。なぜ村長を呼ぶ必要があるのだろうか。
すると、先程の女性が帰ってきた。村長も一緒だ。
「この子なのですかい…?」
おそるおそる尋ねてくる村長に俺は力強く頷く。すると、村長は俺を睨みつける。
「此奴は異能の家族の末裔です。一週間後、神へ生贄として捧げ、駆逐する予定だったのですが…」
村長は一切悪いと思っていないような口調でそう話す。俺は信じられなかった。
(この時代に生贄…?それより異能とは…?)
「異能とは…?」
俺が尋ねると、村長はニヤリと笑って、
「精神破壊の異能です。対象者の精神を粉々にして殺す。そういう一族でしたから」
少し笑いながらそういう村長に俺は怒りが頂点に達した。
「とりあえず、この子は俺の花嫁だ」
きっぱり言い切って、俺はその場を立ち去った。
その直前、村長は、
「異能の少女、手に入れし者、悪染まりけり」
と言った。
俺はそれを聞き流した。
帰りの馬車の中、俺は少女に質問した。
「名前は?」
少女はおじおじと、
「星藍…です」
と答えた。俺はすかさず次の質問を問いかける。
「星藍は俺の花嫁になる気はあるか?」
そう尋ねると、星藍は頷いた。俺は星藍の頬を撫でる。そして、
「俺が冷徹だと思うか?」
と尋ねる。すると、星藍はおそるおそるだが、頷く。俺はあははと笑ってしまう。
「冷徹じゃない。俺は星藍を見た時から大好きだ」
すると、星藍は頬を真っ赤にする。これからこの少女と未来を歩むと思うと、嬉しくて仕方がない。
「星藍、もう一度言う。俺の花嫁になってくれ」
「…はい」
出会ってから初めて星藍の笑みを見た。