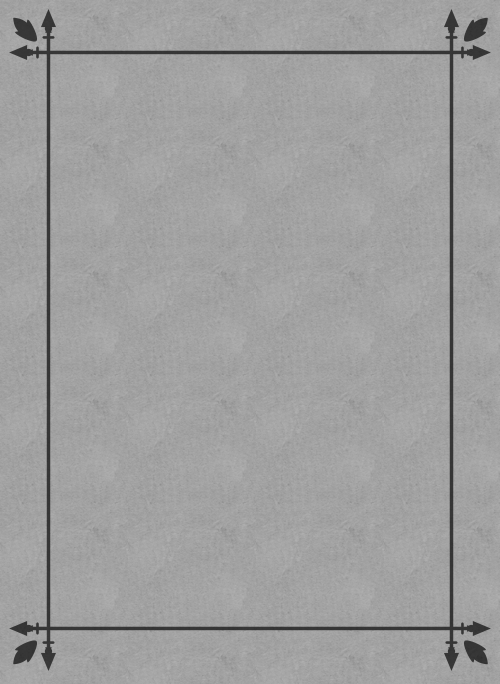公民館の裏手に回る道は、昔より狭く感じた。
子どもの頃は裏庭みたいに思っていたのに、今日のそこは、「立入禁止の場所」だった。
フェンスが増えている。
黄色と黒のバー。赤いコーン。
そして、いちばん目に痛い紙――「関係者以外立入禁止」の張り紙が何枚も、風にめくれている。
「……ほんとに閉鎖されてる」
桃が、小声で言った。
凛が、僕の横で淡々と確認する。
「フェンスの外から。中には入らない」
「分かってる」
僕は頷いて、カメラを構えた。
レンズ越しの芝生は、画面の中だとさらに広く見えた。
(……あのSDカードの映像と同じだ)
広い芝生。低いフェンス。向こうに見える建物の屋根。
一致する。気持ち悪いくらい一致する。
「ここ、夏祭りやったよね」
桃が遠い目をした。
「焼きそば、死ぬほど並んだ」
「並ぶのは今も得意?」
凛が尋ねる。
「得意じゃない、やりたくない」
僕はレンズを少しだけ下げた。
芝生の中心に、そこだけ色が違う場所がある。
黒い。
焦げたみたいに黒い。
「……え」
桃が声にならない声を出した。
凛が、目を細める。
「焼け跡?」
僕はズームを寄せた。
芝の緑が途切れて、土がむき出しで、黒ずんだ斑点が広がっている。
まるでそこだけ、画面にノイズが乗ったみたいだった。
(火事?ボヤ?)
頭の中で言葉が浮かぶだけで、喉が乾く。
燃えた理由。閉鎖の理由。
半年前の時期。
全部が一本の線になりそうで、怖い。
「だから閉鎖されたのかな」
桃が呟いた。
「火事があった、とか」
「可能性はある」
凛が淡々と言う。
「でも、火事だけなら、ずっと閉鎖は不自然かも」
「……事故って言ってた」
桃が小さく続ける。
「誰かが言ってた。詳しくは知らないけど」
(詳しくは知らない)
その言葉が胸に刺さる。
僕も同じだ。いつもそうだ。いつも知らない側にいる。
「和真」
凛が僕を呼んだ。
「顔、固い」
「……固いのがデフォだろ」
僕は言い返そうとして、やめた。
(違う。今は固いんじゃなくて、怖い)
僕はRECを押した。
赤い点が点灯する。
音は拾わない設定のまま。
僕の心臓が暴れても、記録されない。ありがたい。
「中に入らないって決めたのに、撮るのはいいの?」
桃が囁く。
「撮るのはフェンスの外から」
凛が先に答えた。
「映るのは芝生。人じゃない」
「人じゃない……」
桃がその言葉を飲み込むみたいに、息を吐いた。
僕は、焼けた場所を中心に、ゆっくりパンした。
芝の広さが、逆に不安を増やす。
「……あれ、なに?」
桃が、フェンスの低い部分を指差した。
視線を追うと、フェンスの支柱の根元に、小さなものが引っかかっている。
封筒だ。名刺サイズより少し大きいくらい。
しかも透明なビニールに包まれている。
「……封筒?」
僕の声が勝手に落ちた。
凛がすぐに周囲を見回す。
「誰も見てない。……でも、変なことはしないで」
「変なことって言うな」
僕は小声で返しながらも、手は慎重に動いていた。
フェンスの外側。こちら側に引っかかっている。
中に入らなくても取れる位置だ。
僕は封筒をそっと外した。
ビニールの感触が、妙に現実的で冷たい。
「防水してる」
凛が言った。
「雨でも残るように」
ビニールを開けると、中には封筒が一つ。
封筒の口は、丁寧に糊付けされている。
手書きで、短い一言。
みつけたなら、読んで。
映さなくていい。
(……映さなくていい)
その言葉が、なぜか救いだった。
映すことが正義じゃない。
見せない優しさを、ここでも要求されている。
僕は封筒を開けた。
中から、三つのものが出てきた。
一つは、短いメモ。
二つ目は、フィルムみたいに細長い紙――台詞テープ。
三つ目は、見覚えのある不自然な紙。
僕の指先が、台詞テープに触れた瞬間、ぞわっとした。
紙なのに、フィルムの代用品みたいで。
「言葉を映像みたいに扱う」発想が、痛いほど映画部らしい。
凛が隣で覗き込む。
「メモ、何て?」
僕はメモを開いた。そこには、短く。
ここで止まっていたら、また誰かが燃える。
私は過ちを犯した。
「……どういうこと?」
桃が眉を寄せる。
僕は、台詞テープを広げた。
細長い紙に、印刷された言葉が一本の線みたいに並んでいる。
私は過ちを犯した。
言葉は刃にもなる。
だから、刃先を丸めたい
読み上げた瞬間、胸の奥が痛くなった。
刃。
切り抜き。
編集。
僕が毎日やっていることが、全部刃の側に見えてしまう。
(紗季先輩……)
先輩の顔が浮かぶ。
部室で、編集画面を覗き込みながら笑っていた顔。
「ここ、切ると人が泣くよ」って冗談みたいに言った声。
冗談だったのか。予告だったのか。
今はもう、判断できない。
凛が、静かに言った。
「過ちって……半年前から先輩が消えたことと何か関係があるの?」
「……たぶん」
僕は言いかけて、凛に睨まれた。
「たぶん禁止」
凛の声が低い。
僕は息を吸って、吐いた。
「……関係してると思う」
答えは、今は出ない。
でも、次へ行くための鍵はある。
僕は三つ目――あの不自然な紙を手に取った。
意味のない文字列。規則的な行。
本の中で見たやつと同じ匂いがする。
「これ、次の指示だ」
僕は言った。
凛が、穴あきしおりを取り出す。
「重ねる?」
僕は頷き、紙の上にしおりを置いた。
穴の中の文字だけが、すっと意味を持つ。
「病院の自販機。水ばっかり」
僕は読み上げて、思わず顔をしかめた。
「……水ばっかり?」
凛は、言葉の意味を分解するみたいにゆっくり言う。
「次の指示は病院の自販機……ってこと?」
「行く?」
桃が僕を見る。さっきまでの軽さじゃない目。
凛も僕を見る。
淡々としてるのに、逃げ道を塞ぐ目。
僕は芝生の焼け跡にもう一度視線をやった。
燃えた跡は、夕方の光の中で余計に黒い。
まるで「ここで止まるな」と言っているみたいだった。
(ここで止まっていたら、また誰かが燃える)
メモの言葉が、胸の中で鳴る。
僕は台詞テープをそっと折り、封筒に戻した。
映さなくていい。
でも、忘れないように。
「……行こう」
僕は言った。
「病院、探す。自販機、水ばっかりのやつ」
桃が小さく頷いた。
「水ばっかりの自販機、見つけるまで終われないやつね」
凛が淡々と付け足す。
「終われないのは、いつもでしょ」
僕はカメラのRECを止めた。
焼け跡は記録した。
でも、封筒の中身は記録しない。
それが今の僕の刃先の丸め方だ。
帰り道、ポケットの中で台詞テープがかすかに擦れる。
紙の音。
声じゃない音。
それだけが、僕の背中を押していた。
子どもの頃は裏庭みたいに思っていたのに、今日のそこは、「立入禁止の場所」だった。
フェンスが増えている。
黄色と黒のバー。赤いコーン。
そして、いちばん目に痛い紙――「関係者以外立入禁止」の張り紙が何枚も、風にめくれている。
「……ほんとに閉鎖されてる」
桃が、小声で言った。
凛が、僕の横で淡々と確認する。
「フェンスの外から。中には入らない」
「分かってる」
僕は頷いて、カメラを構えた。
レンズ越しの芝生は、画面の中だとさらに広く見えた。
(……あのSDカードの映像と同じだ)
広い芝生。低いフェンス。向こうに見える建物の屋根。
一致する。気持ち悪いくらい一致する。
「ここ、夏祭りやったよね」
桃が遠い目をした。
「焼きそば、死ぬほど並んだ」
「並ぶのは今も得意?」
凛が尋ねる。
「得意じゃない、やりたくない」
僕はレンズを少しだけ下げた。
芝生の中心に、そこだけ色が違う場所がある。
黒い。
焦げたみたいに黒い。
「……え」
桃が声にならない声を出した。
凛が、目を細める。
「焼け跡?」
僕はズームを寄せた。
芝の緑が途切れて、土がむき出しで、黒ずんだ斑点が広がっている。
まるでそこだけ、画面にノイズが乗ったみたいだった。
(火事?ボヤ?)
頭の中で言葉が浮かぶだけで、喉が乾く。
燃えた理由。閉鎖の理由。
半年前の時期。
全部が一本の線になりそうで、怖い。
「だから閉鎖されたのかな」
桃が呟いた。
「火事があった、とか」
「可能性はある」
凛が淡々と言う。
「でも、火事だけなら、ずっと閉鎖は不自然かも」
「……事故って言ってた」
桃が小さく続ける。
「誰かが言ってた。詳しくは知らないけど」
(詳しくは知らない)
その言葉が胸に刺さる。
僕も同じだ。いつもそうだ。いつも知らない側にいる。
「和真」
凛が僕を呼んだ。
「顔、固い」
「……固いのがデフォだろ」
僕は言い返そうとして、やめた。
(違う。今は固いんじゃなくて、怖い)
僕はRECを押した。
赤い点が点灯する。
音は拾わない設定のまま。
僕の心臓が暴れても、記録されない。ありがたい。
「中に入らないって決めたのに、撮るのはいいの?」
桃が囁く。
「撮るのはフェンスの外から」
凛が先に答えた。
「映るのは芝生。人じゃない」
「人じゃない……」
桃がその言葉を飲み込むみたいに、息を吐いた。
僕は、焼けた場所を中心に、ゆっくりパンした。
芝の広さが、逆に不安を増やす。
「……あれ、なに?」
桃が、フェンスの低い部分を指差した。
視線を追うと、フェンスの支柱の根元に、小さなものが引っかかっている。
封筒だ。名刺サイズより少し大きいくらい。
しかも透明なビニールに包まれている。
「……封筒?」
僕の声が勝手に落ちた。
凛がすぐに周囲を見回す。
「誰も見てない。……でも、変なことはしないで」
「変なことって言うな」
僕は小声で返しながらも、手は慎重に動いていた。
フェンスの外側。こちら側に引っかかっている。
中に入らなくても取れる位置だ。
僕は封筒をそっと外した。
ビニールの感触が、妙に現実的で冷たい。
「防水してる」
凛が言った。
「雨でも残るように」
ビニールを開けると、中には封筒が一つ。
封筒の口は、丁寧に糊付けされている。
手書きで、短い一言。
みつけたなら、読んで。
映さなくていい。
(……映さなくていい)
その言葉が、なぜか救いだった。
映すことが正義じゃない。
見せない優しさを、ここでも要求されている。
僕は封筒を開けた。
中から、三つのものが出てきた。
一つは、短いメモ。
二つ目は、フィルムみたいに細長い紙――台詞テープ。
三つ目は、見覚えのある不自然な紙。
僕の指先が、台詞テープに触れた瞬間、ぞわっとした。
紙なのに、フィルムの代用品みたいで。
「言葉を映像みたいに扱う」発想が、痛いほど映画部らしい。
凛が隣で覗き込む。
「メモ、何て?」
僕はメモを開いた。そこには、短く。
ここで止まっていたら、また誰かが燃える。
私は過ちを犯した。
「……どういうこと?」
桃が眉を寄せる。
僕は、台詞テープを広げた。
細長い紙に、印刷された言葉が一本の線みたいに並んでいる。
私は過ちを犯した。
言葉は刃にもなる。
だから、刃先を丸めたい
読み上げた瞬間、胸の奥が痛くなった。
刃。
切り抜き。
編集。
僕が毎日やっていることが、全部刃の側に見えてしまう。
(紗季先輩……)
先輩の顔が浮かぶ。
部室で、編集画面を覗き込みながら笑っていた顔。
「ここ、切ると人が泣くよ」って冗談みたいに言った声。
冗談だったのか。予告だったのか。
今はもう、判断できない。
凛が、静かに言った。
「過ちって……半年前から先輩が消えたことと何か関係があるの?」
「……たぶん」
僕は言いかけて、凛に睨まれた。
「たぶん禁止」
凛の声が低い。
僕は息を吸って、吐いた。
「……関係してると思う」
答えは、今は出ない。
でも、次へ行くための鍵はある。
僕は三つ目――あの不自然な紙を手に取った。
意味のない文字列。規則的な行。
本の中で見たやつと同じ匂いがする。
「これ、次の指示だ」
僕は言った。
凛が、穴あきしおりを取り出す。
「重ねる?」
僕は頷き、紙の上にしおりを置いた。
穴の中の文字だけが、すっと意味を持つ。
「病院の自販機。水ばっかり」
僕は読み上げて、思わず顔をしかめた。
「……水ばっかり?」
凛は、言葉の意味を分解するみたいにゆっくり言う。
「次の指示は病院の自販機……ってこと?」
「行く?」
桃が僕を見る。さっきまでの軽さじゃない目。
凛も僕を見る。
淡々としてるのに、逃げ道を塞ぐ目。
僕は芝生の焼け跡にもう一度視線をやった。
燃えた跡は、夕方の光の中で余計に黒い。
まるで「ここで止まるな」と言っているみたいだった。
(ここで止まっていたら、また誰かが燃える)
メモの言葉が、胸の中で鳴る。
僕は台詞テープをそっと折り、封筒に戻した。
映さなくていい。
でも、忘れないように。
「……行こう」
僕は言った。
「病院、探す。自販機、水ばっかりのやつ」
桃が小さく頷いた。
「水ばっかりの自販機、見つけるまで終われないやつね」
凛が淡々と付け足す。
「終われないのは、いつもでしょ」
僕はカメラのRECを止めた。
焼け跡は記録した。
でも、封筒の中身は記録しない。
それが今の僕の刃先の丸め方だ。
帰り道、ポケットの中で台詞テープがかすかに擦れる。
紙の音。
声じゃない音。
それだけが、僕の背中を押していた。